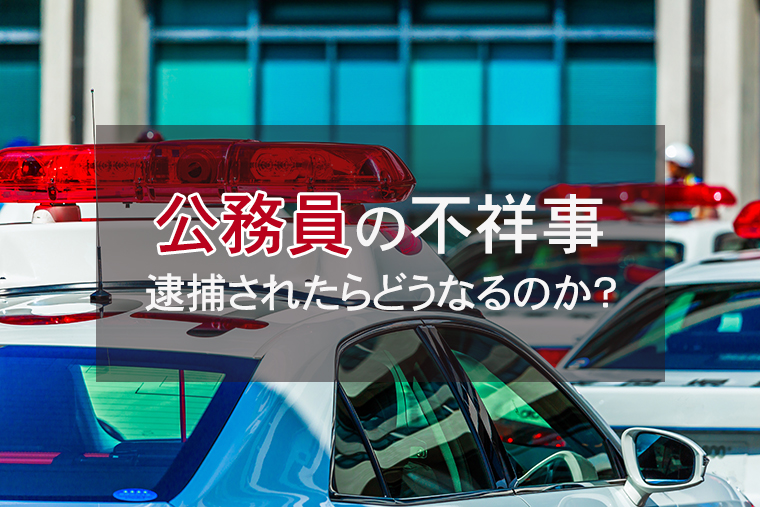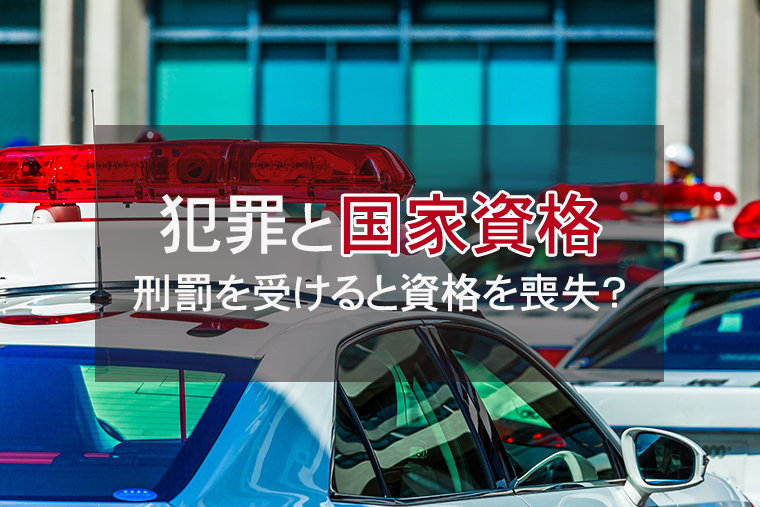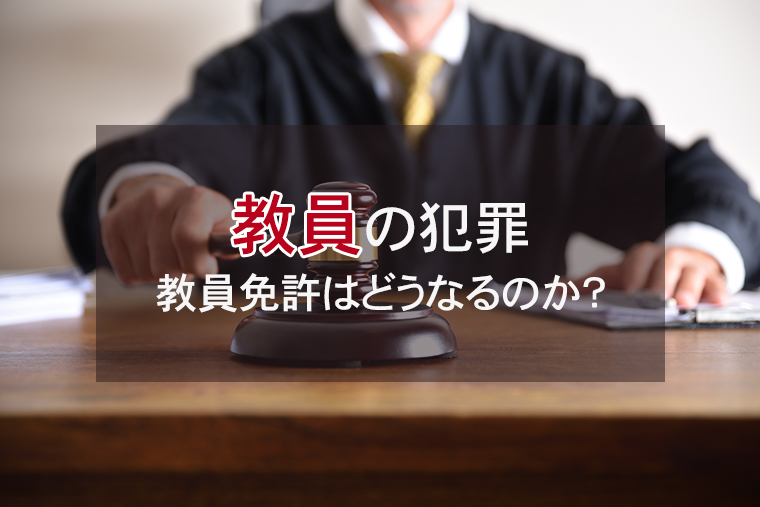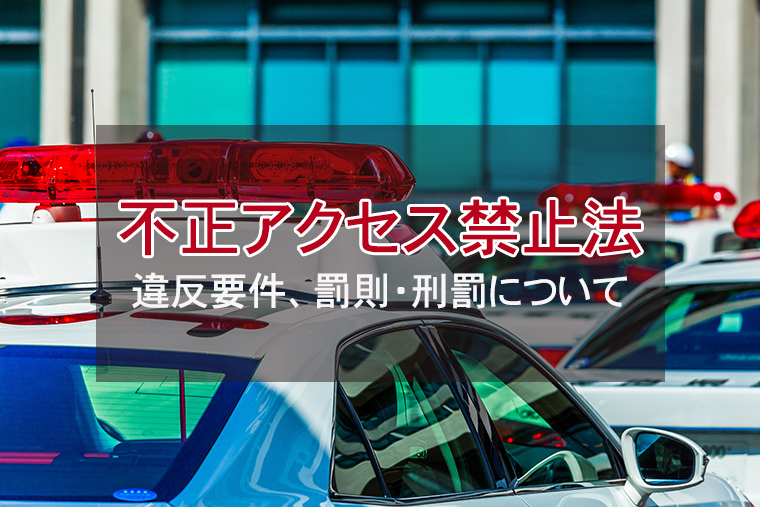秘密漏示罪とは?正当な理由で不起訴になるのか
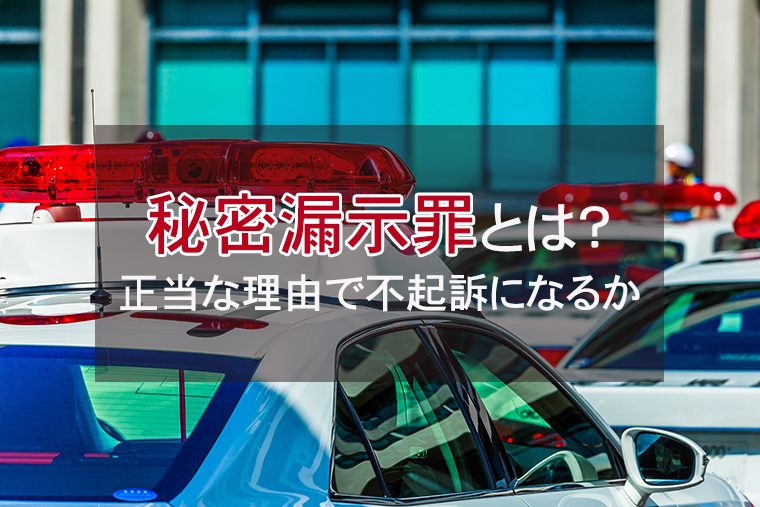
医師、弁護士、薬剤師、宗教職者など、業務の性質上、他人の秘密を知る立場にある職業に就いている方は、日々多くの機密情報に接しています。
患者の病歴、依頼者のプライベートかつ個人的な悩みなどの情報を守ることは、職業上の信頼関係の基盤ともなります。
しかし、何らかの理由でこうした秘密を漏らしてしまった場合、単なる職業倫理上の問題では済まされません。刑法第134条に規定される「秘密漏示罪(ひみつろうじざい)」により、刑事責任を問われる可能性があるのです。
近年、SNSの普及やデジタル化の進展により、意図せずして秘密を漏らしてしまうリスクが高まっています。何気ない投稿や会話が思わぬ法的トラブルに発展することも珍しくありません。
もし、秘密漏示で告発されてしまったならば、一人で対処しようとせず、速やかに刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
以下では、秘密漏示罪の詳細について解説いたします。
1.秘密漏示罪の概要・定義
秘密漏示罪は、刑法第134条に規定されている犯罪です。
刑法第134条
第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第2項 宗教、祈祷とう若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
秘密漏示罪の特徴は、特定の職業に従事する者のみが処罰対象となる「真正身分犯」であることです。対象となる職業は法律で限定列挙されており、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教職者(神職、僧侶、神父、牧師、祈祷師など)が含まれます。
これらの職業は、その業務の性質上、他人の重要な秘密に触れる機会が多く、社会的に高度な守秘義務が求められています。
重要なのは「その職にあった者」も処罰対象に含まれている点です。
つまり、既に退職や転職をしていても、在職中に知り得た秘密を漏らせば犯罪が成立する可能性があります。
職を離れた後も守秘義務は継続し、違反すれば刑事責任を問われるリスクがあることを理解しておきましょう。
なお、条文にない看護師や公務員に秘密漏示罪は成立しませんが、別の法令などにより刑罰が科される可能性はあります。
2.秘密漏示罪の構成要件
秘密漏示罪が成立するためには、いくつかの要件(構成要件)が満たされる必要があります。
(1) 対象となる職業の範囲
刑法134条に明記されている職業は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、そして宗教・祈祷・祭祀の職にある者です。
類似の職業であっても法文に明記されていなければ本罪の対象とはなりません。
ただし、「弁護人」には国選弁護人や私選弁護人が含まれ、「医師」には歯科医師も含まれるなど、解釈上の幅があることに注意が必要です。
ご自身の場合は当てはまるのか?と不安な方は、刑事事件に強い弁護士に確認をしてみると良いでしょう。
(2) 「業務上知り得た秘密」の解釈
ここでいう「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、本人が秘密にしておきたいと考えている事柄を指すことが多いです。
学説上の争いはありますが、客観的に秘匿性があり、かつ本人に秘匿の意思があることが要求されると考えましょう。
また、「業務上知り得た」という点も重要で、職務に関連して知った情報でなければなりません。
たとえば、医師が患者から聞いた病歴は該当しますが、医師が休日の外出中に偶然街で聞いたような情報については該当しないことになります。
(3) 「正当な理由」の判断基準
秘密漏示罪には「正当な理由がないのに」という要件があります。つまり、法令に基づく報告義務などの事情がある場合は犯罪が成立しません(違法性が阻却されます)。
具体的には、感染症予防法に基づく届出義務、児童虐待防止法に基づく通告義務、裁判での証言義務などが正当な理由に該当します。
しかし、何が「正当な理由」に該当するかの判断は複雑で、個別の事案により異なります。自己判断せず、疑問がある場合は専門家に相談することが重要です。
(4) 被害者の告訴が必要
秘密漏示罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ検察官は起訴することができません。
これは、秘密の性質上、被害者の意思を尊重し、さらなる秘密の拡散を防ぐためです。
告訴期間は犯人を知った日から6ヶ月以内と定められており、この期間を経過すると告訴権が消滅し、起訴できなくなります。
3.秘密漏示罪を弁護士に依頼するメリット
秘密漏示罪に関する問題が発生した場合、速やかに刑事事件に精通した弁護士に相談することが重要です。
(1) 法的な問題から検討が可能
秘密漏示罪の構成要件は複雑で、法的な専門知識なしに適切な判断を行うことは困難です。
「秘密」に該当するか、「正当な理由」があるかなどの判断には、判例の知識や豊富な経験が必要です。
秘密漏示の疑いをかけられた場合でも、弁護士が検討すれば、無罪・不起訴処分の可能性を見極めることができます。
仮に秘密漏示にあたる場合でも、適切な初期対応により事態の悪化を防ぐことができます。
訴訟や懲戒処分に発展するリスクがある場合でも、被害者との示談交渉により刑事告発を回避したり、減刑ができたりする場合もあります。
(2) 捜査段階での適切な対応も可能
警察の取り調べに際しては、弁護士の助言により、不利な供述を避けることができます。
黙秘権の行使や供述調書への署名・押印についても、適切な判断が可能になります。
(3) 職業上の信頼回復を望める
刑事事件として立件された場合でも、適切な弁護により執行猶予・罰金刑となれば、職業生活への影響を最小限に抑えることができる可能性があります。
また、所属する職能団体への報告や対応についても、専門的なアドバイスを受けることができるでしょう。
4.各職業における具体的な注意事項
(1) 医師・歯科医師
患者の病名、症状、治療内容、既往歴などはすべて守秘義務の対象となります。
特に注意すべきは、診療録の管理、他の医療従事者との情報共有、学会発表や論文執筆時の匿名化処理です。
さらに、SNSでの症例紹介や、待合室での他の患者が聞こえる場所での会話も問題となる可能性があります。
例え患者の家族であっても、本人の同意なく病状を伝えることは原則として禁止されていますので、医師の方は十分に注意するべきです。
(2) 弁護士
依頼者との相談内容、事件の詳細、訴訟戦略などは守秘義務の対象です。
注意が必要なのは、事件終了後や依頼関係終了後も守秘義務が継続することです。
法律事務所内での情報管理、解決事例の掲示などについても注意が重要です。
(3) 薬剤師
処方箋の内容、患者の服薬歴、副作用情報、薬歴管理簿の記載内容などが守秘義務の対象となります。
特に、薬局では患者同士が近い距離にいることが多いため、服薬指導時の声の大きさや、薬袋の取り扱いに注意が必要です。
また、医師への疑義照会時にも、必要最小限の情報のみを伝えることが重要です。
(4) 助産師
妊産婦の妊娠・出産に関する情報、家族構成、既往歴などが対象となります。新生児の健康状態や家族の状況についても同様です。
特に未婚での妊娠、中絶歴、不妊治療歴などは非常にセンシティブな情報であり、細心の注意が必要です。
(5) 公証人
公正証書の作成過程で知り得た当事者の財産状況、家族関係、契約内容などが対象となります。
遺言公正証書の場合は特に機密性が高く、相続人であっても遺言者の生前には内容を明かすことはできません。
(6) 宗教職者
信者からの告白、相談内容、個人的な悩みなどが対象となります。宗教的な告白は極めて機密性が高く、他の信者や家族に対しても原則として秘密を守る必要があります。
布教活動や説教の際に、個人を特定できる形で信者の体験談を話すことは避けるべきです。
5.まとめ
現代社会では、SNSの普及やデジタル化により、意図しない秘密漏示のリスクが飛躍的に高まっています。何気ない投稿、メールの誤送信、クラウドサービスの設定ミスなど、従来では考えられなかった経路で秘密が拡散する危険性があります。
一度インターネット上に流出した情報は完全な削除が困難で、被害が拡大し続ける可能性があります。
専門職として培った信頼と職業生命を守るためには、日頃からの注意深い情報管理が不可欠です。
しかし、万が一秘密漏示の疑いをかけられた場合は、一人で抱え込まず、直ちに刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談ください。
秘密漏示問題は、刑事責任だけでなく、民事上の損害賠償責任や職能団体による懲戒処分など、複数の法的問題が同時に発生することがあります。
経験豊富な弁護士であれば、これらの問題に適切に対応し、最適な解決策を提案することができます。