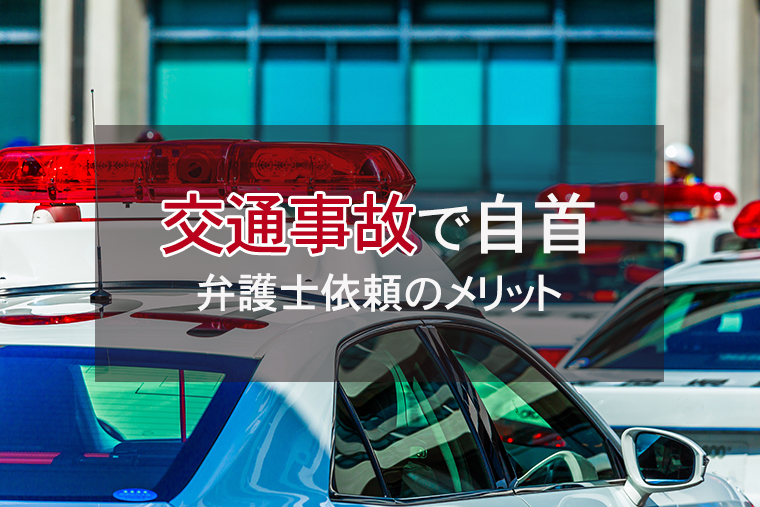危険運転過失致死傷罪の刑事弁護全般

1.危険運転過失致死傷罪とは
人身事故・死亡事故を起こす可能性の高い悪質な運転で人身事故・死亡事故を起こした場合には、刑罰の重い危険運転過失致死傷罪が成立します。
危険運転過失致死傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称「自動車運転死傷行為処罰法)」)において、以下の通り規定されています。
自動車運転死傷行為処罰法 第二条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の拘禁刑に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為自動車運転死傷行為処罰法 第三条
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
2.危険運転過失致死傷罪の法定刑
危険運転過失致死傷罪の法定刑は、自動車運転処罰法2条に該当する場合、「被害者が負傷にとどまる場合は15年以下の懲役刑」「死亡させた場合は1年以上の拘禁刑(この場合上限は30年の懲役刑)」となります。
同法制定以前は、刑法の業務上過失致傷罪(刑法211条)が成立し、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金でしたので、厳罰化がかなり進んでいると言えます。
刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
しかも、危険運転過失致死傷罪が成立する場合は同時に道路交通法違反も成立することが大半で、その場合には法定刑の長期は併合罪加重されます。危険運転過失致傷の場合は法定刑の長期15年が1.5倍加重され、長期の法定刑は22年6月の懲役へと加重されます。
危険運転過失致死罪の場合は1年以上の拘禁刑で、有期刑の上限が定まれていない場合は20年となり、併合罪加重により法定刑の長期は30年となります。
3.危険運転過失致死傷罪と同時に道路交通法違反が成立する場合
(1) 飲酒運転の場合
飲酒運転には、「酒酔い運転」「酒気帯び運転」の2種類があります。
「酒気帯び運転」では3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒酔い運転では5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
上記酒酔い運転、酒気帯び運転の場合には道路交通法違反としてそれだけでも重い刑罰を科されますが、危険運転過失致死傷罪にも該当する場合は先に述べましたように併合罪加重となり、法定刑は致傷の場合には長期22年6月、致死の場合には長期30年の懲役刑となります。
① 「酒酔い運転」
酒に酔った状態(アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態)で自動車等の車両を運転することを言います。道路交通法はこの酒酔い運転に対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑罰を科しています。
道路交通法第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
酒酔い運転かどうかは、アルコール検査(血液、呼気)の結果に関わらず、捜査を担当した警察官が「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」の各項目をチェックして客観的に判断して決めることになります。
項目は、言語や態度の状況、歩行能力、直立能力、酒臭、顔色、目の状態などで、上記カードに記載した上で判断することになります。
② 「酒気帯び運転」
酒酔い運転の程度まではいかず、道路交通法、同法施行令でアルコール検査の結果、血液1mlにつき0.3mg、呼気1Lにつき0.15mgを身体に保有する場合を言います。道路交通法は酒気帯び運転に対して3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑罰を科しています。
道路交通法第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの道路交通法施行令第44条の3
法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1Lにつき0.15mgとする。
(2) ひき逃げ運転の場合
ひき逃げとは、道路交通法72条1項に規定された、事故を起こした場合において被害者を救護する義務(救護義務)、警察への報告義務(報告義務)、道路上の危険を防止する措置をする義務(危険防止義務)を怠り、その場から離れる、逃走することを言います。
上記救護義務とは、事故を起こした運転者が負傷者に救急処置をしたり、119番通報をして救急車を呼ぶなど、負傷者を救護する義務です。人身事故を起こしたことは分かっていても軽傷だろうと考えて、あるいは用事が済んでから現場に戻ろうと考え現場を去る行為も救護義務違反、報告義務違反、危険防止措置義務違反としてひき逃げとなります。
このひき逃げ運転については道路交通法72条1項,119条1項、2項で厳しい刑罰が科されています。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。道路交通法第117条
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
上記ひき逃げの場合には道路交通法違反としてそれだけでも重い刑罰を科されますが、危険運転過失致死傷罪にも該当する場合は、併合罪加重により、法定刑は致傷の場合には長期22年6月、致死の場合には長期30年の懲役刑となります。
(3) 無免許運転の場合
無免許運転は道路交通法64条、同法117条の2の2で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
道路交通法64条
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第64条(無免許運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
上記無免許運転の場合も道路交通法違反として重い刑罰を科されますが、危険運転過失致死傷罪にも該当する場合は、併合罪加重により、法定刑は致傷の場合には長期22年6月、致死の場合には長期30年の懲役刑となります。

[参考記事]
無免許運転で交通事故を起こした場合の罰則
4.危険運転過失致死傷罪の刑事弁護
危険運転過失致死傷罪は人の生命・身体を侵害する犯罪であるので、刑事弁護は示談を取り付けることが重要になります。
致傷の場合は、(負傷の程度にもよりますが)軽傷の方が示談を取り付けやすいと言えます。
加害者(被疑者)は任意保険に加入しているのが通常ですが、加害者が被害者への謝罪などをせずに損害保険会社任せにしてしまった場合には被害者の被害感情が悪化して弁護士による示談交渉が難航することがあります。
当然のことですが、加害者は損害保険会社任せにせずに、被疑者に誠意を尽くして謝罪をすることが重要となります。
致死の場合は弁護士が被害者遺族の方に示談交渉をすることになりますが、結果の重大性、遺族の被害感情、危険運転過失致死傷罪であるため犯行態様が悪質であることから、示談は難航するのが通常です。
道路交通法違反を伴う場合、道路交通法は社会の交通の安全という社会全体の利益を保護する法律であるため、理論上は「被害者は社会全体」ということになり、示談はありません。
しかし、人身事故を伴っている場合には、被害者ないし遺族の方から示談を取り付けることができれば、道路交通法違反については特段問題視されないのが通常です。
5.検察官・裁判所の処分、判決
(1) 被害結果が負傷にとどまった場合
危険運転をして被害者に傷害結果を負わせた場合において、前科前歴(特に同種の交通前科前歴)がない場合でも、検察官は危険運転という犯行態様の悪質性から起訴(公判請求)をします。これに対して裁判所は、犯行態様の悪質性の程度、動機、被害結果の重大性、被害賠償の有無・程度、示談の有無、前科前歴の有無・程度を総合考慮して判決を下します。
負傷が軽微で、任意保険に加入して被害賠償がなされていること、示談を取り付けることができれば、執行猶予判決の可能性が高いと受け止めております。
(2) 被害結果が死亡の場合
死亡事故では、被害結果の重大性、危険運転という犯行態様の悪質性から、遺族の方から示談を取り付けられないと裁判所は実刑判決を下すと受け止めております。
示談については、被害結果が死亡という重大なものであり、かつ危険運転という犯行態様が悪質であることから、遺族の方の被害感情・処罰感情は強いものがあるため、謝罪も受け付けてくれず、まして示談に応じていただけることは極めて難しいと受け止めております。
犯行態様が危険運転には当たらない自動車運転過失致死罪の場合には、任意保険に加入して被害弁償がなされ、被告人(加害者)が十分反省し、同種前科前歴もない場合には、遺族の被害感情・処罰感情が強く刑事上の示談に応じていただけない場合であっても、裁判所は執行猶予付き有罪判決を下すものと受け止めております。
6.終わりに
交通人身事故を起こし、危険運転致死傷罪が成立する場合は、検察官による起訴までは相当期間あるのが通常です。しかし、その間損害保険会社任せにしてしまうと示談交渉に悪影響を及ぼす可能性が高いものです。
そうならないように、事故後速やかに弁護士にご相談、ご依頼してください。
弁護士泉義孝が弁護依頼を受けた自動車運転過失致死罪の事案では、事故後直ちにご依頼いただき、不起訴となった場合もあります。
弁護士が見当たらない場合には、交通人身事故の刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝にぜひご相談・ご依頼ください。