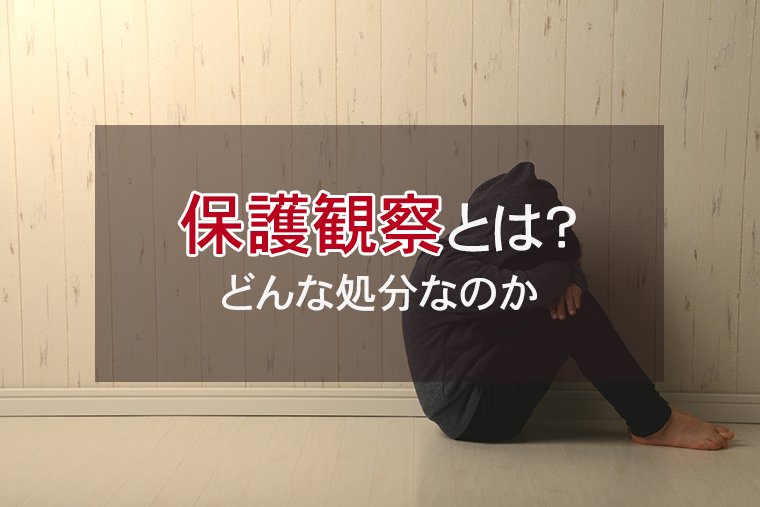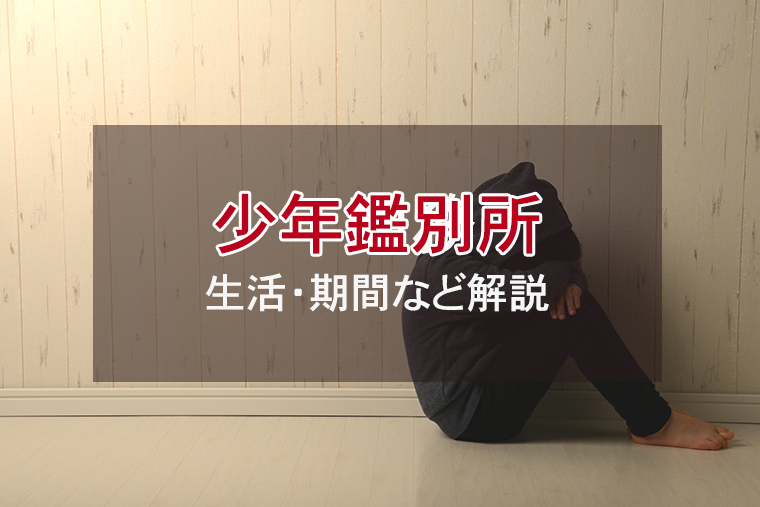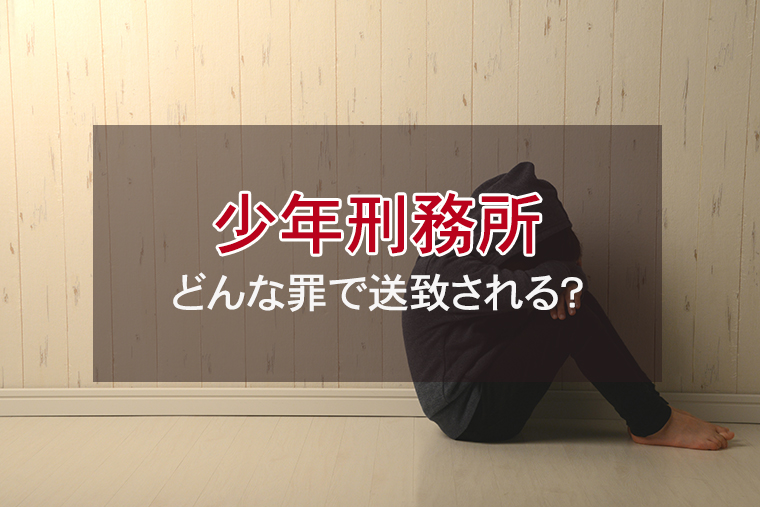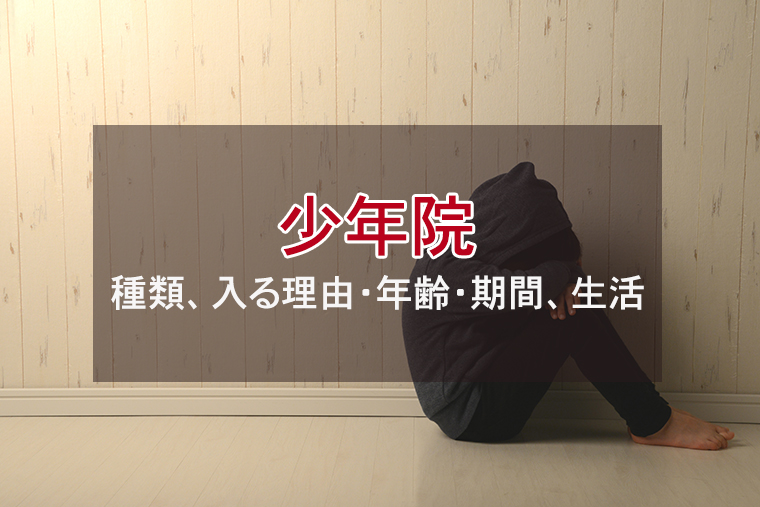児童相談所とは?役割・一時保護等について解説

子どもを守る組織としての児童相談所の存在には、近年注目が集まっています。
児童相談所は、太平洋戦争での敗戦後、町に大量の戦災孤児・浮浪児があふれ出した時代に、これらの子ども達を保護するために生まれたのが始まりです。
その後、今日まで一貫して、子どもおよび子育てに悩む親を支援する役割を担ってきたという古い歴史があります。
また、児童相談所には、刑罰法規に違反する行為を行った14歳未満の子ども(少年)の状態と事案を調査するために「一時保護」するという役割もあります。
本コラムでは、児童相談所に関する基本的な知識を解説の上、特に後半では「一時保護」に焦点を当てて説明します。
1.児童相談所とは?
児童相談所とは、児童の福祉を図り、その権利を擁護するための様々な活動を行う地方自治体の行政機関であり、児童福祉法に基づいて設置されています。
市区町村と協働・連携・役割分担をしつつ、児童や保護者などからの相談に応じ、適切な助言や援助を行います。
都道府県と政令指定都市は、法律で児童相談所の設置義務があります。中核市と東京都特別区も、政令の指定を受ければ設置が可能となっています(児童福祉法第12条第1項、第59条の4第1項)。
各自治体は、その人口に応じて、複数の児童相談所の設置が可能であり、2023(令和5)年7月1日現在、全国で230カ所以上の児童相談所が設置されています。
なお、児童福祉法の対象となる「児童」とは、18歳未満の者です。
2.児童相談所の役割・業務
児童相談所には様々な業務・権限が与えられています。その機能は、①相談機能、②一時保護機能、③措置機能、③市区町村援助機能の4つに大きく分けることができます。
(1) 相談機能
解決に専門的知識・技術が必要な相談に対し、児童福祉司・児童心理司・保健師などの多様な専門職の力を集め、方針を決めたうえで援助を行います(児童福祉法第12条第2項、第11条1項2号、3号)。
(2) 一時保護機能
児童を家庭から離して一時保護します。
これには
(ⅰ)児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図る必要がある場合の「緊急保護」
(ⅱ)児童の心身の状況、環境その他の状況を把握するために必要がある場合の「アセスメント保護」
があります(児童福祉法第12条第2項、第11条1項2号、第12条の4、第33条)。
一時保護の詳細は後述します。
(3) 措置機能
児童と保護者に対する援護、児童の育成・更生のために、児童相談所長には様々な措置を行う行政処分の権限が与えられています。
例えば、児童や保護者を児童福祉司などに指導させたり、里親等に委託したり、児童福祉施設等に入所させたりすることができます(児童福祉法第26条)。
(4) 市町村援助機能
児童福祉法は、住民にもっとも身近な存在である市区町村に、児童をめぐる問題への対応義務を課しています(児童福祉法第10条)。
児童相談所は専門機関として、市区町村間の連絡調整を行ったり、情報を提供したり、専門的な指導・助言を行ったりして、市区町村をバックアップする役割があります(児童福祉法第12条第2項、第11条1項1号)。
3.児童相談所に相談できる内容
自分の悩み事が、児童相談所で受け付けてくれる内容かどうかを心配する方は多いと思われます。
児童相談所に寄せられる相談内容は多様ですが、便宜、次のように分類できます。
- 養護相談
保護者が行方不明、育児放棄されている、離婚や病気で親による養育が困難、虐待されいる等、家庭の養育状況の相談です。里親についての相談も含まれます。 - 障害相談
身体に障害がある、ことばの遅れや吃音がある、知的障害・自閉症・アスペルガー症候群・学習障害等に関する相談です。 - 非行相談
14歳以上の犯罪少年として家庭裁判所から送致された少年、14歳未満でも触法行為があったとして警察署から通告や送致のあった少年、家出・徘徊などのぐ犯少年はもとより、虚言癖・浪費癖・不純異性交遊・飲酒・喫煙などの問題行動に関する相談です。 - 育成相談
どうも落ち着きがない、内気すぎる、家庭内暴力を振るう、不登校、生活習慣が著しく乱れているなどの生活や行動についての相談、しつけや進路選択の相談などです。 - 保健相談
低体重での出生、虚弱体質、小児喘息など、疾患のある児童についての相談です。 - その他の相談
上記の分類は寄せられる相談内容を各種類に分けただけであり、分類自体には特に意味はありません。上記に分類できない相談もありますし、上記に当てはまらなければ、相談を受けつけないというわけではありません。
こんな相談をして良いのか?と悩まずに、まずは相談してみることが大切です。
なお、児童相談所には誰でも相談できます。児童本人、両親、家族、親戚、知人、近隣住民など、子育てや児童をめぐる問題に悩んでいる方なら、誰からの相談でも応じます。
教育機関、保健所、医療機関など、児童にかかわる機関や団体からの相談にも応じます。
特に、誰であろうと、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、速やかに児童相談所等に通告をしなければならないと法定されていますから、直ちに連絡をしてください(児童虐待の防止等に関する法律第6条1項)。
また、児童相談所は、地方自治体の行政機関ですから、管轄区域があり、保護者の居住している地域の児童相談所が問題に対応することを原則としています。
ただ、管轄が異なる方からの相談であっても、児童相談所側が管轄を有する児童相談所を教えてくれたり、必要に応じて管轄のある児童相談所に申し送りしたりしてくれますから、どこの児童相談所に相談しようか迷う前に、まず最寄りの児童相談所に相談をすることが大切です。
4.児童相談所の「一時保護」について
一時保護とは、児童相談所長等が、①児童の安全確保または②児童の心身や環境の状況を調べるために、一時保護所や委託先で身柄を預かることです。
一時保護の期間は2ヶ月までです。ただし、児童相談所長等が必要と認めた時は、引き続き一時保護が可能です(児童福祉法第33条3項、4項)。
また、引き続きの一時保護が親権者の意に反する場合には、2ヶ月を超えるごとに家庭裁判所の承認が必要です(児童福祉法第33条5項)。
(1) 保護の基準
①緊急保護
児童の安全を迅速に確保する必要がある場合です。具体的には、次のような事例です。
- 迷子、置き去り、家出など、保護者や宿所がなく直ちに保護の必要があるとき
- 保護者の死亡、離婚、病気などで、家庭での生活が困難なとき
- 虐待等で、児童を家庭から一時引き離す必要があるとき
- 児童の行動が自身や他人の生命・身体に危害を及ぼすとき
- 重大事件の触法少年として警察から送致等を受けたとき
②アセスメント保護
児童の心身状況・環境等を調査・把握する必要がある場合に、身柄を保護して、生活の全場面における行動を十分に観察・診断して、総合的な評価を行います。
これによって、適切な援助方針をたてることができます。
③短期生活指導
児童の行動や精神的な問題を改善するために、短期間の心理療法・カウセリング・生活指導等が有効と考えられる場合で、遠隔地などのために、他の方法での支援が困難な場合に、一時保護での実施を行います。
(2) 一時保護の開始と解除
一時保護を開始するときは、児童や保護者に対して、保護の理由、目的、予定の保護期間、保護中の児童相談所長の権限などを丁寧に説明したうえ、同意を得て保護します。
ただし、児童の安全確保のために緊急保護が必要なときには、同意がなくても保護を行います。
また、一時保護の目的を達すれば、速やかに保護を解除します。今後、在宅で指導を行う予定のときは、継続的な支援ができるように市町村など関係諸機関との調整を行います。
里親委託や施設入所となるときは、養育環境の変化による精神的負担などを除去するよう丁寧なケアを行います。
児童相談所の「一時保護所」で保護する場合と、児童福祉施設、里親等に委託して保護する場合があります。
児童相談所を設置する地方自治体には、最低一か所の一時保護所が設置されています。2019(令和元)年4月現在で、全国に139か所の一時保護所があります。
(3) 一時保護中の生活について
児童相談所の一時保護では、おおむね2歳から17歳までの児童が、様々な理由から一時的に保護者と離れて生活を送っています。よって、各年齢や心身の状態にあわせて、学習・運動・遊びなどの日課があります。
そこで、児童相談所ではできる限りその児童にあわせた個別的な対応をし、良好な家庭での養育環境と同様な生活環境を保障するようにしています。
自分の学校への通学も可能ですが、通学によって児童の安全と一時保護の目的に支障を生じる危険があるときは登校させず、代わりに一時保護所内で教員免許を保有する職員の指導で勉強をします。
なお、一時保護を委託する場合、委託先は児童福祉施設または里親となりますが、約6割が児童福祉施設に委託されています。
児童福祉施設では、その施設に入所している子どもたちと同様の日課に基づいて生活します。
委託先の学校に通学することが原則ですが、可能であれば安全性を確保しつつ、もともとの自分の学校に通学することもあります。
(4) 一時保護中の児童と保護者との連絡方法
一時保護中の児童と保護者の面会・電話・手紙等への対応は、児童の人権に配慮しつつ、児童の最善の利益に資するか否かという観点から、児童毎に個別に判断します。
保護者との面会ややりとりが児童を安心させ、安定した生活に役立つケースもあれば、それが却って児童の精神的な負担となり逆効果のケースもあるからです。
特に、虐待のために一時保護した場合には、児童の安全を図るべく一時保護場所は非開示としたうえ、面会・通信を制限することも可能です(児童虐待防止法第12条)。
5.14歳未満の少年事件での一時保護
日本において、刑事責任年齢は14歳とされています。
14歳に満たない少年が法に触れても、これを強く非難することはできない(犯罪が成立する要件のひとつである「責任」が欠けている)とされるので、処罰することはできないのです。
しかし、児童相談所の「一時保護」によって身体拘束を受ける場合があります。
少年事件が発覚すると、まずは行政機関のひとつである警察の「行政活動」としての「行政調査(触法調査)」を受けることになります。
そして、必要な調査を終えてから、警察から児童相談所に事件が「通告」されます(児童福祉法25条1項)。通告とは、児童相談所に報告してその職権発動を促すことです。
通告を受けた児童相談所は、事実や少年の状態を調査したうえで、児童福祉法上の各種の福祉的な援助措置(児童福祉司等による指導、里親などへの委託、児童自立支援施設等への入所など)を行います。
また、触法の内容が以下に当てはまれば、通告と共に警察から児童相談所に事件が「送致」されます(少年法6条の6第1項1号及び2号)。
- 一定の重大事件である(故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪、あるいは死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)
- 家庭裁判所での少年審判手続を受けさせることが適当と判断される
「送致」とは、正式に児童相談所の扱う事件として受付けさせるということです。この送致に際しては、警察による事件の調査結果等も同時に送られます。
このように事件を受けた児童相談所では、事案や少年を調査し、少年の指導、訓戒を行います。
その上で、児童相談所が触法少年を家庭裁判所の審判を受けさせるべき(少年審判手続に委ねることが相当だ)と判断すれば、児童相談所は少年を家庭裁判所に送致します。
(※一定の重大事件を起こした触法少年の事件は家庭裁判所に送致することが原則とされています。)
警察が家庭裁判所に直接に送致することは許されず、いったん児童相談所に送致して、福祉的観点からの調査と判断を行わせるのが14歳未満の少年事件の特徴です。
6.まとめ
以上、児童相談所の基本的な知識について説明しました。
子どもをめぐる悩みがあるなら、まずは躊躇せずに児童相談所へ相談をしてみることが大切です。
また、少年は身体的にも精神的にまだ若く、少年事件を起こしても更生して通常の生活を行うことが可能です。
少年事件でお困りの方は、直ちに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
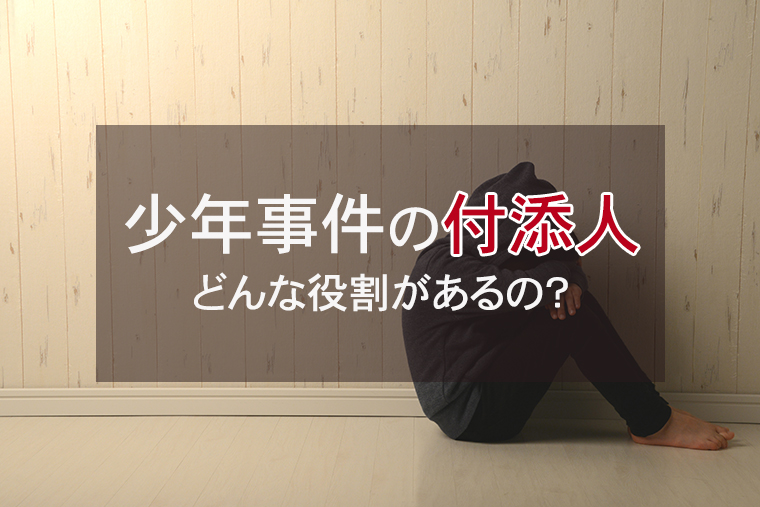
[参考記事]
少年事件における付添人の役割