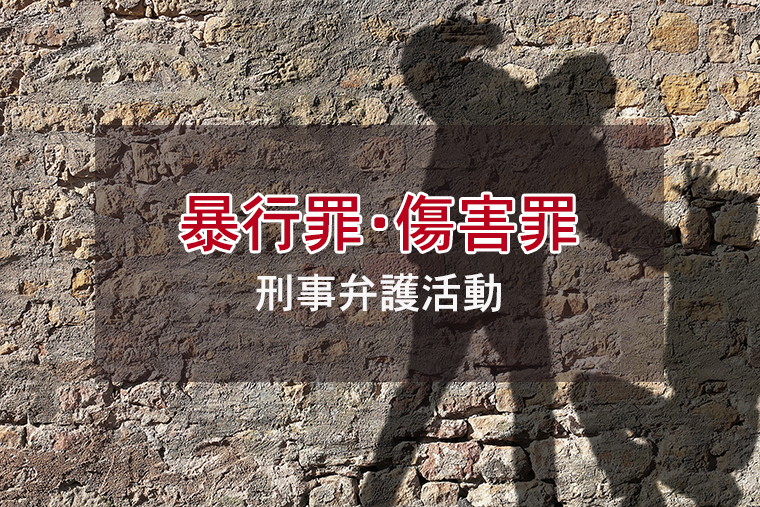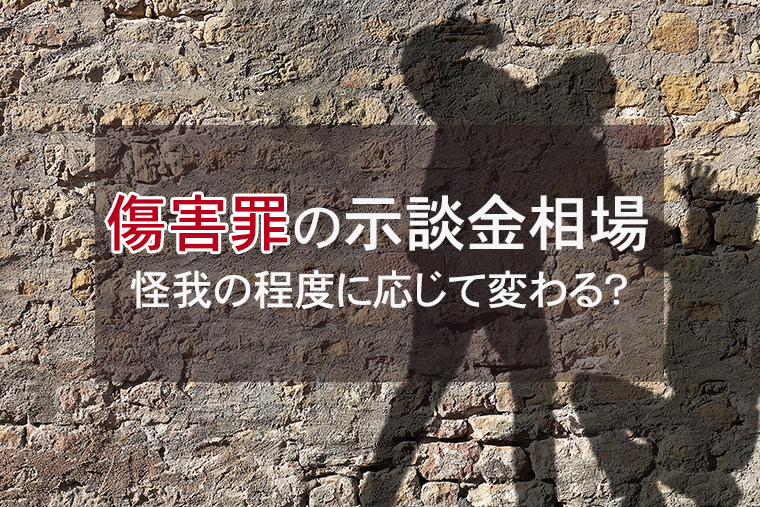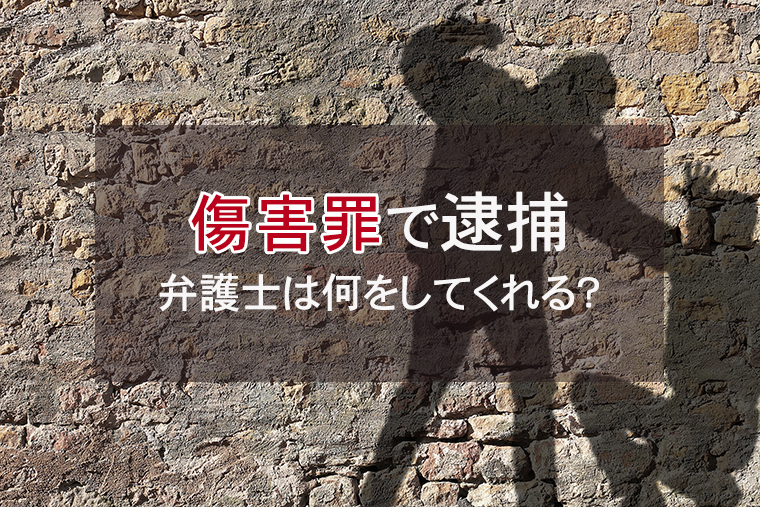傷害・傷害致死の弁護
傷害とは?
傷害罪とは、人の身体を傷害した場合に成立するものです(刑法204条)。
典型例としては、暴力をふるった結果、相手に怪我を負わせた場合です。しかし、暴力の行使だけでなく、たとえば「深夜に嫌がらせ電話をかけ続けて相手をうつ病にさせた」場合や、「性交によって性病をうつした」場合においても、傷害罪が成立します。
なお、傷害罪は、加害者に暴行する意図があれば成立するとされており、相手に怪我を負わせる意図までは成立要件とされていません。
以下の行為が「傷害」にあたります。
- 相手を殴って、全治1ヶ月のケガを負わせた
- 相手を木刀で殴りつけ、骨折させた
- 自身が性病患者であることを認識したうえで性交におよび、相手に性病をうつしてしまった
- 嫌がらせ目的でいたずら電話や怪文書を送り付け、相手がうつ病になった など
また、怪我をした相手が最終的に死亡してしまった場合には「傷害致死罪」が成立します。例えば、相手を押した結果相手が倒れ、頭を打って死亡したという事例は傷害致死罪になります。
一方、殺意を持って暴行し相手が死亡した場合には「殺人罪」が成立します。殺すつもりはなかったが結果的に死亡した場合には「傷害致死罪」です。
しかし、「もしかしたら相手が死ぬかもしれない」という程度の認識も殺意になります。
なお、殺意をもって相手に怪我を負わせたが、死亡には至らなかった場合には「殺人未遂罪」が成立します。傷害罪とかなり類似しますが、「殺意」という故意があったかどうかが異なる点です。
故意ではなく、あくまでも過失によって相手に怪我を負わせてしまった場合には「過失傷害罪」が成立します。
暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪と傷害罪の2つの違いは、暴行した相手の「怪我の有無」です。
暴行罪とは、暴行したものの、相手を怪我させるに至らなかった場合に成立します。
一方、傷害罪とは、暴行したかどうかは問わず、とにかく相手に怪我を負わせた場合に成立します。
したがって、暴行を加えた結果相手が怪我を負わなかった場合には暴行罪にとどまり、怪我を負ってしまった場合には暴行罪に止まらず傷害罪になる、とご理解いただくと良いでしょう。
傷害罪の刑罰
傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法204条)です。
暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められているため、傷害罪はこれに比べかなり重い刑罰となっています。
一般的に、傷害罪の量刑を行う場合、次の項目を基準として総合的に判断します。
- 傷害結果の程度(治療に必要な期間の長さ、後遺症の有無)
- 示談の有無・示談金額
- 傷害行為の態様(悪質性、計画性、凶器使用の有無など)
- 傷害行為の動機
- 被害者側の事情(事件に至る経緯に被害者にも責任があるか)
弁護士に刑事弁護を依頼しなかった場合でも、相手の怪我の程度が軽度で、かつ初犯であれば、略式手続により罰金刑で終わるケースが多いです。
しかし、暴行や傷害といった同種の前科がある場合には、「何度も繰り返しており、罰金にしても刑罰としての効果がない」と判断され、公判請求されて刑事裁判になることもあります。
この場合、公判請求されるのが初めてであれば、多くは執行猶予付き判決が下されます。ただし、重症の場合などや同種の前科が多数ある場合には、実刑となる可能性もありえます。
なお、傷害行為などの前刑の執行猶予中に犯罪が行われた場合には、実刑判決となり、前刑の執行猶予も取り消しとなるのが通常です。また、実刑で服役後5年以内に傷害行為などの犯罪を行い起訴されれば、執行猶予はつかず実刑判決になります。
傷害罪の弁護方針
傷害罪は、被害者からの告訴がなくても起訴することができる非親告罪です。したがって、示談成立後、告訴を取り消してもらえたとしても必ず不起訴になるというわけではありません。
とはいえ、実際には前科がなく、傷害結果が軽微で、かつ被害者との示談を取り付ければ、不起訴あるいは執行猶予付判決になるといっていいでしょう。
示談成立を目指す
不起訴処分や執行猶予付き判決を下してもらうべく、検察官や裁判官への心証を良くするためには、弁護士に被害者との間で示談を成立させてもらうことが傷害罪の量刑において最も有効な手段です。
当事務所の弁護活動としては、まずは早急に被害者にお会いして誠意をもって謝罪を伝えるとともに、適切な示談金を提示して早期の示談成立を目指します。
被害者は被疑者(加害者)に対して警戒心や憎悪感を抱いていることが多く、被疑者と直接やり取りをすることを拒むのが一般的です。
しかし、弁護士が検察官に「示談交渉のために被害者の連絡先を教えてほしい」と言えば、検察官は被害者に連絡を取り「弁護士に連絡先を教えて良いか?」と打診します。そして、了承を得られた場合のみ、検察官から弁護士に被害者の連絡先が伝えられる仕組みとなっています。
仮に、同種前科が多い、傷害結果が重大など、示談ができていなければ公判請求されるような場合でも、弁護士が被害者と示談を成立させることで不起訴あるいは罰金刑にとどまることが多いといえます。
ご相談内容「示談したい」
反省文・謝罪文を書く
傷害行為に及んでしまったという事の重大さを被疑者の方に理解してもらい、深く反省してもらいます。「被害者が謝罪を受け入れてくれたかどうか」という点はとても重要ですので、被害者に対して弁護士経由で十分に謝罪します。
また、謝罪と合わせて治療費や慰謝料など、十分な被害弁償も行います。
さらに、被疑者の方には謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出することで、猛省している姿勢を理解していただきます。
早期釈放を目指す
被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指して、次の弁護活動を行います。
裁判官に対して勾留請求しないよう、家族の身元引受書、上申書、弁護士意見書など、勾留の必要性がないことを主張する書類を検察官に提出して交渉します。
その結果、検察官が裁判官に勾留請求しないことも多数あります。
それでも検察官が裁判官に勾留請求してしまった場合には、裁判官が勾留決定しないよう、家族の身元引受書や上申書、弁護士意見書などを裁判官に提出して勾留決定しないように働きかけます。
裁判官は、検察官の場合よりも勾留決定をせず釈放することが多いようです。
それでも勾留決定が下されてしまった場合には、勾留決定を取り消してもらうよう裁判官に対して要求する、いわゆる「準抗告」を行います。準抗告とは、3名の裁判官からなる裁判所に、別の裁判官がすでに下した勾留決定を取消してもらう裁判をいいます。
以前では、準抗告はほとんど認容されることがありませんでした。しかし、準抗告に関する最高裁判所判決が出されて以来、少数ですが認められるケースも増えています(もっとも、重大事件や否認などの場合には準抗告は棄却されることになります)。
当事務所では、勾留決定による被疑者・家族への重大な不利益などを中心として、勾留の必要性がないことを主張する準抗告書を作成し提出します。
準抗告が認容されますと、裁判官の勾留決定が取り消されて被疑者は釈放されます。
ご相談内容「釈放・保釈してほしい」
「酔っていて記憶がない」と無罪を主張したい場合
傷害事件において、「酔った勢いでけんかになり相手に怪我を負わせてしまった」というのはよくあるケースです。
確かに、アルコールを摂取したことで是非善悪の判断能力が低下することもありますが、そういった場合での判断能力低下を理由に無罪となったケースはほとんどありません。
酔ってけんかになって相手を怪我させ、それを覚えていない場合でも、怪我をさせるほどの行為は判断能力がなければできないことです。よって、覚えていないという言い訳は警察や検察官、裁判所に通用しません。
むしろ、被疑者本人の「酔っぱらっていたので覚えていない」という主張は、検察官や裁判官にしてみれば反省がないどころか、否認している、容疑を認めていないと受け取られ、逮捕されることになります。
「正当防衛だった」と主張したい場合
正当防衛とは、「相手からの急迫不正の侵害に対して、自分または他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為であれば、罰しない」とするものです。
したがって、「相手の方が先に殴りかかってきたので、自分を守るために行った」という暴行事件ならば、不起訴や無罪になる可能性があります。
正当防衛が成立するかどうかは、次の点がポイントになります。
- 侵害を予期していたか
- 積極的な加害意思があったか
したがって、“相手からの侵害を予期しておらず、相手の暴行に対して応戦するにしても積極的な加害意思を持たなかった“という場合に、正当防衛が成立すると言えます。
当事務所の弁護活動としては、被疑者の方から事情を細かく聴取して、正当防衛を裏付ける事情があれば捜査機関や裁判官に対して粘り強く主張していくことで正当防衛を認めてもらい、不起訴処分や無罪を目指していきます。
もっとも、「相手方から先に侵害行為を行ったので、反撃として傷害行為を行った」という場合において、検察官や裁判所が簡単に正当防衛を認めることは通常ないとお考えください。
このような場合には相手方が暴行(傷害)、こちらは傷害として相互に立件されると思われます。
相手方が診断書をつけて被害届を出せば、こちらは傷害の被疑者として警察に取り調べを受けます。それに対してこちらも暴行(傷害)事件として被害届を出すべきかどうかですが、仮にこちらも被害届を出して受理されれば、相手方も暴行(傷害)の被疑者となります。
相手方が罰金などの前科をつけたくないと考えれば、双方の間で0円での示談ないし通常より低い示談金で示談を成立させることができるでしょう。
もっとも、相手方が被害届を出されたことに反発して「罰金前科がついても構わないから争いたい」と考えることもありますので、弁護士と十分相談して方針を決める必要があります。