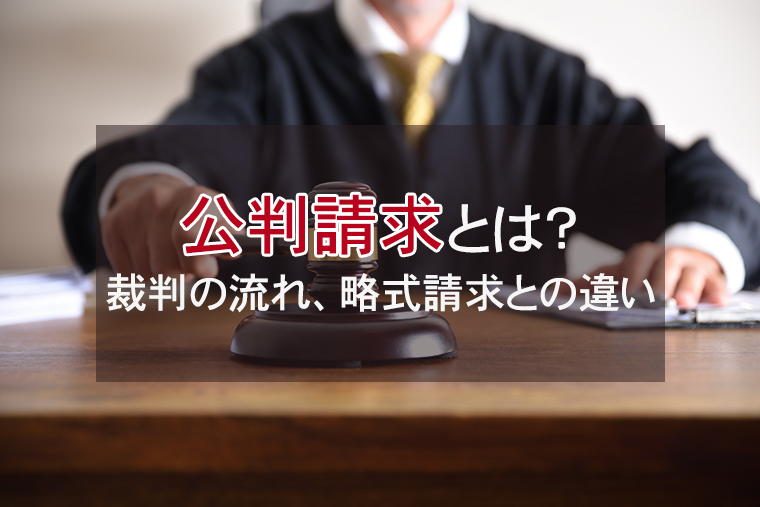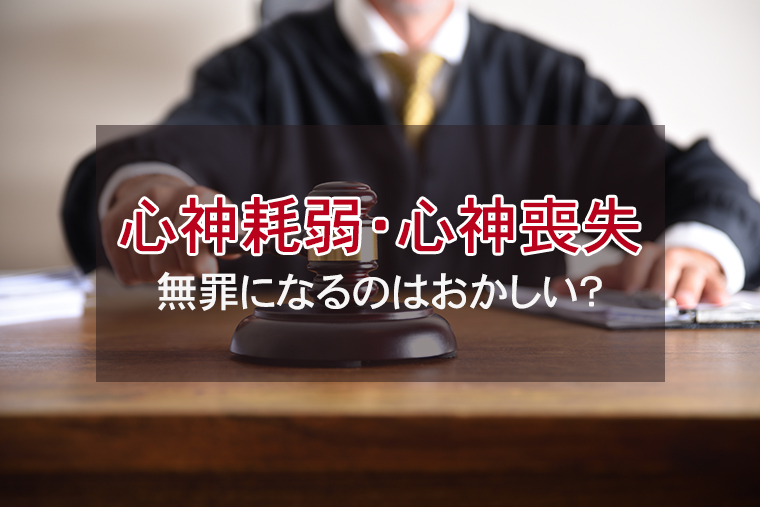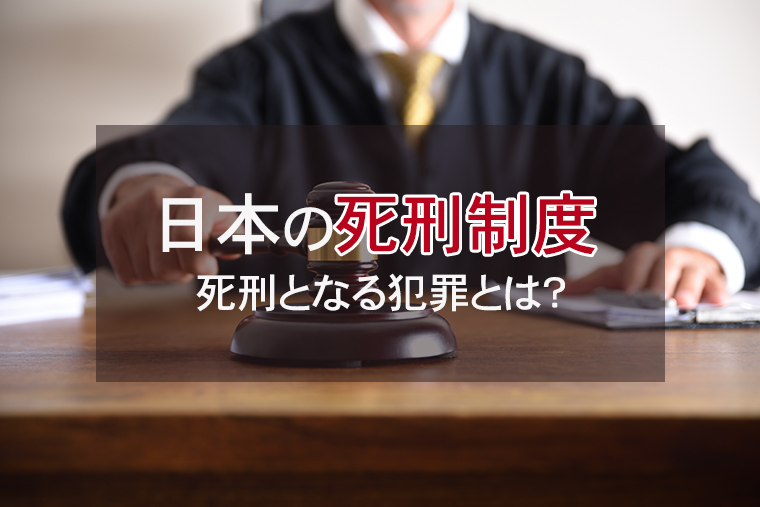即決裁判手続とは?対象事件・要件を解説
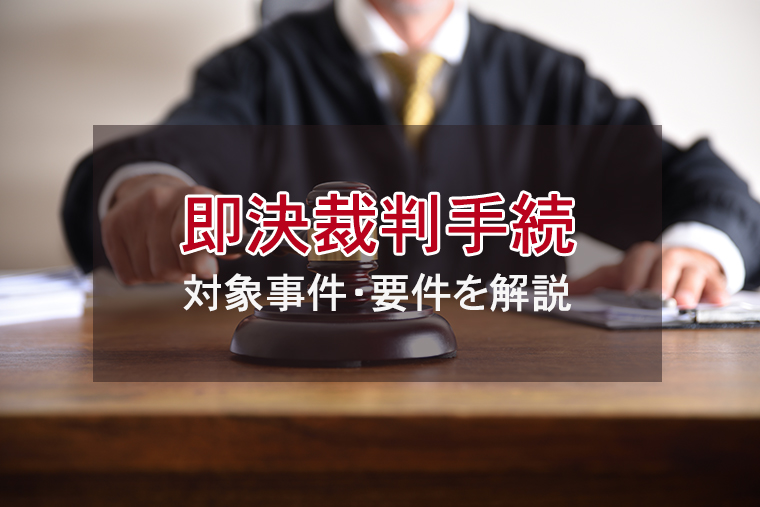
通常の刑事裁判手続は、「人定質問」「起訴状の朗読」「黙秘権の告知」「罪状認否」「検察官の冒頭陳述」「証拠調べ」「論告」「弁論」といった多数の手続きを経て判決に至ります。
そして、証拠の採否及び取り調べの方法については、刑事訴訟法(刑訴法)等の法律における厳格なルールに従います。
しかし、事案明白であり軽微な事件について、常に通常の刑事裁判手続に従い審理を行うことは、被告人の精神的負担や、裁判における時間・労力・費用などの負担の観点から望ましいとはいえません。
そこで、一定の刑事事件について、刑事裁判の手続を簡略化して迅速に事件を終結させるための手続として、「即決裁判手続」が導入されています。
本コラムでは、「即決裁判手続」の詳細を解説します。
1.即決裁判手続の要件
即決裁判手続の対象となる事件は、事案明白かつ軽微であること、証拠調べの速やかな終了の見込があることなどの事情を考慮して相当と認められるものに限定されています(刑訴法350条の2第1項本文)。
また、死刑又は無期もしくは短期1年以上の拘禁刑に当たるような重大犯罪は除外されます。
そして、即決裁判手続を採用し最終的に判決するには、被疑者及び弁護人の同意を必要とします(刑訴法350条の2の第2項及び第4項)。
これは、簡略化された手続きとはいえ即決裁判手続では有罪判決(罰金刑・拘禁刑)が下されるのが通常であるため、最終的に刑罰という不利益を課せられる被疑者・被告人及びその弁護人の意思を尊重する趣旨です。
また、この同意に関する確認及び意見表明は慎重に行うべきものであり、かつ、裁判所の確認対象となるため、必ず書面により行われ、記録化されます。
なお、被疑者としては即決裁判手続についての助言等を弁護士に求めたい場合があるでしょう。さらに、最終的にはその弁護人の同意を必要としますから、適宜、被疑者の請求あるいは裁判長の職権により国選弁護人を選任できることになっています。
なお、即決裁判手続によることは不相当であると裁判官に判断された場合には、通常の刑事裁判手続となります。
2.即決裁判手続の特徴
(1) 手続の迅速性・簡略化
即決裁判手続の第1回の公判期日は、原則、起訴後14日以内に指定され、即日判決となります(刑訴法350条の13)。
このような手続の迅速性は即決裁判手続の特徴の1つです。
通常の刑事裁判の場合、第1回の公判期日は起訴後1〜2ヶ月後になります。
自白事件の場合は即時判決になることがほとんどですが、第2回期日が指定された場合は裁判の終了まで起訴後2~3ヶ月かかることが多いです。
なお、迅速化・簡略化された手続により判決する関係から、被告人の公判期日の出頭義務は徹底されています。
また、即決裁判手続に関する公判期日は、弁護人のいない場合には開くことはできません。
(2) 判決内容の制限
即決裁判手続による判決において、被告人に拘禁刑を科す場合には、必ず刑の全部について執行猶予を言い渡します(刑訴法350条の14)。
※拘禁刑とならない場合の有罪判決は、罰金刑が言い渡されることになります。
簡略な手続により有罪判決を下すことの反面、その判決内容に制限を設けているのです。

[参考記事]
執行猶予とは?執行猶予付き判決後の生活について(仕事、旅行)
3.即決裁判手続と略式手続の違い
即決裁判手続と混同されることがある手続き方法として、「略式手続」という制度があります。
略式手続とは、簡易裁判所の扱うことのできる事件について、公判を開くことなく、書面上の審理により100万円以下の罰金・科料を科す手続です(刑訴法461条~470条)。
即決裁判手続と略式手続の根本的な違いは、即決裁判手続は簡略化されているとはいえ公判手続(裁判)であるのに対して、略式手続は書面上の審理であり裁判が開かれることはないという点です。
また、略式手続では必ず罰金・科料を科すことになりますから、その点でも拘禁刑判決が有り得る即決裁判手続とは異なります。さらに、略式手続は即決裁判手続のように弁護人の同意は必要ありません。
なお、略式手続においては、略式命令の告知日から14日以内に正式裁判を請求できます(刑訴法465条1項)。
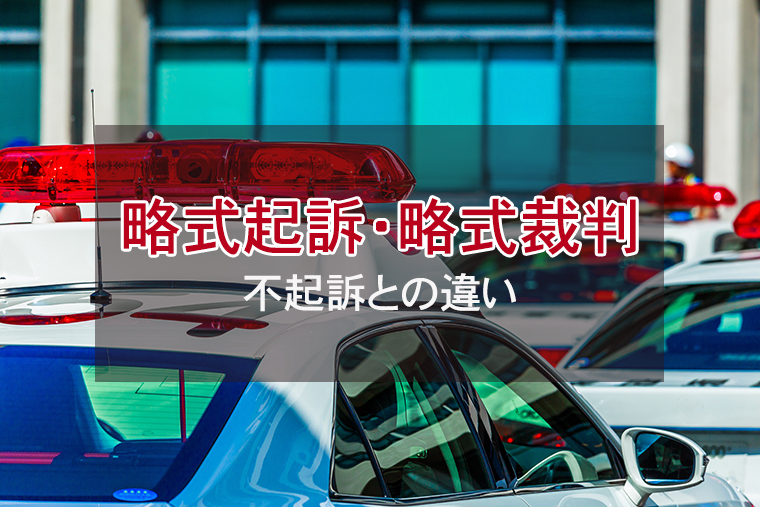
[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
4.即決裁判手続のメリットとデメリット
即決裁判の主たるメリットは、手続の迅速性と実刑の回避です。
即決裁判手続は、先に説明した通り、起訴後14日以内に指定された公判期日における即日判決により終了します。被告人にとっては早期に刑事裁判手続から解放されることになり、心身の負担は小さくて済みます。
また、即決裁判手続による判決において実刑判決はあり得ません。必ず執行猶予がつきますから、その意味では、被告人にとって早期に社会に復帰できることになります。
他方、即決裁判手続のデメリットとしては、「事実誤認を理由とした控訴はできないという制約がある」というものが考えられますが、基本的にはメリットの方が多い制度と言えます。
5.即決裁判手続の利用率
(1) 即決裁判手続の利用率は低い
少し前のデータですが、平成27年(2015年)の統計によれば、実際の刑事裁判において即決裁判手続の利用された被告人の数は568人です。
これは、通常の刑事裁判により判決を言い渡された被告人の数に対し約1%に過ぎません。
そして、平成27年において即決裁判手続が利用された事件の約70%は薬物事犯でした。
これは、①初犯の軽微な薬物事犯の場合に執行猶予はほぼ確実であること、②薬物事犯には被害者は存在しないこと、③薬物事犯においては客観性の高い物証が存在していることが多いこと等から、即決裁判手続を利用しやすい面があるからと思われます。
(2) 利用されない理由
このように、即決裁判手続は現実にはあまり利用されていません。その背景には、以下の点が影響していると考えられます。
まず、即決裁判手続の対象事件に当てはまる事件自体は多いのですが、拘禁刑を相当とする事案ならば、再犯防止等の観点から、被告人に罪を犯したことの重大性につき自覚を促すため通常の刑事裁判手続を選択することは十分に考えられるのです。
また、通常の刑事裁判でも、自白事件であれば1回の公判期日により審理を終了して、適宜即日判決することもできます。こうなると、特に即決裁判手続における手続の迅速性は大きな利点にはならず、通常の刑事裁判でも最終的に執行猶予を付されることになりますから、即決裁判手続により執行猶予が約束されることも大きな魅力になりません。
6.刑事事件・裁判は泉総合法律事務所へ
即決裁判手続による判決を行うためには必ず弁護人の同意を必要としています。つまり、即決裁判手続において弁護人となる弁護士の存在は不可欠なのです。
さらに、即決裁判手続によることの妥当性は事案の内容に応じて様々ですから、その点につき弁護士からの適切なアドバイスを受けるメリットは大きいです。
刑事事件で逮捕された際、犯罪内容によっては起訴されて裁判となってしまう可能性があります。起訴されずとも罰金となれば前科になってしまい、今後の生活に様々な影響が現れます。
刑事事件で逮捕されてしまったという方は、お早めに泉総合法律事務所にご相談ください。初回相談は無料となっております。