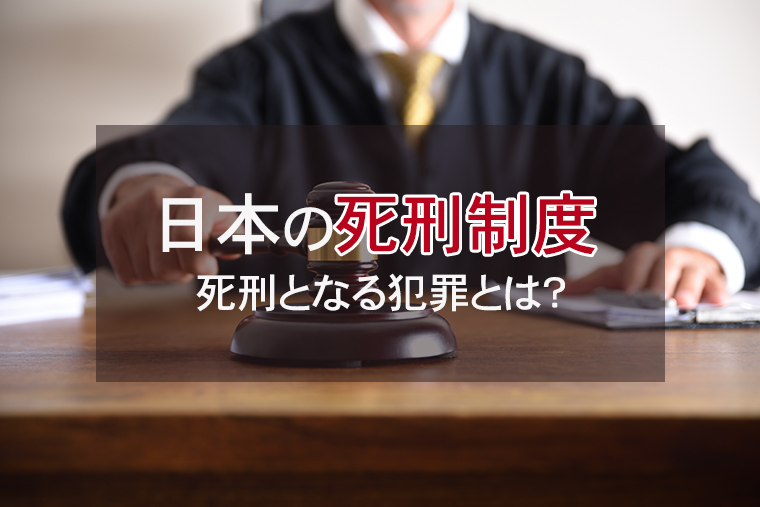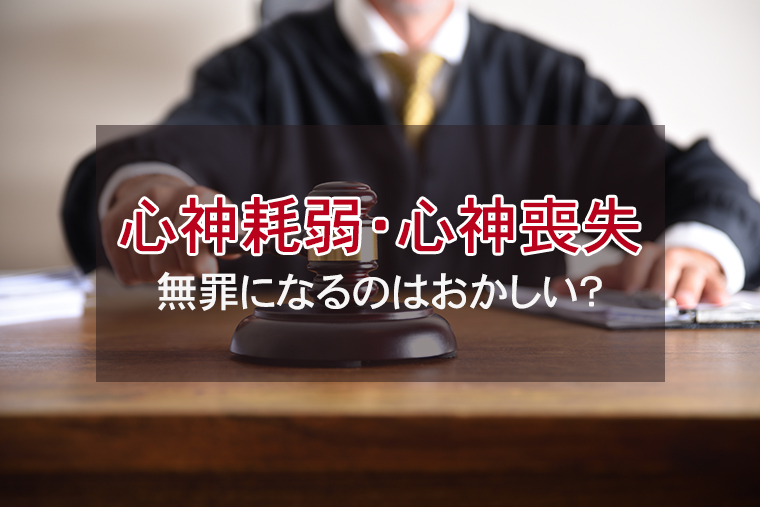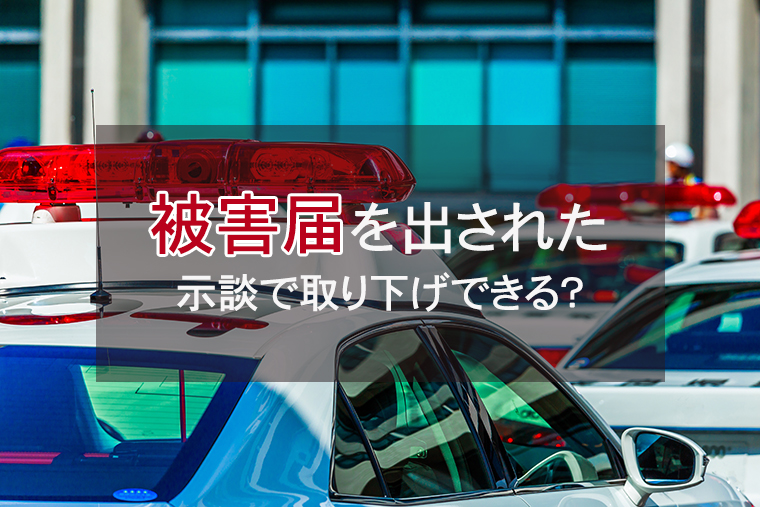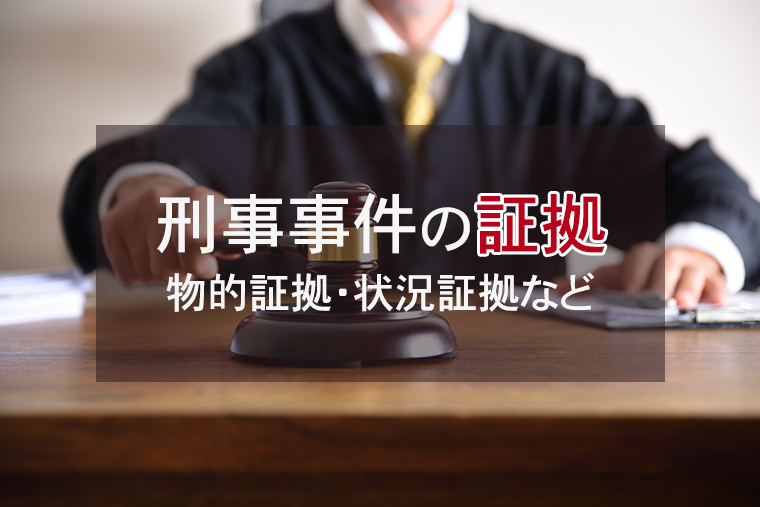略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
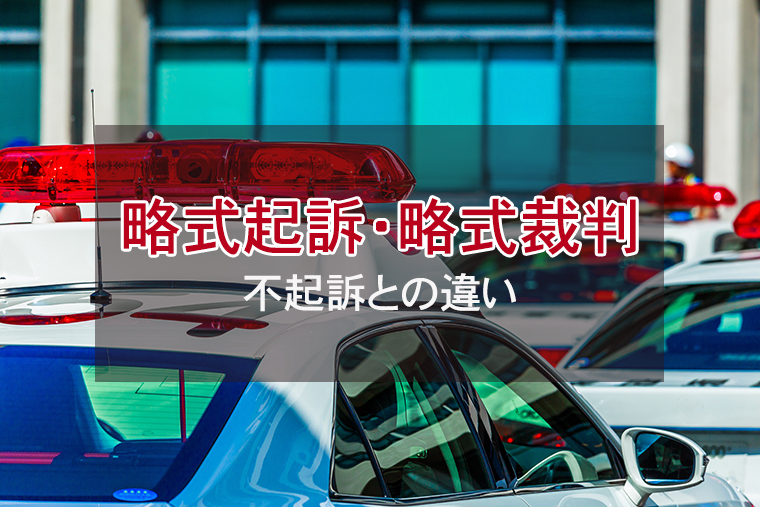
刑事事件で逮捕されてしまっても、初犯であったり比較的軽微な事件であったりするならば、正式な公開裁判を経ずに簡易な手続きで終わる「略式手続」で処理されるケースもあります。
略式手続(略式起訴・略式裁判)では、法廷が開かれることはなく、裁判所が書類上の手続だけで罰金の納付を命じます。これに同意した被疑者は、書類を受け取って罰金を支払えば刑事手続が終了します。
罰金刑でも前科はついてしまいますが、その後は原則としてその刑事犯罪について責任を追及されることはありません。
ただし、略式命令の罰金刑も有罪判決ですから、前科となります。
不起訴の獲得が難しく起訴を免れることができないような案件では、弁護士は略式手続(罰金刑)を目指して刑事弁護活動を行なっていくことになります。
この記事では、略式手続(略式起訴・略式裁判)について詳しく解説していきます。
1.略式起訴とは?
(1) 起訴について
まず、「起訴」とは、検察官が犯罪の有無とその量刑(処罰)の判断を求めて、裁判所に裁判をしてほしいと要求し公訴を提起することです。
被疑者を起訴にするか不起訴にするかを決めるのは検察官です。刑事事件を起こし逮捕されてしまった後でも、検察官に対し良い情状(被害者に被害弁償をしたか、十分に反省しているかなど)があることを正しく主張することができれば、起訴・不起訴の結果は変わります。
検察官が行う「起訴」には、①正式裁判、②略式裁判、③即決裁判手続という3種類があります。
なお、①正式裁判において、公開の法廷で行われる刑事裁判のことを「公判」といいます。
(2) 略式起訴の内容
略式起訴は「略式命令請求」とも言われ、法廷が開かれることはなく、簡易裁判所が書類上の手続だけで罰金または科料の刑罰を課す裁判手続です。
こうして開かれる略式裁判は簡素な手続きで終了するため、被告人の肉体的・精神的な負担が少なくて済みます。また、検察庁・裁判所にとっても、人的・物的・時間的なコストを抑えることができます。
このような一連の起訴手続きを「略式手続」と言います。
略式命令請求が可能なのは、比較的軽微と言える刑事犯罪です。
より具体的には、「簡易裁判所の管轄に属し、100万円以下の罰金又は科料を科し得る事件」であり、かつ「略式起訴に関して被疑者に異議がないこと」が前提になります。
2.略式手続の流れ
これまでにご説明した通り、略式手続は正式裁判等よりも簡易的に手続きが進みます。
被疑者としては、略式手続について検察官に同意をすれば、あとは後に罰金を納める以外に何もすることはありません。
(1) 被疑者に意義がないかどうかを確認する
略式起訴は、正式裁判よりも被疑者にとってのデメリットが少ない手続きです。
しかし、犯罪事実を争いたい場合や、そもそも無罪を主張したい時など、被疑者が略式手続に異議を持つこともあるでしょう。
よって、検察官は簡易裁判所へと略式命令請求をする前に、被疑者に対して略式手続について説明し、略式手続を受けることに異議がないかどうかを確認しなければなりません(刑訴法461条1項)。
正式裁判で争うこともできますので、略式裁判に納得ができないならば、これに同意しないようにしましょう。
略式手続に異議がないならば、被疑者は「略式請書」に署名・指印をします(刑訴法461条の2)。
(2) 検察官が裁判所に略式命令を請求する
検察官は、上記の「略式請書」の他に、「起訴状」「科刑意見書」、その他の証拠物などをまとめて簡易裁判所に提出し、略式手続を要求します。
簡易裁判所は、検察官からの書面や資料を調査・審理し、14日以内に略式命令を発するかどうかを判断します。
中には、簡易裁判所が略式命令を発さずに、通常の公判手続きを行うことになるケースもあります。
あまりないケースですが、例えば、「現状の証拠で罰金刑と判断するのは早計であると思われる場合」や、「そもそも公訴時効が完成しているため、免訴すべきと考えられる場合」「事案が複雑であると考えられる事件であるため公判が相当であると判断された場合」などが挙げられます。
被疑者が身体拘束されている(身柄事件の)場合は、略式手続が終わり次第留置場から釈放されます。一方、在宅事件ならば略式命令請求から半月前後で自宅に略式命令書が届きます。
(3) 罰金の支払い
釈放された被疑者は、決められた期間内に罰金を検察庁指定の方法で納付しなければなりません。
通常は、一括で検察庁に直接納付するか、検察庁が指定する金融機関に送金することになるでしょう。
仮に期間内に罰金刑を支払わずにいれば、財産について強制執行をされることになります。
強制執行をかけられるような財産がなければ、せっかく略式起訴になったにも関わらず刑事施設内の労役場に留置され、実刑と同じように労働を行うことになります。労働の期間は、罰金は2年以下、科料は30日以下という期限内で裁判官が決めますが、実務では1日5,000円で計算する例が多いです。
3.略式起訴を目指すためにするべきこと
前科・前歴があるケースや、犯行態様が悪質であるケース、罰金刑があるものの比較的重い犯罪を起こしてしまったケースでは、不起訴の獲得が難しいと考えられることもあります。
そのような場合でも、公判請求を避けることができれば、被疑者は起訴となっても裁判を受けることなくすぐに釈放されます。早期に釈放がされ、実刑を免れることができるのは大きなメリットがありますので、略式起訴を目指して情状を良くすることが大切です。
不起訴や略式起訴を目指すためには、(個人が被害者の場合には)被害者との示談を成立させるのが最も効果的です。
被害者との示談が成立すれば、それは仮に起訴を免れない案件であっても良い情状として評価されます。刑法66条では、「犯罪の情状に斟酌すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」とされているのです。
よって、被害者と示談ができれば、示談ができなかったケースに比べて、略式命令請求(罰金)にとどめるのも相当であると検察官が判断してくれる可能性が高くなるでしょう。
仮に被疑者と示談ができなかったり、被疑者が存在しない犯罪事件である場合は、贖罪寄付・供託といった方法も有効です。
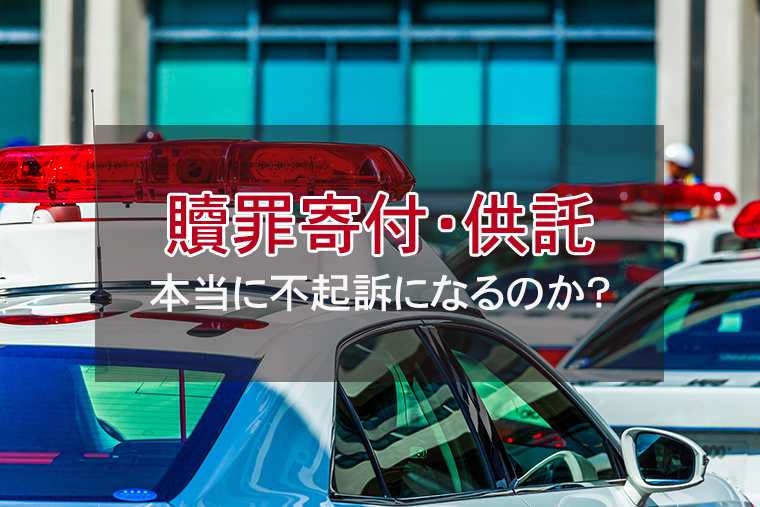
[参考記事]
贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?
他にも弁護士は、被疑者の家族など信頼のおける身柄引受人を確保し、今後の監督を誓約した「身柄引受書」を検察官に提出すると共に、本人の反省が真摯で再犯の危険性がなく、裁判は不要であることを主張するなどします。
なお、示談が成立しなかった、事件内容が悪質である、そもそも罰金刑がない犯罪であるなど、あらゆる要素により公判請求となってしまった場合は、できる限り軽い刑(執行猶予の獲得など)を目指して活動することになります。
万が一公判請求となってしまった際、弁護士が引き続き示談を試みることはもちろんですが、被告人質問、情状証人の準備などのために、ご依頼者様やそのご家族にもご協力いただくことになります。
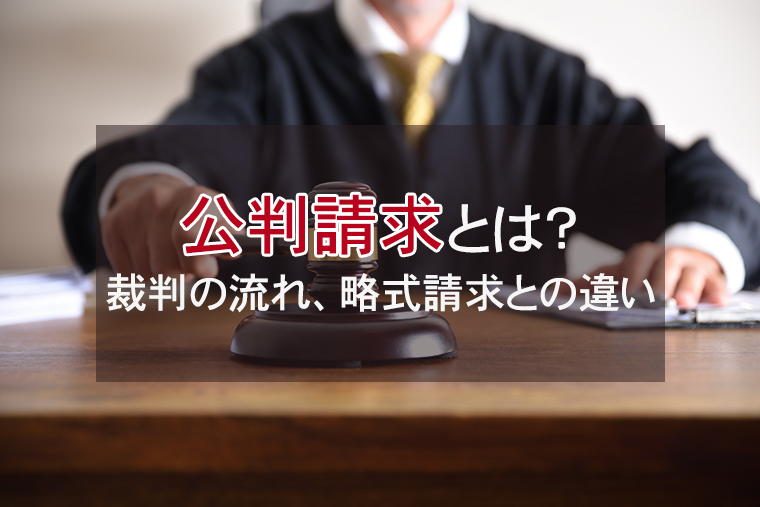
[参考記事]
公判請求とは?裁判の流れ、略式請求との違いを解説
4.略式命令に不服がある場合の対応
例えば、略式手続自体には同意したものの、略式命令で出された罰金額等に不服があるケースもあるかもしれません。
その場合、告知を受けた日(=略式命令謄本を受け取った日)から14日以内であれば、略式命令を出した簡易裁判所に対して書面で正式裁判を請求することができます(465条1項)。
刑事裁判では、証拠をもとに法的な論点で争わなければなりません。
一般の方が自力で裁判を進めることは不可能とも言えますので、必ず刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
公判で争った結果有罪判決となれば、罰金刑ではなく拘禁刑が科される可能性もあります(情状により執行猶予が見込まれることもあります)。
「裁判をすれば無罪になるのでは」と考える方もいるかもしれませんが、日本では起訴後の有罪率は99%を超えるとも言われていますので、本当に正式裁判を請求するべきかどうかは慎重に考える必要があります。
5.実刑を避けるなら泉総合法律事務所にご相談を
刑事事件では、前科を避けるためにもまずは被害者との示談交渉などで不起訴を第一に目指すことは大前提になります。
しかし、犯罪の種類や罪状、示談の難易度などによっては、どうしても起訴を免れないような事案も存在します。このような場合は、実刑を免れるために略式起訴を目指すことになります。
起訴を免れないような重大な事案では、刑事弁護に強い弁護士に弁護活動を依頼することが大切です。弁護士は、起訴され有罪判決は免れないような事件の場合でも、条件を満たすなら略式起訴による罰金刑に留めるよう求めていきます。
泉総合法律事務所の弁護士泉義孝は、様々な刑事事件の弁護経験が豊富にあり、多くの案件で不起訴処分・略式起訴を獲得しています。ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。