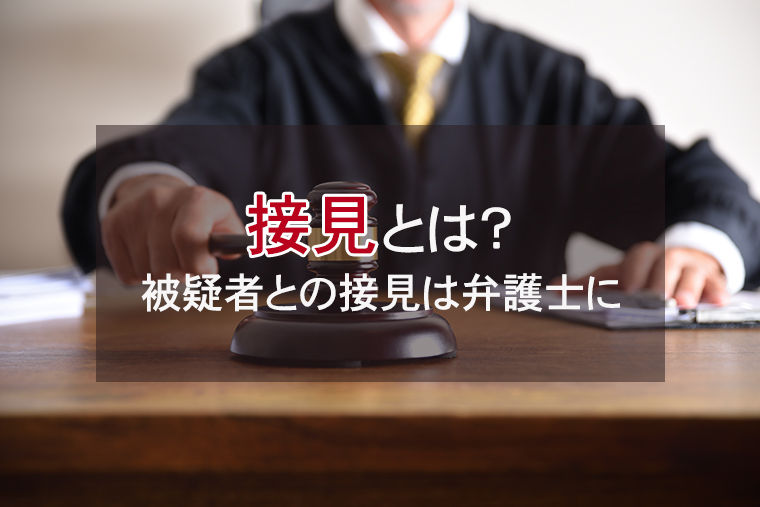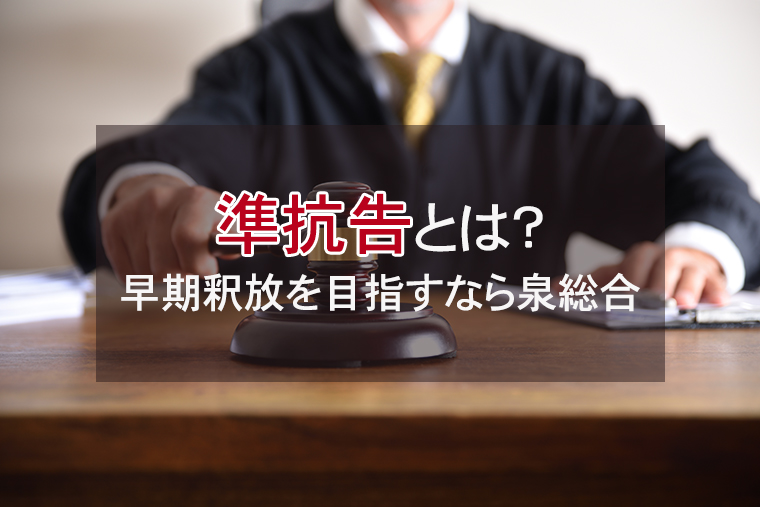刑務所の中の生活。家族・友人はどんな暮らしをしているの?
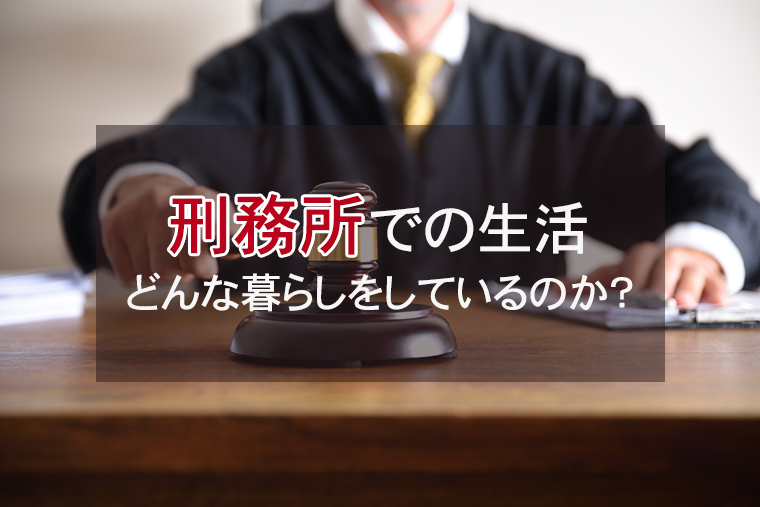
拘禁刑の有罪判決が確定すると、被告人だった者は収監されることになります。
自分の家族や友人が収監された場合、どのような暮らしをしているのか、辛い生活なのではないかと気になるのは当然です。
また、刑務所に入ると仮釈放される可能性がありますが、家族としては仮釈放の要件や仮釈放までの流れについても気になるでしょう。
この記事では、刑務所について、刑務所の生活や一日のスケジュール、仮釈放などについて解説します。
1.刑務所とは
(1) 刑務所に行く可能性がある犯罪
刑務所とは、有罪判決(拘禁刑)が確定した犯罪者が収容される施設のことを言います。
例えば、窃盗罪(刑法235条)、傷害罪(刑法204条)、不同意わいせつ罪(刑法177条)などには法定刑に拘禁刑がありますので、同罪を犯した場合には、刑務所に収監されてしまう可能性があります。
一方で、過失傷害罪(刑法209条)等の一部の罪は、法定刑が罰金のみですので刑務所行きになることはありません。
また、刑務所に送られるといっても、罪を犯した全ての者が送られるというわけではありません。
被疑者が起訴された後、拘禁刑が確定した被告人だけが刑務所に送られることになります(刑の全部の執行猶予付き判決を除く)。
実際には、被害者との示談などにより不起訴となったり、起訴されても執行猶予が付いたりする場合が多いです。
(2) 刑務所の種類
受刑者については、政令(※受刑者の集団編成に関する訓令)によって処遇指標が定められており、これに従って適当な刑務所に収監されることになります(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律86条1項)。
参考:刑事施設一覧
例えば、東京拘置所(※)はW、Aに分類されていますので、W(女子)と、A(依存症回復処遇課程の者)が収監される可能性があります。
※拘置所は、本来、有罪判決の確定していない未決拘禁者を拘束するための施設ですが、それ以外にも死刑囚や拘禁刑受刑者も入所しています。拘置所で拘禁刑の受刑者が服役するのは、死刑囚や未決拘禁者のための炊事、洗濯、清掃などの作業を担当させるためです。これを「本所(当所)執行受刑者」と呼びます。
2.刑務所での一日の生活
では、刑務所での一日の生活を見ていきましょう。
なお、受刑者のスケジュールは各施設や更生プログラムによって異なります。以下でご紹介するのは一例であるとご理解ください。
(1) 刑務所での一日の生活スケジュール
刑務所内の平日の一日は、大まかに以下のような流れで進んでいきます。
6:45 起床
部屋の掃除、洗面、人員点検7:05 部屋での朝食(15分)
朝食後、部屋を出て作業場などに向かいます。
更衣室で作業着に着替える際に、検査を行います。8:00 刑務作業、更正・教育プログラム開始
12:00 昼食時間(30~40分)
16:40 刑務作業、更正・教育プログラムム終了
作業中に運動時間が必ずあり、個別の面会や診察が行われることもあります。
作業終了となると着替えの際に身体検査が行われ、各自の部屋に帰ります。17:00 夕食
17:00〜21:00 自由時間
夕食後は自由時間となり、テレビを見る、漫画・小説を読む、手紙を書くなどができます。希望すればクラブ活動にも参加できます。21:00 就寝
朝は早く起き、夜は早く寝るという規則正しい生活のほか、平日の日中は刑務作業や更生・教育プログラムの実施をすることになります。刑務作業だけでなく、長い自由時間もあることに意外と感じた方も多いかもしれません。
施設によっては、平日も毎週一日を教育指導日として、テレビの教育番組の視聴や読書の日と指定しているので、実際の刑務作業日は週4日程度になります。
(2) 食事メニューや作業外時間の暮らしについて
次に、刑務所の中での食事や自由時間について詳しくみていきましょう。
①食事
食事は朝、昼、晩と三食きっちり出ます。
食事内容は栄養士が管理し、ヘルシーで健康的なメニューが出ます。麦入りご飯を主食とするメニューが中心ですが、おかずは和洋中とバラエティに富んでいます。デザートも定期的にメニューに組み込まれています。
刑務所の食事といえば、俗に「臭い飯」と呼ばれ、不味い食事の代名詞と思われていましたが、現在は全くそんなことはありません。
②自由時間
休日や夕食後の自由時間には、読書やテレビ、ラジオの鑑賞などが許されています。この時間に家族に手紙を書いたり、日記をつけたりもします。
必要なものがあれば、自分でお金を出して購入することも可能です。しかし、いつでも購入できるわけではなく、購入の申請をできる日は毎月決まっていますので、その日に申請を忘れると来月まで購入できないことになります。これを「自弁物品」と言います。
購入できるものとしては、衣料品(下着や靴下など)、お菓子、室内装飾品(写真立てや切り花など)、日用品(ちり紙、ノート、便せん、封筒、切手、筆記用具)、書籍(単行本、雑誌)、新聞などがあります。いずれも刑務所外より値段は高く設定されているようです。
売店が設置されている刑務所もあります。
もちろん、自由時間といっても部屋から出ることはできません。
③運動時間、入浴
健康を維持するためには、運動や体を清潔に保つことも大切です。刑期を全うするためにも、運動時間や入浴は必要となります。
運動時間については、平日30分あてられています。
運動内容としては、全員で準備体操をした後は、個々が自由に運動をすることが許されます。決まったグラウンド、体育館内で散歩、ランニング、筋トレのほか、野球やソフトボールも可能です(道具は貸与されます)。
入浴時間は、夏季に週3回、これ以外の時期は週2回と決まっています。一回の入浴は15分という短い時間となっています。
石鹸は支給されますが、自弁で購入すればシャンプーやボディソープも使用できます。
3.受刑者への差し入れ
受刑者が辛い思いをしないよう、差し入れをしたいと考える家族・友人は多いです。
次に、受刑者への差し入れについて解説します。
差し入れにもいくつかの制限がありますので、(1)差し入れの時間帯、(2)差し入れできるもの、(3)喜ばれるものに分けてご説明します。
(1) 差し入れの時間帯
差し入れを行う場合は、面会時に行うことになります。よって、差し入れの時間帯は面会可能時間に準じています(しかし、各施設により異なることもあるため、確認するようにしてください)。
また、差し入れは直接渡すことはできません。各施設にある差し入れ窓口に申し込みが必要となります。
この際、身分証明書が必要になるので、面会時に持参してください。
さらに、差し入れしたものは、受刑者に渡されるまでに早くとも数日程度の時間がかかります。
検査を行うためということもありますが、手続きに時間がかかることもあります。
(2) 差し入れできるもの
差し入れについては、その刑務所の指定業者の品物でなくてはいけないという決まりはありません。家族が普通の店で購入したものでも差し入れできます。
しかし、どんなものでも差し入れできるわけではなく、物品ごとに規格が決まっています。
例えば、「ノートのサイズはA4でとじ具に金属を使用していないものに限る」「ヒモや金具のついた衣類は差し入れができない」など制約が多く、せっかく買ってきた差し入れ品が無駄になることは珍しくありません。
したがって、基本的には、現金を除いて差し入れ業者から購入したもののみと考えたほうが安全です。
施設にある売店では、差し入れすることができる品物のカタログがあり、そこから選ぶことが可能です。
どうしても売店にない物品を差し入れしたいと思うときには、必ず事前にその刑務所に電話をして、差し入れ可能かどうかを尋ねてください。
なお、書籍類は、漫画・小説などの単行本・雑誌などを差し入れが可能ですが、新聞や何かを書き込むことを前提とした書籍(クロスワードパズルなど)は差し入れできません。
新聞については、自弁で好きな新聞を購入できる他、休み時間に無料で読むことができる新聞が置かれています。暴力団関係の記事は黒塗りされたうえで受刑者に渡されます。
また、食中毒や毒殺の危険があるので、食べ物は差し入れできません。
(3) 喜ばれるもの
受刑者の多くが最も喜ぶのは現金です。差し入れされた現金で好きなものを購入することができるからです。
刑務所内では指定業者からしか購入できないので、個々の品物の値段は一般よりも割高です。このため刑務所内では、案外、手持ちの現金が急速に減っていくのです。
したがって、現金こそ、もっとも喜ばれる差し入れです。
遠くに住んでいるためなかなか面会できないという方は、郵送での差し入れも可能です。書籍類は郵送が簡便です。現金の差し入れは現金書留で郵送できます。

[参考記事]
勾留中の生活・面会・差し入れについて
4.仮釈放とは?
(1) 仮釈放の条件
罪を犯して刑務所に入れられても、仮釈放が認められる場合があります。
仮釈放とは、受刑者の更生が見られた場合に、受刑者を刑務所から釈放する制度です(刑法28条)。仮釈放された場合、必ず保護観察に付されます(更生保護法40条。以下、同法を「法」と略記)。
刑法28条
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
「行政官庁の処分」とは地方更生保護員会による決定であり(法39条1項)、その仮釈放の決定基準は「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」という政令の第28条に具体化されています。(以下、同規則を「規則」と略記)に定められています。
規則28条
仮釈放を許す処分は、拘禁刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
仮釈放は刑期満了までとなります。
無期刑の場合、刑期満了が無いため、一生保護観察に付されることになります。
(2) 仮釈放までの流れ
刑務所に収容されると、すぐに仮釈放の判断のために必要な情報が調査されて、刑務所から地方更生保護委員会と帰住地の保護観察所へ通知されます(規則7条1項柱書)。
本人を特定するための氏名・生年月日・本籍、仮釈放の要件や期間を算定するための刑の宣告日・確定日・執行の始期・終了日、仮釈放の適否を判断するための犯行内容・共犯者や被害者の状況・生活歴・心身の健康状況・帰住予定地・引受人・釈放後生活の計画などが通知される情報です(規則7条1項各号)。
その後、仮釈放を許可するために必要な期間が経過すると、受刑者等のいる刑事施設の長が、上記規則に該当し、仮釈放の要件を充足するか否かを判断します。要件を充足すると判断した場合、仮釈放の権限を有する地方更生保護委員会に対し申出を行います(法34条1項)。
申出を受けた地方更生保護委員会が仮釈放を許すか否かを判断します。その際には、受刑者と委員の面接を実施することが必要です。これを通称「本面接」と呼びます。
実務では、これに先立ち、通称「仮面接」と呼ばれる保護観察官との面接が実施されて、仮釈放を受ける意思の確認など、予備的な調査が行われます。仮面接の実施時期は受刑者や刑期によって様々です。
また犯罪被害者等の意見を聞く場合があります(法37条1項、38条1項)。決定により仮釈放を認めた場合、仮釈放の日にちや帰住先を決定します(法39条1項、2項、3項)。
5.家族が逮捕されたら早めに弁護士に連絡を
家族が逮捕されてしまったら、誰もが動揺します。
しかし、逮捕されたら勾留請求までは3日しかありません。勾留が決定されると身体拘束が長くなってしまい、社会生活にも影響が出るため、それまでに釈放を目指すことが大切です。
また、勾留が決定した後でも、不起訴を勝ち取ることで裁判を避けることができます。
刑事裁判では、有罪判決が出る確率が圧倒的に高くなります。軽い犯罪でない限り、有罪で刑務所に収監される可能性も高くなるのです。収監されてから出所するまでの期間は長期間となります。
早いうちにご相談いただければ、裁判になってしまった場合でも執行猶予判決を目指すことができます。
刑事弁護はスピード勝負です。できるだけ早い段階で、刑事弁護に精通した泉総合法律事務所にご相談ください。