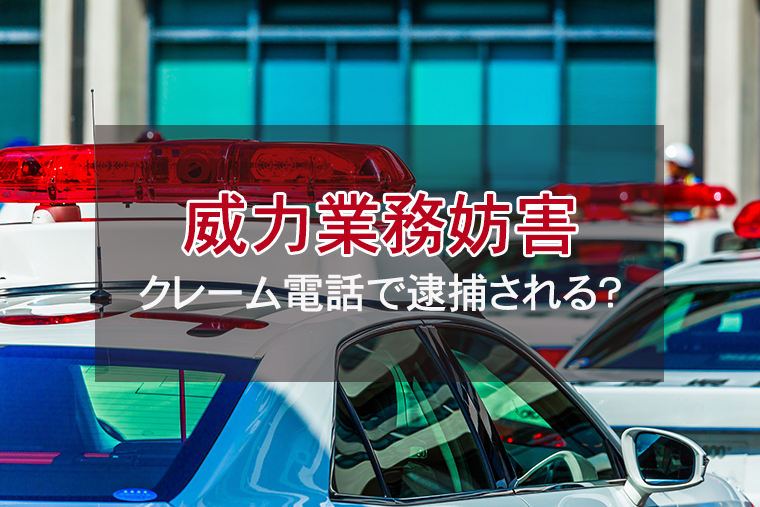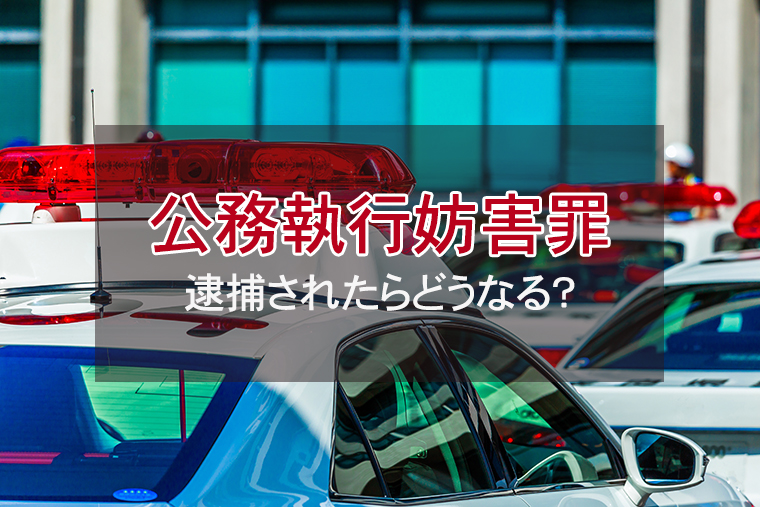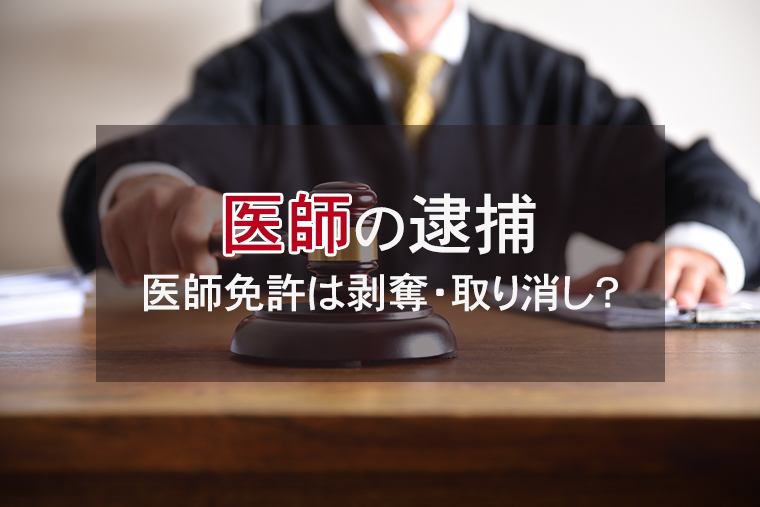不正競争防止法とは?違反した場合の刑事罰
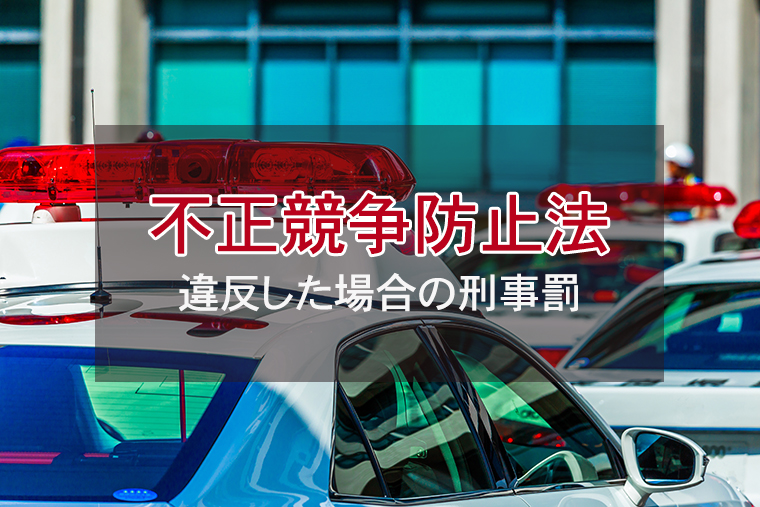
電子部品メーカーの元社員が、部品の金型データを外国メーカーにメール送信したとして、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)で逮捕されたという報道がありました(※産経新聞サイト(2025年10月22日記事)「東芝系企業から営業秘密の金型データを中国流出 元社員ら再逮捕 仲介利益700万円得る」)。
このようなデータ持ち出しなどで、個人が不正競争防止法違反に問われる刑事事件は少なくありません。
このコラムでは、近年増加している個人の不正競争防止法違反について、基本的な知識を説明します。
1.不正競争防止法とは?
不正競争防止法2条は、次の10種類の「不正競争行為」を定めています。
- 周知表示混同惹起行為(2条1項1号)
- 著名表示冒用行為(2条1項2号)
- 形態模倣商品の提供行為(2条1項3号)
- 営業秘密の侵害(2条1項4号~10号)
- 限定提供データの不正取得等(2条1項11号~16号)
- 技術的制限手段無効化装置等の提供行為(2条1項17号、18号)
- ドメイン名の不正取得等の行為(2条1項19号)
- 誤認惹起行為(2条1項20号)
- 信用毀損行為(2条1項21号)
- 代理人等の商標冒用行為(2条1項22号)
不正競争防止法の目的は以下の通りです。
(1) 経済の健全な発展のために不公正な競争行為を禁止する
資本主義社会では、事業者が経済活動を競うことで経済が拡大・発展していきます。そのためには、経済的な競争が「公正」に行われることが必要です。
もし、他者が開発した新商品・新技術、他社が長年の努力で築いたブランドを無断で使用するなどの「不公正な方法による競争」が許されるならば、事業者の正当な利益が害されるだけでなく、誰も新商品・新技術を開発する意欲、企業努力を継続する意欲を持たなくなり、経済活動は停滞してしまいます。
これでは国民経済の健全な発展は望めなくなります。
不正競争防止法とは、このような事態を防止する法律です(同法1条)。
(2) 不公正な競争行為を防止する他の法制度を補完する
もちろん、不公正な競争を防止するための法制度は他にもあります。
例えば、企業ブランドを表すロゴなどの「商標」は、商標法によって保護され、他社のロゴを勝手に自社製品に使用することはできません。
しかし、商標法の保護を受けるためには、商標を文化庁に登録する必要があり、手間もコストもかかります。
他方、商標が未登録だからといって、他社のブランドを勝手に使う行為を放置するべきではありません。
そこで、不正競争防止法では、商標登録の有無にかかわらず、他社ブランドと誤認させる行為それ自体を、「不公正な競争行為」として禁止しています。
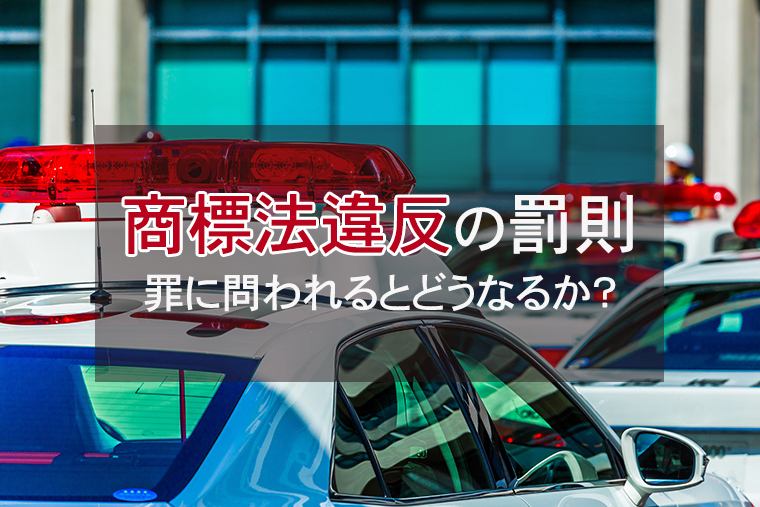
[参考記事]
商標法違反の罰則|罪に問われるとどうなるか?
また、他人の権利や利益を害する行為は、民法の不法行為制度(民法709条)によって損害賠償請求を受けることになります。しかし、これは事後的に損害賠償を請求することができるだけで、権利・利益を侵害する加害行為を事前に予防することは原則として認められておらず、権利保護として不十分な面があります。
そこで、不正競争防止法では、不公正な競争行為を事前に差し止めることが認められています。
さらに、技術や営業ノウハウなど、経済活動上有益で重要な情報は、それ自体が企業の財産であって、これを無断で取得したり流出させたりする行為も不公正な競争行為です。
しかし、伝統的に物理的な有体物を財産として保護してきた刑法の規定では、これら情報を保護するには十分ではありません。
そこで不正競争防止法は、このような営業秘密などの情報を侵害する行為について、とくに刑事罰を定めています。
このように、不正競争防止法は、不公正な競争行為を禁ずるために、他の法制度では不十分な部分を補う役割を担う法律と言えます。
2.一個人が不正競争防止法違反で告訴されるケース
不正競争防止法が定める10種類の不正競争行為は、これを行った企業の法的責任を問われる場合だけでなく、その行為を行った個人が法的責任を問われる場合もあります。
(1) 退職時に会社のデータ・営業秘密を持ち出した
退職にあたって、会社のデータ・営業秘密を勝手に持ち出す行為、「不正の手段」で取得する行為は、営業秘密の侵害行為として不正競争行為に該当する危険があります。
「営業秘密」とは、①秘密管理性(秘密として管理されていること)、②有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること)、③非公知性(公然と知られていないこと)を満たす情報を指します。
「不正の手段」とは、窃盗・詐欺・強迫といった刑法上の犯罪に該当する手段はもちろん、その他、社会通念上、犯罪と同等の強い違法性があると判断されるような公序良俗に違反する手段まで含まれます。
不正の利益を得る目的や会社に損害を加える目的で、詐欺・暴行・脅迫・窃盗・施設侵入・不正アクセスなどにより営業秘密を取得した場合は、個人につき10年以下の拘禁刑もしくは2000万円以下の罰金刑が科され、この両方の刑が併科される場合もあります(21条1項1号)。
(2) 社内の機密データを同業他社に売却した
営業秘密を「不正の手段」で取得する行為だけでなく、こうして取得した情報を第三者に開示する行為も営業秘密の侵害行為となります。
不正の利益を得る目的や会社に損害を加える目的での開示行為には、個人につき10年以下の拘禁刑もしくは2000万円以下の罰金刑となり、両方が併科される場合もあります(21条1項2号)。
【裁判例】
通信教育会社でシステム開発を担当した派遣社員が、会社の顧客データ(約3千万件)をコピーして持ち出し、ネットにアップロードした事案で、派遣社員は、懲役2年6月、罰金300万円となりました(東京高裁平29年3月21日判決・ベネッセ事件)
(3) 限定情報へログインしてデータをコピー・USBに保存した
「限定提供データ」を、窃取・詐欺・強迫等の不正の手段によって取得する行為、取得したデータを、自ら使用したり、第三者に開示したりする行為等は、不正競争行為として禁止されています(2条1項11号~16号)。
「限定提供データ」とは、①業として特定の者に提供する情報として電磁的方法で、②相当量が蓄積され、③管理されている、技術上・営業上の情報をいいます。なお「営業秘密」に該当するものは除きます。
たとえば、気象データ・地図データ・走行データなど、蓄積したデータを複数企業が共有して活用するケースです。
不正競争防止法は、限定提供データの不正取得行為に対して、特別な罰則は定めていません。しかし、限定提供データの不正取得行為が窃盗・詐欺・強迫など刑法に違反する場合や、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する場合は、当該法律の定める刑事罰が適用されます。
(4) ある会社の商品について根拠のない噂を流す
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為や流布する行為は、不正競争行為として禁止されています(2条1項21号)。
「競争関係」とは、双方の営業につき、その取引者を共通にする可能性があることを指し、現実に競争しているかどうかは問いません。
不正競争防止法は、信用毀損行為に対する特別の刑事罰を定めていません。しかし、刑法上の信用毀損罪や業務妨害罪が適用され、処罰される危険があります(刑法233条:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑)。
3.不正競争防止法で告訴された場合の対処法
個人が不正競争防止法違反の被害を受けたと称する企業などから刑事告訴を受けた場合、まずは、刑事手続の専門家である弁護士に相談し、刑事弁護を依頼することがベストです。
(1) 構成要件を満たすかどうかを検討する
不正競争防止法は、一般の方には馴染みのない法律であり、また、その内容は他の刑罰法規と比較しても専門性が高く、複雑・難解な法律です。
不正競争防止法違反だと指摘されたとしても、刑事罰を受ける行為に該当するか否かは、法律専門家の目で厳密に検討してなくては判断がつきません。
つまり、弁護士に法的判断を相談することは必須なのです。
(2) 被害者との示談交渉を行う
仮に不正競争防止法違反の事実があった場合でも、被害企業側と示談交渉を行い、示談をまとめることができれば、刑事告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
営業秘密侵害罪は刑事告訴が不要な非親告罪ですが、示談成立による刑事告訴の取り下げがなされれば、検察官による不起訴処分(起訴猶予処分)を勝ち取ることができる可能性が高まります。
示談交渉は刑事事件に強い弁護士にお任せください。
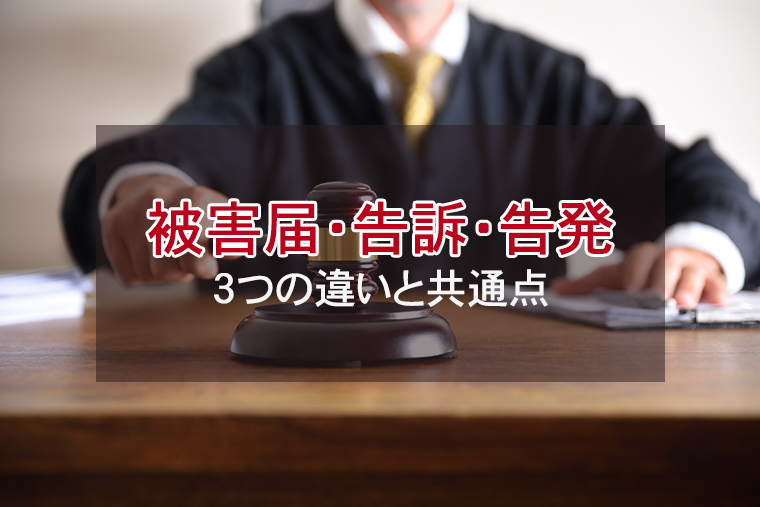
[参考記事]
被害届・告訴・告発の違いとは?取り下げたら不起訴になるのか
4.まとめ
不正競争防止法では、個人の行為であっても同法違反として告訴され、処罰される場合があります。
刑事処分を回避するために、刑事事件に注力している弁護士への依頼をおすすめします。
お困りの方がいらっしゃいましたら、泉総合法律事務所の弁護士・泉義孝にご相談ください。