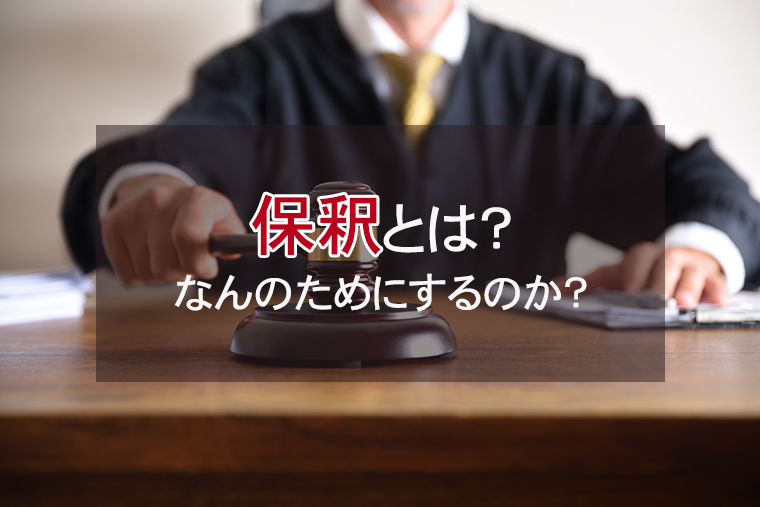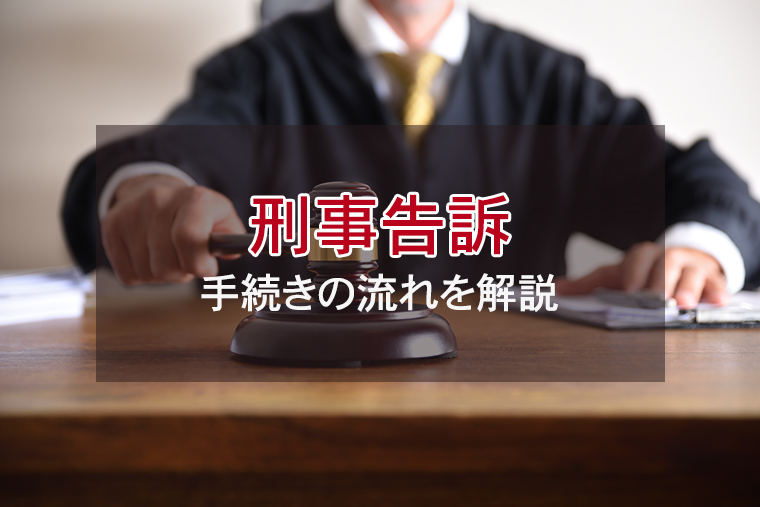著作権法違反の罰則|どこからが犯罪になるのか?
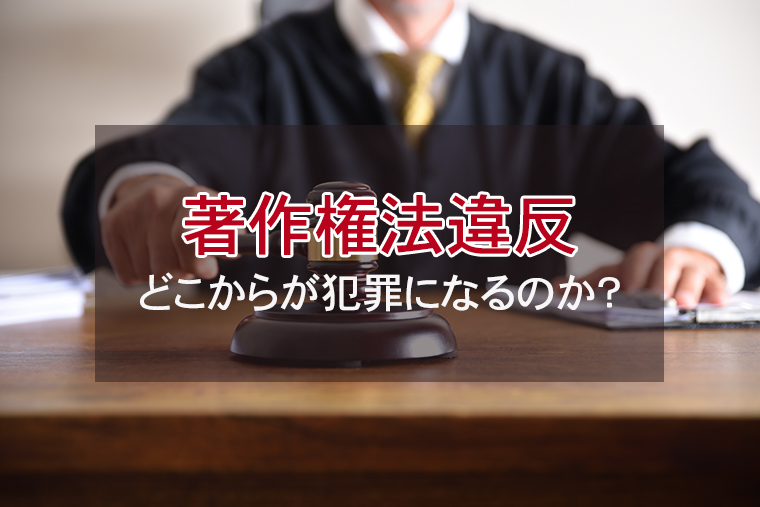
インターネットの普及により、音楽や映像、画像などは簡単にアップロード・ダウンロード・共有等ができるようになりました。
しかし、それと同時に著作権法違反のリスクも身近なものとなっています。「これくらいなら大丈夫」と思っていた行為が、実は重大な犯罪に該当する可能性があります。違法ダウンロード、海賊版の販売・購入、無断転載など、実は日常的に行われがちな行為の中にも犯罪に該当するものが多数存在するのです。
著作権法違反は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い刑罰が科される場合もあります。
どのような行為が著作権法違反として問題となるのか、正しい知識を身につけることが重要です。
著作権法違反として検挙されてしまった方や、著作権違法に該当する行為をしてしまったのではないかと不安に感じている方は、是非こちらのコラムをご覧ください。
1.「著作権法違反」について
(1) 著作権とは
「著作権」は、「著作物」に対する著作者の独占的な利用権です。
「著作物」とは、文芸や学術、美術や音楽などの文化的なジャンルで、人間の思想や感情を創作的に表現したものです。たとえば、本や写真、絵画や劇、音楽などが著作物に該当するので、それらの作者には著作権が認められます。
著作権は、特に登録などの手続をしなくても、作品を作ると同時に著作者に発生します。
また、著作物かどうかを判断するとき、文化的なもので人の思想や感情を創造的に表現しているかどうかが問題となるため、作品の巧拙は関係ありません。子どもが作ったものでも、初心者が作った稚拙なものであっても、有名人が作ったものと同じように著作権が認められるのです。
これらの著作物を勝手に公衆に発信したり、改変したり、コピーしたりすると、それだけで著作権法違反となってしまいます。
例えば、YouTubeの動画は、一般の人が簡単にアクセスできて日常的に楽しんでいるものですが、これも利用方法によっては著作権法違反になってしまうことがあります
YouTubeの動画には、動画作成者の著作権が認められます。著作者には、著作物に対する独占的な使用権が認められるので、YouTubeに上げられている他人の動画を勝手にダウンロードしたり、他人の作った動画を勝手にYouTubeに上げたりすると、著作権法違反となってしまう可能性があるのです。
【判例集】商標法・著作権法違反事件
(2) 著作権法違反のリスク
著作権法違反となると、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。
差し止め請求
他人の著作物を勝手に使っていると、著作者から「差し止め請求」される可能性が高いです。
たとえば、他人が作成した動画や画像を勝手にネット上にアップしていたら「掲載を辞めるように」求められます。他人の制作したイラストをSNSなどのアイコンにしているケースも同様です。
損害賠償請求
差し止め請求をされるだけではなく、違法に著作物を利用したことによって著作者が受けた損害について、損害賠償請求をされる可能性があります。
これは後述する刑事責任による罰金とは別のもので、民事上の責任(民事事件としての不法行為に基づく損害賠償義務)ということになります。
刑事責任の追求
著作権侵害は犯罪行為です。
著作権や出版権、著作隣接権の侵害の場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑となります。
氏名表示権や公表権などの侵害の場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などとなります。
これらの懲役と罰金は、併科される可能性があります。
また、法人が著作権(著作者人格権以外)を侵害した場合、3億円以下の罰金刑が科されます。
さらに、平成24年10月に著作権法が改正されて、「私的使用目的」であっても、対象の動画などが無断でアップロードされていることを知っており、かつ有償で提供されているものであると知っていた場合、そのサイトからダウンロードしただけで犯罪が成立することになりました。
この場合の刑罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金となっています。
2.違法アップロード・ダウンロードの具体例
では、具体的にどのような行為が著作権法違反となる可能性があるのでしょうか?
(1) 違法アップロード(公衆送信権の侵害)
違法アップロードとは、著作権者の許可なしに他人の著作物をネット上にアップすることです。
インターネットに上がっている画像や動画は、漏れなく作成者の「著作物」です。
そして、その著作物をネット上にアップする行為は、著作権の権利の一種である「公衆送信権」に該当します。
画像や動画をインターネット上にアップして良いのは、公衆送信権を持つ著作権者のみです。著作権者に許諾を得ずにアップすると、著作権者の公衆送信権侵害となり、著作権法違反が成立します。
著作権者の許可なしに違法アップロードをする例としては、以下のようなケースがあります。
- XやYouTube等のSNS上に、自分の好きなイラストレーターのイラストやアーティストの動画を投稿した
- インターネット上に、好きなテレビドラマや映画のワンシーン動画を投稿した
- 自作動画のBGMとして、好きなアーティストの曲を流した
- 自作動画の中で好きなアニメ・漫画のイラストを利用した
- 自分が見ているドラマの宣伝をしたくて、10秒程度のドラマの動画を使った
- 尊敬しているイラストレーターの画像を勝手にSNSのアイコンに利用した
- 保存した画像や動画を自分のSNSやブログなどで再アップロードした
以上のような行動はすべて著作権法違反です。
たとえ「自分で購入したCDやDVDを使った」「自分で購入した画集からスキャンした」という場合であっても、利用は許されません。
さらに、「○秒以内ならOK」「編集・加工を加えているから大丈夫」ということもありません。
そもそも著作権の内容として「同一性保持権」や「翻案権、翻訳権」があるので、勝手に改変すること自体が著作権法侵害となります。
(2) 違法ダウンロード
SNSや動画公開サイトでは、他人がアップロードしている画像・動画を自分のパソコンやスマホなどに簡単にダウンロードすることができます。
しかし、このとき、ダウンロードしただけで「著作権法違反」となってしまうおそれがあります。
ダウンロードが違法と評価されるのは、「(他人の著作権を侵害して)違法にアップロードされたもの」あるいは「有償で提供されているコンテンツ(本来はお金を支払わないと見られないドラマや映画、お金が必要な音楽など)」を、「違法と知りながらダウンロードすること」です。
違法ダウンロードが犯罪となる典型例は、違法にアップロードされているアーティストの楽曲や、映画、ドラマ、テレビ番組などを勝手にダウンロードしてしまうケースです。
また、合法的にアップされた画像や動画でも、勝手に保存・ダウンロードすると、著作者の「複製権」を侵害することになってしまいます。
ただし、複製権については、「私的利用目的」の場合、違法にはなりません。収益などを得ず、自分や家族だけで楽しむためなどの場合であればダウンロード可能です。
しかし、YouTubeなど一部のサイトでは、規約上で基本的にすべての動画をダウンロードすることを禁止していることもあります。
たとえ合法的に投稿されている画像や動画であっても、著作権者が許可をしている場合を除き、勝手にダウンロードすることは極力避けた方が安全と言えるでしょう。
また、ダウンロードした動画を販売したり人に貸したりすると、著作権法違反となります(※合法的にダウンロードした動画であっても違法となります)。
3.著作権法違反で逮捕されたらどうなるのか
では、仮に著作権法違反をしてしまい、警察に逮捕されたらどうなるのでしょうか?
(1) 警察の捜査が開始する
著作権侵害が発覚するきっかけは様々ですが、多くは権利者からの告発です。著作権侵害罪は一部を除き親告罪のため、著作権者による告訴が必要です。
(※告訴の前に、権利者は発信者情報開示請求を行い、加害者の身元を特定します。)
告発を受けた警察は捜査を開始し、容疑が固まると逮捕状が発付されます。
逮捕後は、罪状などにより身柄事件とするか、在宅事件とするかで分かれます。
2018年12月30日から、著作権侵害罪は一部非親告罪化されました。非親告罪の対象となるのは、以下の3つの要件を全て満たす場合のみです。
①対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
②有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
③有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が、不当に害されること
例:漫画、小説、映画などの海賊版の販売・配信行為
身柄事件の場合
身柄事件では、逮捕後に引き続き勾留されて、身体拘束をされたまま捜査が行われます。
著作権侵害をしてしまった場合、比較的重大な事案や、逃亡・証拠隠滅のなどのおそれがあったら、身柄捜査になる可能性があります。
身柄捜査になった場合には、逮捕〜勾留までが最大3日間、勾留期間が最大20日間になるので、最大23日間留置所で身柄拘束されます。
その間に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
在宅事件の場合
在宅事件とは、逮捕後に被疑者が釈放され、普段通りに自宅で過ごす状態で捜査が進められる方法です。
在宅事件になるのは、比較的軽微な事案、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合などです。
在宅捜査になった場合、捜査に期限がないので、いつ検察官が処分を決定するかが明らかになりません。
検察官から呼び出しを受けて取り調べが行われ、時が来たらこれまでの捜査結果により検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
(2) 起訴・不起訴の判断
著作権法違反を含め、刑事事件となった場合には、起訴されるか不起訴になるかは非常に重要です。
というのも、刑事事件で起訴されるとほとんどのケースで有罪判決となってしまうからです。
有罪になると、たとえ罰金刑でも一生消えない前科がつきますので、はじめから不起訴処分を受けることが有効な対策方法となります。
著作権法違反で不起訴になるための一番の方法は、「被害者との示談」です。
著作権法違反は原則として親告罪なので、示談が成立して被害者が刑事告訴を取り下げれば、確実に不起訴になります。
また、著作権法違反の場合、被害者は多くのケースで刑事訴訟とは別に損害賠償請求をしてきます。特に、刑事裁判などが終わった後に民事裁判を提起するということもあり、こうなると加害者側の負担がかなり重くなります。
そうであれば、刑事事件係属中に示談をして、損害賠償をめぐる紛争を解決しつつ不起訴処分を獲得できた方が、加害者にとってもメリットが大きいです。
とは言え、加害者側が自分で被害者と示談交渉をしようとしてもうまくいかないことが多いので、お困りの際には弁護士にご相談ください。
→示談したい
4.著作権法違反の相談も泉総合法律事務所へ
ご自身の好きなイラストや動画などを利用するとなると、誰しもまさか刑事事件になってしまうとは考えないでしょう。
しかし、被害者からしてみると「自分の作品(著作物)を勝手に使われている」ことになり、犯人を特定して刑事告訴に及ぶこともあります。
このように、思わぬ行為が犯罪に当てはまり、逮捕されてしまう事例は誰にでも起こり得ることです。
著作権法違反以外でも、刑事事件で被疑者になってしまったら、お早めに刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。