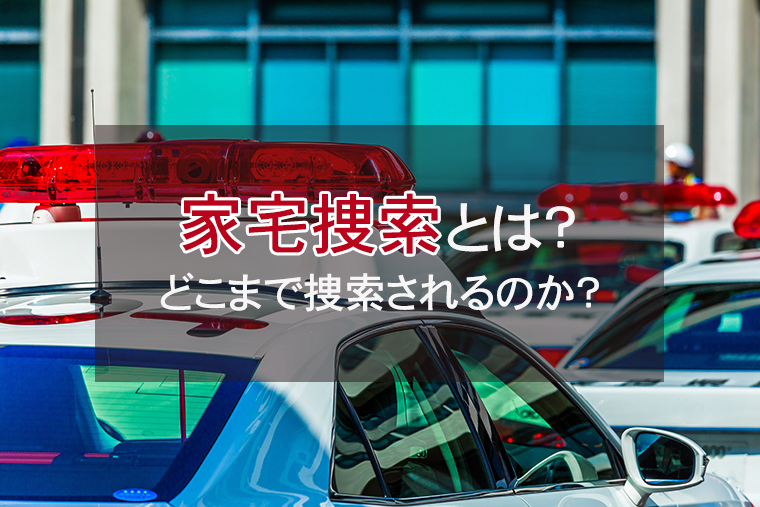警察による取り調べの対応策を弁護士がアドバイス
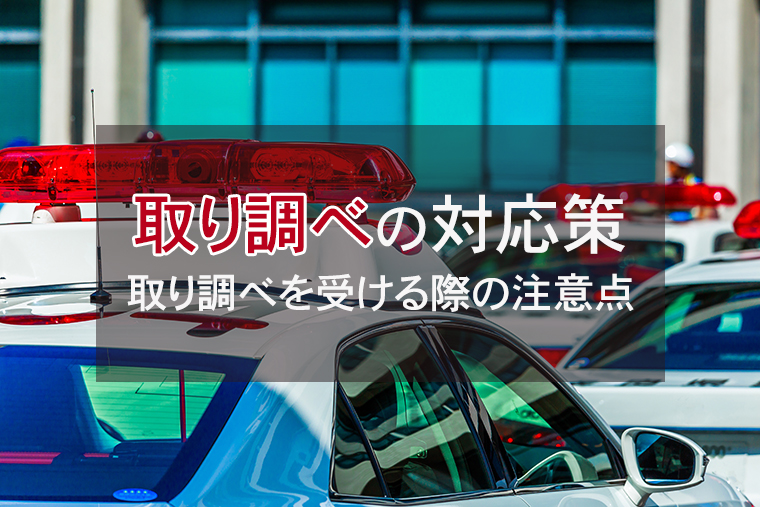
刑事事件の「取り調べ」は、刑事ドラマなどで得るイメージとは往々にして異なります。
今回は、刑事事件を犯してしまい警察から取り調べを受ける被疑者の方、またはその家族の方に向けて、警察の取り調べの実情について簡単に解説した後、取り調べを受ける立場になってしまった場合の対応(取り調べの際に気をつけるべきこと、弁護士が行ってくれる取り調べに関する弁護活動)についても解説していきます。
1.「取り調べ」とは?
(1) 取り調べでは何を聞かれるか
取り調べとは、捜査機関が、被疑者に対して出頭を求めた上、事件の内容について聴取することです。当事者の取り調べは、警察・検察の重要な捜査活動と言って良いでしょう。
取り調べの結果は供述調書に記載され、後に刑事裁判で使用されます。
取り調べでは、「事件について関与しているか」「その時間何をしていたのか」等を聞かれます。
なお、逮捕後であっても、取り調べ中は手錠は外されます。
取り調べの時間は、単純な事件であり、被疑者が自白しているような場合でも、短時間で終わらないことが通常です。
取り調べとは、①取調官が質問し、被疑者が答える問答を繰り返し、②取調官がメモした内容を調書に文章として起こし、③他の証拠資料と付き合わせて内容を吟味し、捜査側からみて問題がないと判断したうえで、④被疑者に文章を読み聞かせ、⑤内容に間違いがないと確認させて署名・指印をさせることが通常の流れですから、1回あたり1〜2時間で済むことはまずありません。
丸1日、短くとも半日はつぶすことになることが普通です。
なお、逮捕・勾留され、その事件の担当警察署の留置場に拘束されているケースでは、取調室までの移動に時間も手間もかかりませんので、頻繁に取り調べの機会を設けることが可能なため、1回1~2時間で調書作成まで行わない取り調べを細切れに繰り返すこともあります。
しかし、在宅事件や事件の担当でない警察署の留置場に拘束されている場合は、上のように1度の取り調べに時間をかけることが一般的というわけです。
(2) 警察と検察の取り調べの違い
警察官も検察官も捜査権限を持っています。
警察官は、被疑者の身柄を拘束してから48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致し、その後、被疑者の身柄を受け取った検察官も取り調べを行います。
警察官と異なって、検察官は法律家です。検察による取り調べは、警察による取り調べ内容のチェックをする機能以外にも、事件を裁判にかけて有罪判決を得ることができるか否かという厳密な法律的観点から捜査を実施します。
したがって、警察が取り調べ済みで既に供述調書が作成されている内容であっても、検察官は独自に取り調べた上で、自らも供述調書を作成します。
【警察と検察の供述調書の違い】
供述調書の違いは、公判(裁判)の場で明らかになります。
被害者・参考人の供述内容を録取した供述調書は、原則として証拠として法廷に提出することはできません(刑訴法321条1項柱書、326条1項)。もっとも、一定の条件を満たせばどちらの供述調書も証拠とすることが許されるのですが、その例外を許す条件が、検察官調書よりも警察官調書の方がはるかに厳しいのです(刑訴法322条1項2号及び3号)。これは公益の代表者(検察庁法4条)である検察官の作成した調書の方が、警察官調書よりも信用性が高いと評価されていることを示します。
(3) 取り調べは拒否できるか
逮捕・勾留されていない限り、取り調べは拒否ができます。
「取り敢えず一度拒否してから、弁護士に相談した上で取り調べに応じる」ということも可能です。また、警察や検察から出頭要請があり、事前に日時を調整してくれます。
ただし、取り調べにまったく応じないと、罪証隠滅のおそれや逃走のおそれがあると判断されてしまい、逮捕状を請求されるリスクも0ではありません。
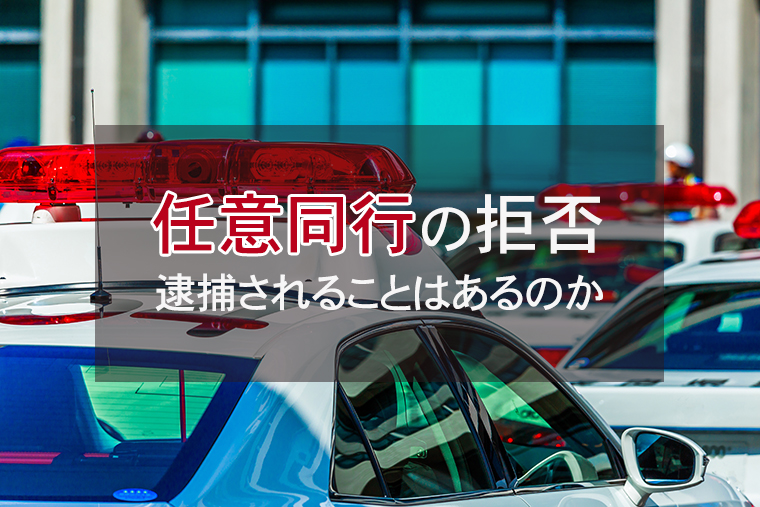
[参考記事]
任意同行は拒否できない?逮捕されることはあるのか
一方、逮捕後の被疑者は取り調べを拒否できない運用になっています。
そのため、勾留施設から取調室まで連れていかれること、取調室に留まって取り調べを受けることまでは受忍せざるを得ないのが現状です。
もっとも、後述のとおり黙秘権がありますから、取り調べに対して供述する義務はありません。
2.取り調べを受ける際の注意点
(1) 供述調書の内容をよくチェックする
供述調書は、取り調べ対象者が話した内容を逐一記録するものではなく、話を聞いた警察官・検察官が、聞いた内容を取捨選択したうえで作文したものです。
したがって、被疑者の有罪を立証し不利な情状を明らかにする事情だけが記載されるなど、被疑者に有利な事情が記載されていないことが多いものです。
そのような場合は、有利な事情も記載してくれるよう主張し、聞き入れてくれないときには調書への署名・指印を拒否することが有効です。
供述者の署名・指印のない調書は、本当に供述者の話した内容どおりに記載されているか否かが担保されないので、原則として裁判の証拠とすることはできません。調書を作成する際に、自分の言っていないこと、ニュアンスとして間違っていることがあれば訂正してもらいましょう。
また、調書に記載してもらえない有利な事情は、できるだけ早い段階での接見時に弁護士に伝えておくことが重要です。弁護士がその内容を書面化しておくことで、後の公判で有利な証拠として用いることができる可能性があります。
なお、1つの事件で供述調書が1つだけということはありません。
通常、供述調書は「身上調書」という、どこで生まれて、学校や仕事関係、家庭関係について記載した履歴書のような供述調書と、それ以外の「事件に関する供述調書」の2種類に分けることができます。身上調書以外の調書は、必要に応じて何通でも作成されます。
(2) 黙秘権の行使
被疑者には、憲法上、黙秘権が保障されています。よって、刑事手続きがいかなる段階にあろうと、質問に答えるか否かは自由です。
取り調べにおいて一切の供述を拒否することが可能ということです。
もっとも、実際には、黙秘権を主張しても、「ああそうですか」で済むはずがありません。黙秘しても取調室から退出することは許されませんし、捜査官は被疑者が犯罪を犯したことを前提としていますから、黙秘権を行使された程度ではあきらめず、何度も同じことを聞いてくる可能性があります。
当然、対応も苛烈になるため、これに耐えて黙秘を続けることはかなり強靱な精神力が必要です。
それでも、虚偽の自白は後に自己の首を絞めることになるので、絶対にしてはいけません。
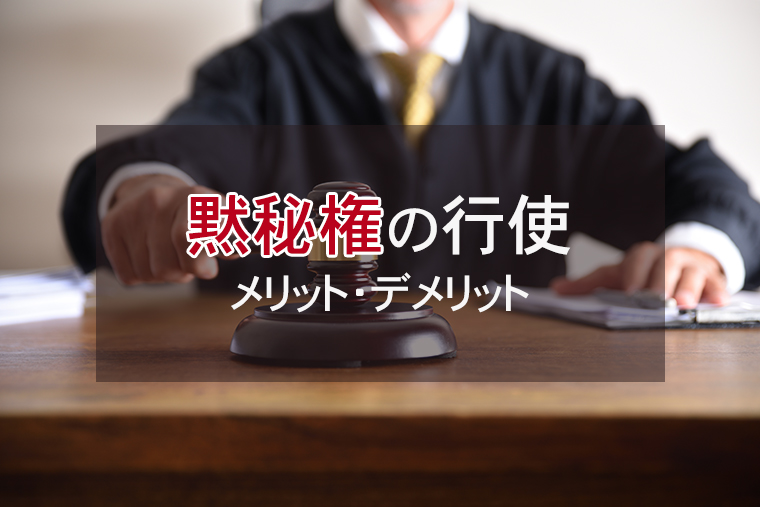
[参考記事]
黙秘権とは?黙秘権を行使するメリット・デメリット
(3) 被疑者ノートの作成
逮捕・勾留後に、弁護士に被疑者ノートを差し入れてもらい、被疑者本人が取り調べ状況を明確に記録することも有効です。
被疑者ノートとは、日弁連が作成・配布しているもので、身柄を拘束された被疑者が、その日の取り調べ状況などを日々記録しておくための専用の日記です。もちろん、このような記録は一般の市販ノートでも構いませんが、記録のし忘れを防止し、誰でも重要な事項を漏れなく記載できるよう詳細な記入欄が設けられている他、被疑者の権利や刑事手続について知っておくべき知識、アドバイスなどが記載されていますのでお勧めです。
必要であれば公証役場にて確定日付をとり、証拠を保全しましょう。
このようにして取り調べの証拠を残しておくことで、後の裁判で、違法な取り調べがあった場合はその内容の真実性を争うことが可能となります。また、こういった証拠の保全活動それ自体が違法な取り調べに対する牽制にもなります。
3.弁護士の取り調べに関する弁護活動
では、弁護士はどのような弁護活動を行ってくれるのでしょうか。
(1) 取り調べに向けてアドバイスをくれる
取り調べを受ける方は、「何を聞かれるのかと」不安になると思います。
刑事事件弁護に強い弁護士を弁護人とすれば、取り調べへの受け答え方法以外にも、事案に応じて黙秘権を行使するべきかどうか、行使した場合のメリット・デメリット、否認を続けた場合と自白した場合それぞれの処分の見通しなどについて、本人の利益になるよう多くのアドバイスをくれます。
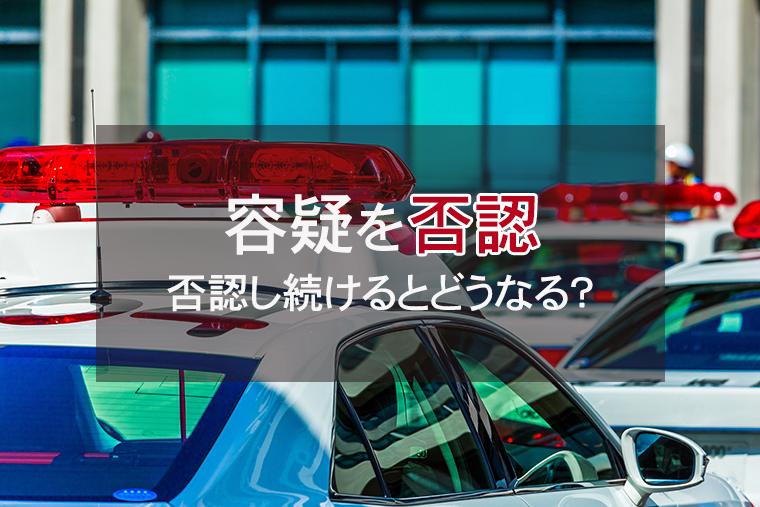
[参考記事]
刑事事件で容疑を否認し続けるとどうなる?
(2) 違法な取り調べの阻止
「罪を認めないと激しく恫喝されるのではないか?」「自白をするまで取り調べが終わらないのではないか?」など、刑事ドラマにありがちなイメージから、取り調べについて恐怖感を抱いている方も多いでしょう。
警察の捜査方法などについて定めた「犯罪捜査規範」では、取り調べのあり方について、強制・拷問・脅迫はもとより、供述の誘導、利益供与、長時間にわたるものや睡眠時間を顧慮しないなどの肉体的・精神的苦痛をあたえる取り調べは、すべて被疑者の人権を侵害するうえ、虚偽の供述による冤罪を誘発する危険性があり、許されません。
今では、検察官の取り調べに問題がある例は報告されなくなりましたが、警察官の取り調べの中には、一部看過できない取り調べが未だに存在します。
過去にも、(ⅰ)被疑者の弁解に一切聞く耳を持たず、犯人と決めつける行為、(ⅱ)実際には共犯者とされる者も否認しているにもかかわらず、共犯者が自白したから、お前も認めろと迫る行為、(ⅲ)素直に認めれば、すぐに釈放し、罰金などの軽い処分で済ませるなどと利益誘導する行為、(ⅳ)机を叩く、耳元で怒鳴り続ける、壁を向いて長時間立たせる、顔面を踏みつけるなどの暴行など、数々の違法な取り調べが行われて来た事実があります。
このような取り調べによっていったん虚偽の自白をさせられ、供述調書が作成されてしまえば、後の裁判でその内容を覆すことは著しく困難となり、無実なのに有罪判決を受けて処罰されてしまうリスクがあります。
違法な取り調べに対しては、弁護人から警察署長、警察署員に対して抗議することができ、苦情の内容は速やかに取り調べ監督官に通知されます(被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則7条)。また、都道府県公安員会に対して苦情を申し出ることもできます(警察法79条1項)。
取り調べ中、取り調べを中断して弁護人との面会を希望することは自由です。
身柄拘束中であっても、弁護人に接見に来るよう連絡をしてくれと申し出ることは可能ですし、これによって弁護人が駆けつければ、取り調べを中断して、弁護士との面会を許さなくてはならないことが原則です。
なお、このような取り調べ状況下においてなされた供述は、証拠能力が否定されることもあります。
(3) 勾留阻止・釈放
逮捕されて検察官に送致された後、検察官が裁判所に勾留請求をすると、裁判官が勾留するかどうかを判断するために被疑者に質問を行います。これを「勾留質問」と言います。
ただ、勾留質問は機械的な流れ作業で行われており、被疑者の言い分をじっくり聴く場とはなっていません。裁判官は検察官の勾留請求書に記載された被疑事実があるか否かをイエスかノーかで答えさせ、弁解があってもごく短時間の聴取にとどめ、詳しい調書を作成することもないのが現実です。
そこで勾留決定を避けるためには、被疑者に有利な事情などを、確実に裁判官に伝えることが必要です。
また、そもそも勾留請求自体をさせないためには、弁護士が検察官との面談や書面の提出で、有利な事情を検察官に伝える必要があります。
弁護士は被疑者に接見して事情を詳しく聞き、被疑者が気づかない有利な事情を聞き取って書面を作成し、検察官やその勾留請求を受けた裁判官に提出します。これにより勾留請求をしないように交渉したり、勾留決定をしないように折衝したりできます。
それでも勾留決定を裁判官が下した場合には「準抗告」という裁判を提起して、勾留決定を取消し、釈放を求める活動をします。
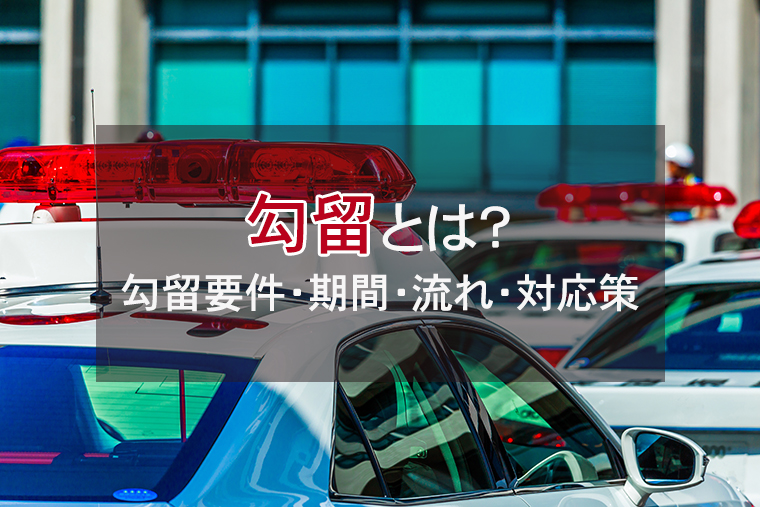
[参考記事]
勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説
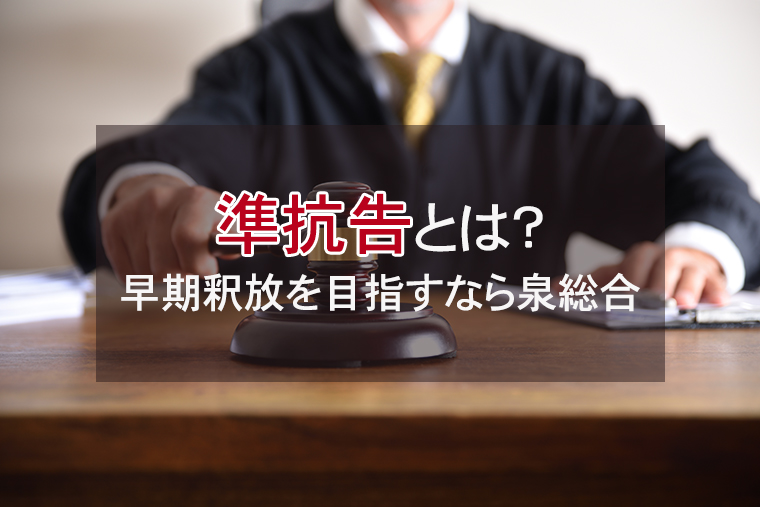
[参考記事]
準抗告とは?早期釈放を目指すなら泉総合法律事務所へ!
4.取り調べへの対処法は弁護士に相談を
まだ逮捕前で、任意出頭しての取り調べが予想または予定されている段階で弁護士に依頼をすれば、事前に取り調べに対処する方法・注意点を知ることができ、心の準備をすることができます。
また、逮捕されてしまった場合でも、当番弁護士への連絡を要求するなどして必ず弁護士のサポートを受けるべきです。
任意の取り調べを受けた後に弁護士事務所に相談に来られた方の中には、取り調べで話した内容の今後への影響に不安を募らせる方や、咄嗟に不合理な言い訳をして否認をしてしまったことで後の処分が重くなったり、今更、事実を認めて被害者と示談交渉をすることは無理ではないかなどと心配している方もいます。
このような事態に陥らないためにも、事前に弁護士に相談することがお勧めです。
特に逮捕・勾留後は、社会と切り離された密室で過ごすことになるので、精神的な負荷は非常に大きく、虚偽の事実を認める自白をしてしまうケースは多く報告されています。弁護士の適切な弁護活動により、望まぬ供述をすることを避けることがとても重要です。
もし取り調べの方法・内容に不安があるという方は、一度、泉総合法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。
5.取り調べに関する実際の質問
-
Q.盗撮の嫌疑をかけられ、警察に自白を強要されています。
社内の更衣室での盗撮の嫌疑をかけられました。同じ職場の女性職員から被害届が出されたのですが、その時間帯に会社にいたのが私とその女性の2人のみでした。
私は断じて盗撮をしておらず、虚偽だと主張しています。更衣室は付近に防犯カメラもない場所で、現在の証拠は相手の供述のみです。
警察から二回、任意の事情聴取をうけましたが、自白を強要するばかりでした。
発覚から4ヶ月経ち、最近家宅捜索があり携帯のみ押収されました。その4日後、書面にしたいから出頭してほしいと連絡がありました。警察は、なぜやってないのに自白を強要するのでしょうか?また、相手の供述のみで家宅捜索に驚いたのですが、今後の任意聴取を拒否したら次は逮捕の可能性ありますか?
なお、当然ながら押収された携帯に証拠はありません。携帯電話も早く返してほしいと思っています。 -
A.逮捕・送検の可能性も0ではないので、弁護士にご相談ください。
警察は、女性職員の供述が具体的で真実性に富んでいること、女性職員の供述以外に客観的な証拠がないことから、質問者様の自白を取りたいのだと思われます。
客観的証拠が一切なければ任意聴取を拒んでも逮捕はないとは思いますが、女性の供述内容が不明なので断言はできません。
警察から検察官に送致され、検察官の取り調べを受けることになる可能性もあります。お困りでしたら、一度弁護士にご相談ください。
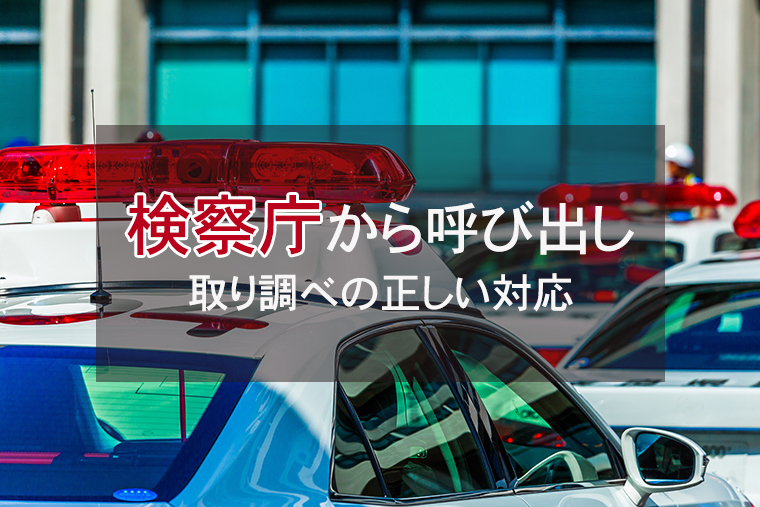
[参考記事]
検察庁からの呼び出し!取り調べを受ける場合の正しい対応