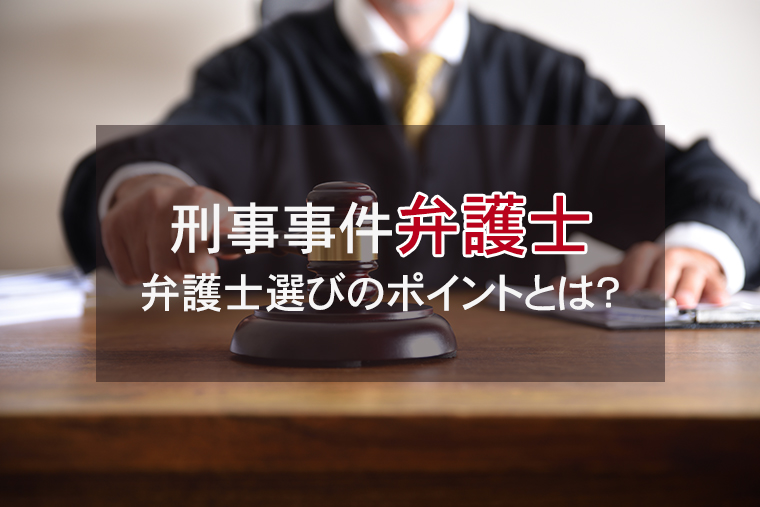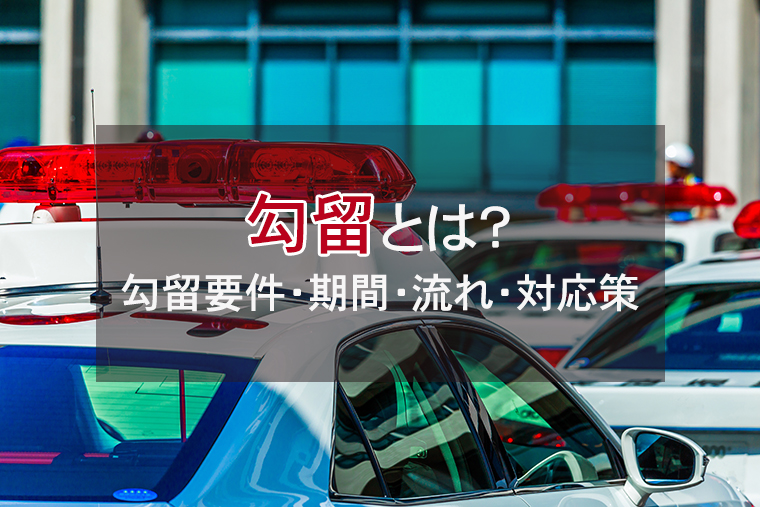虚偽告訴罪(誣告罪)の構成要件と事例について

虚偽告訴罪は、他人を刑事処分や懲戒処分に陥れる目的で虚偽の告訴・告発を行う重大犯罪です。
告訴とは、犯罪の被害者などの告訴権者が捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求めることです。告発は、告訴権者ではない者(第三者)が、捜査機関に犯罪事実を申告して処罰を求めることです。
「虚偽告訴罪」と聞くと馴染みがないかもしれませんが、痴漢冤罪、離婚時のDV虚偽申告など、近年社会問題となっている事例も多いです。
近年では、SNSでの誹謗中傷に関する虚偽の告発も問題となっています。
本記事では、虚偽告訴罪の構成要件と具体的事例、被疑者となってしまった場合の正しい対応方法を解説します。
1.虚偽告訴罪とは?
(1) 虚偽告訴罪・誣告罪について
第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
虚偽告訴罪は、刑法第172条に規定される犯罪で、正式には「虚偽告訴等罪」と呼ばれています。
この罪は、人を刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発、その他の申告をした者に対して科される罪です。
虚偽告訴等罪は、古くは「誣告罪(ぶこくざい)」とも呼ばれていました。「誣告」とは、事実を偽って人を告発することを意味する漢語で、中国の古典法にも見られる概念です。
現在でも法律実務や学術分野では「誣告」という用語が使われることがあり、虚偽告訴と似た意味で用いられています。
虚偽告訴罪には「3月以上10年以下の拘禁刑」という重い刑罰が定められており、罰金刑はありません。単なる嘘の申告ではなく、他人に刑事的・懲戒的な不利益を与える意図を持った悪質な行為として、法的にも厳しく処罰されるのです。
なお、虚偽の告訴等により被害者の方が長期の身体拘束をされる、社会的な地位を失う、実際に懲戒処分されるなどの損失が生じていれば、刑事罰以外にも民事責任を追及される(損害賠償請求を受ける)可能性があります。
(2) 虚偽告訴罪の構成要件
虚偽告訴罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。警察に「Aさんが窃盗しました!」などと告発したとしても、全てのケースで虚偽告訴罪が成立するとは限りません。
虚偽告訴罪が成立するには、以下のような要素が必要です。
- 告訴や告発の内容が虚偽であること
- 告訴者が故意に虚偽の事実を申告していること
例えば、単に事実を勘違いしていた場合(Aが本当に窃盗をしていたと思い込んでいた等)や、告発者が嘘のつもりでも実際には真実であった場合(Aが実際に窃盗犯だった等)本罪は成立しません。
重要なのは、相手を刑事処分または懲戒処分に陥れる目的があったかどうか、そして告発・告訴の内容が真実であったかどうか、という点です。
虚偽告訴罪に未遂はなく、被害届・告訴状・懲戒請求書などが受理された時点で既遂となります。
(3) 虚偽告訴罪とよく似た犯罪
虚偽告訴罪とよく似た犯罪としては、以下のようなものがあります。
| 偽証罪 | 宣誓をした証人が虚偽の陳述・証言をした |
|---|---|
| 詐欺罪 | 人をだまして誤解させ、その誤解を利用して財産を交付させたり、支払いを免れたりした |
| 侮辱罪 | 「バカ」「浮気者」など、抽象的判断(侮蔑的表現)で公然と人を侮辱した |
| 名誉毀損罪 | 真実であるか否かに関わらず、ある事実を言いふらし人の社会的評価を低下させた |
| 軽犯罪法違反の虚構申告 | 事実ではない犯罪や災害を公務員に申告した |
これらの犯罪行為は虚偽告訴罪と似ていますが、詳細は異なります。
2.虚偽告訴罪の具体例
虚偽告訴罪の典型例としては、以下のようなものが考えられます。
(1) 痴漢の冤罪をでっち上げる
痴漢の冤罪は、近年社会問題化している虚偽告訴罪の典型例です。
電車内などで、実際には痴漢行為が行われていないにも関わらず、女性が特定の男性(近くに立っている男性)を痴漢として告発するケースがこれに該当します。
このような虚偽告訴が行われる動機としては、示談金目的が多いと言われています。被害者を装って警察に通報し、後に示談を持ちかけて金銭を得るのです。
中には、近くに目撃者として共犯者を置くというケースもあります。
痴漢の虚偽告訴は、被害者に深刻な社会的ダメージを与えます。たとえ後に無実(冤罪)が証明されても、職場での信用が失墜したり、家族関係が悪化したりしてしまうのは避けられません。
また、このような虚偽告訴が横行すれば、真の痴漢被害者の証言への信頼性も損なわれてしまいます。
(2) 離婚時にDVの虚偽申告をする
離婚において、親権や財産分与・慰謝料請求で有利な立場に立つために、実際には存在しないDVやモラハラをでっち上げ、配偶者を告発するケースも少なくありません。
軽微な夫婦喧嘩を誇張してDVとして申告したり、全く存在しない暴力行為を創作して裁判所に報告したりするのです。
このよう虚偽告訴では、配偶者への個人的な恨みが背景にあることが多いです。相手へ報復したいという気持ちや、離婚後の生活のためにできるだけ多くのお金を得たいという動機もあります。
虚偽のDV を申告されてしまえば、被害者は離婚後の生活や子どもとの面会交流に大きな悪影響を受ける可能性があります。
(3) 窃盗・詐欺の濡れ衣を着せる
金銭トラブルや人間関係の問題(近隣住民とのトラブルなど)を背景に、特定の人物を窃盗・詐欺の犯人として虚偽告発するケースです。
実際には盗まれていない物品について窃盗として告発したり、存在しない詐欺被害を創作して特定の人物を犯人として申告したりします。
また、自分の横領や不正行為を隠蔽するために、他人に罪を着せようとするケースも見られます。
窃盗や詐欺の虚偽告訴を受けた被害者は、警察による取り調べを受けることになり、場合によっては逮捕・勾留される可能性もあります。たとえ後に無実が証明されても、「窃盗・詐欺を疑われた人」という印象を完全に払拭することは困難です。
3.虚偽告訴罪を犯した場合の弁護士対応
虚偽告訴罪は「3月以上10年以下の懲役」という重い刑罰が定められており、実刑判決を受ける可能性も高い重大犯罪です。罰金刑はなく、起訴されれば必ず公判となります。
虚偽告訴罪を犯してしまった場合、最も重要なのは可能な限り早急に弁護士に相談することです。自力で対応しようとすると、却って状況を悪化させる危険性もあります。
虚偽告訴の刑事弁護の内容は、以下のとおりです。
(1) 構成要件を満たしているか検討をする
虚偽告訴罪では、告訴・告発の動機や故意性、真実かどうかが重要な争点となります。
先述の通り、告訴・告発の内容が真実であると思い込みをしていた場合や、告発の内容が実際は真実であった場合には、虚偽告訴罪は成立しません。
仮に構成要件を満たしていた場合でも、弁護士は虚偽告訴に至った経緯や動機について、情状酌量の余地がある事実を整理します。弁護士が検察官に上手く主張することで、身体拘束や厳罰を回避できる可能性があります。
(2) 取り調べの際の適切な対応方法をアドバイス
弁護士は、警察や検察の取り調べに対する適切な対応方法をアドバイスすることも可能です。
虚偽告訴罪などの刑事事件では、取り調べでの発言内容が処分内容に大きく影響します。弁護士と「言うべきこと」「黙秘するべきこと」などを事前に打ち合わせることで、不必要に不利な状況を作ることを避けることができます。
(3) 被害者との示談交渉を行う
被害者との示談は、刑事処分の軽減に関して極めて重要な対応策です。
弁護士は、被害者(あるいはその代理人)と交渉し、被害者の感情に配慮しながら、被疑者の反省の意と謝罪を真摯に伝え、損害賠償金・慰謝料を支払うことで示談を成立させます。
被害者との示談が成立すれば、不起訴や執行猶予の可能性が大幅に高まります。
しかし、被疑者が個人で示談交渉を行うのは困難です。法的に適切な示談書の作成も、弁護士の専門領域と言えます。
有効な示談を成立させるためにも、示談交渉の経験が豊富な弁護士を選んで依頼することが重要です。
→示談したい
4.まとめ
虚偽告訴罪を犯した場合、早急な対応が大切です。
と言うのも、虚偽告訴罪を含める刑事事件は、時間的制約が非常に厳しいです。特に、逮捕・勾留されたようなケースでは、起訴・不起訴の判断まで時間がないため、迅速な対応が可能な弁護士を選ぶ必要があります。
泉総合法律事務所は、土日祝日や夜間でも対応が可能です。代表弁護士である泉と綿密に連絡が取れる体制を整えているため、緊急を要する案件でも迅速に対応することができます。
虚偽告訴罪などの刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度泉総合法律事務所までご相談ください。
※なお、泉総合法律事務所では、被害者の方からのご相談・ご依頼は承っておりませんので、この点ご了承ください。