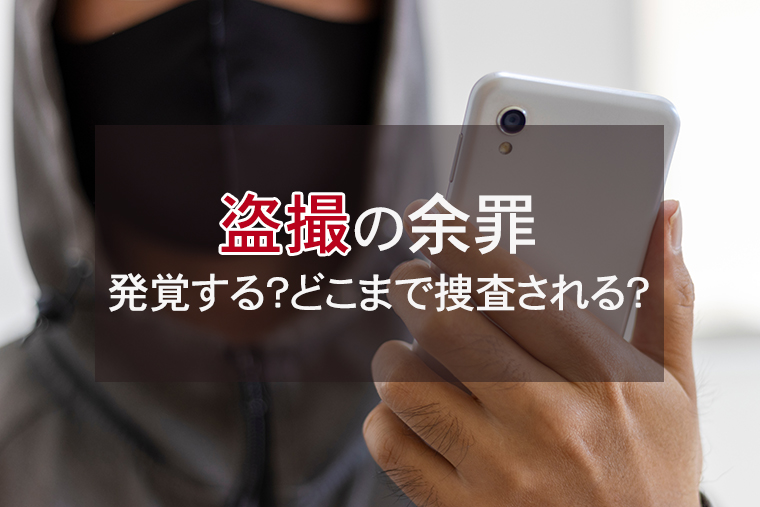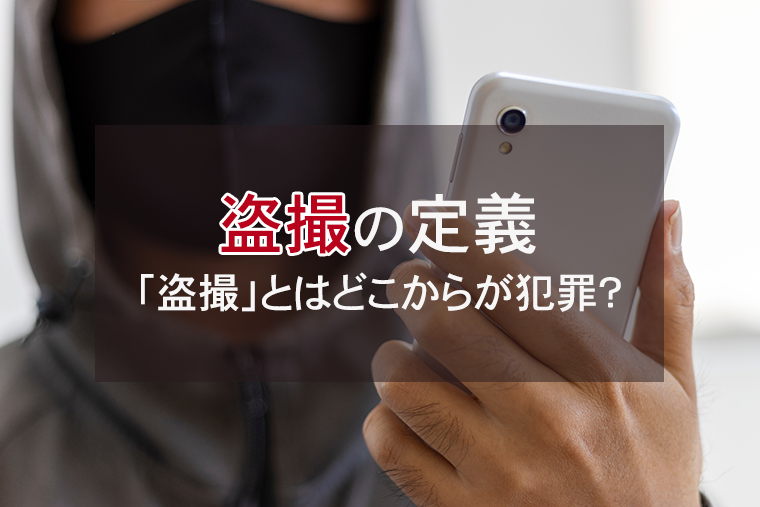盗撮再犯で逮捕されたら罰金?不起訴のための弁護活動
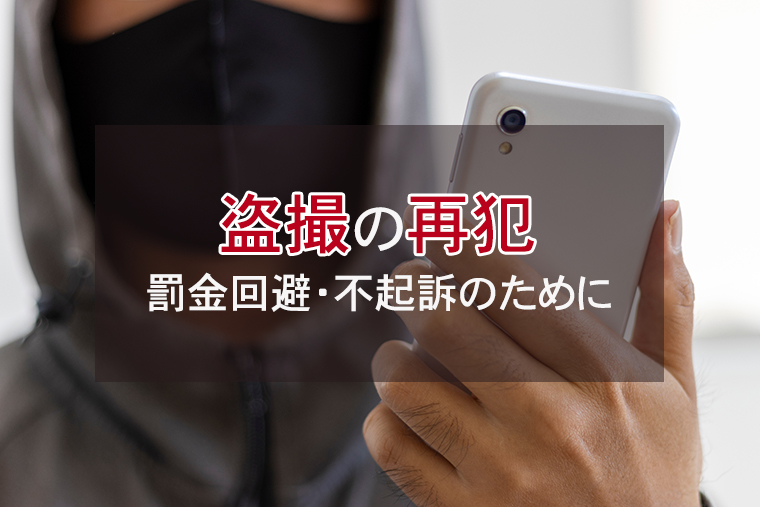
盗撮の再犯は、発覚すれば初犯よりも逮捕・勾留・起訴される可能性が高くなります。
何故なら「前回の犯行から反省をしておらず、処罰しなくては将来的にも犯行を繰り返す危険性がある」と評価されてしまうからです。
しかし、2回目の盗撮だと必ず起訴される(罰金・実刑になる)というわけではありません。
今回は、盗撮の「再犯」「常習犯」で逮捕された場合、不起訴を得るために注意するべき点について説明します。
1.盗撮事件の罰則
盗撮を起こすと、性的姿態撮影等処罰法あるいは各都道府県の制定する迷惑行為禁止条例で処罰されることになります。
性的姿態撮影等処罰法は、2023年(令和5年)7月13日に施行されました。人の性的姿態などをひそかに撮影する(盗撮する)行為などは、「撮影罪」として「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処されます。
一方、東京都の迷惑行為防止条例では、違反した場合に以下の刑罰が定められています。
(※盗撮犯は「常習として」違反行為を行った場合に刑が加重されます。)
| 違反行為 | 刑罰 |
|---|---|
| 人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為 (5条1項柱書、同2号) |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 【常習犯】 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
|
| 人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影するために撮影機器を差し向け又は設置する行為 (5条1項柱書、同2号) |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 【常習犯】 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
どちらの法律が適用されるかについては、盗撮事案の様態によって異なります。
例えば、「エスカレーターに乗って下から前にいる女性のスカートの中・下着を撮影する行為ないし撮影した」「電車内で前に座っている女性のスカートの中の下着を撮影した」というようなケースでは、撮影罪に問われるケースが多いです。
これに対して、およそ女性の下着姿以外の女性(正確には男女問いません)を無断で撮影しようとする行為は、各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されています。
2.盗撮の常習犯と再犯の違い
(1) 「常習犯」とは?
「常習犯」は、法律用語としては、同一の犯罪を「反覆累行する習癖あるもの」と定義されます。
「累行」とは重ねること、「習癖」とは「性癖、習慣化された生活ないし行動傾向、人格的、性格的な偏向など」を意味します。つまり、当該犯行がその者の習癖の発現であると認められる場合であって、はじめて「常習犯」としての罰則が適用されます。
したがって、盗撮犯の場合の常習犯とは、性的な衝動を抑えることができずに盗撮を繰り返してきた場合が典型的です。
ただし、性的動機に限らず、例えば、盗撮した画像をネットなどで販売する営利的な動機で盗撮行為を繰り返したケースなどにも、やはり同一犯罪を繰り返す習癖があるとして、常習犯とされる可能性もあります(最高裁昭和54年10月26日決定)。
常習性の有無を左右する明確な基準を定めた法令や判例はなく、前科、前歴、犯行態様、動機などの諸事情を総合考慮して裁判官が判断します。
多くの場合、同一犯罪の前科があること(すなわち同一犯罪での確定した有罪判決)が重視されますが、それも判断要素のひとつに過ぎません。たとえ前科がなくとも、犯行が習癖の発現と判断されれば常習犯とされます(最高裁昭和25年3月10日決定)。
(2) 「再犯」とは?
「再犯」とは、法律上の用語としては、一定の要件を満たす場合に刑を加重する制度のひとつを意味します。これを「刑法上の再犯」と呼びます。
刑法上の再犯(刑法第56条)は、①懲役に処せられた者が、②その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から、③5年以内に更に罪を犯した場合において、④その者を拘禁刑に処する場合を指します。
前の犯罪が同一犯罪や同種犯罪であることは要件ではありません。例えば、窃盗事件を起こした後に盗撮行為を行なった場合でも「再犯」となります。この点で、同一犯罪の反復を内容とする常習犯とは異なります。
再犯とされた場合、その法定刑の長期は、その罪について定めた懲役刑の長期の2倍以下となります(刑法第57条)。短期は加重されません。
例えば、東京都の迷惑行為防止条例違反において、被害者の盗撮した行為の懲役刑は1年以下ですが、再犯に該当すれば2年以下の懲役刑となります。
盗撮行為が常習犯の行為と認定されれば、通常の懲役刑は2年以下ですが、再犯に該当すれば4年以下の懲役刑となります。
再犯が加重処罰されるのは、懲役刑を受けた経験があるのに反省しておらず、強い非難に値するからです。
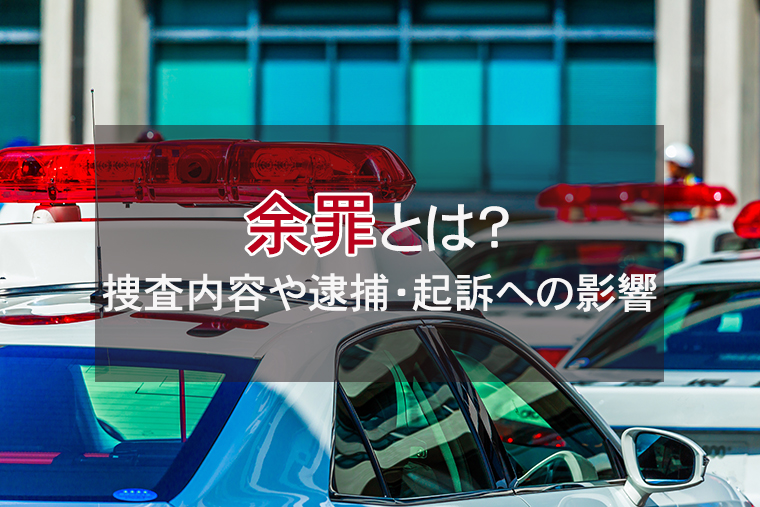
[参考記事]
余罪とは?警察の捜査内容や逮捕・起訴への影響
【常習犯の犯行が複数回に及ぶ場合の加重】
常習犯は、複数回にわたり犯行を重ねても、それがひとつの習癖の発現と認められる限り、包括して一個の常習犯罪一罪として処罰されます(最高裁昭和26年4月10日判決)。
ただし、盗撮行為で迷惑行為防止条例違反となる場合、犯行場所が異なる自治体で、別個の迷惑防止条例が適用されるケースでは違反した条例が異なることになります。よって、一罪と扱うことはできないので、常習犯であっても別個に数罪として刑が加重されます(併合罪加重・刑法45条、47条)(東京高裁平成17年7月7日判決)。
3.再犯の盗撮で不起訴になるための対応策
盗撮行為が露見したときは、逮捕された場合はもちろん、身柄を拘束されていない在宅事件の場合でも直ちに弁護士に弁護を依頼するべきです。
特に再犯の場合、弁護士のサポートを受けることが不起訴の獲得には不可欠です。
再犯の場合、「今後、二度と盗撮はしません」などの言葉を信用する検察官・裁判官はいません。既にその約束を破った実例があるからです。
少なくとも2回にわたり罪を犯しているわけですから、「今回の犯行を行った原因は何か?」「前の反省と今回の反省はどこが違うから次はないと約束できるのか?」という点について、検察官・裁判官に説得的に説明できなくては、今後も犯行を繰り返す危険が大きいと判断されてしまいます。
これは家族についても同様です。今までの監督方法では再犯を抑えることができなかったのですから、その原因を考え、どのように監督方法を変更するか説明できなくては、検察官や裁判官を納得させることはできません。
とはいえ、これらは非常に難しい作業です。現実に今後の犯行を防止するにはどのような対策があるか、具体的に頭を捻る必要があります。
例えば、次のような防止策が考えられます。
- 女子学生等が多い交通機関に乗らないよう通勤経路を変更する
- 毎日帰宅後はスマホを妻が保管し、保存された画像をチェックする
- パソコンは家族共用のものだけとし、家族がデータをチェックする
- 性的衝動を抑制するためカウンセリングを受け、通院をする
大切なのは、本人と家族が真剣に再犯してしまった原因と向き合い、様々な防止策を考えこれを実行する決意を持っていると検察官や裁判官に知ってもらうことです。
4.再犯の盗撮事件で逮捕されたら弁護士へ
再犯事件における弁護士の役割のひとつは、法的な専門知識と刑事弁護の経験から本人やご家族にアドバイスをし、その結果を書面や口頭で検察官・裁判官に伝えて、処分の軽減を働きかけることにあります。
再犯事件では、まだ更生の可能性が残っていることを検察官、裁判官に理解してもらう必要があります。再犯であっても罰金などの不利益を回避して不起訴を勝ち取れる可能性は0ではありません。もちろん、被害者との示談交渉も弁護士が行うことが可能です。
盗撮再犯の刑事弁護は経験豊富な弁護士に依頼するべきですので、刑事事件に力を注いでいる泉総合法律事務所の弁護士泉義孝にぜひご相談ください。
なお、刑事事件について過去に前科・前歴がないケースは「初犯」とされますが、検察官はたとえ1回目の盗撮でも起訴する権限があります。
確かに、再犯・常習犯がある場合と比べ、初犯の場合は刑事手続きにおいて厳しい処分が出されることは少ないですが、初犯であっても起訴される可能性は0ではないのです。
初犯・再犯問わず、盗撮事件を起こしてしまったら一日でも早く弁護士に相談・依頼することをお勧めします。