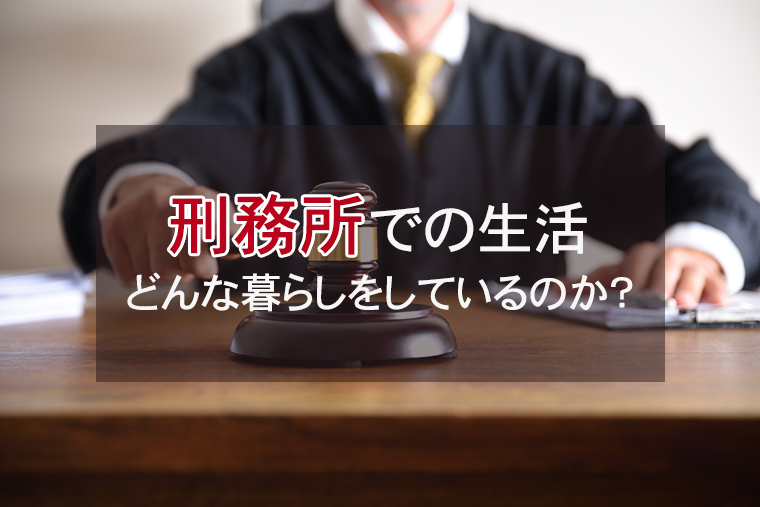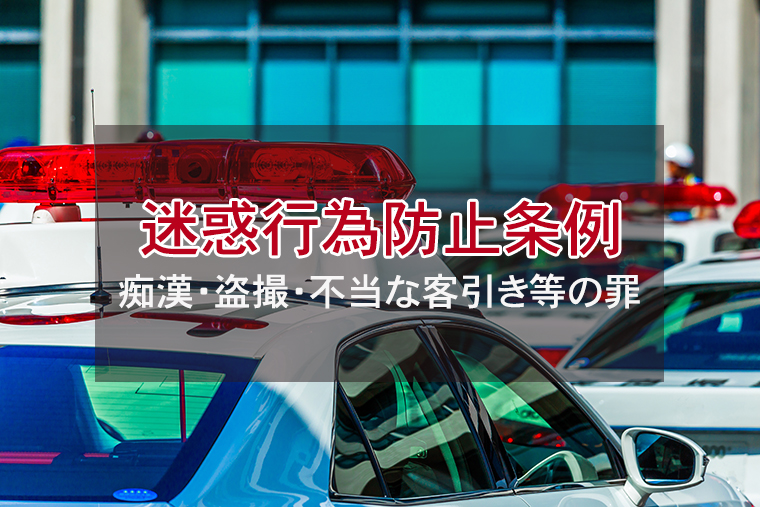再犯・累犯とは?刑罰の加重について
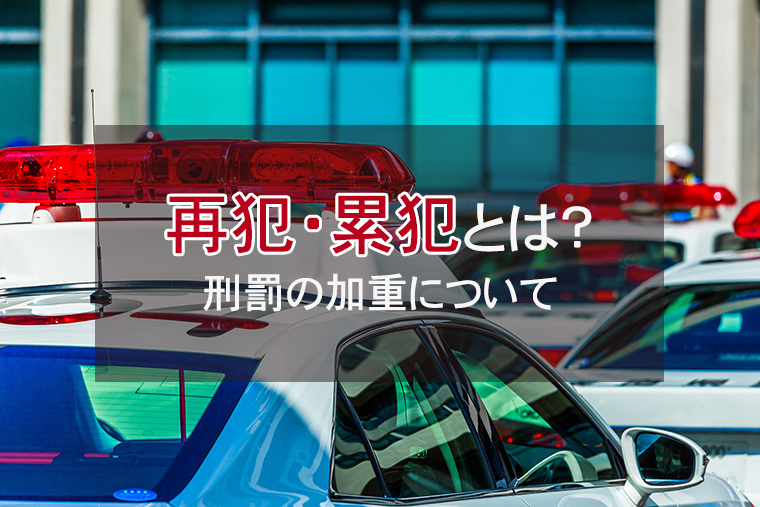
過去に刑事犯罪を犯した者が再び罪を重ねる「再犯」「累犯」は、初犯の場合よりも刑罰を加重する制度が設けられており、一般的な被疑者よりも重い処罰が科されます。
しかし、弁護士が適切な弁護活動をすることで、被疑者の反省・社会復帰の可能性を主張し、減刑を臨める可能性があります。
本コラムでは、再犯・累犯の定義と、具体的な刑罰加重の仕組み、再犯・累犯に対する弁護士の刑事弁護内容について解説していきます。
1.再犯・累犯の違い
(1) 「再犯」とは?
刑法第五十六条
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を拘禁刑に処するときは、再犯とする。
刑法上の再犯は、①懲役に処せられた者が、②その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から、③5年以内に更に罪を犯した場合において、④その者を拘禁刑に処する場合を指します。
前の犯罪が同一犯罪や同種犯罪であることは要件ではありません。
例えば、窃盗事件を起こした後に盗撮行為を行なった場合でも「再犯」となります。
(2) 「累犯」とは?
刑法第五十九条
三犯以上の者についても、再犯の例による。
累犯とは、犯罪を重ねる(再犯を重ねる)うちに、一定の要件を備えることにより刑が加重されることをいいます。反復するごとに「再犯」「三犯」「四犯」等と呼ばれ、その総称が「累犯」です。
(3) 「常習犯」との違い
「常習犯」は、法律用語としては、同一の犯罪を「反覆累行する習癖あるもの」と定義されます。
「累行」とは重ねること、「習癖」とは「性癖、習慣化された生活ないし行動傾向、人格的、性格的な偏向など」を意味します。つまり、当該犯行がその者の習癖の発現であると認められる場合であって、はじめて「常習犯」としての罰則が適用されます。
このような意味合いから、常習犯とみなされるのは同一犯罪を繰り返してきたケースに限ります。
常習性の有無を左右する明確な基準を定めた法令や判例はなく、前科、前歴、犯行態様、動機などの諸事情を総合考慮して裁判官が判断します。
多くの場合、同一犯罪の前科があること(すなわち同一犯罪での確定した有罪判決)が重視されますが、それも判断要素のひとつに過ぎません。たとえ前科がなくとも、犯行が習癖の発現と判断されれば常習犯とされます(最高裁昭和25年3月10日決定)。
(4) 前科・前歴との関係
「前科」とは、簡単に言うと有罪となったことの記録です。
正式に裁判を受けて裁判所で有罪判決を宣告された場合だけでなく、略式起訴をされて裁判官から略式命令(罰金刑)を受けた場合も前科になります。
「前歴」とは、被疑者として捜査対象になったものの最終的に不起訴処分となった事実を指します。有罪判決が下されていない場合であっても前歴はつきます。
再犯や累犯は、あくまで懲役に処せられた者が更に罪を犯したケースを言いますので、「前科」とは異なります。
とはいえ、前科や前歴があるかどうかというのは、やはりその後に事件を起こした場合の処分の内容に影響してくる場合があります。
例えば、一度警察に逮捕されたものの不起訴になったケースは、再犯でも前科でもありませんが、「前歴」としては警察の方で記録が残っていますので、再度同じような事件を起こした場合に「今回も不起訴になるだろう」と安易に考えることはできません。
2.再犯・累犯による刑罰の過重
前回の不起訴処分からどのくらいの期間が空いているのか?などにもよりますが、再犯をすると、「反省していない」「更生しない」と判断され、正式起訴又は略式命令請求をされて前科がついてしまう可能性がかなり高くなるのが通常です。
再犯とされた場合、その法定刑の長期は、その罪について定めた懲役刑の長期の2倍以下となります(刑法第57条)。短期は加重されません。
例えば、東京都の迷惑行為防止条例違反において、被害者の盗撮した行為の懲役刑は1年以下ですが、再犯に該当すれば2年以下の懲役刑となります。
盗撮行為が常習犯の行為と認定されれば、通常の懲役刑は2年以下ですが、再犯に該当すれば4年以下の懲役刑となります。
また、刑法第56条に明記されている加重の有無をまとめると以下の通りになります。
| 前回の刑罰 | 再犯の刑罰(5年以内) | 加重の有無 |
|---|---|---|
| 懲役 | 拘禁刑 | 加重 |
| 禁固・罰金 | 加重なし | |
| 禁錮 | – | 加重なし |
| 執行猶予 | – | 加重なし |
懲役に処せられた者が、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯した場合で、その者を拘禁刑に処す場合には、再犯として刑が加重されます(刑法56条1項)。
一方、禁錮に処せられた者が、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯し、その者を拘禁刑に処す場合には、再犯として刑が加重されません。
また、懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯した場合で、その者を禁錮や罰金に処す場合にも、再犯として刑は加重されません。
3.再犯・累犯で刑罰を軽くしたい場合
再犯・累犯者であっても、適切な弁護活動を受けることにより刑罰の軽減を図ることは可能です。
上記で説明した加重が適用される状況下でも、不起訴・執行猶予などを目指すならば、弁護士による専門的なサポートを受けるようにしましょう。
弁護士に依頼をすれば、以下のような弁護活動を行ってくれます。
(1) 被害者との示談交渉・被害回復に尽力
まず、痴漢、盗撮、窃盗、暴行などにより被害が生じている場合は、被害弁償や示談を行うことが最も重要です。
再犯・累犯者の場合、原則として不起訴や執行猶予の適用は困難となります。しかし、犯罪が軽微である場合には、被害者との示談成立、被害回復への努力を検察官に示すことで、減刑の可能性も0ではありません。
また、弁護士が犯行に至った特別な事情の存在などを丁寧に主張すれば、これも情状として考慮される可能性があります。
(2) 依存症が疑われる場合の再犯防止策
再犯・累犯事件では、被告人の更生意欲や環境改善の取り組みを具体的に示すことが不可欠です。
例えば、依存症が背景にあると考えられる場合は、専門的な治療プログラムへの参加実績や今後の治療計画を提示することで、裁判官に対して再犯リスクの低下をアピールできます。
また、就労環境の確保や家族のサポート体制を整えることも、社会復帰への真摯な取り組みとして評価されます。
裁判所や捜査機関は、依存症についてまったく理解がないわけではありません。
これらは一般的な犯罪でも同様のことがいえますが、依存症による犯罪は、刑罰ではなく治療という選択肢を積極的に提示することがより重要といえます。依存症であるならば、再犯防止策についてどのように考えて行動しているのかという点が重視される傾向があるということです。
専門の医療機関で治療を開始したり、自助グループへ参加したりして再犯防止の具体的な取り組みをしているという事情を主張しましょう。
4.刑事事件の再犯をしたら弁護士へ
再犯・累犯が加重処罰されるのは、懲役刑を受けた経験があるのに反省しておらず、強い非難に値するとされるからです。
よって、再犯・累犯事件は厳しい処罰が予想されますが、適切な弁護活動により刑罰の軽減・執行猶予の獲得が実現できる場合があります。
被疑者にとって良い情状を主張したり、被害者と示談し被害回復を測ったり、更生環境を整備したりするなどの活動は、専門的知識と経験が求められる複雑な手続きとなります。よって、早期の段階から刑事弁護に精通した弁護士にご相談・ご依頼されることを強くお勧めします。
一人で悩まず、まずは泉総合法律事務所の弁護士・泉義孝までお気軽にお問い合わせください。