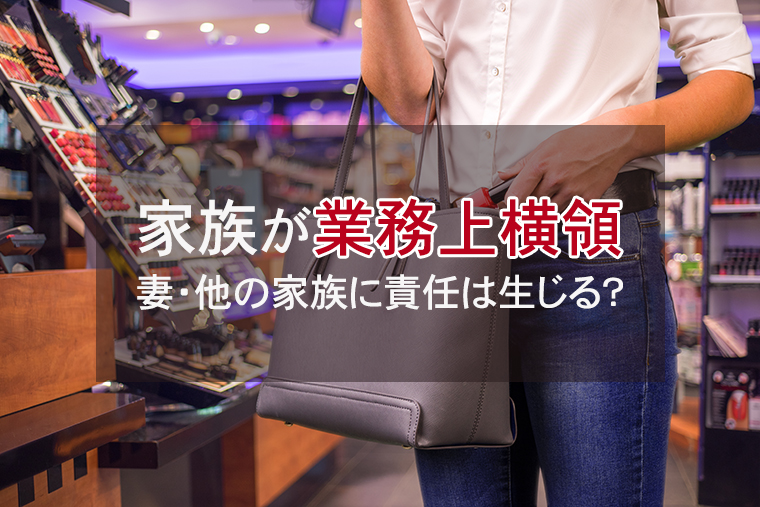背任罪とは?構成要件や逮捕後の対応について
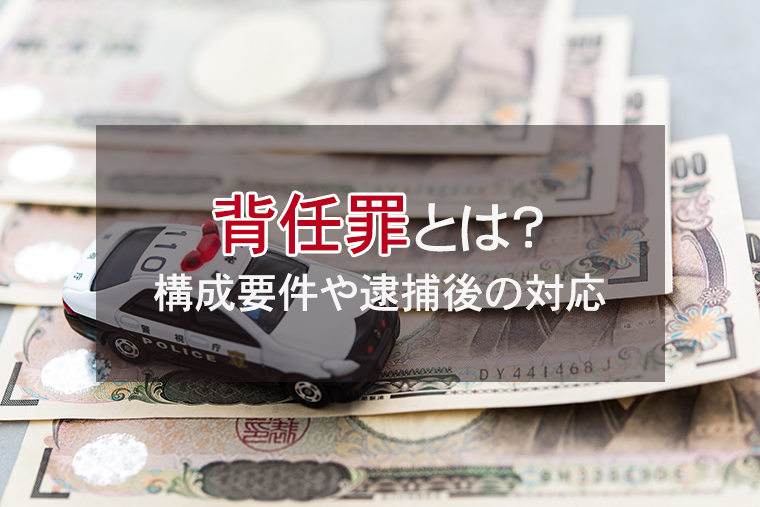
会社の財産を浪費するなどした場合には「背任罪」が成立することがあります。
窃盗罪や強盗罪と異なり、背任罪はあまり露見しない犯罪であるため、その要件や具体例がイメージしにくいです。
この記事では、背任罪の構成要件や逮捕後の対応について解説します。
1.背任罪とは?
(1) 背任罪の構成要件
背任罪は、刑法247条に規定があります。
なお、背任罪の時効は5年となっています。
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、背任行為により本人(会社)の全体財産が減少したこと又は得られるはずだった利益を得られなかったことをいいます。
したがって、背任行為をしたが会社の財産が減少しなかった場合には、背任未遂罪(刑法250条)が成立します。
「他人のためにその事務を処理する者」とは
これは、委託者から事務の処理を委託された者をいいます。
会社の社員などは、会社から委託され、会社のために業務を行っています。そのため「他人(会社)のためにその事務を処理する者」と言えます。
もっとも、背任罪は財産犯なので、委託された事務は会社の財産と関係あるものでなければなりません。
また、背任罪は他人の財産権を侵害する犯罪ですから、事務とは「他人の事務」であることを要します。「他人の事務」とは、本来は本人がなすべき仕事を本人に代わって担当する場合と言えます。
例えば、売主が商品を買主に引き渡す行為は、売主自身がなすべき「自己の事務」に過ぎないので、引渡を怠っても背任罪とはなりません。買主が代金を支払う行為や、賃貸物件の借主が貸主に物件を明け渡す行為なども同様です。
ただ、抵当権設定者が抵当権者のために登記を共同申請する行為のように、本来は抵当権設定者がなすべき自己の事務でありながら、抵当権者の権利保全という他人の事務としての側面をも有する場合があります。
そのような場合、判例・通説は、抵当権者の財産権保護を重視し、他人の事務として背任罪の成立を認めます。
「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」について
「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」は、図利加害目的(とりかがいもくてき)ともいわれるもので、これは、本人(会社)の利益のために任務に背く行為をした場合に背任罪が成立しないことを裏から規定したものです。
およそ取引行為には損害発生のリスクが内在していますから、役員や従業員がこれを認識しつつも、あえて会社のために取引を行う事態は格別珍しくありません。
そのような行為が結果として損害を発生させた場合、これを犯罪とするのでは処罰の範囲が広すぎて現実的ではなく、せいぜい委任契約や労働契約上の義務違反として民事責任を問えば足ります。
そこで、本人の利益を目的とした行為を処罰対象から除外する意味で、図利加害目的を要求したのです。
「その任務に背く行為」とは
これは、「誠実な事務処理者として法的に行うべきでない行為をすること」又は「事務処理者として法的に行うべき行為をしないこと」をいい、その判断には法令、通達、定款、内規、契約などが考慮されます。
例えば、不正融資、蛸配当、自己取引、リベート受領などがこれに当たります。
(2) 横領罪との違い
刑法252条1項
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
横領罪は委託信任関係に基づいて「自己が占有する他人の物」を横領する犯罪です。
横領とは「不法領得の意思」を実現する行為一切を指し、これを領得行為と呼びます。
「不法領得の意思」とは「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意志」とされます(※最高裁昭和24年3月8日判決)。
このように横領罪は領得行為による任務違反行為ですから、その成立範囲は、背任罪の成立範囲に含まれ、横領罪は背任罪の特別な場合と位置づけられます。
つまり当該行為が両罪の成立要件を満たす場合は、横領罪だけが成立し、背任罪とはなりません。
それ故、任務違反行為については、まず横領罪の成否を検討し、これが否定された場合に、背任罪の成否を検討することになります。
横領罪について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
会社のお金を横領したら逮捕される?
(3) 背任罪の具体例
以上の構成要件を参考に背任罪の具体例を考えると、以下のようなものとなります
- 会社が決めた値段よりもかなり安い金額で友人に商品を売った
- 会社の極秘情報をライバル会社に意図的に漏洩させた。
一方、「会社から管理保管を任されていた金銭を使い込んでしまった」などという場合は横領罪(業務上横領罪)となります。
2.背任罪で逮捕された後の流れ
背任罪を犯し会社に発覚すれば、会社は事実関係の調査の後、警察に被害届を出す、刑事告訴するという可能性があります。
捜査を開始した警察は、容疑が固まれば背任を行った者を逮捕することがあります。
背任罪は、罪質上現行犯逮捕されるというケースはなく、通常の逮捕をされることになります。
しかし、背任罪は警察の捜査にも時間がかかるケースが多いため、発覚してすぐに起訴される、というケースは少ないです。
逮捕された場合、警察官の下で取り調べを受けます。その後、48時間以内に検察官の下へ身柄が送致され、検察官からの取り調べを受けることになります。検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、被疑者の勾留を裁判官に請求するか否か決定します。
勾留請求が裁判官に認められた場合、続けて被疑者は10日間から20日間身体拘束されます。
勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか否か決定します。
起訴された場合には、被疑者は被告人と呼称が変わり、その後刑事裁判となります。
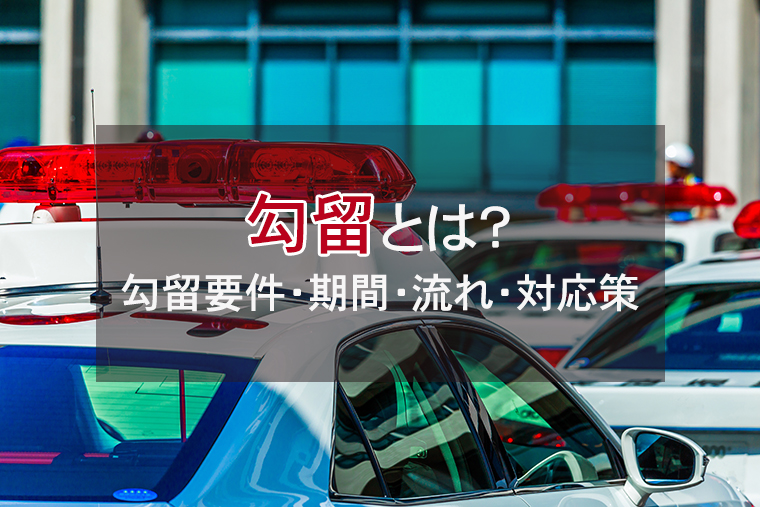
[参考記事]
勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説
3.背任罪の弁護活動
刑事事件を犯した場合には、身体拘束期間を短くする(早期釈放を目指す)、不起訴処分を獲得する、起訴された場合に量刑を軽くするための弁護活動が重要となってきます。
背任事件の特徴としても、会社内部での役員や従業員による背任行為が発覚しても、
①組織内部のいわば身内の犯行であること
②不祥事発生を外部に知られることを避けたいこと
③執行部、役員会、上司らの責任問題に波及する懸念があること
④内部の会計資料等を捜査機関の目にさらしたくないこと
などから、会社としては被害届や刑事告訴に踏み切らず、むしろ内々の処理を希望するケースが多々あります。
したがって、社内で事件が発覚してしまったときは、できるだけ早く被害者(会社)と示談をまとめて、被害届・刑事告訴に至る前に終息させてしまうことが肝要です。
そのためにも、早い段階から弁護士を代理人として、会社側との示談交渉を任せるべきです。
ただ、コンプライアンスが重視される近年では、株主代表訴訟などのリスクを避けるため、背任行為の存在を積極的に公表して刑事事件化せざるを得ないという姿勢をとる会社もあります。
そのようなケースでは、外部の目があるので、会社側も示談によって安易な妥協をすることはできません。
しかし、事件化したからと言って、示談の余地が完全に絶たれたわけではありません。
会社としては、事件を隠蔽しなかった態度さえ対外的に示すことができれば十分で、損害がある程度賠償されれば刑事罰まで求める必要はないと判断することも少なくないからです。
とはいえ、そのような場合でも、会社としては株主や社外役員など関係者に対し、法的に適正かつ妥当な示談を成立させたと説明できることが何よりも重要です。
その会社側の希望に応えるためにも、加害者側も弁護士に示談のとりまとめを依頼することが大切なのです。
4.背任罪の刑事弁護は泉総合法律事務所へ
背任罪の容疑をかけられた場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士は示談交渉だけでなく、今後逮捕された場合の取り調べに向けてのアドバイスをしたり、被疑者に有利な証拠を集めたりするなどの活動を行います。
それにより、被疑者に不利になる自白をするのを防ぐ、また起訴や起訴された場合に重い判決が下されるのを防ぐことができます。
背任罪を犯してしまった場合には、どうぞお早めに泉総合法律事務所にご相談ください。