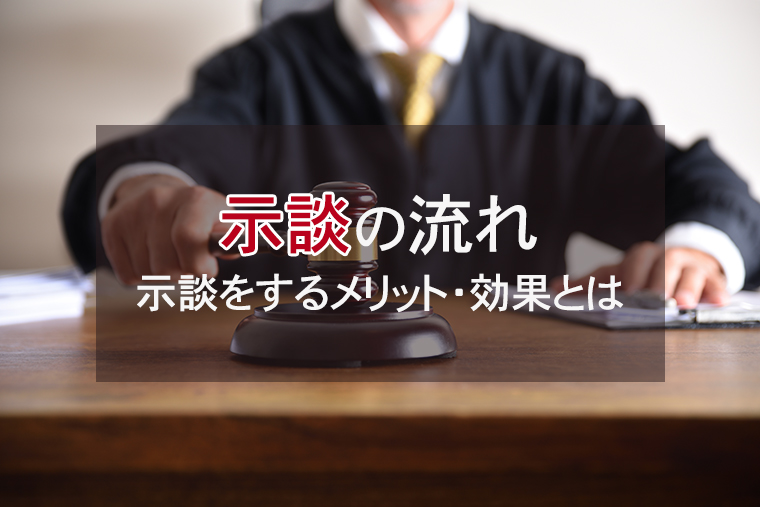家族(夫)が会社の金を業務上横領|妻に責任は生じる?
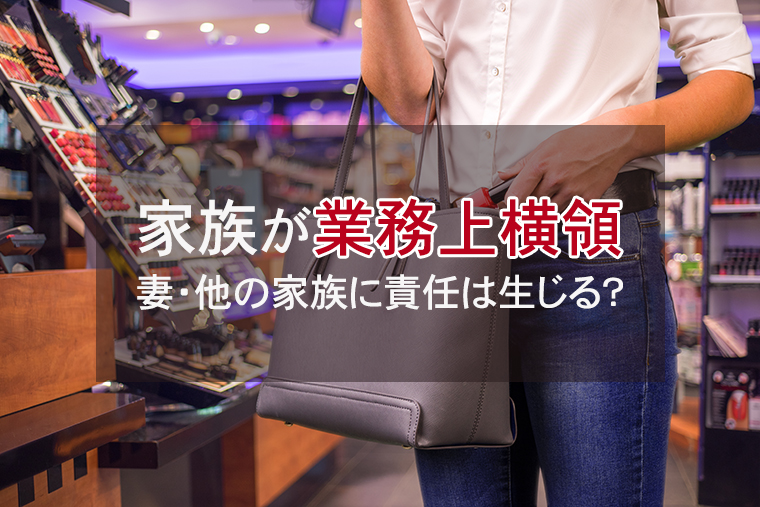
夫、あるいは息子さんなどの家族が会社のお金を横領したと発覚して逮捕・起訴されてしまった場合、妻(配偶者)や家族は返済の責任を負うのでしょうか?
また、返済する義務はない場合でも、支払いたい気持ちがあれば任意に支払ってもよいのでしょうか。
今回は、横領事件によって生じる家族の法的責任について解説します。
1.横領によって生じる法的責任
法的責任については、刑事責任と民事責任の面からそれぞれを分けて考える必要があります。
なお、刑事責任と民事責任は別個のものですが、まったく無関係というわけでもありません。
たとえば、会社に対して被害弁償したという事実や示談が成立したという事実は、刑事事件において有利な事情として考慮され、不起訴処分となったり、刑事裁判で量刑が軽くなったりする要素となります。
(1) 刑事責任
横領罪は、平たく言えば、信頼関係に基づいて管理を任された他人の財物を勝手に使ってしまう犯罪です。
例えば、次のような行為は横領罪となります。
- 会社から預かっている現金を勝手に使ってしまう
- 会社から管理を任された銀行預金口座から、勝手に自分や友人の口座に送金する
- 営業先で集金した売掛金を持ったまま逃げてしまう
そして、会社における業務として財物を占有していた場合は、「業務上横領」となります。
刑法253条 業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁形に処する。
業務上横領罪は罰金刑がないため、刑事告訴をされた場合、裁判所の法廷で刑事裁判を受け、最悪の場合は執行猶予のつかない実刑となることがあります。

[参考記事]
業務上横領罪で逮捕!初犯・少額でも懲役刑になるのか?
(2) 民事責任
民事責任は、被害者に対して負う財産上の責任です。
要するに、横領犯人が、横領の被害者である会社に対して横領によって生じた損害を賠償する責任のことです。これは、刑事罰を科される上記の刑事責任とは別のものです。
横領行為は、会社に対して違法に損害を与える「不法行為」ですから、横領犯人は損害を賠償する義務があります(民法709条)。
また、会社の金銭を消費したケースでは、会社に損失が生じる一方で、横領犯人は法律上の原因なくして利得しているので、「不当利得」として、利得した金銭に利息を加えて会社に返還する義務があります(民法704条)。
会社としては、不法行為と不当利得のどちらか、あるいはその両方を根拠として、横領犯人に賠償を求めることが可能です。
また、通会社の就業規則に従って懲戒処分を受ける可能性も高いです。
2.家族に業務上横領の法的責任はある?
(1) 横領犯の家族の刑事責任
家族が業務上横領罪を犯した場合、罪を問われるのは横領行為を行った本人だけであり、他の家族が罪に問われることはありません。夫の犯罪で妻が責任を問われるようなことはないのです。
何故なら、刑事法の分野では、行為者の行った個人的行為についてのみ責任を問えるという「個人責任の原則」が認められ、団体責任や連座責任は原則として否定されているからです(※山口厚「刑法総論(第2版)」(有斐閣)6頁、大塚仁「刑法概説(総論)第4版」436頁など)。
ただし、家族が横領行為をそそのかしたり、家族と共謀して横領行為を行ったりしたなどの共犯関係が認められる場合は、当然に家族も業務上横領罪に問われます。
また、例えば、横領して得た会社の金銭を、それが横領行為によって得られたものであると知る者が譲り受けたときには、盗品等譲受罪(刑法256条1項)という犯罪が成立します。
もっとも、横領犯人と譲り受けた者との間に、配偶者・直系血族・同居の親族などの関係がある場合には刑を「免除」するものとされているので(刑法257条1項)、妻が処罰されることはありません。
横領犯人と一定の親族関係がある場合は、被害品と知りつつ受けとってしまうことも無理からぬ面があり、強く非難できないからです。
(2) 横領犯の家族の民事責任
「本人と家族が共犯となる場合や、家族が盗品譲受罪となるなどの場合でない限り、家族は責任を負わない」のは、民事責任でも同じです。
一方、本人と家族が共犯となる場合や、家族が盗品譲受罪となる場合は、家族自身も犯罪者ですから、横領犯人と共に共同不法行為責任を負い、横領犯人と連帯して損害賠償責任を負担します(民法719条)。
また、横領による金銭と知っていたか、または知らない場合でも重大な過失があるときは、家族も不当利得に基づく責任を負います。
もっとも、(本人と家族が共犯である場合はともかくとして)横領犯人の夫から妻が金銭を受け取って、横領した金と知りつつ生活費に使ったという場合、会社の損失と家族の利得との間には横領犯人の行為が介在しているので、不当利得の要件のひとつである「損失と利得の因果関係」が欠けるのではないかという疑問があります。
判例(※最高裁昭和49年9月26日判決/最高裁判所民事判例集28巻6号1243頁)によれば、不当利得制度は損失者と利得者の「実質的な公平」を図る制度なので、損失と利得との間に横領犯人の行為が介在していても、一方の損失によって他方の利得が生じたと社会通念上認めることができれば足ります。
そして、不当利得のもうひとつの要件である「法律上の原因を欠く」利得であることも、実質的公平の観点から判断するべきであり、妻が横領による金銭と知っていたか、または、知らない場合でも重大な過失があるときは要件を満たすと考えられます。
【家族が身元保証人の場合】
日本では古くから「身元保証」という制度があり、会社に入社する際に、身元保証書の提出を求める会社も少なくありません。この身元保証書は、民法の保証契約(民法466条)を成立させる書面ですから、本人が会社に損害を与えた場合には、身元保証人はその損害を賠償する義務を負います。
ただし、身元保証契約は、本人と身元保証人の人間関係から安易な引き受けがなされることが多いので、いったん身元保証人となった以上、会社が受けた損害の全額を負担しなくてはならないとするならば、予期しない多大な賠償義務を負う過酷な結果を招いてしまいます。そこで、身元保証人が責任を負う期間と範囲は、「身元保証ニ関スル法律」という特別法で規制されています。
身元保証契約には厳格な規制がありますので、もし会社から身元保証人として損害賠償を求められた場合でも、本当に賠償義務を負うかどうか、仮に負うとしてもいかなる範囲で責任を負うかを、弁護士に相談してください。
3.敢えて家族が支払いをすることは可能
上述した場合を除き、家族が「法的」な刑事・民事責任を負うことはありません。
では、法的な民事責任がないことを承知のうえで、敢えて家族が会社に被害弁償することはできるのでしょうか。
結論からいえば、法律上の賠償義務はないと分かったうえで、会社に対して賠償することは可能です。民法は債務者以外の第三者による弁済を有効と認めているからです(民法473条)。
また、実際にも、家族からの被害弁償の申し出を受けた際に、会社が受け取りを拒む可能性は低いですし、万が一受領を拒否された場合には法務局に供託することができます(民法494条1項1号)。
4.示談交渉を弁護士に依頼するメリット
被疑者本人やその家族は、弁護士に依頼することで、会社に対して示談交渉してもらうことができます。
法律の専門家である弁護士は交渉力にも長けておりますので、分割弁済など円満に解決するための交渉以外にも、被害届や告訴状を出さないように会社を説得してくれます。
家族の民事責任の有無を問わず、家族が被害弁償することで被害者(会社)に現実の被害がなくなるため、不起訴処分で終わる可能性が出てきます。仮に起訴された場合でも、量刑が軽くなる可能性があります。
また、解雇や減給、降格などの懲戒処分を軽くすることができる可能性もあります。
弁償状況によっては、諭旨解雇や、退職金なしの自己都合退職などに扱いを変更してもらえるケースがあります。
仮に被害届や告訴状が出されてしまった場合や、刑事裁判を起こされた場合にも、初期段階から事案の内容を把握している弁護士であれば、安心してその後の刑事弁護を依頼できます。
5.業務上横領と返済に関するまとめ
本人と家族が共犯となる場合や盗品譲受罪となるなどの場合でない限り、家族は刑事・民事の責任を負いません。
すなわち、罪を問われるのは横領行為を行った本人だけであり、家族が罪に問われることはありませんし、家族が支払いをする必要もないのです。
ただ、敢えて家族が会社に被害弁償することは可能です。これを会社が拒む可能性も低いです。
家族が被害弁償することで被害者(会社)に現実の被害がなくなるため、不起訴処分で終わる可能性が出てきます。
また、仮に起訴された場合でも、量刑が軽くなる可能性があります。
被害者(被害会社)への対応次第では、家族のサポートにより懲戒処分の内容を軽くしたり、不起訴・執行猶予を獲得できたりする可能性があるということです。
横領の罪を犯してしまいお困りの方やその家族は、泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。