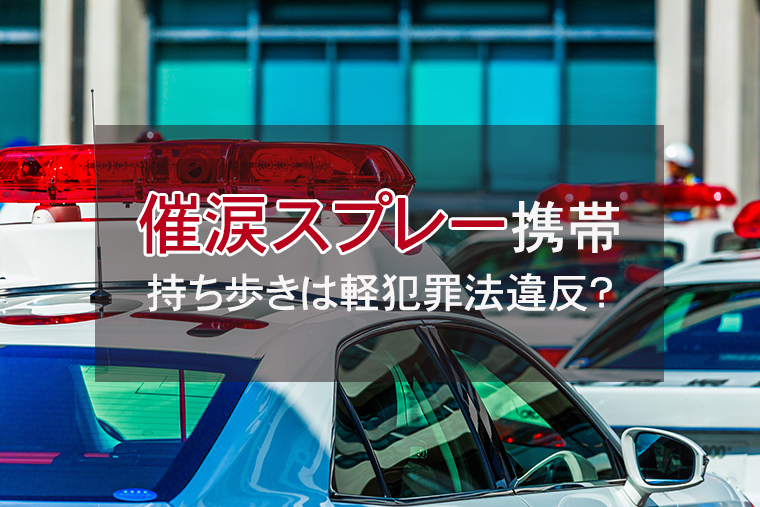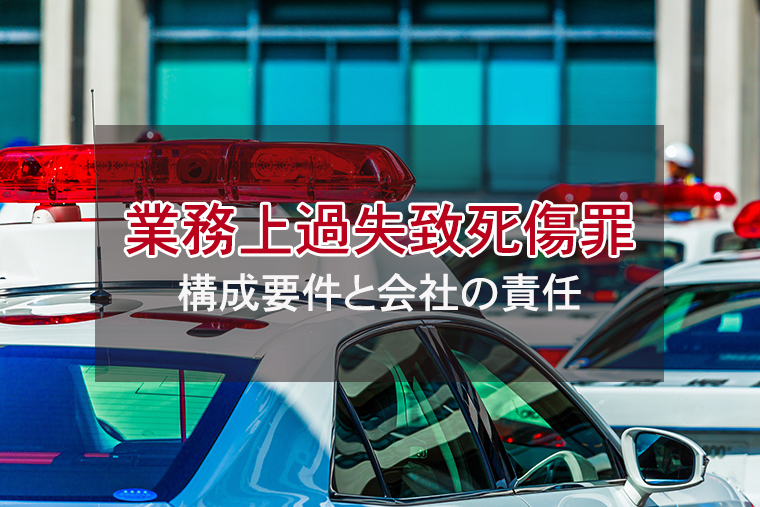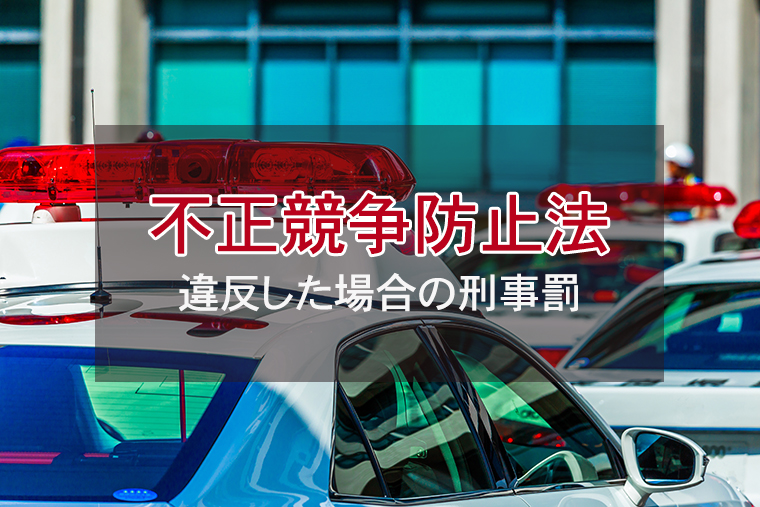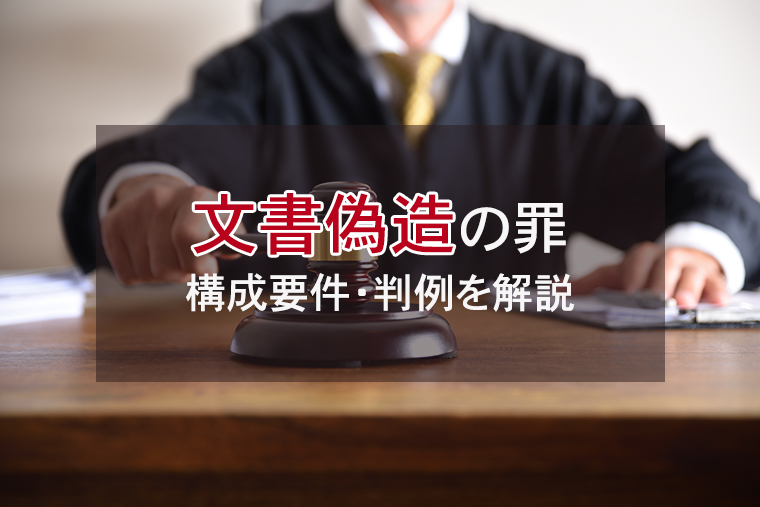銃刀法違反の逮捕基準|刃渡りと関係あるか
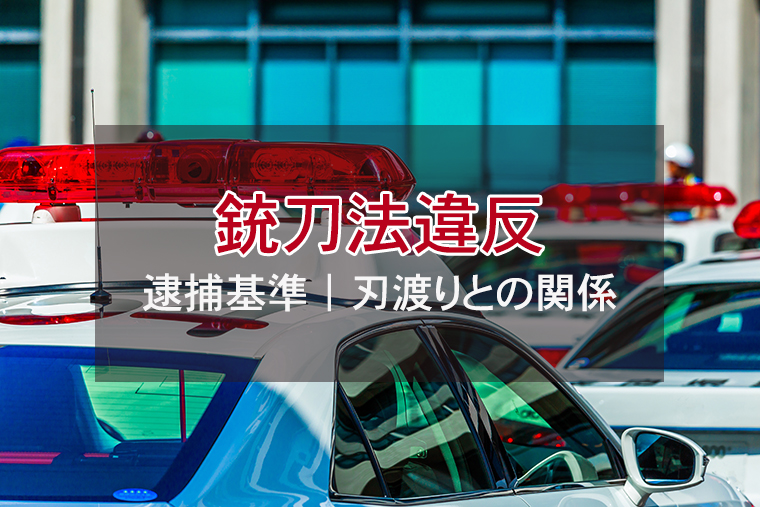
時々、テレビやインターネット上で「銃刀法違反でX容疑者を逮捕」というニュースを見たことがあると思います。
少し前になりますが、2020年4月に、横浜で包丁2本を携帯していたとして高齢の男が逮捕されるという事件が発生しました。
このように、我々の身近でも、銃刀法違反となるような事例が発生しています。
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法 )とは、銃や刃物を所持・携帯することを規制している法律です。
本コラムでは、銃刀法違反で逮捕される基準と、逮捕されてしまった場合の正しい対応方法について解説します。
1.銃刀法が規制している対象
銃刀法が規制している対象は、鉄砲、刀剣類、刃物に分類されます。
- 鉄砲:拳銃(ピストル)、小銃(ライフル)等です。エアガンであっても、人の生命に危険を与える威力を持つように改造を施している場合は鉄砲に該当し、銃刀法違反となります(銃刀法2条1項)
- 刀剣類:刃渡り15センチメートル以上の刀や槍、刃渡り5.5センチメートル以上の剣などが対象となります(銃刀法2条2項)(※1)
- 刃物:刃体の長さが6センチメートルを超えるものが対象です(銃刀法22条)(※2)。
また、金属製であれば、模造けん銃・模擬銃器・模造刀剣類も規制の対象になります(銃刀法第22条の3ないし4)。
そのため、アニメキャラクターなどのコスプレにおいても、金属製は避ける方が無難です。
(※1)「刃渡り」とは、「刃長(刃の長さ)」ですが、その測定方法は刀剣類の種類によって異なります。日本刀などの場合、切先(きっさき)から、棟区(むねまち)までを直線で測ります。日本刀の刀身のうち、使用時に柄(つか)の中に隠れる握りの部分は凹んでおり、これを「茎(なかご)」と呼びます。刀身の刃のつけられていない側を「棟(むね)」と呼び、棟側の茎の凹んだ箇所が棟区です。「刃渡り」は、次の「刃体の長さ」とは別概念であることに留意してください。
(※2)「刃体の長さ」は、切先(または刃体の先端)から、柄部における切先(または刃体の先端)にもっとも近い点を結ぶ直線の長さを測定します(銃刀法施行規則101条1項)。また、切り出しナイフや日本カミソリのように、刃体と柄部の区別が明らかでない場合は、刃物の全長から8センチメートルを差し引いた長さを「刃体の長さ」とするなど、これも刃物の種類に応じて測定方法が異なります。ただし、刃体の長さに関係なく、正当な理由なく刃物を隠して携帯する行為は軽犯罪法で禁止されています(軽犯罪法第1条2号)。そのため、「刃体の長さが6センチメートル以下だから法律違反ではない!」ということにはなりません。
2.規制される行為
銃刀法が規制している行為は、規制される凶器によって異なります。
- 鉄砲
原則として所持・輸入・譲り渡し・貸し付け・譲り受け・借り受けが禁止されます。例えば、けん銃の所持は、1年以上10年以下の拘禁刑です。
また、鉄砲の中でも、けん銃の場合は、その部品(銃身や回転弾倉)や実包(弾丸)の所持等もほぼ同様に禁止されています。 - 刀剣類
原則として所持が禁止されています。違反は、3年以下の拘禁刑は50万円以下の罰金です。 - 刃体の長さが6cmを超える刃物
携帯が禁止されています。違反は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。
もっとも、これらの物の所持や携帯が許される例外があります。
例えば、警察官によるけん銃の所持や、法定の機関から所持の許可を受けた場合などです。けん銃や刀剣類を許可を受けないで所持等した場合は、基本的に違法となります。
他方、刃体の長さ6センチメートルをこえる刃物の携帯に関しては、許可の制度はなく、正当な理由がある場合の携帯が許されます。
例えば、料理人が業務目的のため刃物を持ち歩く場合や、自宅内で調理するために包丁を買って帰る場合などがこれに当たります。しかし、護身のための携帯はこれに当たらないと解されています。
なお、6センチメートルをこえる刃物でも、政令で定める種類・形状のものは対象から除外されます。例えば、刃体の長さが8センチ以下で、刃体の厚さが0.15センチ以下、先端部が丸みをおびた果物ナイフなどです。
また、注意が必要なのは、先述のように、刃体の長さが6センチメートルをこえなくても、正当な理由のない刃物(ハサミ、カッターナイフ等)を隠しての携帯は軽犯罪法で規制されています。軽犯罪法違反は、拘留又は科料となります。
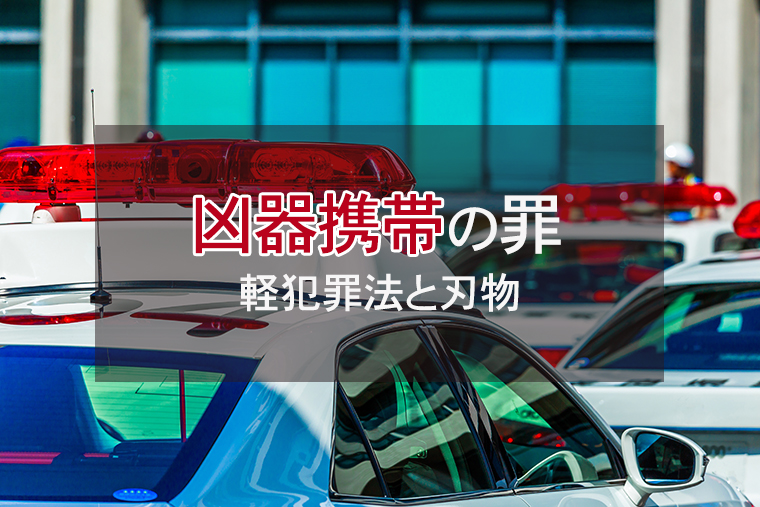
[参考記事]
軽犯罪法と刃物|凶器携帯の罪について
「所持」と「携帯」は似ているようで異なる意味を持ちます。所持とは、自己の支配に置くことを言います。そのため、手で持っている場合や鞄に入れている場合だけでなく、家のどこかにおいている場合も所持していると評価されます。
他方、携帯とは、持っていたり身につけていたりする場合などを指します。そのため、家のどこかに包丁をおいている場合には携帯していると評価されません。
このように、「携帯」より「所持」の方が、カバーする範囲が広い概念なのです。
3.銃刀法違反で逮捕されるケース
銃刀法に違反して刃物などを携帯した場合に、逮捕される可能性はあります。
もっとも、「刃体の長さが10センチメートルをこえた場合は逮捕される」といったように、刃体の長さが、逮捕するか否かの判断に直接繋がるというわけではありません。
銃刀法に違反した場合に逮捕されるか否かは、逮捕の必要性があるか否かで決せられます。
逮捕の必要性があるか否かは、被疑者に逃亡の恐れがあるか、又は、罪証隠滅の恐れがあるか等を基準に判断します。
例えば、被疑者が容疑を否認していたり、住所が不定だったり、被疑者が暴力団構成員で対立団体との抗争という組織的な犯罪行動の一環として凶器を所持していたりした場合、罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断され、逮捕がなされることが多いでしょう。
逆にいえば、仮に刃体の長さがかなり長いものである場合でも、逮捕の必要性がなければ逮捕はされません。
ただ、罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れがなくても、現行犯逮捕は許されます。刃物を手に握りしめ商店街を歩いた場合などには、周りの人の生命や身体を守るため、刃物を提出させることができます(銃刀法第24条の2)。これに素直に従わなければ、現行犯逮捕が行われることがほとんどでしょう。
4.銃刀法違反で逮捕されたらすぐに弁護士に相談を
銃刀法違反で逮捕された場合、2~3日の身体拘束がなされます。また、続けて勾留の必要性があると判断された場合は、更に10日以上の身体拘束がなされてしまいます。
操作によって検察官が起訴の判断を下した場合は、罰金刑や公判請求を受けることになってしまい、前科の可能性がかなり高くなります。
特に、公判請求(裁判)を受けることは非常に多くの負担がかかります。前科があるなどの理由で執行猶予がつかなければ、即刑務所行きという事もあり得ます。
これらの事態を防ぐため、銃刀法違反で検挙されたらなるべく早期に弁護士に相談することが重要です。
例えば、キャンプに持って行くためのナイフをうっかりバッグに入れたまま外出してしまい、たまたま職務質問を受けて銃刀法違反として検挙されてしまうケースがあります。
このようなケースではほとんど罰金刑で済みますが、罰金刑であっても前科となってしまいます。
バッグに入れていたことを忘れていたなら、故意がなく犯罪とはなりませんし、そのナイフが規制対象となる大きさかどうか微妙なケースも少なくありません。
ただ、本人だけで警察・検察に対してこのような主張を行い、理解させることは事実上至難の業です。刑事弁護に詳しい弁護士にお任せください。
弁護士ならば、万が一起訴された場合でも法廷で弁護活動を行ってくれます。
銃刀法違反などの刑事事件を犯して逮捕されたら、どうぞお早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。