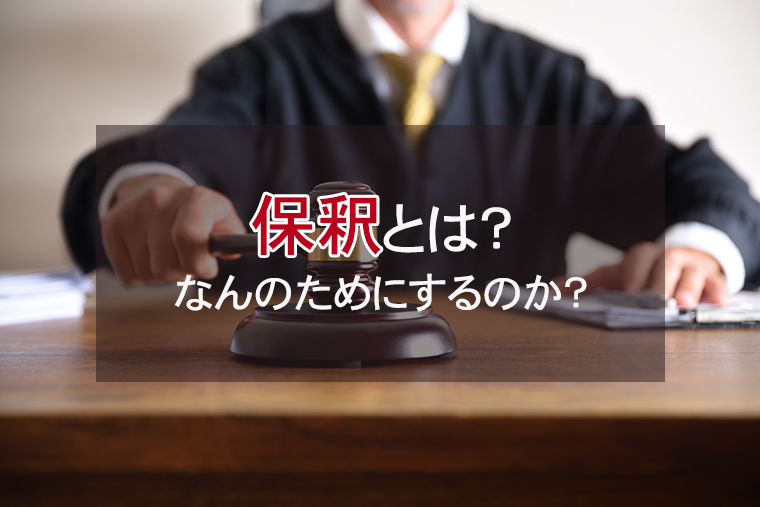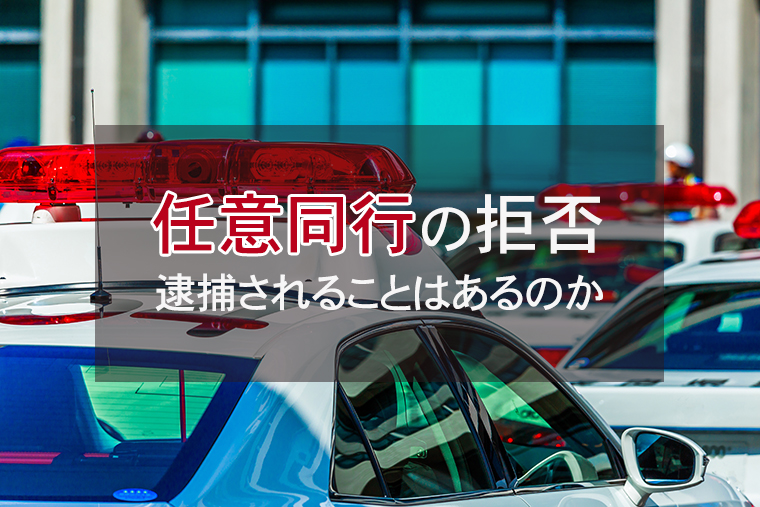刑事事件の控訴とは?上訴・上告・再審との違い

刑事事件で逮捕された場合、事案によっては裁判になってしまうこともあります。
裁判となり下された地方裁判所や簡易裁判所の判決に納得がいかない場合、「控訴」することができます。
しかし、控訴するには具体的にどうすればいいのか、どのような場合に控訴が認められるのか(控訴して無駄にならないのか)等、分からない方も多いと思います。
また、控訴という言葉を聞くと、「上告」「上訴」「再審」という言葉も頭によぎる方がいると思います。これらの違いについて理解されている方は少ないのではないでしょうか。
以下においては、控訴の要件や効果、上告・上訴・再審との違いについて解説していきます。
1.控訴とは?
(1) 控訴の内容
控訴とは、地方裁判所又は簡易裁判所が下した第1審の判決に不服がある場合に、高等裁判所に対し、その取消・変更を求める申立てのことをいいます。
控訴の申立てをすることができるのは、第1審判決を受けた当事者である検察官と被告人です。被告人の法定代理人(弁護士など)も控訴することが可能ですが、被告人の明示の意思に反した申立ては許されません(刑事訴訟法353条等)。また、犯罪の被害者は控訴することができません。
控訴の提起期間は、第1審の判決の宣告のあった日から14日(初日は算入されませんので、判決宣告日を含めると15日)以内です。その間に控訴しなければ控訴権が消滅し判決が確定します。
反対に、控訴を行えば刑事裁判の判決は確定せず、控訴審(控訴後の裁判)が行われます。
また、控訴審では、原則として、被告人に公判期日の出頭義務はありません。
(2) 控訴審の流れ
控訴審は事後審(第1審の審理や判決について違法・不当な点がないかどうかを事後的に審査すること)ですので、はじめから裁判をやり直すわけではありません。
したがって、控訴審では、公判を開いても、検察官や弁護人が判決に誤りがあるかどうかについて意見を述べるだけで、第1審のように法廷で証人やその他の証拠の取り調べをしないのが原則です。
もっとも、第1審の証人を呼んで聞き直したり、第1審当時は様々な事情で調べることのできなかった証人を取り調べたりして、事実を確かめることは許されています。
記録を調査したり、事実の取り調べをしたりした結果、第1審の判決に誤りのないことが分かった場合には、控訴審は第1審判決を維持する「控訴棄却」の判決をします。
一方、第1審の判決に誤りが発見された場合には、控訴審はこれを取り消すため「原判決破棄」の判決をします。原判決が破棄されますと、まだ第1審の判決が出されていないのと同じ状態になります。
そこで、破棄差戻し(移送)か破棄自判することになります。
「原判決破棄差戻し」「原判決破棄移送」は、更に証拠を取り調べたり、誤りを正して判決をやり直したりした方がよい場合に言い渡します。そうすると、事件は再び第1審で審理されることになります。
「原判決破棄自判」は、控訴審での審理の結果、すぐに結論が出せる場合に、第1審に差し戻さないで代わりに自ら判決を言い渡すことをいいます。
なお、控訴審で「原判決破棄」される多くの理由は判決後の情状、量刑不当、事実誤認、法令適用の誤りです。
少し古いデータですが、平成30年度の裁判所司法統計(控訴事件)を記載します。控訴審で終結した事件の総人数は5,710人ですが、このうち第一審判決が破棄されたのは576人で約10%にとどまります。
| 破棄事由 | 内容 |
| 判決後の情状 | 第1審の判決後に、刑の量刑に影響を及ぼす情状事実がある |
|---|---|
| 量刑不当 | 第1審の判決の言い渡した刑が、重過ぎあるいは軽過ぎて合理的な裁量の範囲外にある |
| 事実誤認 | 第1審の判決の認定した事実が、訴訟記録中の適法な証拠を考慮に入れて認定されるべき事実と合致していない |
| 法令適用の誤り | 認定された事実に対し適用すべき法令を適用していない |
| 控訴終局総人員 5,710人 |
破棄人員 576人(10.1%) | ||||
| 判決後の情状 | 量刑不当 | 事実誤認 | 法令適用の誤り | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113人(19.6%) | 456人(79.1%) | 178人(30.9%) | 40人(0.06%) | 1人(0.0%) | |
参考:司法統計「控訴事件の破棄人員」「控訴事件の終局総人員」
*2以上の控訴理由がある場合はそれぞれの理由欄に計上
2.控訴ができる要件
控訴の申立ては、刑事訴訟法第384条が定める事由を理由とする場合に限り可能です。
控訴申立理由は以下の通りです。
- 法律に従って判決裁判所を構成しなかった
- 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した
- 審判の公開に関する規定に違反した
- 不法に管轄又は管轄違を認めた
- 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却した
- 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をした
- 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがある
- 訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである
- 法令の適用に誤りがあってその誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかである
- 刑の量定が不当である
- 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること
3.上告・上訴との違い
(1) 上告とは?
上告とは、高等裁判所の判決に不服がある場合に、最高裁判所に対しその取消・変更を求める申立てのことをいいます。上告の申立権者は、控訴の申立てと同じです。
控訴が「地方裁判所」又は「簡易裁判所」が下した「第1審」の判決に対する申立てであるのに対し、上告は「高等裁判所」で行われた「第1審や第2審、控訴審」の判決が確定する前に、その判決について不服申立てを行うという違いがあります。
(2) 上訴とは?
上訴とは、「控訴」「上告」を総称したものです。
確定前の判決に不服がある場合に、上級の裁判所に対し、その取消・変更を求める申立てのことを広く「上訴」と言います。
4.再審とは?
(1) 再審について
「再審」とは、確定した判決に事実認定の誤りがある場合に、これを是正するためにとられる非常救済手続のことです。
最近では、約60年前の袴田事件について、2023年10月から計15回開催された再審公判が結審し、再審無罪が確定しました。
確定判決には既判力(確定力)が生じており、通常の手続では争うことができません。しかし、誤った裁判をそのままにしておくことは司法の正義に反するため、このような手続が認められているのです。
再審裁判においては不利益変更禁止の原則が適用され、原判決より重い刑を言い渡すことはできません。
これまでの著名な再審無罪判決(確定)には、袴田事件以外に以下のようなものがあります。
- 弘前大学教授夫人殺し事件(仙台高判昭52.2.15高刑集30・1・28、判時849・49)
- 青森老女殺し事件(青森地判昭53.7.31判時905・15)
- 免田事件(熊本地八代支判昭58.7.15判時1090・21)
- 財田川事件(高松地判昭59.3.12判時1107・13)
- 松山事件(仙台地判昭59.7.11判時1127・34)
- 徳島ラジオ商殺し事件(徳島地判昭60.7.9判時1157・3)
- 梅田事件(釧路地判昭61.8.27判時1212・3)
- 島田事件(静岡地判平元.1.31判タ700・114)
- 足利事件(宇都宮地判平22.3.26判時2084・157)
- 布川事件(水戸地土浦支判平23.5.24)
- 東電OL殺人事件(東京高判平24.11.7)
- 東住吉事件(大阪地判平28.8.10)
- アンドレイ事件(札幌地判平29.3.7)
(2) 再審公判をするための要件
再審請求の対象となるのは、有罪の言渡しをした確定判決です。その他一定の場合に、控訴棄却・上告棄却の確定判決も対象になります。
再審請求をするためには、一定の再審事由が必要です。これは刑事訴訟法435条各号に記載されています。
再審請求の多くは、6号の事由です。有罪判決を受けた者に無罪等を言い渡し、あるいは原判決よりも軽い刑を認めるべき「明らかな証拠」(証拠の明白性)を「あらたに発見した」(証拠の新規性)ことを根拠とするものです。
かつての実務は、裁判の確定による法的安定性を重視し、6号事由における証拠の明白性・新規性を厳格に解釈してきました。
しかし、最高裁は、昭和50年、いわゆる白鳥事件決定で、
「法435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきであるが、右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、果たしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、この判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用される」
と説示しました(最決昭50.5.20刑集29・5・177)。
そして、最高裁は、「疑わしいときは被告人の利益に」という原則を具体的に適用するに当たっては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであることを必要とし、かつ、これをもって足りるとしています(最決昭51.10,12刑集30・9・1673〔財田川事件決定〕)。
実例として再審が認められるものは、道路交通法違反、過失運転致死傷罪などの交通事故が相当部分を占めています。
それらの交通事犯については、犯人の身代わり、保険金目当ての事故偽装、氏名冒用などが発覚した事例が多いとされています。
(3) 再審の流れ
裁判所は、再審請求が不適法であると認めるときは、決定でこれを棄却し、適法であっても理由がないのであればやはり決定でこれを棄却しなければなりません。
一方、再審の請求が要件を満たしている時は、裁判所は再審開始決定をしなければなりません。
最近の実情では、年間の再審請求件数は平均すれば200件強のようです。
それらのうち、再審開始決定があったのは数件程度で、そのほとんどが検察官請求によるものです。
再審開始の決定をしたときは、原確定判決による刑の執行を停止することができます。
また、高裁による再審開始決定に対し異議の申立てができます。
再審開始決定が確定すると、再審で取り消してほしい最初の判決(原判決)をした裁判所が裁判のやり直しを行います。
5.刑事裁判も泉総合法律事務所へご依頼ください
刑事事件で裁判になってしまい、判決内容に納得がいかないという場合には、「控訴」することで再び争うことができます。
しかし、控訴審では第1審が不当であるということを的確に主張していかなければなりません。それは、ただでさえ様々な不利益を被っている被告人にはとても困難なことです。
とはいえ、「自白や共同被告人の供述、目撃供述といった直接証拠に頼った捜査をしてした」「無実を訴えている被告人の供述に耳を貸さなかった」「違法な取調べやでされた自白を肯定した」「捜査官側の専門家の意見のみに依拠した」「証拠・検証・鑑定の結果に疑惑があるのにその解明を怠った」など、あらゆる事象で判決が覆る可能性はあるものです。
控訴を考えているならば、あなたのことを親身になって弁護してくれる、刑事事件に強い弁護士に相談するべきです。
刑事事件でお悩みの方は、経験豊富な泉総合法律事務所に是非一度ご相談ください。