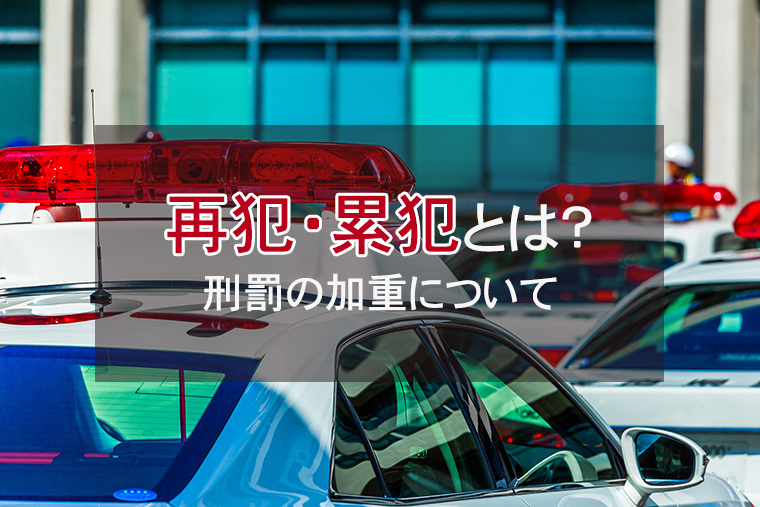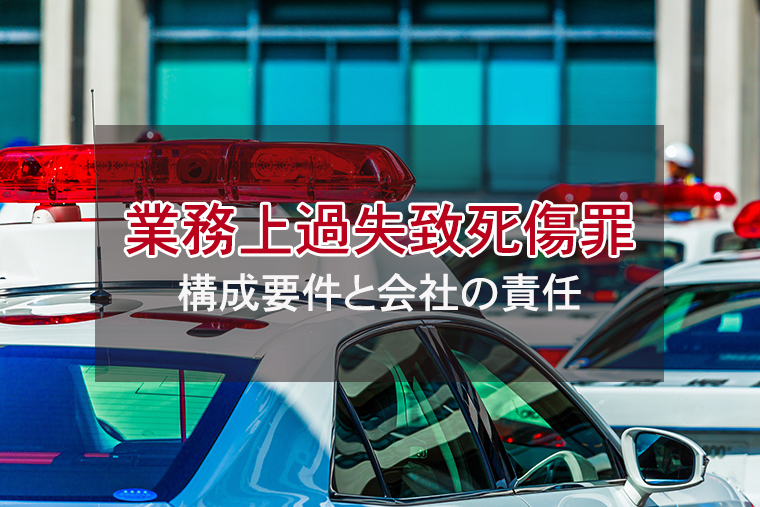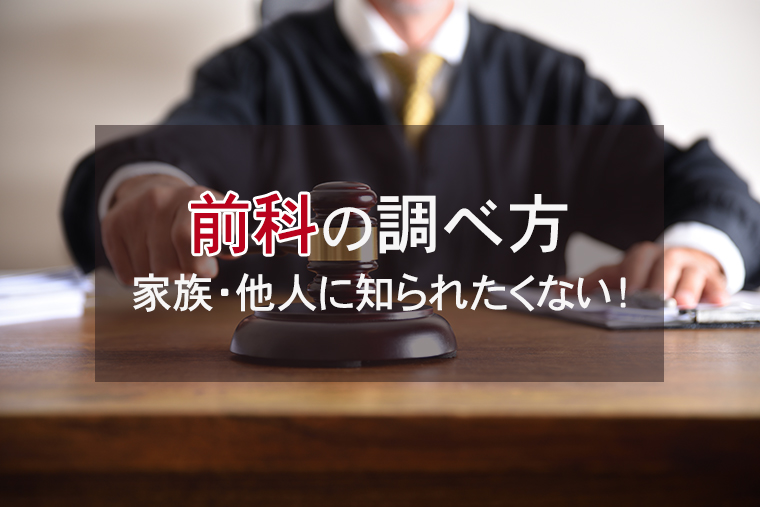実刑判決後の再保釈は認められるのか?
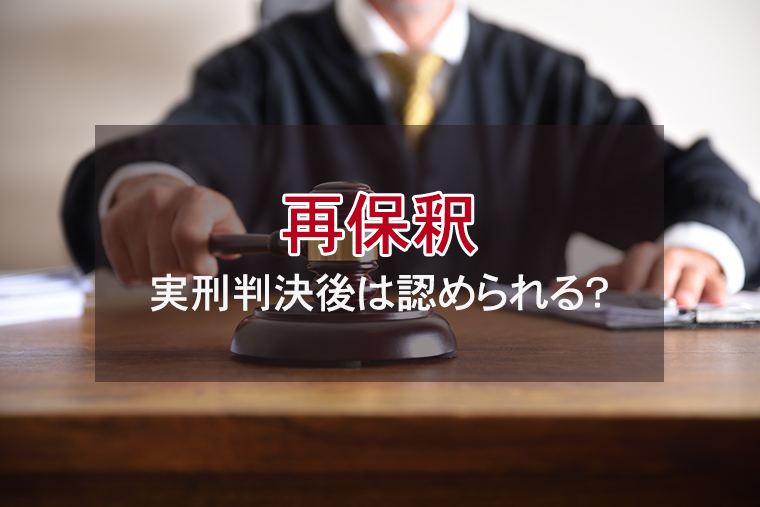
刑事事件の「被疑者」として逮捕・勾留された者が、検察に起訴され、刑事裁判にかけられることが決まると「被告人」となります。被告人となった後は、保釈金(保釈保証金)を裁判所に納付すること引き換えに、釈放してもらえる場合があります。これが「保釈」制度です。
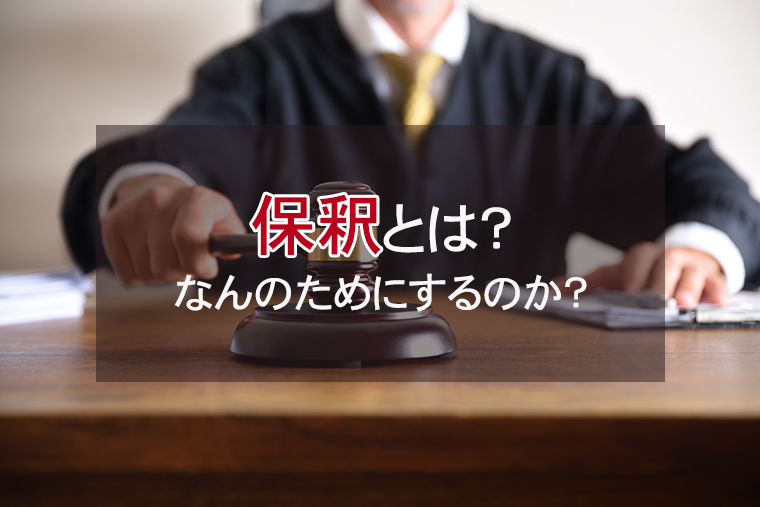
[参考記事]
保釈をわかりやすく解説|なんのためにするのか?
保釈されれば、自宅で家庭生活をし、職場で仕事をするなどしながら、並行して刑事裁判を受けることができます。
では、その刑事裁判(第一審)が進み、刑務所行きという実刑判決を受けてしまった場合は、二度と保釈される機会はないのでしょうか?
実は、その機会はあります。それが「再保釈」です。
1.再保釈とは?
(1) 拘禁刑以上の有罪判決で保釈は失効する
保釈されて身柄を拘束されないまま刑事裁判を受けている被告人が、その裁判において拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けると、保釈の効力は失われます(刑訴法343条1項)。
拘禁刑以上の刑とは、具体的には、死刑または拘禁刑です。
保釈を失効扱いとするのは、
①判決の確定前とは言え、第一審判決の結論は重視すべきこと
②判決前よりも逃亡のおそれが強くなり、刑の執行を確保するべく身柄拘束の必要性が高まること
などが理由とされています。
保釈の効力が失われる結果、被告人は、検察官の指揮を受けた検察事務官等によって刑事施設(拘置所)に再収容されることになります。
具体的には、法廷における判決の宣告後、検察事務官が被告人を一般公衆の目に触れない場所(裁判所内の被告人専用通路など)へと任意に連れ出したうえ、直ちに身柄を拘束し、いったん検察庁の建物へ連行することが通例です。
その後、さらに検察庁から拘置所まで連行することになります。
(2) 再保釈で再収容を阻止できる
このような有罪判決による再収容を阻止するには、再度の保釈を申請し、これが裁判所に認められる必要があります。これが「再保釈」です。
有罪判決に対する控訴の有無にかかわらず、再保釈の申請は可能です。

[参考記事]
刑事事件の控訴とは?上訴・上告・再審との違い
再保釈の申請が控訴前の場合は、有罪判決を宣告した当該裁判所に対して申請を行います。
控訴後の再保釈請求は控訴審の裁判所に対して行いますが、控訴後でも訴訟記録が控訴審の裁判所に到達する前は、やはり有罪判決を宣告した裁判所に対して再保釈を申請します。
したがって、有罪判決を宣告された当日のうちに収容される事態を阻止するには、①控訴するか否かは後回しにして、ただちに再保釈を申請するか、②ただちに控訴すると共に、再保釈を申請するかのどちらかの方法をとることになります。
2.再保釈が認められるのは難しい?
では、この再保釈は、最初の保釈(有罪判決を受ける前の保釈)よりも認められることが難しいのでしょうか?
(1) 保釈制度の種類
そもそも保釈には、異なる2種類の制度があります。「権利保釈」と「裁量保釈」です。
権利保釈
権利保釈とは、保釈の申請があれば、法定の除外事由がない限りは必ず保釈が認められる制度です。
除外事由としては、被疑事実が重大犯罪であるとき、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるときなどが法定されています(刑訴法89条)。裁量保釈
裁量保釈とは、権利保釈の要件を満たさない場合でも、裁判官の裁量で保釈を認める制度です。裁判官が諸事情を考慮して適当と認めるときに、職権で保釈を許すことができます。
裁判官の考慮するべき事情とは、以下のものとされています。
- 被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれの程度
- 身体拘束の継続で被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・刑事裁判における防御の準備上の不利益の程度
- その他の事情
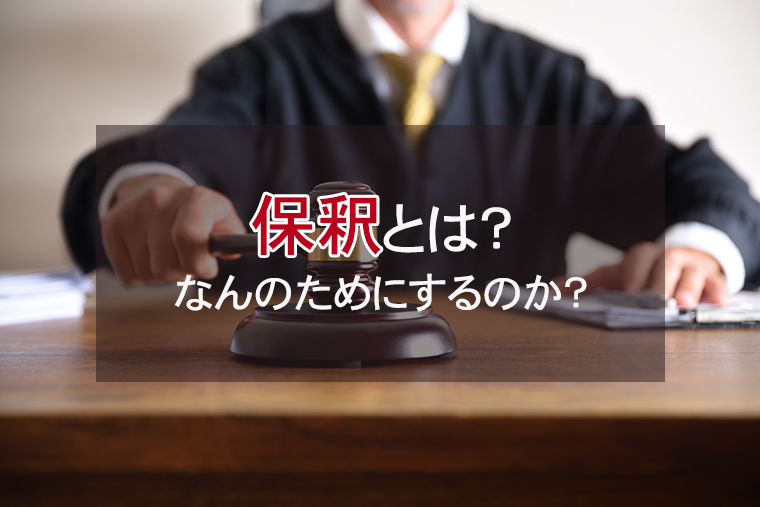
[参考記事]
保釈をわかりやすく解説|なんのためにするのか?
(2) 有罪判決後は裁量保釈しか認められない
拘禁刑以上の有罪判決の宣告を受けた後の被告人には、権利保釈の制度は適用がなく、裁量保釈を求めることしかできません。これは、逃亡のおそれが高くなり、同時に、刑執行のための身柄確保の必要性も高くなるからです。
しかも、この場合の裁量保釈は、前述の裁判官の考慮するべき事情につき、「①身体拘束の継続によって被告人が受ける不利益の程度が著しく高い場合」または「②逃亡のおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由がある場合」でなくては、保釈を認めることはできません。
このように、再保釈が認められるためのハードルは、有罪判決前よりも高く設定されているのです。
3.再保釈に向けた弁護活動について
保釈中の被告人が一審で有罪判決を受けた場合、身柄拘束を回避するために再保釈の手続を行うことは、弁護士にとって重要な弁護活動のひとつと言えます。
(1) 再保釈の申請には事前の準備が必須
前述のとおり、第一審で拘禁刑以上の有罪判決を受けた場合、ただちに身柄を拘束されます。そして、再保釈の決定がない限りは、その日のうちに拘置所など刑事施設に収容されてしまいます。
これを回避するには、控訴するか否かにかかわらず、判決当日のうちに再保釈を認めてもらうべく、有罪判決を受けた直後に、その裁判所に対して再保釈の申請を行う必要があります。
その日のうちに迅速に再保釈申請を行うには、有罪判決の可能性に備えて、事前に再保釈申請の準備を完璧にしておかなくてはなりません。
また、再保釈が許されると、前に納付済みの保証金は再保釈の保証金の一部として納付されたものとみなされますが、保釈保証金は再保釈で増額されることが通常ですので、予想される増額分を事前に手配しておき、すぐに納付できるよう準備しておくことも必要です。
これらの手続きを、当日のうちに短時間でスムーズに進めることができるのは、刑事手続の専門家である弁護士だけです。
(2) 弁護士が適切に資料を集めて主張できる
前述のとおり、再保釈の場合は権利保釈が認められず、裁量保釈が許される条件も狭くなっています。
そこで弁護士が、「①身体拘束の継続で受ける不利益の程度が著しく高いこと」または「②逃亡のおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があること」を、証拠をもって裁判官に示し、職権を発動してくれるよう説得する必要があります。
有罪判決前の保釈よりもハードルが高いことを前提として、前に保釈が認められた際よりも、より説得力のある理由と証拠を提示する必要があります。
(3) 反省を示すため保釈請求をしないという方針について
起訴事実に間違いがないと自白しており、有罪判決が確実な場合は、保釈請求をしない方が良いのではないか?という意見があります。
あえて身柄を拘束されたままにしておくことで、真剣に反省している態度を示せば、量刑上有利な事情として、裁判官に斟酌してもらえるという考え方です。
たしかに、申請すれば保釈される可能性が高く自己資金などで保証金の調達も容易なのに、あえて保釈を求めず、それが「真摯な反省の態度の表れ」と主張し裁判官に一定の評価をしてもらえるケースはあります。
さらに、比較的軽い罪状の事案では、「これまでの身柄拘束によって、既に十分な制裁が終わっている」と主張することもできます。
したがって、このような方針も、裁判への臨み方のひとつであり、頭から否定するべきではありません。
ただ、身柄拘束中は、弁護士以外の者とは(家族であっても)短時間しか面会が許されませんし、事案によっては家族であっても面会が禁止される場合もあります。
このため、仕事の処理や引き継ぎ、家族の生活状況などについて、必ずしも十分な準備・対応をできないままで、服役生活に突入してしまう危険があります。
それよりも、保釈や再保釈で収容を免れ、今後見込まれる服役期間中の懸案事項などについて十分な対処をしてから収容の日を迎える方が、安心して服役し、内省を深めることができます。
また、保釈、再保釈で身柄を開放されることは、控訴審を戦うためにも非常に有益です。たとえ事実関係に争いはなくとも、量刑不当などで有罪判決の内容に不服がある場合、再保釈が認められれば、弁護士との打ち合わせなど、控訴審対策に十分な時間をとることもできます。
これらの理由から、弁護士としては、保釈・再保釈の申請をお勧めするのが通常です。
4.再保釈で虫歯の治療をした事例
再保釈によって対策できる問題のひとつに、たとえば被告人自身の健康問題があります。具体例をご紹介しましょう。
弁護士から有罪判決を受ける可能性があると助言されていた被告人Aさんは、残念ながら地裁で2年間の拘禁刑を宣告されました。
服役にあたる弁護士からの助言は複数に渡りましたが、そのひとつに、「虫歯があるなら、収監までに、全部、完全に治療を終えておくべきです」というものがありました。
刑務所の中でも歯科の治療を受けることはできますが、設備も歯科医も足りず、順番待ちになります。どんなに虫歯が痛くなっても、治療してもらえるまで数ヶ月も待たされるケースもあります。
その間、鎮痛剤だけで対処するのはかなり辛い生活になるのです。
Aさんはこのアドバイスを受け入れて、再保釈申請を弁護士に依頼しました。再保釈は裁判所に認められましたので、再保釈中に歯科医院に通い、最終的に実刑判決が確定して収監されまでの間に、複数あった虫歯の治療を完全に終えることができました。
これにより、少なくとも虫歯の激痛に悩まされる不安なく刑を終えることができました。
5.実刑判決後の保釈請求は刑事事件に強い弁護士へご相談を
一審で実刑判決を受けても、再保釈によって身柄拘束を免れることができ、仕事や今後の家族問題への対処、服役の準備、控訴審対策などに注力することが可能となります。
ただ、再保釈は最初の保釈よりもハードルが高くなり、事前の十分な準備が必要となるなど、刑事弁護に強い弁護士に依頼することが肝要です。
お困りの方やその家族は、再保釈の実績もある泉総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。