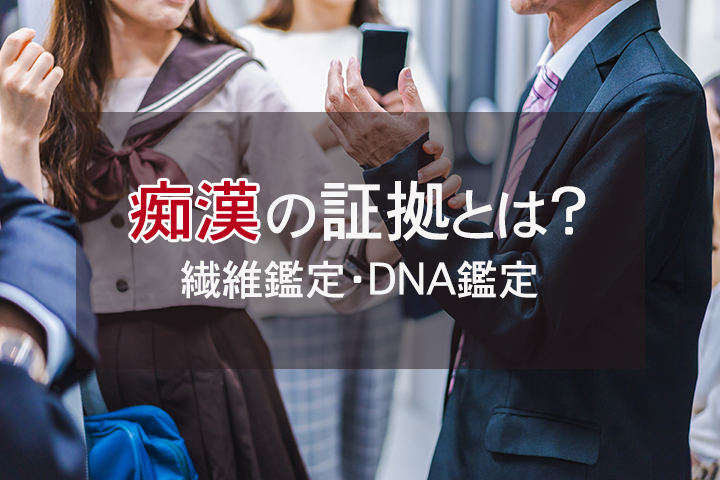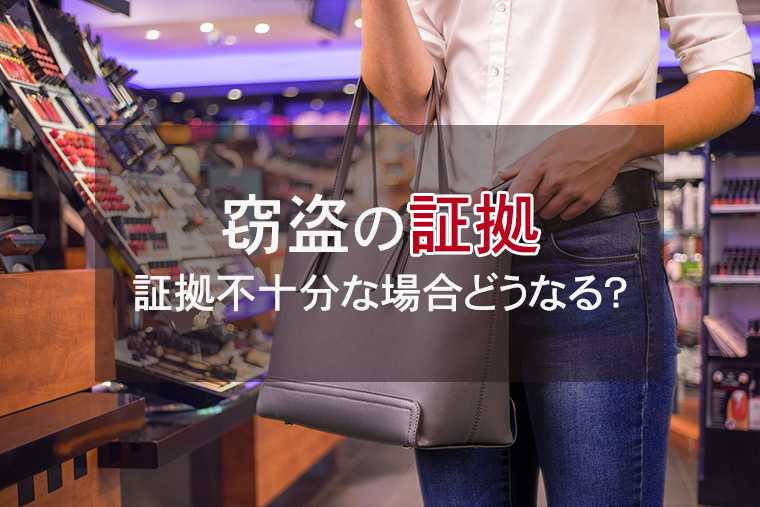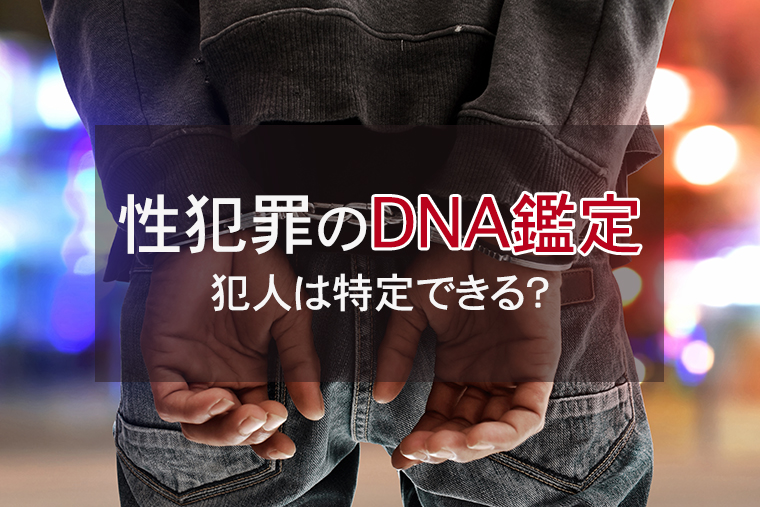刑事事件の証拠になるもの|物的証拠・状況証拠など
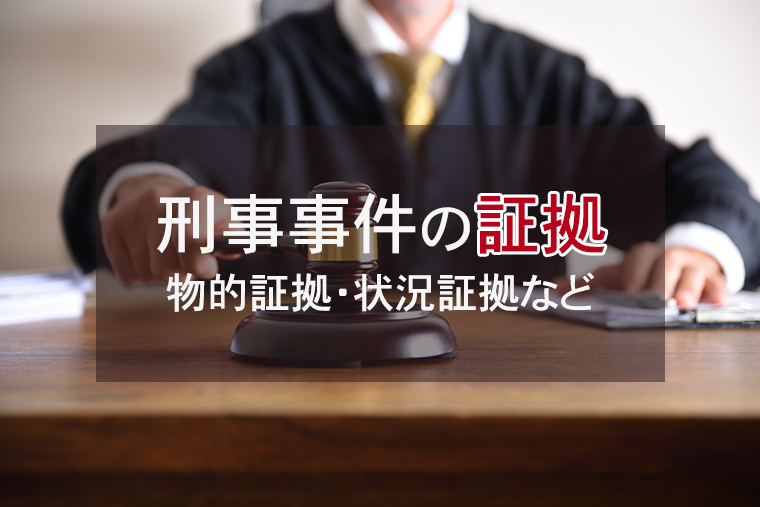
刑事事件における「証拠」とは、「裁判上、事実認定の基礎とすることのできる資料」のことをいいます。
そして、「証拠」は様々な観点から分類することができます。
インターネット上では、「無断で録音した音声データは違法な証拠なのでは?」「物的証拠がなく状況証拠のみで判決が出るなんて…」という意見が出ることもあります。
刑事事件の証拠になるものとしては、どのようなものがあるのでしょうか?
1.物的証拠と人的証拠の違い
(1) 物的証拠
物的証拠とは、物理的な形態を持つ証拠のことを指します。
分かりやすく言えば、凶器や血痕、指紋、DNA、文書、写真、ビデオ映像、衣服、遺留品など、事件に関連する様々な物品が含まれます。
物的証拠の最大の特徴は、その客観性にあります。物は嘘をつきませんし、記憶が曖昧になることもありません。そのため、時間が経過しても証拠価値が変わらず、科学的な鑑定によって客観的な分析が可能です。
例えば血液型やDNA鑑定、指紋照合などの科学捜査によって、高い精度で事実関係を証明することができます。
ただし、物的証拠にも限界があります。物それ自体は何も語らないため、その物がどのような状況で、誰によって、どのように使用されたかを解釈するには、他の証拠との組み合わせや専門家による鑑定が必要になります。
(2) 人的証拠(供述証拠)
人的証拠とは、人間の知覚や記憶に基づく証拠のことで、主に証人尋問や被告人質問などの供述証拠を指します。例えば、Aが「私は、B課長が女子社員C子の胸を無理矢理触るところを見た」という目撃者の証言や、被害者の供述、被疑者の自白などがこれに該当します。
人的証拠の強みは、事件の経緯や動機、状況などを具体的に語ることができる点にあります。
しかし、人の知覚・記憶・表現・叙述というプロセスには、嘘や誤りが混入しやすいものです。利害関係や感情、思い込みによって証言が歪められる可能性もあります。
誤判を防止するためには、本当にAが「BがCの胸に触るところを見た」のか、その真実性を吟味しなくてはなりません。吟味ができないのであれば、この証言を証拠とすることはできないことが原則です(刑事訴訟法321条1項3号)=伝聞法則。
一方、例えば録音テープにC子の悲鳴が録音されていた場合に、これをC子がわいせつの被害を受けた事実の証拠とするには、C子の発言内容が真実であったかどうかは問題となりません。悲鳴をあげた事実それ自体が、犯行を推認する証拠となるからです。
この場合、吟味は不要であり、録音テープの証拠能力は認められます。これを「現場録音」と呼びます。
なお、もちろん、それが本当にC子の悲鳴かどうか、本当に犯行当日に犯行現場で録音されたものかどうか、偽造や修正がないかどうかは吟味されなくてはなりませんが、それは証拠一般について要求される証明力の問題です。
2.直接証拠と状況証拠の違い
一般的には、要証事実を直接に証明するのに用いられる証拠を直接証拠といい、要証事実を直接証明することはできないがこれを推認させる事実を証明するのに用いられる証拠を状況証拠(間接証拠)といいます(※状況証拠の定義にはこれ以外にも様々な考え方があります)。
しかし、このように定義を説明されてもピンとこないでしょうから、以下でそれぞれの証拠の具体例を解説していきます。
(1) 「AがBを包丁で突き刺して殺害した」事例
この事例において、Cが「Bの死の直後、Aが包丁を持っているのを見た」と供述したとします。Cの供述は(もし信用できることを前提とするならば)Aによる包丁の所持については直接証拠となります。
しかし、この供述は「甲が乙を包丁で突き刺して殺害した」という要証事実を直接証明するものではありません。
Bの死の直後のAによる包丁の所持という事実(間接事実)からは、Aの包丁によるBの刺殺という事実(要証事実)が推認される関係にあります。
この間接事実を証明する証拠を状況証拠(=間接証拠)といいます。よって、Cの供述は、殺害事実については状況証拠ということになります。
一方、「Aがジャンパーの内ポケットから包丁を取り出し、包丁の柄を両手で握り、刃先を前に向け、Bの腹部目がけて包丁で刺したのを見た」という供述や、「自分がBを殺すため、包丁でBの腹部を突き刺した」と認める被告人甲の自白は、直接証拠となります。
(2)「AがB宅から指輪を盗み取った」事例
例えば、「犯行の前、金に困っていた被告人AはBにお金を貸してくれと言ったが断られていた」という関係者の供述や、「犯行直後にB宅前で被告人Aの姿を見かけた」というCの供述、「被告人甲がその後間もなく指輪を入質した」という質屋の供述等は状況証拠になります。
この複数の状況証拠があれば、これらを総合して被告人甲を窃盗の犯人と認めることも可能です。
一方、「Aが鏡台から指輪を盗むのを隣室で見ていた」というBの供述や、「自分がB宅で鏡台にあった指輪を盗んだ」と認める被告人Aの自白が、直接証拠となります。
3.状況証拠のみで事実認定できるのか?(判例)
結論から言えば、直接証拠と状況証拠との間には、証拠の価値の点で差がありません。
最決平19.10.16(刑集61巻7号677頁)は、「有罪認定に必要とされる立証の程度としての『合理的な疑いを差し挟む余地がない』の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と状況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。」旨判示しています。
さらに、最判平22.4.27(刑集64巻3号233頁)は、
「状況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが、直接証拠がないのであるから、状況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。」
旨判示しています。
この太字部分の趣旨は、「状況証拠による事実認定に際して、被告人が犯人であるとすればそのすべてが矛盾なく(合理的に)説明できる場合に、直ちに被告人が犯人であると速断することを戒め、逆に被告人が犯人でないとしても合理的に説明し得る余地はないか(他の者が犯人である合理的可能性はないか)を裏側から検証して有罪立証の確実性を確認するように注意を喚起したものと理解される。」とされています。
また状況証拠によって有罪認定をする場合は、総合評価に加わる個々の間接事実の単体としての推認力は低くてもよい、とするのが多数説とされています。
例えば、ある間接事実から犯人となり得る者がA、B、Cのいずれかと認められ、それと別個独立の他の間接事実から犯人となり得る者がA、D、Eのいずれかと認められれば、犯人がAであることは高度の蓋然性をもって推認できます。
なお、現在の実状を見ますと、被告人が犯人でない可能性はどの程度あるのか(=被告人が犯人でないとしたならば合理的な説明が極めて困難である事実関係があるのか)についても検討されているのが一般です。
以上から、状況証拠のみで事実認定をするのは間違っているわけではないことになります。
4.違法収集証拠の扱いについて
それでは、法令を遵守しない(違法な)捜査手続で獲得した証拠は、そのまま裁判で証拠として使用できるのでしょうか?
最高裁は、違法な捜査により収集した証拠は、一定の要件に該当する場合には、裁判の証拠とすることはできないとしています。
これを講学上「違法収集証拠排除法則」と呼びます。
例えば、極端な例ですが、警察官が令状なしに被疑者の家に立ち入り、捜索をし、発見した物を押収した場合、当該行為は憲法・刑事訴訟法が定めた手続に違反した違法な捜査となります。
ただ、全ての手続違反について証拠能力を否定してしまうと、刑事訴訟の目的のひとつである真実の発見をあまりにも困難にしてしまいます。
したがって、どの程度の違反があれば排除するべきなのか、バランスが問われることになります。
そこで最高裁は、違法に収集した証拠に該当するケースについて、
①令状主義の精神を没却する重大な違法があること
②将来違法捜査抑制の見地から証拠利用が相当でないこと
という2つの要件を挙げています。(※最判昭和53年9月7日最高裁判所刑事判例集32巻6号1672頁)
(1) 証拠の排除について争われたケース
被告人の承諾なしにポケットから証拠物を取り出したケース
警察官が、覚せい剤所持等が疑われる被疑者の内ポケットを、被告人の承諾なしに捜索して証拠物を押収しました。この手続きは裁判所により違法なものと認定されました。加えて被告人は、当該証拠物の証拠能力を否定するべきだと主張しました。
しかし最高裁は、先ほど述べた基準を持ち出し、①職務質問の要件が存在したこと、②所持品検査の必要性と緊急性が認められたこと、③所持品検査として許容される限度をわずかに超えるに過ぎないこと、④捜査官に令状主義に関する規定を潜脱する意図が認められないことなどを指摘して、本件では証拠能力が否定されないとしました。
(上掲、最判昭和53年9月7日)
逮捕状を呈示せず、また、内容虚偽の報告書を作成・裁判において虚偽の供述をするなどしたケース
かねてから被告人に窃盗の事実で逮捕状が発付されていましたが、警察官は逮捕状を携帯せずに被告人宅に行き、逮捕状を呈示せずに逮捕しました。同日、覚せい剤の使用が疑われる被告人に対して尿検査が実施され、被告人の尿から覚せい剤成分が検出され、その結果を記載した鑑定書が作成されました。
その5日後、この鑑定書を覚せい剤取締法違反事実の疎明資料とし、捜索差押令状が発布され、被疑者宅の捜索によって、薬物が発見・押収され、鑑定の結果、覚せい剤であることが判明し、その鑑定書が作成されました。
裁判で被告人は、令状を呈示していない逮捕手続は違法なので、違法な逮捕後に行われた尿検査と関連する証拠は排除されるべきだと主張しました。
地裁と高裁は、「(ⅰ)尿の鑑定書」だけでなく、これを資料として発布された捜索差押許可状に基づいた捜索で収集された「(ⅱ)覚せい剤」「(ⅲ)覚せい剤の鑑定書」について、すべて証拠能力を否定し、覚せい剤の「自己使用」と「所持」の両方について無罪としました。
最高裁判所は、一連の警察官の行為には、令状主義の精神を没却する重大な違法があり、証拠能力を認めることは将来の違法捜査抑止の見地から相当でないとして、尿の鑑定書を排除し、覚せい剤の自己使用を無罪とした地裁・高裁の判断を支持しました。
他方、覚せい剤とその鑑定書については、尿の鑑定書を疎明とした捜索差押許可状による捜索で収集されたとはいえ、(ア)捜索差押許可状それ自体は司法審査を経ていること、(イ)もともと発布されていた窃盗被疑事実に関する捜索差押許可状の執行も併せて実施されていたことなどから、覚せい剤及びその鑑定書の入手手続に重大な違法があるとまでは言えないとしました。
このため、地裁・高裁の各判決のうち、覚せい剤とその鑑定書の証拠能力を否定して覚せい剤所持を無罪とした部分を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。
(最判平成15年2月14日最高裁判所刑事判例集57巻2号121頁)
(2) 無断録音した音声データの証拠の有効性
警察官の捜査以外にも、無断で録音した音声データが問題になることは多いです。
相手に秘密で会話内容を録音することは犯罪になるのでは?と考える方も多いのではないでしょうか。
確かに、会話当事者の承諾が全くないのに、その会話を盗聴して録音することは、当事者のプライバシー権・人格権や通信の秘密を侵害する重大な違法行為です。
そこで、例えば、最高裁の判例では、「捜査機関が電話の通話内容を当事者の同意を得ずに傍受することは、重大犯罪に関する十分な嫌疑があり、他の方法では重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの特別な事情がある場合に、裁判所の発する特別な検証許可状があることを条件に、刑事訴訟法上の強制捜査として例外的に許される」と判断していました(※最高裁平成11年12月16日決定)。
したがって、捜査機関が電話の会話を盗聴して録音したテープは、それが通信傍受法の要件を満たしておらず、令状主義の精神を没却する重大な違法がある場合には、違法収集証拠として排除され、証拠能力は認められません。
では、同様の行為が一般民間人によって行われた場合はどうなるでしょうか?
私人である会話当事者の一方が、相手方の同意を得ないで会話を録音する行為です。
この場合、侵害されるのは、せいぜい「私的な会話を相手に録音はされないだろう」という相手方の自由やプライバシーに対する期待にすぎませんから、一般的には、重要な利益を侵害したとまでははいえません。
そのため、違法とはいえず、刑事訴訟にあっても証拠能力は肯定されると解されています。
例えば、以下のような事例があり、録音テープの証拠能力が肯定されています。
- 私人Aが、殺人事件に関する被告人Xとの会話を録音した場合(松江地判昭57.2.1判時1051・162)
- 新聞記者Aが、取材の結果を正確に記録しておくため、相手方の同意を得ないで会話内容を録音した場合(最決昭56.11.20)
- 詐欺の被害を受けたと考えたAが、後日の証拠とするため、被告人Xとの会話を録音した場合(最決平12.7.12)
では、捜査機関が、会話当事者の一方の同意を得て会話を録音した場合はどうでしょうか?
この場合も、やはり相手方が侵害されるのはせいぜい期待権に過ぎませんから、重大な権利・利益を侵害するものとは言えず、刑事訴訟法上の強制処分にあたらないので、任意処分として許されます。
5.まとめ
刑事事件でどのような証拠が決定的となるのかは、その事件の内容によって様々です。
刑事事件で裁判となってしまった場合、刑事弁護を弁護士に頼むならば、様々な刑事事件を経験し判例の理解を含む証拠法に精通している弁護士に依頼しましょう。
泉総合法律事務所は、様々な刑事事件を解決してきた実績が豊富な弁護士が代表を務めております。
刑事事件で裁判となりそうな場合だけでなく、逮捕されてしまった場合に起訴を避けるためにも、お早めにご相談ください。