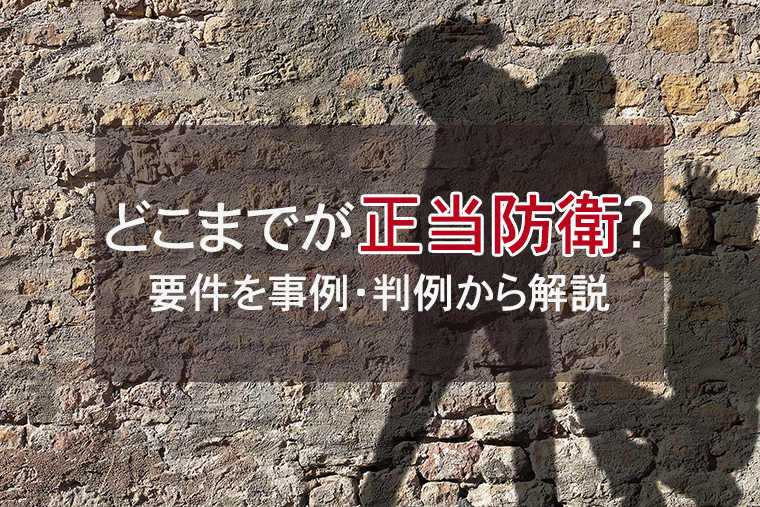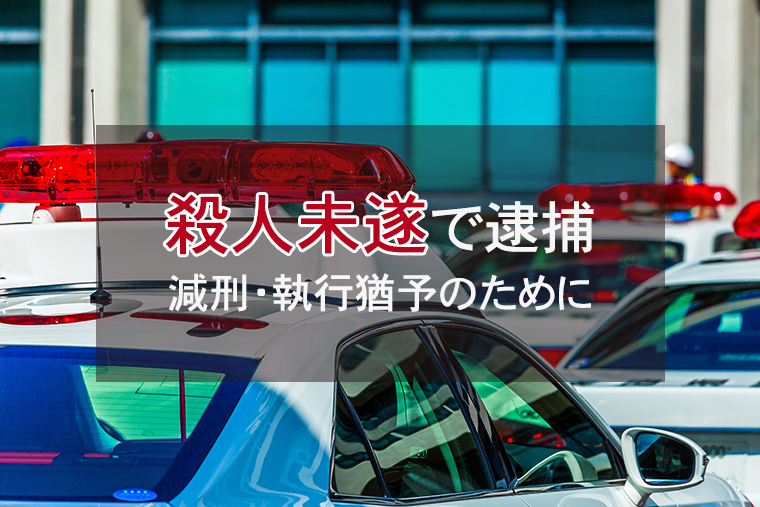インターネット上の誹謗中傷で訴えられたらどうすれば良い?

誰でも手軽に情報発信できるインターネットの世界では、リアルでは言えないようなことでも軽い気持ちで投稿してしまいがちです。
しかし、不用意な言動により他人を誹謗中傷してしまうと、ご存知の通り「名誉毀損罪」「侮辱罪」などで法的な責任を問われることもあります。実際に「ネットへの書き込みで訴えられました」という知恵袋などの書き込みを見たことがある方も多いでしょう。
5ちゃんねる(2ちゃんねる)やX(Twitter)、雑談たぬき等で誹謗中傷をしたまま放置していると、開示請求により相手に身元が知られ、民事の損害賠償請求が行われる・名誉毀損等に基づく刑事告訴がされる(訴えられる)可能性があるのです。
2022年10月1日からはプロバイダ責任制限法の改正法も施行されており、誹謗中傷をした人物(発信者)を特定する手続きが迅速化し、簡易になりました。
発信者情報開示命令に係る意見照会書が届いても無視しているのは危険です。
今回のコラムでは、ネット上で誹謗中傷をしてしまい、訴えられた場合の善後策について解説します。
1.ネット誹謗中傷は何罪になる?
SNSや掲示板は自由で多様な言論の場ですが、他人の権利を侵害する言動は罪に問われることもあります。
どこからが違法な誹謗中傷となるのかの線引きは、法的な評価によるため判断が難しい面もありますが、成立する可能性がある罪について簡単に解説します。
(1) 名誉棄損罪
特定の個人や会社について、社会的評価を低下させるような具体的事実をネット上に表示させると「名誉棄損罪(刑法230条)」に問われることがあります。
「社会的評価を低下させるような事実」とは、平たく言えば世間の評判を悪くするような事実で、次のような言動が典型例といえます。
「○○は痴漢の常習者で逮捕歴もある」
「○○はギャンブル依存症で多額の借金がある」
このような事実は、虚偽である場合はもちろん、真実であったとしても罪に問われる可能性があります。
また、本罪は会社企業についても適用されますので、「B社の取締役は暴力団と繋がりがある」など、特定の企業のデマを流した場合でも名誉毀損罪が成立する可能性があります。
罰則:3年以下の懲役または禁錮若しくは50万円以下の罰金
(2) 侮辱罪
特定の個人や会社について、具体的な事実ではなく侮蔑的な評価をネット上に表示させると「侮辱罪(同法231条)」に問われることがあります。
「○○は仕事ができない無能」「○○はブラック企業」などの書き込みは侮蔑的表現とされる可能性があります。
罰則:拘留(30日未満刑事施設へ収容される刑)または科料(1万円未満を徴収される刑)
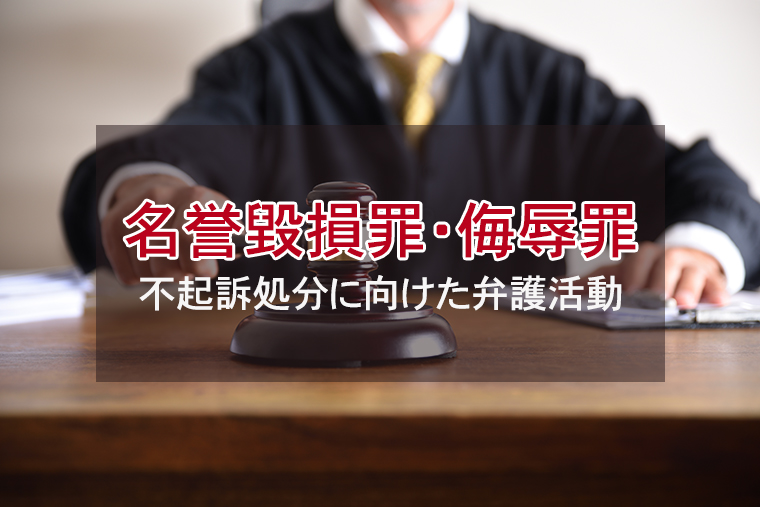
[参考記事]
名誉毀損罪・侮辱罪とは?不起訴処分に向けた弁護活動
(3) 信用毀損罪・業務妨害罪
虚偽の情報をネット上に表示させて人の信用を毀損したり、他人の業務を妨害したりした場合、「信用毀損罪(刑法233条)・業務妨害罪(刑法234条)」が成立することがあります。
例えば、「○○店で注文した料理に異物が混入していた」という真実に反する情報を表示することは「虚偽の風説を流布し」て、商品の品質に対する「信用を毀損した者」として、「信用毀損罪」に該当します。
また「○○動物園のライオンが放たれた」「○○駅に爆弾を仕掛けた」というような虚偽の事実を流布して必要のない警備をさせたり、休園や運行休止をさせたりして業務を妨害する危険を生じさせた場合には「業務妨害罪」が成立します。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
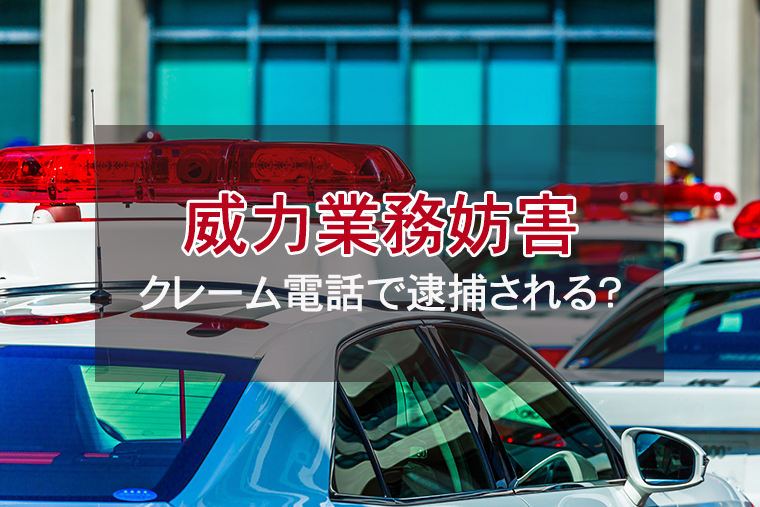
[参考記事]
クレーム電話は威力業務妨害|逮捕・罰金・懲役になるか
(4) 恋人などの性的画像を投稿した場合
恋人や元恋人などの性的な画像・動画をネット上にアップした場合には、リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)における私事性的画像記録公表罪など(3条1項)で規制を受けます。
相手が18歳未満の児童である場合には、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)の児童ポルノ提供罪など(7条6項)により処罰されます。
リベンジポルノ被害防止法の私事性的画像記録公表罪の場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、児童ポルノ禁止法の児童ポルノ提供罪では「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。
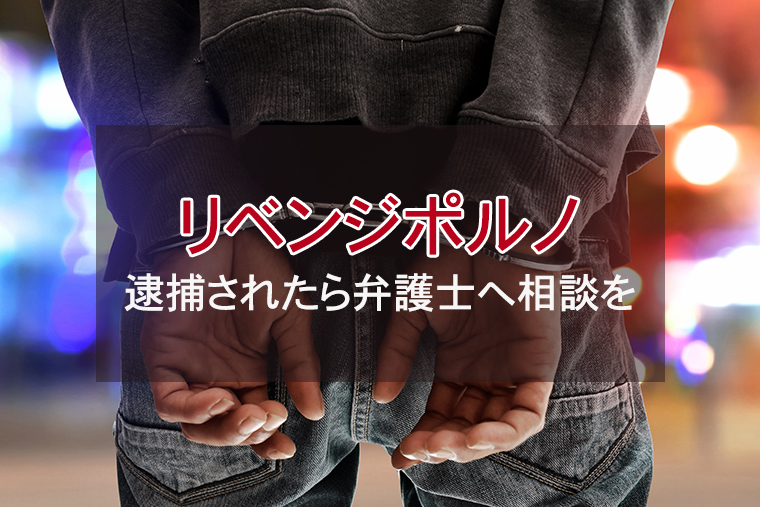
[参考記事]
リベンジポルノで逮捕されたら弁護士へ相談を
2.ネット誹謗中傷の被疑者の責任
現在、ネットの誹謗中傷が事件になると非常に注目を集めやすいです。名誉棄損による逮捕事例がニュースとして取り上げられることも珍しくなくなりました。
被害者が「発信者情報開示命令」を利用すると、発信者のもとに契約しているプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が送付されてきます。
その書類が届くと、近々発信者が特定されてしまいます。
なお、発信者が投稿やアカウントを削除しても、プロバイダがデータを復元することは容易ですし、被害者がスクリーンショットを保存してあれば十分な証拠となります。
いったんネット上で誹謗中傷をしてしまうと瞬時に拡散されてしまうことが多いですので、加害者側も簡単に罪を逃れることはできないのです。
こうして発信者が特定されると、被害者は法的責任を追及するために民事訴訟を提起したり、刑事告訴したりすることが可能になります。
(1) ネット誹謗中傷による民事責任(損害賠償請求)
上記のような誹謗中傷行為や業務妨害は、違法に他人の権利・利益を侵害する行為として、法律上の不法行為(民法709条)に該当します。
不法行為を受けた被害者は、加害者に対し損害賠償請求を行う権利があります。
特に、誹謗中傷行為やプライバシー侵害行為は、被害者に精神的な苦痛という損害を発生させたと評価されるので、慰謝料請求の対象となります。
ほとんどの被害者は、弁護士費用や裁判所費用を支払い、加害者を特定した上で法的手続きを実施しているため、全く金銭を支払わないで(謝罪だけで)和解できるケースは稀です。
提訴前に和解できる場合であっても、一定の金銭支払いには応じざるを得ないでしょう。
訴訟の判決が確定したり、訴訟上の和解が成立したりしたにもかかわらず、加害者が支払いを行わない場合には、強制執行によって資産や給料などの差し押さえを受ける可能性もあります。
なお、誹謗中傷行為による名誉毀損やプライバシー侵害における慰謝料の相場は、数十万円~70万円程度が多くなっています(個人の場合)。
(3) ネット誹謗中傷による刑事責任(逮捕・前科)
インターネットの誹謗中傷の被疑者が負う責任は、民事だけではありません。
名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事事件として立件されれば、逮捕されたり、起訴されて前科がついたりする可能性があります。
逮捕の必要性は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれという観点から判断されます。
【逃亡のおそれがあると判断されやすい要素】
・厳しい刑が予想される(殺人罪など重い罪を犯した、前科がある)
・身軽な身上である(定職に就いていない、一人暮らし)【証拠隠滅のおそれがあると判断されやすい要素】
・罪を認めていない(証拠を隠したり被害者に働き掛けたりする可能性)
・共犯者がいる(口裏合わせをする可能性)
ネットの書き込みによる名誉棄損罪や侮辱罪、信用毀損罪・業務妨害罪は、必ずしも重罪とは言えず、犯行態様も単純で悪質性が低いので逮捕される可能性は高いものとは言えません。
しかし、定職を持たない独身者などの場合は、逮捕される可能性は否定できず、現に逮捕の例もある以上は安易に考えるべきではありません。
起訴・不起訴は検察官の裁量で決まります。前科・前歴の有無と内容、犯行の動機・態様の悪質性、被害の深刻さ、反省の度合いなど一切の事情が考慮されます。
なお、名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪ですから、被害者の告訴がなければ起訴できません。被害者との示談を成立させて告訴を取り下げてもらえば、起訴されることはなく、前科はつきません。
(※他方、信用毀損罪・業務妨害罪は非親告罪であり、告訴がなくとも起訴できます。)
3.ネット誹謗中傷で訴えられた場合の対応
では、被害者に住所・氏名を特定されて損害賠償請求や刑事告訴を受けた場合には、その後どうすれば良いのでしょうか。
結論を言うと、損害賠償請求であれ、刑事事件で訴えられた場合であれ、できるだけ早く被害者に謝罪し、示談(和解)をまとめることが大切です。
示談とは、当事者間の特定のトラブルにつき、話し合いで解決する方法です。ネットにおける誹謗中傷投稿やプライバシー侵害の事件でも、示談は頻繁に行われています。
示談が成立すると、加害者から被害者への謝罪、今後このようなことは行わないことの誓約、慰謝料・示談金の金額の確定と支払い方法、示談成立後は損害賠償や刑事告訴を新たに行わないこと、などが示談書に明記されます。
示談を行うことで、刑事事件への発展を防ぐことが可能となるケースが多くあります。
また、すでに告訴を受けている場合でも、示談内容次第で告訴の取り下げをしてもらうことも可能です。示談成立により不起訴処分の可能性も高まりますし、起訴後であったとしても情状がよくなり罰金刑で済む・執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。
被害者の処罰感情の有無、強弱は、検察官や裁判官の判断に大きく影響します。被害者と示談を成立させて、示談金を支払い、宥恕(※寛大な気持ちで許すこと)を得ることができれば、被害者の処罰感情は無くなり、被害も示談金によって金銭的に回復していますから、不起訴や減刑の判断を得やすくなるのです。
たとえ罰金刑で済んでも前科となりますから、不起訴となるに越したことはありません。
このように、民事の訴えや刑事告訴を受けた場合には、一刻も早く示談に取り掛かることが大切です。
しかし、投稿をした本人が被害者と接触することは、被害感情を悪化させる可能性もありお勧めできません。
示談交渉の経験が豊富な泉総合法律事務所であれば、被害感情にも配慮した交渉のノウハウがあり、適正な示談と刑事告訴の回避が期待できます。
→示談したい(ご相談内容)
4.ネット誹謗中傷事件を弁護士に依頼するメリット
ネット誹謗中傷により損害賠償請求や刑事告訴を受けた場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
(1) 交渉格差をなくすことができる
ネット誹謗中傷で法的措置を受けた場合には、被害者側に弁護士がついている可能性が高いです。
弁護士が代理人となっている場合には、法的な知識と経験のない加害者側が単独で相対するには、圧倒的に不利な状況です。
そこで、加害者側も同じように弁護士に依頼して、対等に交渉を進める必要があります。
知識・経験の格差をなくすことで、無理のない金額での示談交渉がまとまったり、減刑ができたりと、より良い結果が目指せます。
(2) 被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高まる
被害者側の弁護士の有無にかかわらず、被害者が加害者との示談に応じない可能性は十分にあります。
被害者が「絶対に許したくない」「話したくもない」と考えている場合は、加害者との接触すら拒絶する場合があります。
このようなケースでは、自力で交渉を行うことは不可能のため、弁護士に相談すべきといえます。
被害者も「加害者と話したくないが、弁護士であれば話を聞いてもいい」と考えてくれるケースは多くあります。最初は示談を拒否していた被害者でも、弁護士が粘り強くコンタクトをとり、少しずつ心を開いてもらうことで、示談交渉へ繋げていくことが可能となります。
また、当事者同士だけで行う交渉は新たな火種を生む危険がありますが、弁護士が入ることで、そのような余計なトラブルも防ぐことができます。
5.ネット投稿の名誉毀損で訴えられたら弁護士に相談を
冒頭でも触れたとおり、インターネット上の誹謗中傷に対する社会の目は厳しさを増しいます。
軽い気持ちで行ったネット上の投稿が炎上することや、拡散されてしまうことは珍しくありません。
ネット上で誹謗中傷行為を行い、投稿者の身元が判明すると、損害賠償請求が行われる確率は高くなります。相手の気持ち次第では刑事告訴が行われる可能性もあり、立件されてしまうとその後の人生が大きく変わってしまうリスクもあります。
そのため、被害者から名誉毀損等で訴えられた場合には早めに対処を行っていく必要があります。
「弁護士に相談するのは警察沙汰になってから」と考えられるかもしれません。
しかし、名誉棄損罪や侮辱罪は親告罪であるため、刑事告訴の回避が大きなポイントとなります。
できるだけ早く示談をまとめることで、起訴を免れる可能性も高くなります。
ネット誹謗中傷で訴えられた方は、刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。専門家と一緒に問題を解決していきましょう。