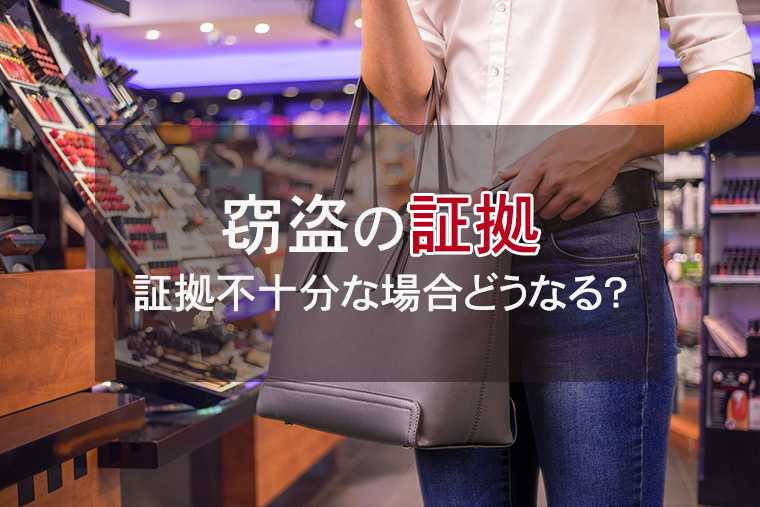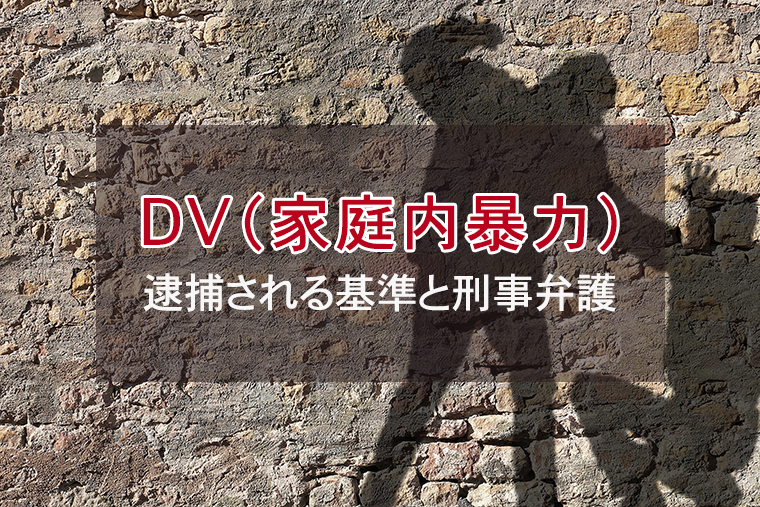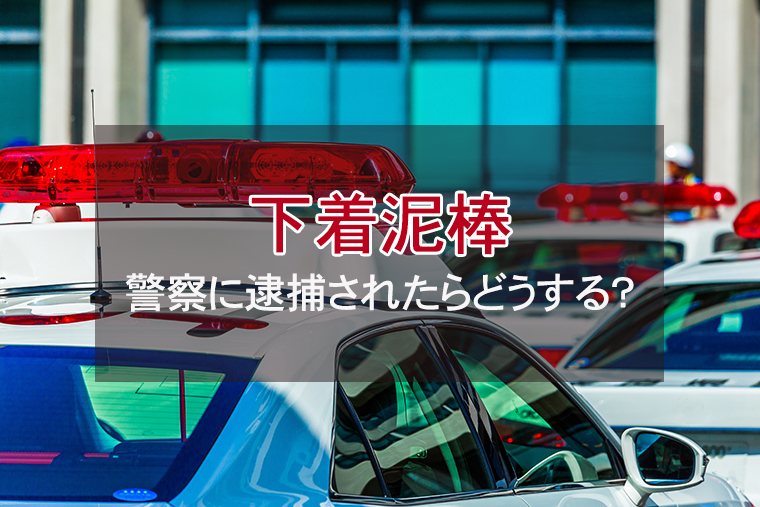労働基準法違反は刑事事件!?刑罰の内容について
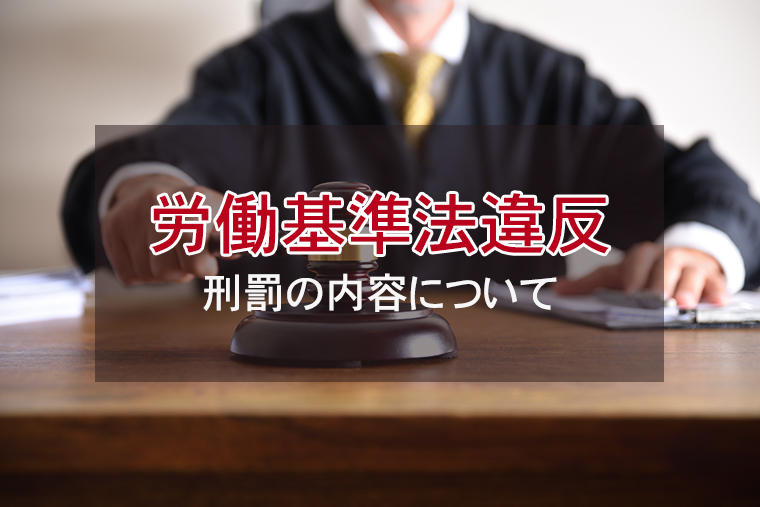
労働者保護の観点から、職場の労働条件の最低基準を定めた法律が「労働基準法」であり、使用者はこれを遵守する法的義務があります。
使用者が労働基準法を守らなくとも、せいぜい労働基準監督署からの行政指導を受ける程度だと考えている経営者もいるようです。
しかし、これは大きな誤解です。
労働基準法違反は犯罪であり、刑事事件として立件され、刑事裁判を経て刑罰を受ける危険性があります。
1.労働基準法違反が刑事事件となる理由
労働基準法違反が刑事事件となるのは、労基法の定める多くのルールには、違反した場合の罰則が定められているからです。
通常、労基法違反に対しては、労基署から是正勧告などの行政指導が行われます。その勧告に従わなかったり、何度も違反を繰り返したり、特に悪質と評価されたりした場合には、検察庁に送検され、刑事事件化してしまう場合があるのです。
実際に、労働基準法違反を含む労働関係法令の違反によって送検された事案は、厚生労働省によって公表されています(※「労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和6年6月1日~令和7年5月31日公表分)」厚生労働省労働基準局監督課)。
2.刑事処罰の対象となる主な労働基準法違反行為
では、刑事罰の適用される労働基準法違反の主なものを、ピックアップして紹介します。
(1) 賃金未払い(賃金支払いの原則違反)
労基法は、労働者が確実に賃金を手にできるよう「賃金の5原則」というルールを定めています。
- 通貨払いの原則(通貨での支払いが必要で、物品での支払を禁止)
- 直接払いの原則(本人への支払が必要で、代理人等への支払を禁止)
- 全額払いの原則(相殺・控除を禁止)
- 確定日払いの原則(不定期の支払を禁止)
- 毎月1回以上支払の原則(支払間隔が1ヶ月を超えることを禁止)
たとえば、家族であっても労働者本人以外の者に賃金を渡すことは、直接払いの原則に違反します。
(2) 長時間労働・残業代未払い
①長時間労働
使用者は、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働者を働かせることは禁止されています。
この制限の例外となる時間外労働が許されるには、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表する者との書面による通称「36(サブロク)協定」を結び、労基署に届出をする必要があります。
また、たとえ36協定を届出しても、時間外労働は、原則として、月45時間・年360時間の限度時間が上限です。
36協定に特別条項(通常予見できない業務量の大幅な増加などの特別な事情があるときの、時間外労働のさらなる延長を可能とする条項)を設けることもできますが、それでも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満などの上限があります。
これらの例外要件を満たさないのに時間外労働行わせた場合は違反となります。
②残業代未払い
使用者は、時間外労働に対する「割増賃金」の支払義務があります。
割増率は25%以上で、時間外労働が1ヶ月に60時間を超えた場合は50%以上です。
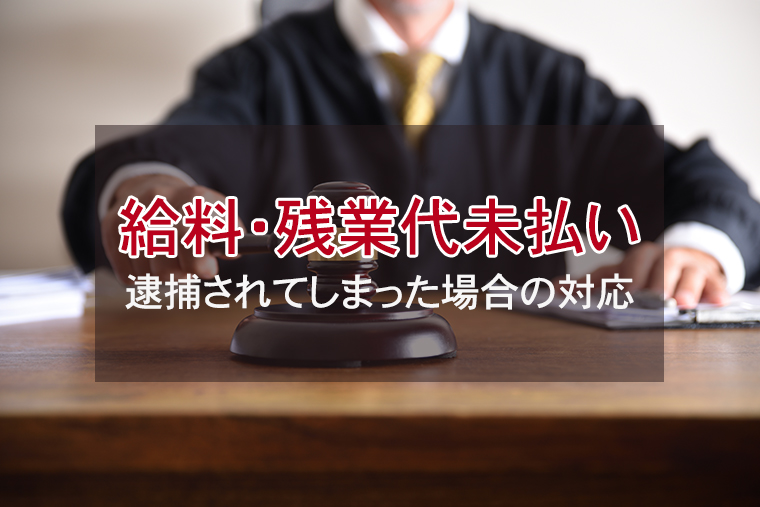
[参考記事]
給料・賃金未払い、残業代未払いで逮捕されてしまった場合の対応
(3) 不当解雇・解雇予告手当未払い
①不当解雇
【解雇禁止期間の解雇】
労働者が安心して病気の治療や出産に専念できるよう、「①業務上傷病の療養で休業する期間および、その後30日間」「②産休期間および、その後30日間」は、解雇は禁止です。
【差別的な解雇など】
差別的な解雇や、労働者の正当な行為に対する不利益取扱いとしての解雇は、各種法律の規定で禁止されています。
労基法でも、①国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いとしての解雇(3条)、②労基法違反の事実を監督官庁等に申告したことなどを理由とする不利益取扱いとしての解雇(104条2項)を禁止しています。
②解雇予告手当未払い
労働者の失職による経済的な打撃を緩和し、再就職活動を容易にするため、使用者が解雇をする際には、30日前の予告かこれに代わる予告手当金(最低30日分以上の平均賃金)を支払う義務があります。
予告もせず、予告手当金も支払わない場合は、労働基準法違反となります。
(4) 年次有給休暇の付与拒否
雇い入れから6ヶ月間継続して勤務し、8割以上の出勤をした労働者には、10日の有給休暇を与える必要があります。
その後も、8割以上の出勤をしていれば、1年ごとに、一定の日数を加算した有給休暇が必要です。
労働者が時季を指定して有給休暇を請求したときは、代わりの人員の確保ができないなど、事業の正常な運営を妨げる場合でない限り、請求に応じる義務があります。
有給休暇を与えなかったときは、労働基準法違反となります。
(5) 就業規則の未作成・未届出
就業規則は、職場の共通ルールを定めるものであり、法律によって事業場の労働条件の最低基準を画する効力も与えられています。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労基署に届出をする必要があります。未作成・見届出は違反です。
(6) 労働条件の明示義務違反
労働者が雇入時の説明と異なる労働条件を強いられることを防止するため、契約の際、労働条件を労働者に明示する義務が使用者に課せられています。
契約期間、賃金、就業場所などの特に重要な事項は書面での明示が原則です。明示義務に違反すれば、労働基準法違反となります。
3.労働基準法違反の刑罰内容と量刑基準
(1) 各違反行為に対する具体的な刑罰
先に御紹介した各労働基準法違反に対する刑罰は、次のとおりです。
■30万円以下の罰金刑(労基法120条1号)
・賃金支払いの原則違反
・労働条件の明示義務違反
・就業規則の未作成・未届出
■6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑(119条1号)
・割増賃金の未払い
・解雇予告手当の未払い
・解雇禁止期間中の解雇
・差別的取扱いの解雇
・労基法違反の申告などを理由とする不利益取扱いの解雇
・年次有給休暇の付与拒否
なお、労基法には、これ以外の刑罰として次のものがあります。
■1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金刑(117条)
強制労働の禁止(暴行・脅迫・監禁その他精神・身体の自由を不当に拘束する手段で、労働者の意思に反して労働を強制することの禁止)に違反した場合(5条)
■1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(118条1項)
最低年齢(満15歳以後の最初の3月31日が終了した後)に満たない児童の使用禁止に違反した場合(56条)など
(2) 法人処罰(両罰規定)の仕組み
労働基準法違反で刑罰を受けるのは、違反行為を行った「使用者」です。この「使用者」とは、事業主、経営担当者(会社役員など)だけでなく、労働条件などにつき、実質的に指揮・監督・決定の権限を有する者を全て含みます。
したがって、管理職のように、会社との関係では労働者である者も、使用者として労働基準法違反の罰則を受ける場合があります。
また、労働基準法違反の行為が、事業主である会社の代表者、役員、従業員などによって会社のために行われた場合は、違反行為を行った者の処罰とは別に、会社にも罰金刑が科されます。
これを「両罰規定」と呼び、違反行為で利益を得ようとする事業主が処罰を免れることを防ぐ制度です。
(3) 初犯・再犯での処罰の違い
労働基準法違反を含む刑事事件では、起訴して刑事裁判にかけるか否かを決める裁量権は検察官にあります。検察官が、犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の情況といった諸事情を考慮して、刑事処分まで必要がないと判断すれば不起訴として事件を終了とすることができます。
初犯であれば起訴猶予処分の可能性は高く、そうでなければ起訴されてしまう危険性が高くなります。
また、起訴されて刑事裁判にかけられた場合でも、初犯か否かによって裁判官の量刑が異なります。
(4) 実刑と執行猶予の判断基準
労働基準法違反は、刑事事件として立件されても、通常は罰金刑が適用されます。
しかし、拘禁刑も定められている以上、必ず罰金で済むとは言えません。
起訴された場合、拘禁刑の実刑判決を受けて刑務所に服役することになるか、それとも罰金刑や執行猶予付き判決によって服役を免れるかは大きな違いです。
執行猶予は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑に対して付けることができます。
執行猶予を認めるか否かは、あくまでも裁判官の裁量です。一般論としては、判断の主要なポイントは、
①同種の違法行為を抑止するために重い罰を科す必要のある悪質・重大な事案か否か
②更生するためには刑務所内での矯正教育が必要か、それとも通常の社会生活を送りながらの更生が期待できるか
という点です。
そこで、犯行の態様に悪質性がないこと、計画性に乏しいこと、被害の結果が重大とは言えないこと、示談の成立・被害の賠償が済んでいること、真摯に反省していること、今後の指導監督を誓約する者がいることなど、被告人に有利なあらゆる事情を、弁護人を通じて裁判官に伝える必要があります。
4.実際の刑事事件・逮捕事例と判決内容
労働基準法違反の実例を、いくつか紹介します。
(1) 割増賃金不払いで逮捕、身柄を送検
労働者9名の時間外労働の割増賃金不払いで、青森県の食品製造業など複数社の代表取締役社長を兼任する男が、労働基準法違反を理由に逮捕されたうえ、身柄を送検されました。
労基署の調査に対して、虚偽の賃金台帳を提出するなどして、証拠隠滅の恐れがあったために逮捕に踏み切ったものと報じられています。
※労働新聞ニュース2022年2月24日記事「割増不払いで社長逮捕 9人合計500万円弱に 十和田労基署」
(2) 割増賃金不払いで書類送検
奈良県の有名進学校を経営するT学校法人が、教員36名の時間外労働・休日労働の割増賃金約130万円(2024年10月分)を支払わなかったとして、奈良労働基準監督署が、同法人・校長・事務局長・事務長を書類送検しました。
前年に労基署から是正勧告を受けたにもかかわらず、翌年の立入調査で再び不払いが明らかになった事案とされています。
※時事ドットコムニュース2025年3月17日記事「東大寺学園と校長ら書類送検 教員への割増賃金不払い容疑―奈良労基署」
(3) 違法な長時間労働の労働基準法違反で旅行会社に罰金刑
大手旅行会社H社が、営業担当者2名に、労使協定の上限を超える違法残業をさせたとして、東京労働局によって書類送検され、東京区検察庁によって略式起訴となり、東京簡易裁判所から30万円の罰金刑を受けました
※1:日本経済新聞2018年6月13日記事「HISに罰金30万円 違法残業で東京簡裁」
※2:株式会社エイチ・アイ・エス「当社の略式起訴と罰金の納付について」(2018年6月20日)
(4) 時間外労働の労働基準法違反で大手企業に罰金刑
大阪市に本社を置き、数百店舗ものファミレスなどを経営するS社が、本社と4つの店舗で、7人の従業員に月40時間の上限を超えた違法な時間外労働をさせた事案で、大阪簡易裁判所は同社を50万円の罰金刑としました。
この事件では、担当した大阪区検察庁は書面による審理を求める略式起訴としましたが、これを受けた大阪簡易裁判所では、略式手続では不相当と判断して、正式裁判が開かれました。このように事案が重大で社会的影響が大きい場合には、簡易裁判所の判断で正式裁判となります。
他にも、大手広告代理店における違法残業で、過労による自殺者まで出た事案の重大性・社会的関心の高さから、検察官の求めた略式起訴を退け、正式裁判が開廷された例があります(※4)。
※3:産経新聞2017年6月1日記事「従業員に違法時間外労働『和食さと』罰金50万円 『社会的影響、少なくない』大阪簡裁」
※4:産経新聞2017年7月12日記事「電通違法残業事件、正式裁判に 東京簡裁『略式不相当』」
5.労働基準法違反とされたら弁護士へ
労働基準法違反が発覚した場合は、労基署への対応も含めて弁護士に依頼することをお勧めします。
労基署は、違反の事実を確認するために立入調査を行ったり、帳簿など各種書類の提出を要求したり、関係者に質問し事情聴取を行ったりします。
この調査に対し、拒否したり、虚偽の事実を報告したりすれば、それ自体が犯罪となり、30万円以下の罰金刑となります。
したがって、調査には真摯に対応する必要があり、労働関係に強い弁護士の助言を受けながら対応するべきです。
また、違反事実が確認され、労基署から是正勧告を受けたならば、その指定された期日までに是正措置を行い、これを報告する必要があります。
勧告に従わない場合は、悪質な事案として送検される危険があります。
是正勧告書には、是正するべき違反事実が明示されていますから、弁護士の法的アドバイスを受け、労基法に適合するよう改善に努めるべきです。