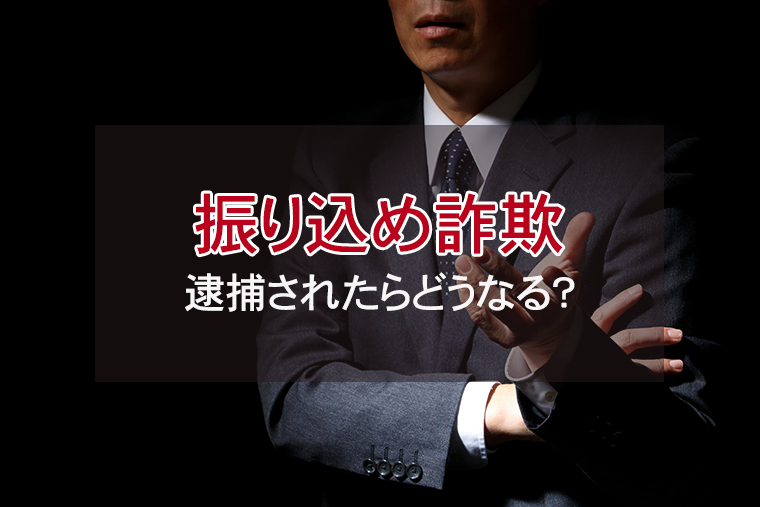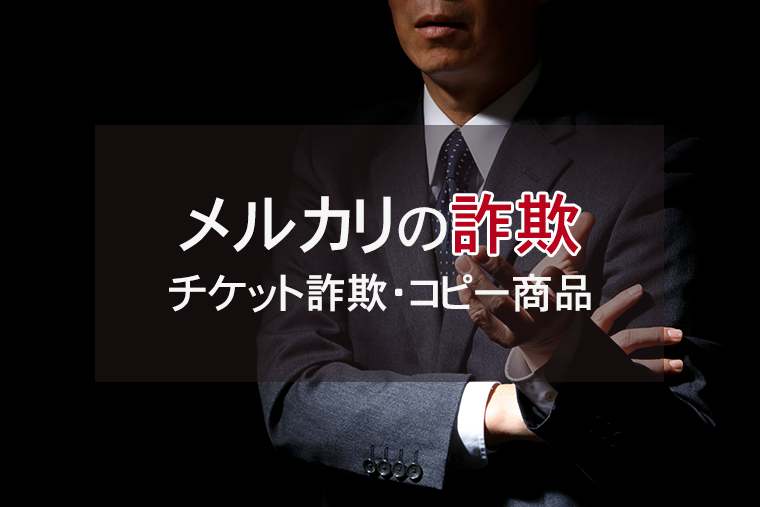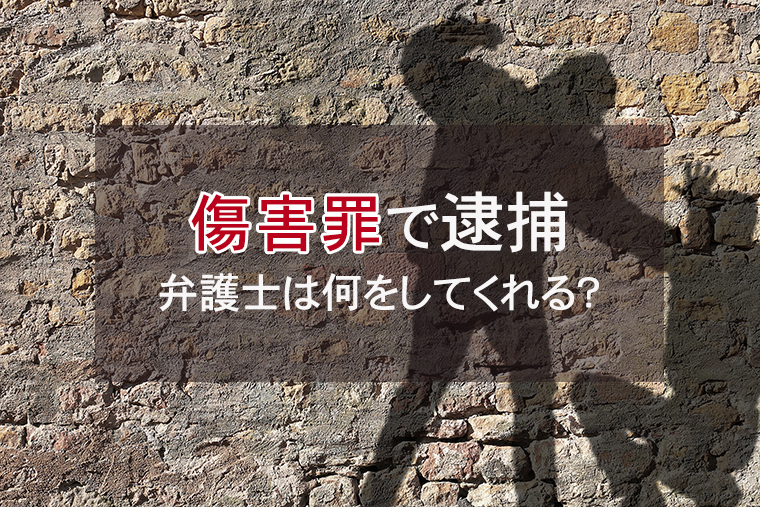友人が借りたお金を返さない場合、犯罪になるのか?
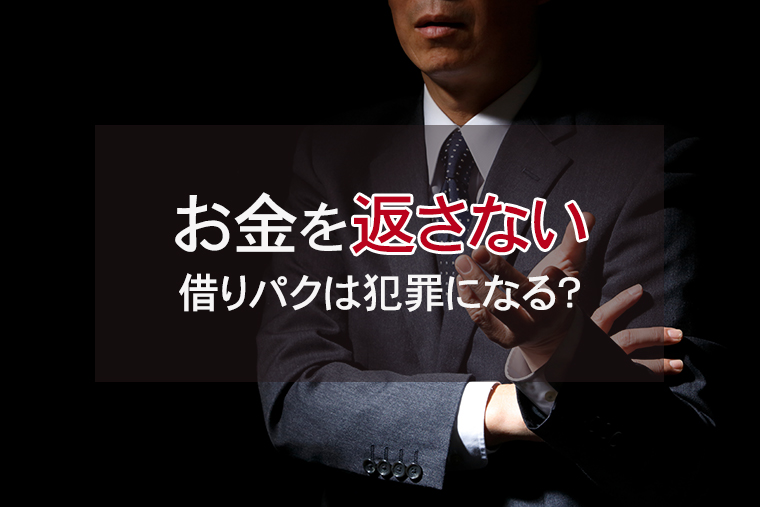
「借りパク」という言葉には聞き覚えはあると思います。借りパクとは、言わば借りたお金を返さずに自分の利得とすることを言います。
「お金を貸したがその友人が音信不通になった等で借りパクされた」あるいは「自ら借りパクをした場合」、友人関係のトラブルになることは想像に容易いです。
それでは、借りたものを返さない場合、刑事事件になるのでしょうか?
警察に届け出て有罪にしたい、刑事罰を受けてほしいと思う方もいると思いますが、現実にこれは可能なのでしょうか?
ここでは、「借りパク」した場合に成立しうる犯罪について解説します。
1.借りたお金を返さないことは犯罪?
友人や家族等、個人のお金の貸し借りを行なったものの、返すお金が用立てできなかったり返すのが面倒になったりして、借りたお金を返さなかったとします。
あるいは、銀行や消費者金融からお金を借りたものの、返済日を過ぎてもお金を返さず督促・取り立てを受けていることもあるかもしれません。
このような場合、犯罪が成立し、逮捕・起訴される可能性があるのでしょうか?
(1) 民事上の債務不履行となる
金銭の貸し借りは、民法上の「金銭消費貸借契約」であり、借主には借りたお金の返済義務があります。これを期日までに返さなかった場合には契約違反となり、民事上の債務不履行となります。
債務不履行の責任といっても、金銭債務の場合は、元金に利息(遅延損害金)を加えて返済する責任があるだけです。
ただ、その責任を果たさなければ、場合によっては民事訴訟などの法的手段をとられることもあります。
もっとも、個人間の金銭の貸し借りだと、契約書がない限り借りた・借りていないの水掛け論となる場合も多いです。
たとえ本当に借りていても、債権者が貸金業者である場合や、金額がかなり高額ではある場合を除き、わざわざ裁判所に訴えを提起するという個人はあまりいないと思われます。
結果として、債務者が泣き寝入りをすることになるケースも少なくありません。
(2) 刑事上の責任は問われない
それでは、民事上の責任を超えて、借りパクは刑法上の犯罪にもなるのでしょうか?
刑法上、借りたお金を返さないこと自体を処罰する規定はありません。つまり、「借りパク」の罪は存在しないのです。
そのため、警察が自宅まで来て事情を尋ねてくるといったことはありませんし、捜査の上で逮捕・起訴されることもありません。これは、金銭の貸し借りの場合だけでなく、債務不履行全般に当てはまります。
債務を履行しなかったり、自己の債務が履行不能になったりした(売る約束をした物が焼失した等)場合、民事上の責任が問われる可能性はあっても、債務を履行しない・履行できないというだけで刑事上の責任が問われることはありません。
2.詐欺罪が成立しうるケース
友人からお金を借りたにもかかわらず返済しないという行為は、状況によっては刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立する犯罪で、単なる民事上の債務不履行とは明確に区別されます。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
以下、詐欺罪が成立しうる2つの典型的なパターンについて解説します。
(1) 当初から返す意思がなかった場合
最も典型的な詐欺罪のパターンは、借金をする時点ですでに返済する意思がまったくなかった場合です。この場合、借主は「返す」と嘘をついて相手を騙し、お金を交付させたことになります。
詐欺罪が成立するためには、金銭を借りる時点で既に返済する意思や能力がなく、それを隠して相手を欺いたという事実が必要です。
例えば、多額の借金を抱えていて返済能力がないことを知りながら、その事実を隠して「必ず返すから」と言って借金をした場合や、借りたお金を遊興費に使う目的であったにもかかわらず、「事業資金として使い、すぐに返済できる」などと嘘をついた場合などが該当します。
ただし、借りた当初は返すつもりがあったものの、その後の事情変更により返済できなくなった場合は、詐欺罪には該当しません。
この点の立証は困難な場合が多く、当初の意思を証明するためには、借主の経済状況、借金の使途、返済計画の有無などの客観的な事情が総合的に考慮されます。
(2) お金を借りていないと主張した場合
お金を借りた事実があるにもかかわらず、後になって「そもそも借りていない」「もらったものだ」などと主張するケースも、詐欺罪に該当する可能性があります。
重要なポイントは、単に「借りていない」と主張するだけでは、原則として詐欺罪は成立しないということです。このような主張は民事上の争い(貸した・借りていないの水掛け論)であり、刑事事件ではなく民事訴訟で解決すべき問題とされるのが一般的です。
ただし、借金の事実を否定する際に、以下のような積極的な欺罔行為(騙す行為)があった場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
- 借用書を自分で破棄したり、改ざんしたりして、「証拠がないから借りていない」と主張する
- 第三者(他の友人など)に対して「あの人が勝手にお金をくれたのに、今になって返せと言っている」などと虚偽の説明をして、貸主の信用を傷つける
- 返済を免れる目的で、借金の記録を組織的に隠滅する
- 借りた事実を否定することで、さらに別の友人から「あいつは信用できる」と思わせてお金を借りる
- 本当は友人からの借金があるのにそれが存在しないと誤信させて、何らの債権債務も存在しないと確認する合意書に署名・押印をする
つまり、「借りていない」という主張を裏付けるために証拠を偽造・隠滅したり、新たに人を騙したりすれば犯罪になり得るということです。
また、借金を否定する行為は、詐欺罪以外にも以下の犯罪に該当する可能性があります。
- 証拠隠滅罪:借用書などの証拠を意図的に破棄・隠匿した場合
- 名誉毀損罪:貸主について虚偽の事実を第三者に広めた場合
もし友人との金銭トラブルで詐欺の可能性を疑う場合、被害者としては証拠を保全した上で弁護士や警察に相談する必要があります。
3.まとめ
このように、借りパクをした場合に刑事上の責任を問われるケースは限定的です。
また、貸主が借主と連絡が取れなくなった・お金を返してくれないからといって警察に詐欺の被害届を出したとしても、動いてくれることは少ないです。
しかし、借主が民事上の責任を問われる可能性はあります。支払いを拒んだ場合、お金を貸してくれた友人が法的手段をとることがあるのです。
刑事上の責任と民事上の責任は異なるものです。「詐欺罪じゃないから、借りた金は返さなくても問題ない」とはなりません。
お金の貸し借りや詐欺罪について心配になっている方は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。