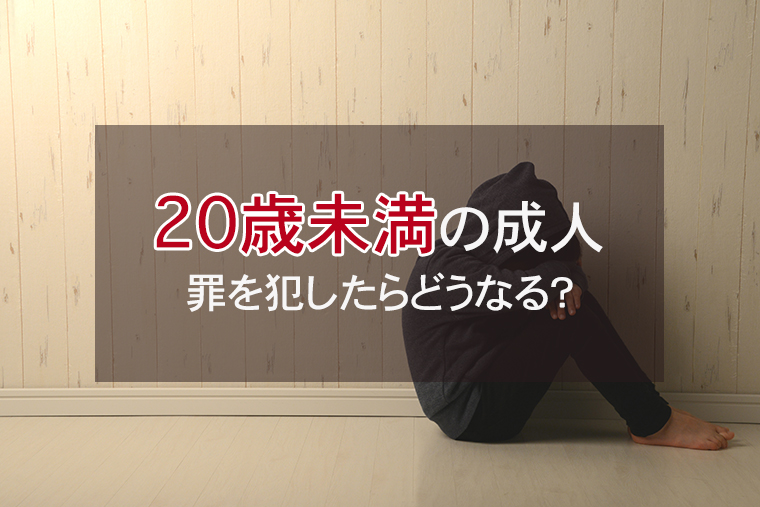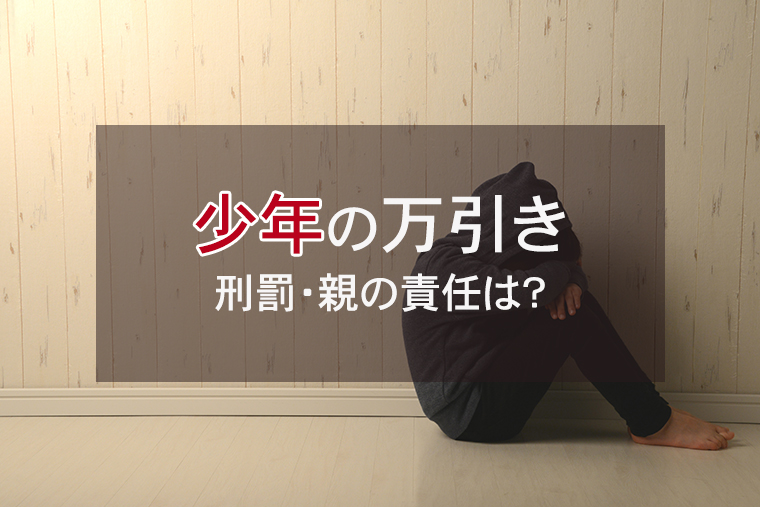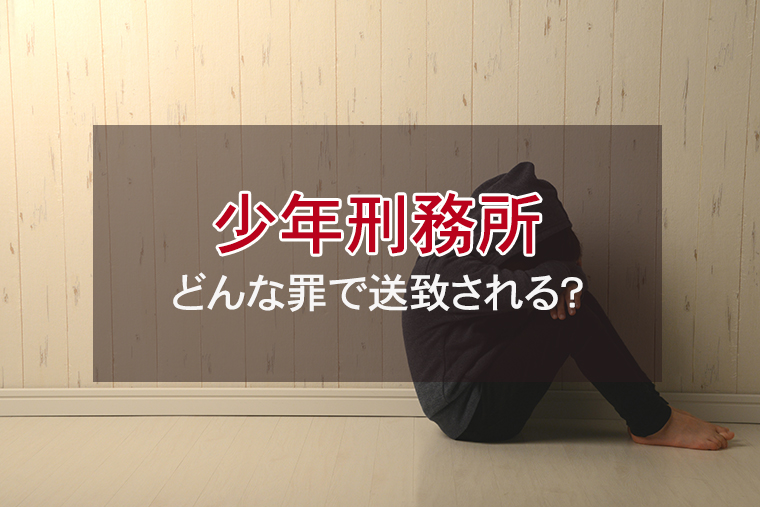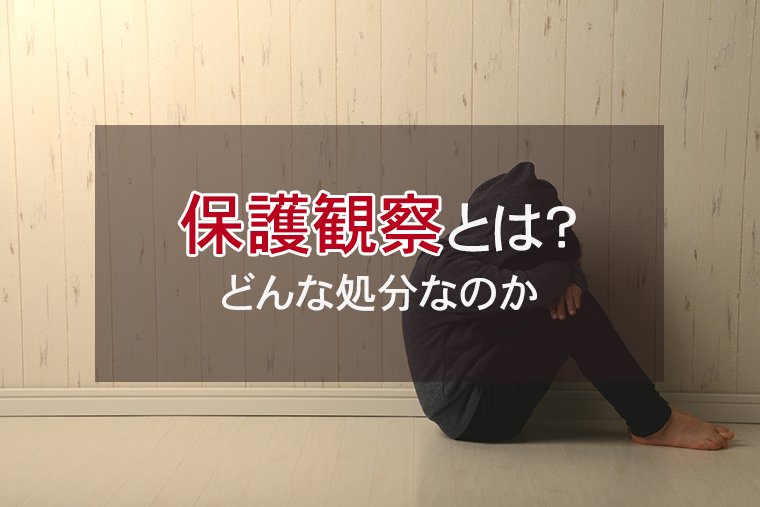補導される年齢と理由|補導されるとどうなるのか?
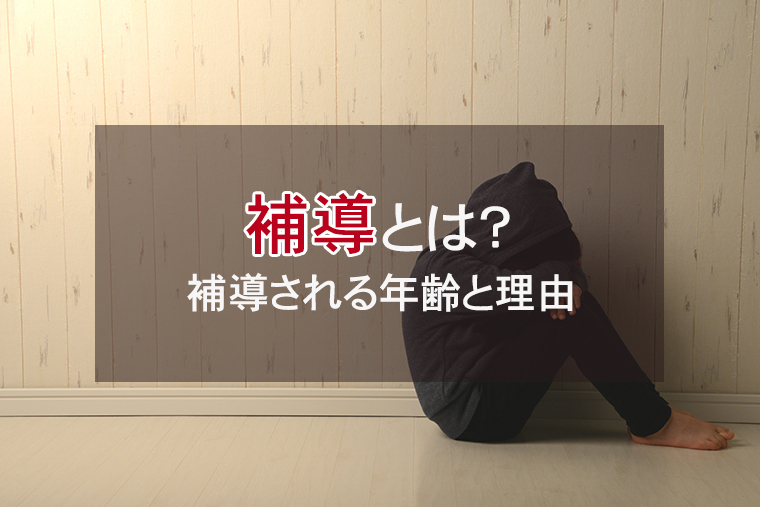
お子さんが警察に補導された、という連絡を受けた時、多くの保護者の方は動揺してしまうかと思います。
「これからどうなるのか」「学校に連絡が行くのか」「将来に影響はないのか」といった不安を抱えられることでしょう。
補導は、未成年者の健全な育成を目的とした制度であり、必ずしも「悪いこと」をしたから行われるわけではありません。しかし、実際に補導が行われたならば、保護者としてやるべき今後の対応を理解しておくことが大事です。
本コラムでは、補導制度の基本的な仕組みから、補導された場合の具体的な流れ、保護者として知っておくべき対応のポイントまで、弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。
1.補導とは?
(1) 補導の目的
補導とは、20歳未満の未成年者が、不良行為やぐ犯行為(将来罪を犯すおそれのある行為)を行った場合に、警察官や補導員が声をかけて注意指導を行う制度です。
補導制度の最大の目的は、未成年者の健全な育成と非行の防止にあります。
補導には、大きく分けて2つの種類があります。
- 街頭補導
警察官や補導員が街頭でパトロールを行い、不良行為を行っている未成年者を発見した際に、その場で注意指導を行うものです。深夜徘徊、喫煙、飲酒、家出などが典型的な対象となります。多くの補導がこの街頭補導にあたります。 - 継続補導
一度の指導では効果が期待できない、または問題行動が反復している未成年者に対して、継続的に指導を行うものです。警察署に呼び出して面談を行ったり、家庭訪問を実施したりして、より深く関わりながら更生を支援します。
補導は懲罰的な措置ではなく、あくまで教育的・福祉的な観点から行われる指導です。ネグレクトや虐待などの劣悪な環境に置かれている子どもを発見できるケースもありますので、補導されること自体が必ずしも悪というわけではありません。
(2) 補導と逮捕の違い
少年が犯罪行為を行うと、その事件の重大性によっては「逮捕」されることもありますが、「補導」と「逮捕」は本質的に大きく異なります。
【逮捕】
刑事犯罪を犯したとして身柄を拘束されることであり、刑事手続き・捜査の対象となる。強制的な措置であり、逮捕を拒否することはできない。逮捕に続き起訴されれば前科がつく可能性がある。【補導の場合】
あくまで指導・教育が目的であり、強制的な身柄拘束には当たらないため本人の意思を尊重した対応がされる(任意同行を求められるのみである)。補導をされても前科はつかない。少年への質問などが行われた後は保護者に引き渡され、すぐに解放されるのが原則。
ただし、補導であっても、「補導歴」は警察に記録として残ることを理解しておく必要があります。この補導歴自体は前科にはなりませんが、同じ未成年者が繰り返し補導されると、「非行について常習性がある」「指導効果が上がらない」と判断され、少年事件となった際には厳しい処分が検討される可能性があります。
特に注意すべきは、補導を繰り返すことで家庭裁判所送致(少年事件化)に発展するリスクがあることです。
補導歴が積み重なると、次に何らかの問題行動を起こした際に「ぐ犯少年」として、家庭裁判所での審判手続きの対象となる可能性があります。結果として、保護観察や少年院送致などの保護処分が下される可能性が高まります。
このため、補導は「注意で済んだ」と軽視せず、保護者としてはお子さんの行動を見直す重要な機会として捉えることが大切です。
→少年事件解決の流れと弁護士依頼の重要性
2.補導される理由
(1) 補導は20歳未満の少年が対象
補導の対象となるのは、20歳未満の未成年者(少年)です。この年齢の制限は、少年法における「少年」の定義に基づいており、満20歳の誕生日を迎えた時点で補導の対象から外れます。
さらに、補導歴は少年が20歳になると破棄されます。20歳以降に刑事犯罪を犯してしまった場合、少年の時の補導歴が量刑に影響を与えるということはありません(※少年事件の対象となる非行少年として補導された「非行歴」は、20歳を過ぎても前歴として残ります)。
なお、「少年」とは性別を問いません。
(2) 補導の対象となる行為
補導の対象となる行為は、警察庁の通達により17つが具体的に定められています。
これらは大きく分けて、実際に犯罪に該当する行為と、犯罪ではないものの将来の非行につながるおそれのある不良行為に分類されます。
- 飲酒
- 喫煙
- 薬物使用(薬物乱用)
- 粗暴行為(けんか・乱暴な言動)
- 刃物等の所持
- 金品不正要求(恐喝に至らない金品の要求)
- 金品持ち出し
- 性的いたずら
- 暴走行為
- 家出
- 無断外泊
- 深夜はいかい(都道府県の青少年保護育成条例で定められた時間帯の外出)
- 怠学(正当な理由のない学校の欠席)
- 不健全性的行為
- 不良交友(暴力団員や不良グループとの交友)
- 不健全娯楽(パチンコ、風俗営業所への立ち入りなど)
- その他(上記の行為以外の非行その他健全育成上支障が生じるおそれのある行為で警視総監又は都道府県警察本部長が指定するもの)
これらの不良行為の中で補導される原因として最も多いのが「深夜はいかい」です。
多くの都道府県では、午後11時以降(地域により午後10時の場合もある)を深夜時間帯とし、この時間に正当な理由なく外出している未成年者は補導の対象となります。
重要なのは、実際に犯罪を犯していなくても補導される可能性があるということです。例えば、深夜にコンビニの前でたむろしているだけでも、「深夜はいかい」として補導されることがあります。
また、学校を休んで繁華街にいるところを発見されれば「怠学」として補導される可能性があります。
保護者の方は、お子さんがこれらの行為を行わないよう、日頃から適切な指導を心がけることが大切です。
これまでの補導歴や非行歴、不良行為の深刻さなどによっては、少年であれ逮捕されてしまうケースも0ではありません。
3.補導後の流れ
(1) 補導から保護者連絡まで
お子さんが補導された場合、以下のような流れで手続きが進みます。
1:少年の身元確認
補導が行われると、まず警察官や補導員がお子さんに対して身元確認を行います。
この際、氏名、年齢、住所、保護者の連絡先、学校名、学年などの情報が聞き取られます。また、補導に至った行為の内容や動機も確認されます。
お子さんが素直に協力しない場合や身元が不明の場合、少年をその場に留めておくことが危険と判断されるような場合には、警察署に任意同行して詳しい事情聴取が行われることもあります。
2:保護者への連絡
身元が確認できた場合、通常はその場で保護者に電話連絡が入ります。
連絡内容としては、以下の通りです。
- お子さんが補導された旨の報告
- 補導の理由(どのような行為で補導されたか)
- 迎えに来てもらう場所と時間
- 必要に応じて、警察署での面談の日時
補導されると、深夜・早朝でも原則として即座に保護者への連絡が行われます。
(※大学生の場合は保護者に連絡されず、口頭での注意にとどまることもあります。)
深夜はいかいのみなど比較的軽微な不良行為の場合や、初めての補導の場合は、現場で注意指導を行った後保護者に迎えに来てもらい、その場でお子さんを引き渡すことで終了となるケースが多くあります。
しかし、この場合でも学校へ連絡が入る可能性があります。
また、お子さんの状況や補導の内容によっては、一回限りの指導では終わらず、継続的な指導が必要と判断される場合があります。これが先述の「継続補導」です。
保護者の方は、補導を「子どもの現状を正確に把握し、今後の指導方針を考える機会」として捉え、警察官との連携を図ることが重要です。
(2) 警察署での手続き
過去の補導歴・非行歴が多い場合や、不良内容が深刻である場合は、児童相談所への送致が行われ、少年事件として少年の保護処分を検討される可能性もあります。
児童相談所での手続きと、その後の家庭裁判所で行われる少年審判による保護処分については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
児童相談所とは?役割・一時保護等について解説
4.補導による影響
(1) 補導歴の記録による不利益
補導されると、「少年補導票」というものが作成され、警察に補導歴として記録されます。この記録は、20歳となるまでの将来にわたって少年に悪影響を与える可能性があります。
補導歴は永久に保管されるものではありませんが、一般的に数年間は警察に記録として残り続けます。この期間中に再び補導されたり、何らかの問題行動を起こしたりした場合、過去の補導歴が参考にされます。
すなわち、補導歴がある状態で再び補導されると、「常習性がある」としてより厳しい指導が行われたり、継続補導の対象となりやすくなったりします。
家庭環境に問題があると判断されれば、次の段階として少年事件化(家庭裁判所送致)のリスクが大幅に上昇することも考えられます。
(2) 進学・就職への影響
補導歴は前科ではないため、一般企業の就職活動や大学受験において、補導歴の提出を求められることは基本的にありませんし、履歴書に記載する必要もありません。
つまり、通常の身元調査では補導歴が判明することはありません。
ただし、採用時の身元調査が厳格に行われる職業・分野では、注意が必要であると言えます。
特に、補導歴ではなく非行歴は前歴として残りますので、将来の採用に影響する場合があります。
(3) 保護観察中・試験観察中の補導のリスク
既に家庭裁判所での審判を受け、保護観察や試験観察の処分を受けている少年が補導された場合、通常の補導よりも重大な影響が生じます。
まず、保護観察中に補導されると、保護観察の条件違反として扱われる可能性が高いです。保護観察所に即座に報告され、場合によっては少年院送致などのより重い処分に変更される可能性もあります。
試験観察中の補導(家庭裁判所で試験観察の決定を受けている場合の補導)についても、やはり試験観察の結果に決定的な悪影響を与えます。
改善の見込みがないと判断される根拠となるため、本審判でより重い保護処分が下される可能性が極めて高くなります。
以上より、特に保護観察中・試験観察中に補導された場合は、直ちに弁護士に相談することを強くおすすめします。
適切な対応を取らないと、お子さんの将来に取り返しのつかない影響を与える可能性があります。
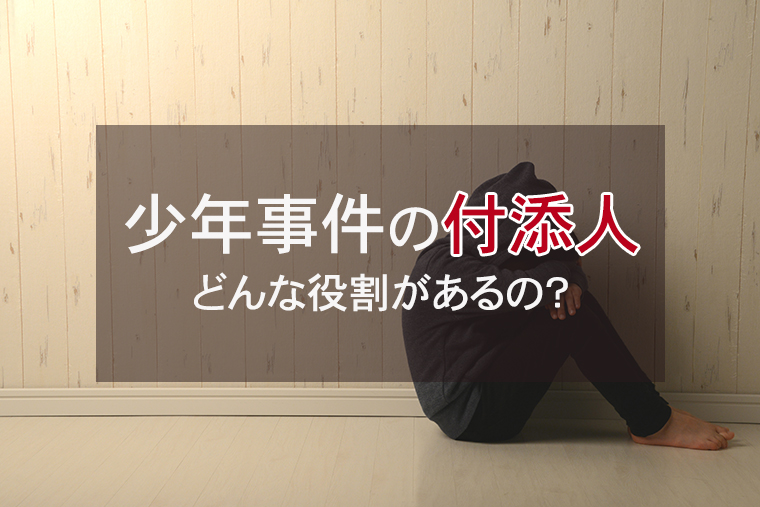
[参考記事]
少年事件における付添人の役割
5.補導少年の保護者が取るべき対応
お子さんが補導された際、保護者の方の対応はその後の少年の人生に大きく影響します。
警察からの連絡を受けた時は、まず動揺せず冷静に対応し、補導の理由と迎えの場所・時間を正確に確認することが重要です。お子さんを責める前に、事実関係をしっかり把握し、警察官の指示に従って速やかに迎えに行きましょう。
お子さんと向き合う際は、感情的にならず、まずお子さんの話をしっかり聞くことから始めてください。補導に至った背景や原因を一緒に考え、今後の生活について具体的な改善策を話し合うことが大切です。
その後は、生活リズムや交友関係の見直しを行い、必要に応じて学校や警察との連携を図り、再発防止に向けた家庭でのルール作りに取り組みましょう。
保護者の方がお子さんに寄り添う対応こそ、お子さんの立ち直りと再発防止の鍵となります。
6.少年の非行・少年事件は弁護士へ相談を
お子さんが補導を繰り返している場合や、より重大な問題行動が発生し少年事件となってしまった場合には、専門家の助けが必要となることがあります。
特に保護観察中や試験観察中の補導、または家庭裁判所での審判が予想される非行の場合は、早期の弁護士相談が重要です。
少年事件に精通した弁護士は、お子さんの処分軽減や適切な環境調整のサポートに向けて、家庭裁判所や関係機関との調整を行います。
また、補導の段階であっても、今後の見通しや対応方法について専門的なアドバイスを受けることで、事態の悪化を防ぐことができます。
一人で悩まず、お子さんの将来のために適切なサポートを求めることが大切です。
7.補導に関する実際の質問
-
Q.18歳になる高校生も補導の対象となりますか?
もうすぐ18歳になる高校生です。
喫煙・飲酒などがなければ、夜間外出をしても18歳の高校生が補導されることはないですか?A.補導の対象となる可能性はあります。
法改正で満18歳で成人となりますが、少年法は変わらず20歳未満を少年としています。したがって、18歳の高校生でも深夜はいかいで補導される可能性はあります。
また、飲酒やたばこは法律で20歳未満は禁止されていることも変わりありません。よって、20歳未満での飲酒・たばこは警察の補導対象となりますし、家庭裁判所の処分を受ける可能性もあります。