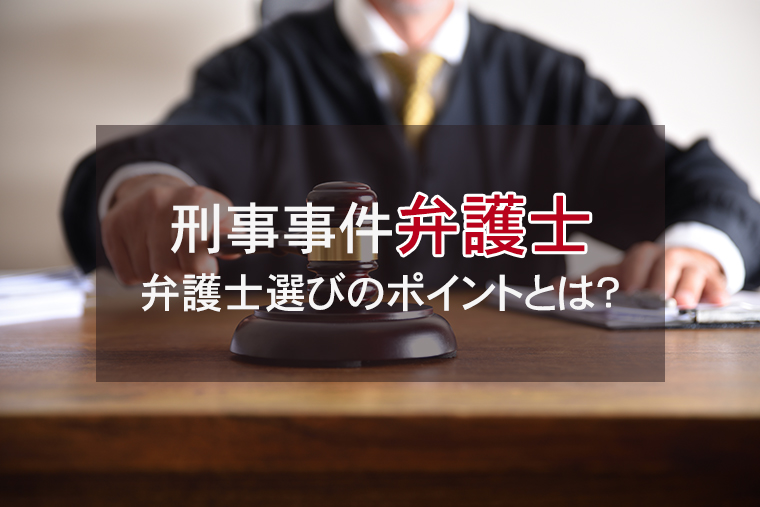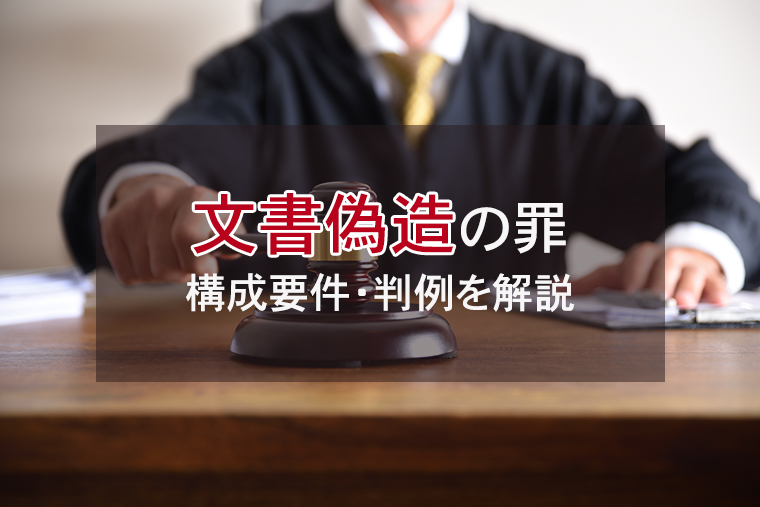起訴猶予とは?不起訴・無罪との違い

刑事犯罪を犯した場合、捜査機関に検挙されても「起訴猶予」と判断される場合があります。
起訴猶予と聞くと、「起訴を先延ばしにされただけで、以降も捜査や訴追されるのではないか?」「自分は本当に無罪になったのか?」と不安になるかと思います。
ここでは、「起訴猶予」は具体的にどのような処分なのかを解説します。
1.起訴猶予とはどのような処分?
(1) 「起訴」と「不起訴」の違い
「起訴」とは、事件の捜査を終えた検察官が裁判所に対し、被告人の処罰(罰金・拘禁など)を求める行為で、「公訴」「公訴提起」「訴追」などとも呼ばれます。
これに対して「不起訴」とは、文字通り検察官が当該事件を起訴しないで終わらせることを決めたということです。
起訴された場合、正式起訴(公判請求)ならば、公開の法廷での裁判となります。裁判で有罪判決となった場合、罰金刑や拘禁刑(執行猶予付きを含む)などが科され、前科がつくことになります(※無罪判決ならば前科はつきません)。
なお、起訴の種類には、書面による手続だけで罰金刑を科す「略式起訴」もあります。初犯の場合や、被害者との示談が成立している場合などには、起訴をされても略式手続にとどまるケースが多いです。
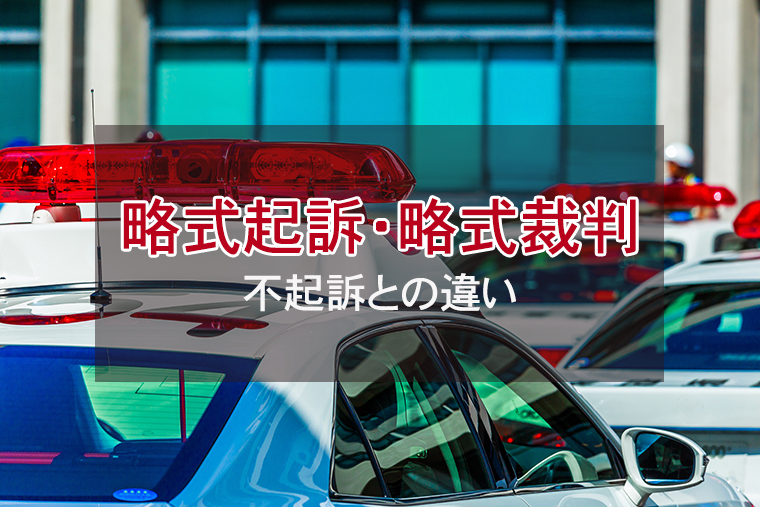
[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
一方、不起訴処分ならばそもそも有罪判決を受けることはありませんので、該当の事件について前科がつくことはありません。
このように、被疑者にとって、「起訴処分」となるか「不起訴処分」となるかはとても重要なものです。
起訴・不起訴の最終的な判断するのは検察官です。
検察官は、起訴するか不起訴にするかの判断において、広範な裁量を有しています。その際の考慮要素として、刑事訴訟法248条では、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状が挙げられています。
比較的軽微な犯罪で、前科がなく、被疑者が犯行を反省している、被害者との示談が成立した場合などには、起訴猶予を理由とする不起訴処分となる可能性が高くなります。
(2) 起訴猶予は不起訴理由の一種
不起訴になる主な理由は、以下の3つがあります。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
1.「嫌疑なし」とは、被疑者として捜査したが全くの人違いが判明した場合や、何の証拠もないことが判明した場合のように、そもそも嫌疑はなかったことが明らかとなったというケースです。
2.「嫌疑不十分」とは、罪を犯したという疑いは残っているが、これを証明するための証拠が十分ではないので起訴しないという判断です。
3.「起訴猶予」とは、犯罪を犯したことを裁判で証明できるが、被害が軽微である、示談ができて被害者も許してくれた、社会的制裁を既に受けている、深く反省しているなどの諸事情を総合考慮して、今回は起訴を見送るという判断です。
このように、起訴猶予とは不起訴処分の理由の1つです。
冤罪ではなく、実際に刑事犯罪を犯してしまっており証拠もあるような場合では、起訴猶予による不起訴を目指すことになるでしょう。
2.起訴猶予になると前科はつかない?
過去の犯罪に関する事実には、「前科」と「前歴」があります。
「前科」とは、なんらかの犯罪で起訴され、有罪の判決を受けてこの判決が確定したという事実のことです。
起訴をされたならば、例え略式命令により裁判が開かれず罰金刑が科されただけの場合でも、有罪には変わりないので「前科」がつきます(前科がつかないのは無罪の場合のみです)。
一方、不起訴処分の場合、そもそも刑事裁判の判決を受けていないので「前科」がつくことはありません。つまり、起訴猶予ならば前科なしです。
「前歴」とは、捜査機関(警察、検察)の捜査の対象となったことがあるという事実のことです。
起訴猶予を含む不起訴処分は、前科としては残りませんが、前歴として残ります。
前歴があっても、その犯罪事実が証明されたわけではありませんから、前例があるだけでマイナスの情状の1つになるわけではありません。
ただし、嫌疑がかかっている犯罪と同種の前歴があれば、事実上、常習犯ではないのかと判断されるのは当然です。例えば、窃盗犯の嫌疑ある場合に、過去に窃盗容疑で捜査を受けた前歴が複数回ある場合などです。このような場合、結果として起訴・不起訴の判断や裁判での量刑上で不利な事実となります。
また、同種犯罪ではなくとも、逮捕の前歴が多数回あれば、事実上、不利に評価されてしまうのは致し方ないところです。
なお、前科による影響については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
前科があると就職に影響するのか?
3.起訴猶予取り消しはあり得るのか?
まず、そもそも起訴されない「起訴猶予」は、起訴されたものの犯罪の証明ができないという「無罪」と本質から異なります。
無罪判決が確定すると、その犯罪容疑(公訴事実)では2度と起訴されることはありません。これを「一事不再理」と呼び、憲法39条が定めています。
万一、同じ公訴事実で起訴されたことが判明した場合は、裁判所は「免訴」という判決で裁判を打ち切らなくてはなりません。
他方、起訴猶予処分には、このような「一事不再理」は適用されません。起訴猶予となった後に起訴することを相当とする事情が生じた場合などには、(公訴時効が完成していない限り)いつでも起訴することができると理解されています(※司法研修所検察教官室編「検察講義案(平成21年版)」法曹会83頁)。
例えば、起訴猶予処分時点では知られていなかった同種の余罪多数が明らかになった場合や、示談が成立したことを考慮して起訴猶予としたところ後に被害者が強迫されて示談に応じていた事実が判明した場合などが、起訴猶予後に起訴される典型例です。
このような起訴猶予の取り消しを受けないよう、被疑者となってしまったなら以下の対応をするようにしましょう。
4.起訴猶予を勝ち取るためのポイント
実際、不起訴処分になる理由としては起訴猶予が最も多いので、自白事件の刑事弁護活動は、起訴猶予の獲得に重点を置くことになります。
起訴猶予の獲得には、被害者と示談をすることが重要です。
被害者と示談が成立しているということは、通常、示談金の支払で金銭的に被害回復がされています。さらに、示談書に宥恕文言(※)の記載があれば、被害者の処罰感情がなくなっていることが明らかなので、この意味でも検察から良い情状として扱ってもらえます。
※宥恕(ゆうじょ)とは、「許す」との意味です。「処罰を求めない」「宥恕する」「寛大な処分を望む」などの記載を宥恕文言と呼び、被害者の同意のもと、示談書に記載させてもらいます。
示談交渉は被害者と行うことになるのですが、実際、被疑者(犯人)本人が示談交渉をしようとしても、被害者としては恐怖のために会うのを拒んだり、犯行に対する怒りから示談交渉を一切受け付けないとの態度をとったりすることが通常です。
また、被疑者と被害者に面識がなければ、そもそも被害者の氏名も連絡先もわからず、警察や検察も決してその情報を教えてはくれませんから、示談交渉の開始自体が不可能です。
しかし、弁護士が弁護人となれば、警察・検察は被害者の承諾を得た上で、弁護士限りで被害者の連絡先を開示してくれます。
また被疑者本人との直接交渉を拒む被害者も、弁護士であれば示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士は被害者の感情にも寄り添い、適切な示談金額でのスムーズな示談成立を目指します。
仮に示談が不成立でも、供託や贖罪寄付を行ったり、検察官に意見書や反省文を提出することにより、被疑者が反省している姿勢をアピールし、起訴猶予を目指していきます。
罪を犯してしまった場合は、不起訴を獲得するためにすぐに弁護士に相談するべきです。
→示談したい
5.起訴猶予の獲得のためには弁護士に相談を
起訴猶予による不起訴処分を得るためには、先述のように被害者との示談を成立させることや、検察官に対し意見書を提出すること等が重要です。
実際に罪を犯してしまい、刑事事件で逮捕されてしまった方でも、弁護士のサポートにより不起訴処分を目指すことは可能です。
どうぞお早めに、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。