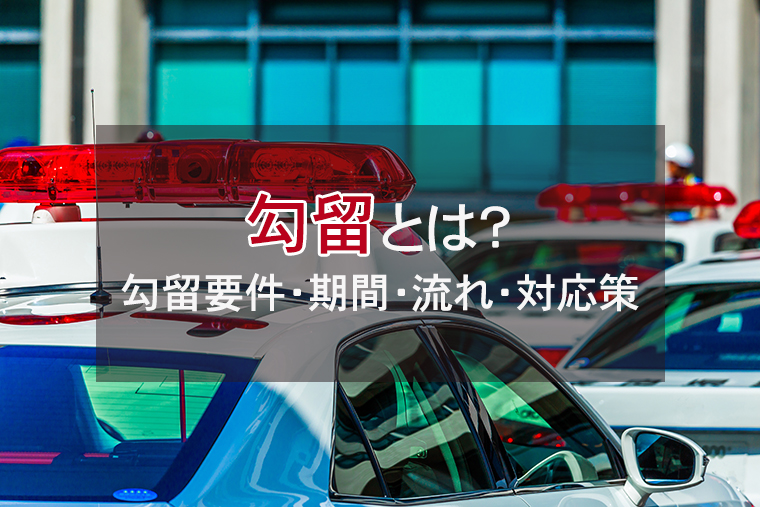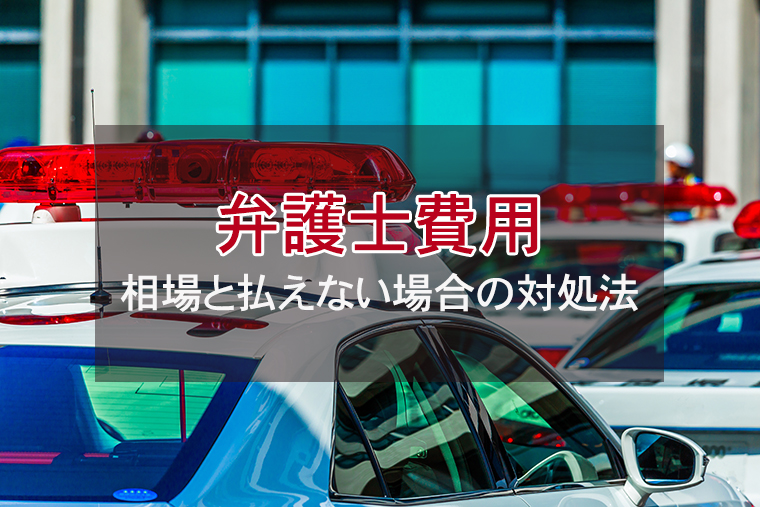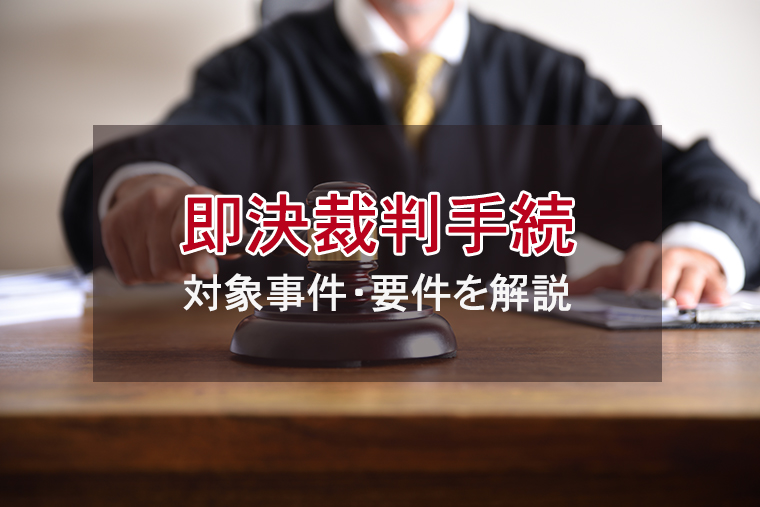微罪処分になる要件|前科・前歴はつくのか?
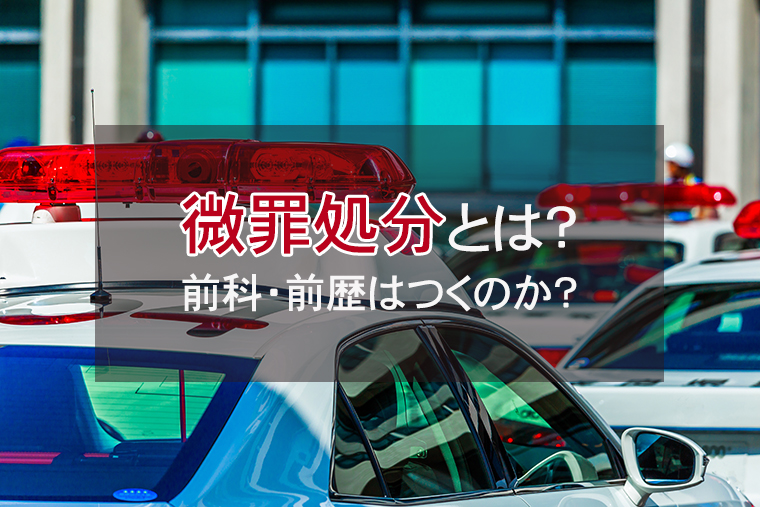
刑事事件の中でも特に軽微な事件を起こした場合、警察に逮捕されたとしても、検察官送致をされずに釈放してもらえることがあります。
そのような処分のことを「微罪処分」と言います。
とはいえ、警察に検挙をされたとなれば、微罪処分と言われても不安を感じることと思います。
微罪処分となるのはどういったケースで、微罪処分の後はどのような流れになるのでしょうか?前科・前歴はつくのでしょうか?
本コラムでは、微罪処分について解説いたします。
1.微罪処分とは?
「微罪処分」とは、警察が刑事事件の被疑者を逮捕し事情聴取したものの、送検せず、事件処理を終わらせる手続きです。
例えば、万引きが見つかって警察署に連れて行かれたとしても、被害額が少なく初犯である場合には事情聴取だけ受けて(被害弁償を促されて)微罪処分として家に帰してもらえることがあります。
警察が犯罪を捜査した時には、事件を検察官に送致しなくてはなりません。送致とは、事件を検察官に引き継ぐということです。
しかし、特に検察官が指定した事件(微罪事件)については、検察官に送致する(=送検する)必要がありません。これが微罪処分となるケースです。
送検については以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
「送検」とはどういう意味?|身柄送検、書類送検
微罪処分の判断をされた場合には、たとえ罪を犯して逮捕されていたとしても、警察に1〜2日留置されただけで、そのまま釈放してもらうことができます。
いったん微罪処分として釈放された場合には、その後同じ罪で逮捕・勾留されることも、あらためて捜査を進められて起訴されたりすることも原則としてありません。微罪処分の後に微罪ではないことが明らかになった場合など、判断の基礎となった事情と真実との相違が発覚したケースでは再度の取り調べが行われるケースもありますが、実際には考えにくい事態です。
なお、刑事事件では警察に逮捕されても釈放されて自宅で生活ができる「在宅事件」がありますが、在宅事件の場合は釈放後も捜査が継続されます。
在宅事件の場合、単に「身柄拘束せずに捜査を進める方法」が選択されただけに過ぎず、書類送検はされるのです。検察官に事件が引き継がれるので、起訴されてしまう危険性が残ります。
これに対し、微罪処分の場合にはそもそも送検されないので、起訴されることはありません。
軽微な事件については、警察・検察・裁判所・刑務所など行刑機関の負担を軽減するために、そして被疑者に対しできるだけ早く社会内での更生の機会を与えるために、このような特例が許されているのです。
2.微罪処分のメリット
微罪処分となると、以下のようなメリットがあります。
(1) 早期に釈放される
1つは、すぐに身柄を釈放してもらえることです。
通常、刑事事件になると、逮捕・勾留されて、逮捕後最大23日間は身柄拘束されてしまう可能性があります。
その間、家族を含めた他の人々と連絡は取れず、接見があるにしても自由に接触することはできません。
一方、微罪処分ならば1〜2日ですぐに解放されますし、警察官から厳しい取り調べを受けることもありません。
身柄拘束されるとしても短期間なので、学校や職場など社会生活への影響もほとんどありません。
会社にもすぐに普通通りに通勤できるようになるため、業務に支障を発生させたり、解雇されたりする可能性は低く、勤務先に犯罪が発覚することも通常はありません。
罪を犯したことを周囲に知られにくく、近所の人などが不審に思うこともありません。
(2) 刑事事件にならない(前科がつかない)
微罪処分となった場合には、有罪判決を受けることもなく、前科もつきません。
しかし、微罪処分となった場合でも「前歴」はつくので、注意が必要です。たとえ送検されなくても、捜査機関のデータベースに残ってしまいます。
前歴は前科とは違い、犯罪の証明があり有罪判決が確定したわけではありませんから、前科ほどの不利益はありません。
ただし、将来何らかの犯罪で捜査を受けた際、前歴があるようなケースでは、起訴・不起訴の判断、裁判所の量刑において不利な事情として考慮される危険はあります。
3.微罪処分になる要件
このように、被疑者にとって微罪処分となることには大きなメリットがあります。
しかし、法律上「このような場合は微罪処分となる」という決まりはありません。
また、微罪処分の内容は、各地方検察庁の検事正がその管轄区域内の警察に指定しており、全国一律とは限りません。
しかも、各地方検察庁が指定する条件は「非公開」です。微罪処分となる条件を明らかにしてしまうと犯罪を誘発してしまう危険があるからです。
したがって、微罪処分の要件の詳細は正確にはわかりません。
文献によると、次のような指定内容が一般的とされています(※参考文献:武内謙治・本庄武「刑事政策学」(日本評論社)165頁)。
指定事件は、窃盗罪、詐欺罪、盗品関与罪、賭博罪、暴行罪等
(1)例えば、次の条件を満たす窃盗・詐欺・横領・これに準ずる盗品関与
・被害が僅少で、かつ、犯罪が軽微なこと
・被害品等の返還や、その他弁償などで、被害が回復済みであること
・被害者が処罰を希望しないこと
・素行不良者ではないこと
・偶発的犯行であること
・再犯のおそれがないこと(2)例えば、次の条件を満たす賭博事件
・初犯者であること
・賭けた金銭などが極めて僅少であること
・犯情も軽微であること
・共犯者のすべてについて再犯のおそれがないこと(3)例えば、次の条件を満たす粗暴犯(暴行、傷害など)
・素行不良者でないこと
・偶発的犯行であること
・被害が軽微であること
ただし、これらは、あくまでも一例であり、必ずこのような指定がされているとは限りませんし、これ以外の事件が指定されていないとも限りませんので、注意してください。
以上のように、微罪処分として認められるための要件はいくつかあります。
警察に逮捕されたり事情聴取を受けたりした場合には、上記に当てはまることをしっかりアピールするのが良いです。
4.微罪処分を獲得する方法
上記のポイントを踏まえ、微罪処分にしてもらうために以下のようなことに注意しましょう。
(1) 反省の態度を示す
第一に、反省の態度を示すことです。
微罪処分としてもらうためには、被疑者がしっかりと反省していて再犯可能性がないと判断してもらわねばなりません。
反対に、小さな事件でも「自分は悪くない」という態度を取っていると、送検される可能性が高くなります。真摯な態度で、反省の気持ちを捜査官に伝えましょう。
(2) 被害回復をする
被害者がいる事件の場合には、被害を回復することが重要です。
万引き・窃盗などであれば、その商品をそのまま返還すれば足りることがあります。
これに対し、暴行や痴漢・盗撮などの場合、損害賠償金(慰謝料)を支払うことを考えるべきです。
その場で示談できない場合、後日必ず被害弁償することを約束することで、警察官が評価してくれるケースもあります。
(3) 監督者がいることを伝える
微罪処分の決定の際、監督者の有無は非常に重要です。
そこで、配偶者や親などがいる場合には、そういった人がいて同居していることなどをきちんと伝えましょう。
そして、早急に警察に迎えに来てもらい、身柄引受書を作成してもらうことが大切です。
(4) 普段の素行が良好・初犯であることを強調する
微罪処分としてもらえるのは、普段の素行が良好で、偶発的犯行(初犯)のケースが多いです。
そこで、警察から事情聴取されるときには、「普段は真面目であること」「定職があり、しっかりと働いていること」などを強調しましょう。
たまたま虫の居所が悪かった、ストレスが溜まっていたなどの事情を説明すれば、今回限りは微罪処分としてもらえる可能性が高くなります。
5.まとめ
微罪処分にしてもらえると、勾留されずに早期に社会復帰でき、また、起訴されず前科もつかないので大きなメリットがあります。
刑事犯罪が検挙されたならば、なるべく早めに刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士までご相談し、示談交渉などをご依頼ください。