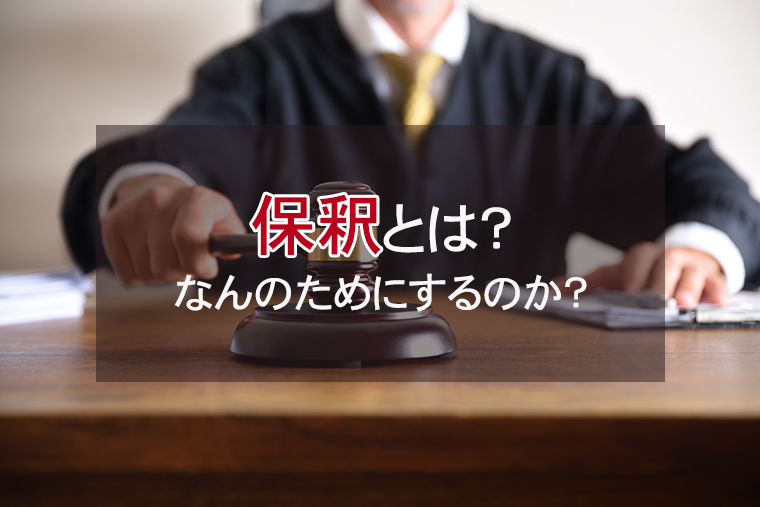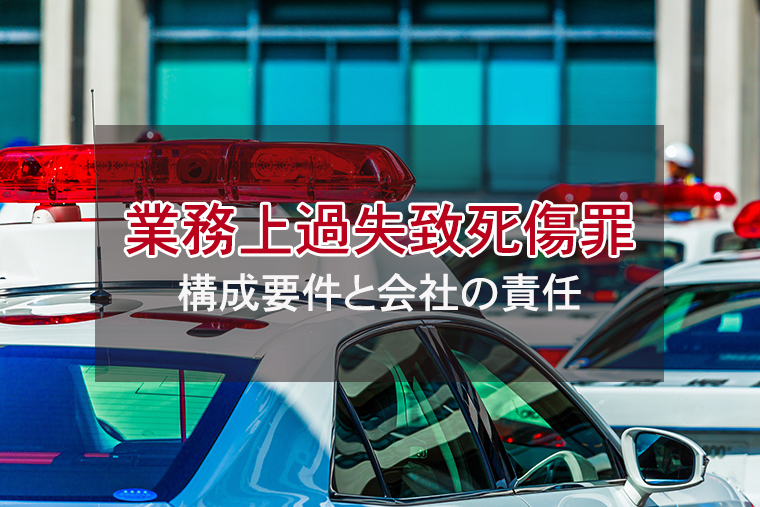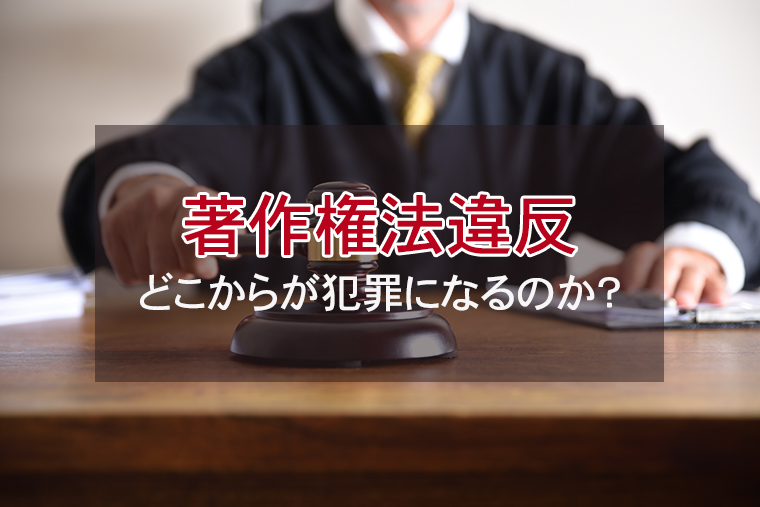刑事告訴されたらどうなる?手続きの流れをわかりやすく解説
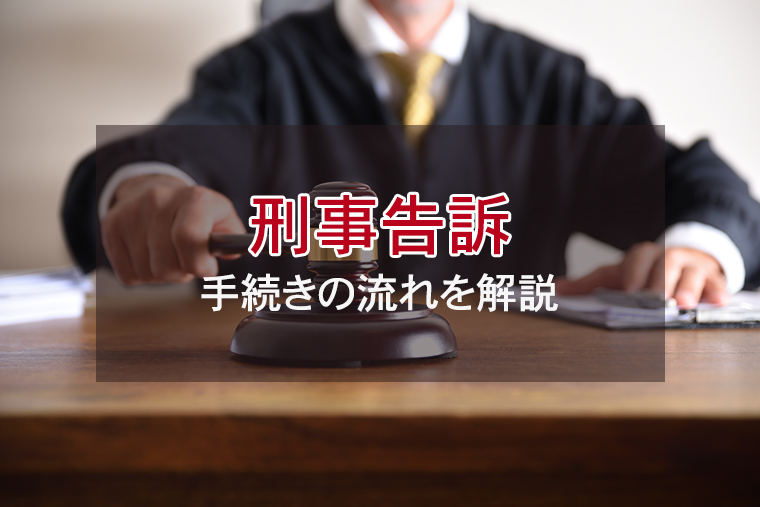
ご自身が刑事犯罪を犯してしまった場合、事案によっては「告訴」される可能性も0ではありません。
本コラムでは、「告訴」の正確な意味を確認し、「告訴されたらどうなるのか」「告訴を取り下げてもらう、避けるためにはどうすればいいのか」などを解説していきます。
1.刑事告訴とは?
(1) 告訴について
刑事訴訟法第230条に定められている「告訴」は、犯罪の被害を受けた者(被害者)などの告訴権者が、警察官や検察官といった捜査機関に対し、発生した犯罪事実について報告を行い、犯罪者の処罰を求める意思表示をする手続きを指します。
「告訴状」という書面形式で捜査機関へ提出する方法と、直接口頭で伝える方法の両方が認められています。口頭による告訴の場合、捜査機関側で告訴内容を記録した調書が作成されることになります。
告訴を行える告訴権者については、被害者本人に加え、被害者の法定代理人が該当します。
未成年者が犯罪被害に遭った場合を例に挙げると、本人による告訴が行われなくても、法定代理人である保護者が代わりに告訴手続きを取ることが可能です。ただし、法定代理人が被疑者やその配偶者に該当する場合には、被害者の親族による告訴が認められています。
被害者が亡くなっている状況では、被害者が明確に反対の意思を示していない場合に限り、配偶者、直系親族、兄弟姉妹による告訴が可能となります。
(2) 被害届との違い
「被害届」は、犯罪被害を受けた当事者(被害者)が、「このような事件による被害を受けました」という事実関係を捜査機関に届け出る制度です。この届出により犯罪被害の発生を捜査機関に把握させ、捜査着手の必要性を示すという機能を果たします。
つまり、被害届と告訴の違いは、犯罪者の処罰を求める意思表示という要素が含まれているかどうかという点です。
一方、告訴・被害届という制度に共通する要素は、捜査機関への被害状況の申告という点です。
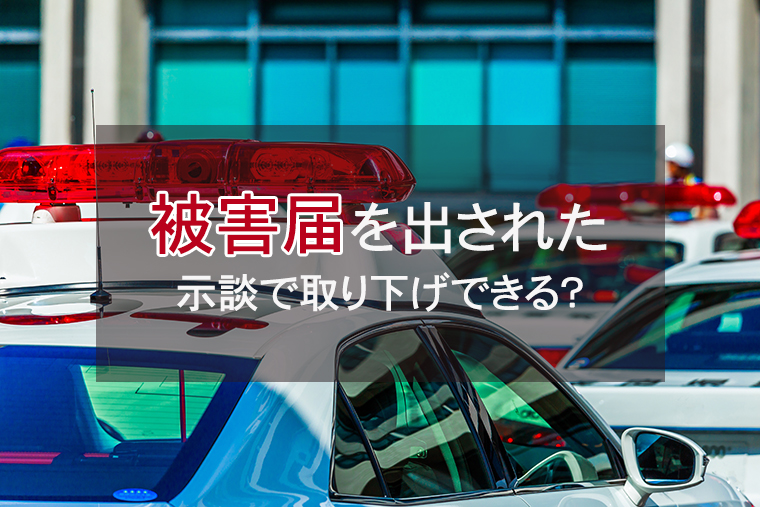
[参考記事]
被害届を出されたら示談で取り下げてもらうことはできるのか?
2.告訴状の受理と捜査について
捜査機関に告訴状が提出された場合、捜査機関は全ての告訴状を受理しなくてはならない、というわけではありません。受理義務を負うのは適法な告訴に限ります。
例えば、公訴時効が完成している場合や告訴期間を過ぎている場合はもとより、犯罪事実の特定を欠き趣旨不明の場合などは不受理扱いが許されます(※1)。
裁判例でも、以下の場合に受理しないことは違法でないとされています。
- 告訴の申立にかかる犯罪が成立しないことが明らかな場合(※2)
- 被害者が告訴の意思を明確に表示していない非親告罪の告訴(※3)
- 記載内容が不明確で特定を欠くのに、告訴人が補正に応じない場合(※4)
※1:元最高検察庁刑事部長検事・弁護士幕田英雄「実例中心・捜査法解説(第3版補訂版)」(東京法令出版)68頁
※2:大阪高裁昭和59年12月14日判決(判例タイムズ553号246頁)
※3:東京高裁昭和57年2月18日判決(判例時報1041巻68頁)
※4:高松高裁昭和58年11月18日判決(高等裁判所刑事裁判速報集417)
告訴状が警察に受理されれば、捜査義務が生じ、たとえ軽微な犯罪であっても警察が微罪処分とすることは許されず、実際の捜査が開始されます。
身柄事件あるいは在宅事件の捜査が続き、検察官による起訴・不起訴処分の決定が行われた際は、その旨が告訴した者へ速やかに通知されます。告訴した者から請求があった場合、処分理由についても通知しなければなりません。
3.起訴を避けるための示談交渉
告訴されたからといって、必ず有罪になるわけではありません。たとえ犯罪事実が本当であったとしても、適切な弁護活動により不起訴を目指すことができます。
告訴状が提出されている場合、被害者と示談交渉を行い、告訴を取り下げる旨の記載も示談書に盛り込んでもらうことを目指します。
特に起訴に告訴を要する親告罪(詳しくは後述)では、被害者との示談において、示談金を現金や預金小切手で支払うのと引き換えに、被害者側が署名押印した「告訴取下書」を受け取り、弁護士が告訴取下書を検察官に提出することで、確実に告訴が取り下げられます。
非親告罪であっても、示談の成立や告訴の取り下げは、被害が金銭的に回復していること、被害者の処罰感情が失われたことを示しますから、有利な事情として考慮され、不起訴となる可能性が高くなります。
あるいは、そもそも告訴前に被害者との示談が成立すれば、告訴や被害届の提出を思い留まってくれる可能性が高いです。
このような理由から、刑事事件ではなるべく早く示談交渉に着手すべきです。
しかし、だからといって被疑者が自分で、あるいは家族に頼んで示談を行うことは、様々なリスクがありお勧めできません。
例えば、被疑者本人やその家族などが被害者に接触しようとすると、嫌悪感・恐怖心・警戒心などから、問答無用で拒否されてしまうケースが珍しくありません。
また被疑者側に他意がなくとも、「被害届や刑事告訴の撤回を強要されたり、証言を翻すよう脅迫されたりするのではないか?」と曲解されるかもしれません。
被害者との示談交渉は、弁護士に任せるべきであると言えます。

[参考記事]
弁護士なしでの示談はリスク大!示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
4.処罰に告訴が必要な「親告罪」
「親告罪」とは、告訴権者による告訴がないと起訴できないとされている犯罪です。
これは、被害者ら告訴権者の意思を尊重するものや、国家権力の介入よりも当事者間での解決が望ましいなどの趣旨によるものです。
親告罪では、例え告訴により捜査が開始したとしても、被害者との示談などによりその告訴を取り下げてもらえれば、検察官が起訴に踏み切ることもありません。
- 事実が公になると、プライバシー侵害など被害者に不利益が生じるおそれのあることから親告罪としているもの
未成年者略取・誘拐罪(刑法229条本文、224条)、名誉毀損罪・侮辱罪(同法232条、230条・231条)信書開封罪・秘密漏示罪(同法135条、133条・134条)- 犯罪被害が軽微なことや悪質性が低いことから、被害者の意思を尊重するべきとして親告罪としているもの
過失傷害罪(刑法209条)、私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(同法264条、259条・261条・263条)- 親族間のトラブルであるため司法が介入するのはできるだけ避けるべきだとの考えにより親告罪としているもの
親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条2項、235条・235条の2)、親族間の詐欺罪・恐喝罪等(同法251条・244条2項、246条、249条など)、親族間の横領罪(同法255条・244条2項、252条など)等
なお、親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴をしなければならないとされています(刑訴法235条)。
そのため、親告罪である犯罪について告訴をせずに6ヶ月経過した場合、検察官は起訴できなくなります。
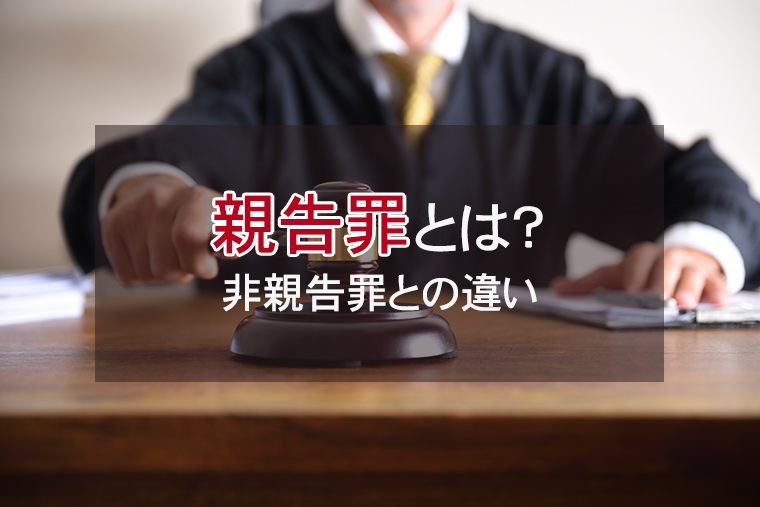
[参考記事]
親告罪とは?非親告罪との違いをわかりやすく解説
平成29年7月13日の刑法改正で、性犯罪の厳罰化の見地から、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪(旧強姦罪・強制性交等罪)が非親告罪とされました。親告罪では、被害者がプライバシー侵害など、いわゆるセカンドレイプの問題から告訴をためらって泣き寝入りする事例が多いため、これらを防ぐ目的があります。
5.告訴される可能性のある方へ
何らかのトラブルを起こし、今後、告訴される可能性がある方は、示談交渉などの対応策をできるだけ早くスタートできるよう、弁護士に相談することを早めに検討するべきです。示談成立などにより不起訴となれば、刑事裁判となる心配はありません。
お悩みの方は、刑事弁護の経験が豊富な泉総合法律事務所にご依頼ください。
初回の相談は無料となりますので、まずは費用の心配をせずにご相談いただけます。