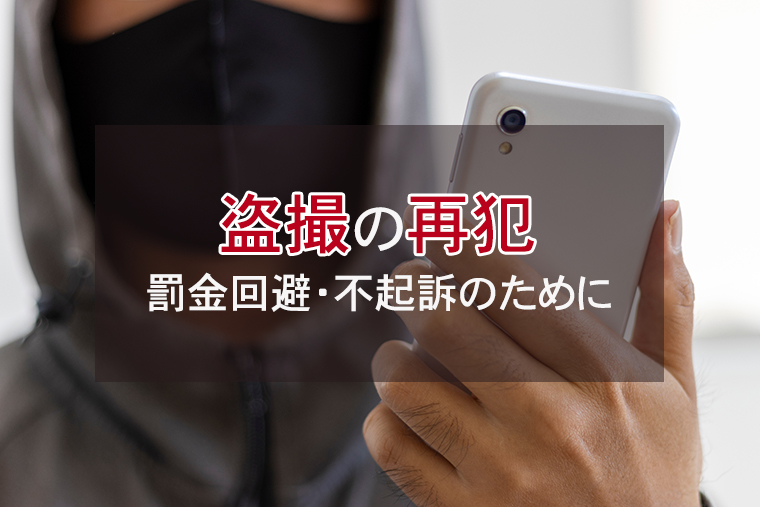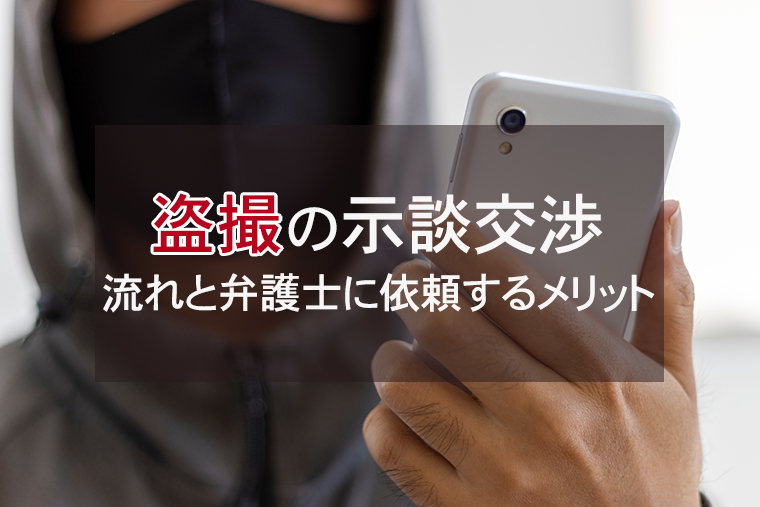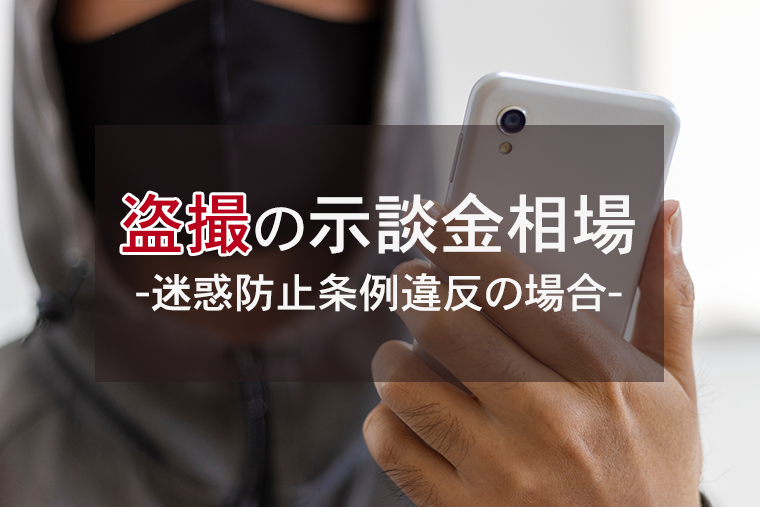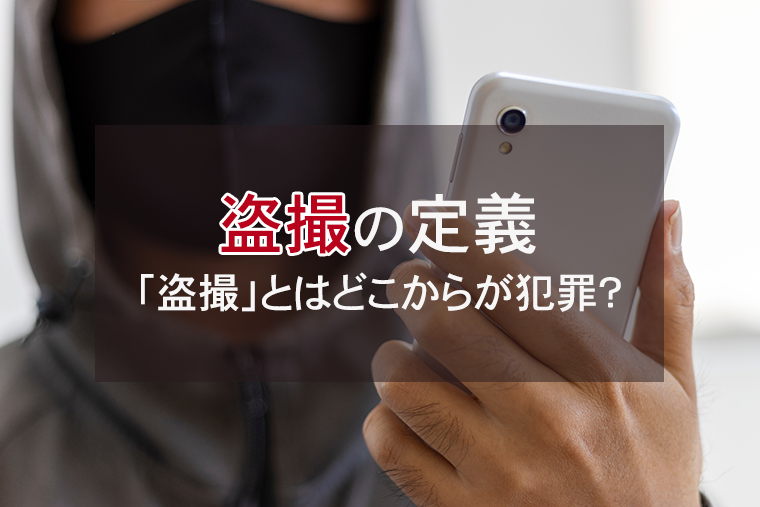盗撮の初犯で逮捕・起訴される?実刑の可能性
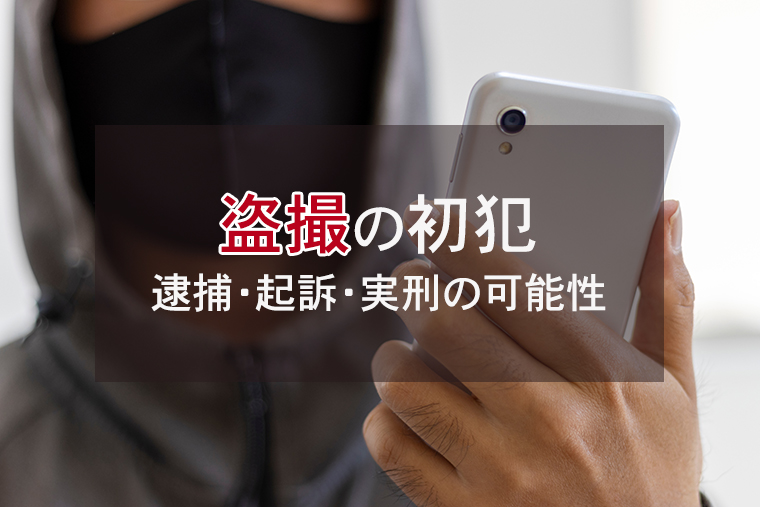
Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/izumilawnet/izumi-law.net/public_html/wp-content/themes/izumi-law/izumi-common-inc/izumi-common-extra-functions.php on line 49
Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/izumilawnet/izumi-law.net/public_html/wp-content/themes/izumi-law/izumi-common-inc/izumi-common-extra-functions.php on line 49
スマートフォン(スマホ)のカメラ機能が普及し、盗撮事件の発生件数はなかなか減りません。
「盗撮は軽い犯罪だ、初犯ならば逮捕されないだろう」と思っている方は多いかもしれませんが、そのような認識は誤りです。
確かに、同種前科がある場合と比べ、盗撮の初犯の場合は起訴率も低く、刑事手続きにおいて厳しい処分が出されることは少ないです。
とはいっても、逃亡や罪証隠滅の恐れがあると判断されれば逮捕・勾留されますし、事案が悪質である・被疑者が反省していない・被害者の処罰感情が強い場合などには起訴される可能性は十分にあるのです。
よって、初犯の盗撮であっても、必ず刑事弁護に詳しい弁護士に相談すべきです。
今回は、初めて盗撮してしまった被疑者の方やその家族に向け、前科などの不利益を避けるためにするべきことについて解説します。
1.盗撮初犯で逮捕・起訴される可能性
盗撮に限らず、刑事手続きは被疑者が身柄拘束されながら進む場合(身柄事件)と、家庭で普通に生活を送りながら進む場合(在宅事件)があります。
盗撮の初犯の場合は、現行犯逮捕されたとしても、取り調べを受けた後ですぐ釈放され、そのまま捜査が進行する「在宅事件」となることがほとんどです。
とは言え、初犯の盗撮=必ず在宅事件になるとも限りません。
逮捕される可能性があるのは、同種前科がある場合のほか、盗撮行為を否認している場合、同一場所で常習的に盗撮を繰り返していた場合、同一女性に対してストーカー的に盗撮を繰り返していた場合などです。また、これらに当てはまらずとも、警察の判断如何では「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」として逮捕されることはあります。
在宅事件では、捜査が進行している間も通勤・通学が普段通り可能です。家庭で普通に生活を送ることができ、捜査機関から呼び出しが来た時には出頭することになります。
よって、混乱や不安を抱えつつも事件をそのままにして、警察からの連絡を待つ方も少なくありません。
とはいえ、在宅事件でも放置しておくと罰金刑などが科され、前科がつく等重大な不利益を残すことになりかねません。
在宅事件での捜査が進行し、被疑者の取り調べ・関係者の事情聴取など証拠の収集が終了した段階で、検察官は処分を決めます。
処分は、「起訴」と「不起訴」に分かれます。
在宅事件だからといって事件を捜査機関に委ねたまま何もしないでおくと、起訴されてしまうことが多いです。
検察は十分な捜査の上、証拠を揃えてから起訴を行うため、起訴されたならば無罪となることはほとんどなく、原則として有罪判決(罰金や執行猶予を含む)となります。
一方、犯罪が行われたことが明らかな場合でも、反省の度合いや示談の成立など、被害回復の状況を鑑みて検察官は訴追を見送ることもあります(=不起訴)。
不起訴となると、その盗撮行為を理由として今後逮捕されたり、刑事処分を受けたりすることは事実上ありません。
2.盗撮の初犯で起訴された事例
泉総合法律事務所が過去に解決した事例で、盗撮をする目的でスーパーの女子トイレに侵入し、スマホで他の個室を盗撮しようとした結果逮捕されたというものがあります。
この事例では、建造物侵入罪と盗撮の罪(当時の迷惑防止条例違反)については分けて対策をとることとなりました。
不起訴処分を得るためには店側と示談するのが不可欠でしたが、弁護士の方で粘り強く示談をお願いしましたが、店側の方針から受け入れてもらえず、建造物侵入の罪について略式起訴で罰金となりました。
一方、盗撮については起訴されることはありませんでした。
このように、盗撮場所が店や住居などで、住居侵入罪も成立する場合には、起訴される可能性が高くなります。
しかし、店側や検察官に謝罪や反省、弁償の意思を伝えられた結果、実刑を避けて罰金刑で終わるケースも多いです。
3.盗撮初犯で起訴された場合の影響
先述のように、例え初犯であっても逮捕・起訴される可能性はあります。
特に、「犯行の様態が悪質である」「常習性がある」「反省をしていない」などと判断された場合、何もしないまま放置すると逮捕・起訴されるケースは少なくありません。
では、身柄事件・在宅事件を問わず、起訴されて有罪となった場合、どのような影響があるのでしょうか。
(1) 刑事処分を受け前科がつく
まず、犯罪を行ったことに対する刑罰を受けます。
盗撮は、性的姿態等撮影罪(=撮影罪)で処罰されるケースがほとんどです。場合によっては、各都道府県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条23項)となることもあります。
また、盗撮行為をするために住居やビル内に立ち入った場合には、別途、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。
有罪判決となれば、拘禁刑、罰金刑等が科されるおそれが生じます(もっとも、情状により執行猶予が見込まれることもあります)。
例え罰金や執行猶予付き判決であっても、刑罰を受けたことになるので「前科」がついてしまいます。
(2) 解雇等の懲戒処分となるリスク
有罪判決を受けて前科がつくと、勤務先を解雇されるリスクが飛躍的に高まってしまいます。
民間企業では、就業規則において、「会社の名誉、対面、信用を毀損したとき」には解雇を含めた懲戒処分を行うと定められていることが一般的であり、盗撮行為はこれに該当するものとして懲戒解雇をされてしまう場合があります。
法律的には、盗撮など業務と無関係な私生活上の犯罪行為を原因として解雇することは(例外的な場合を除いては)許されず、そのような解雇は無効です(最高裁昭和49年3月15日判決)。
しかし、法的に無効といっても、実際に解雇されればそれまでなのが実情です。民事訴訟で争わなくてはならなくなり、時間的にも費用的にも大変なコスト負担となります。
また、国家公務員でも地方公務員でも、有罪判決が公務員としての欠格事由とされており、当然に失職となります(国家公務員法38条、76条。地方公務員法16条、28条)。
他にも、前科があることで一部職業への就職が不利になったり、渡航先の入国審査で入国を拒否される可能性は0ではありません。
4.初犯の在宅事件で不起訴を獲得する方法
以上のような不利益を見て分かる通り、盗撮事件を起こしてしまったら、起訴処分を受けないこと、すなわち不起訴処分を獲得することが極めて重要になります。
では、盗撮の被疑者が不起訴処分となるためにはどうすれば良いのでしょうか。
最も有効な方法は、被害者との示談です。
刑事事件における示談では、示談金(慰謝料)を支払う代わりに、被害者から「被疑者の処罰を望んでいない」という意思を示してもらい、それを記載した示談書を作成します。
示談が成立したら、示談書に、「被疑者を宥恕(ゆうじょ)する」あるいは「寛大な処分を求めます」「処分を求めない」などの文言を記載してもらい、これを検察官に提出します。
(※「宥恕」とは寛大な気持ちで許すという意味です。)
盗撮行為が初犯で、示談が成立していれば、特別な事情のない限りほとんどのケースで不起訴となります。
被疑者本人が示談交渉を行うのは現実的ではないため、示談交渉は刑事弁護の依頼を受けた弁護士が行うのが通例です。
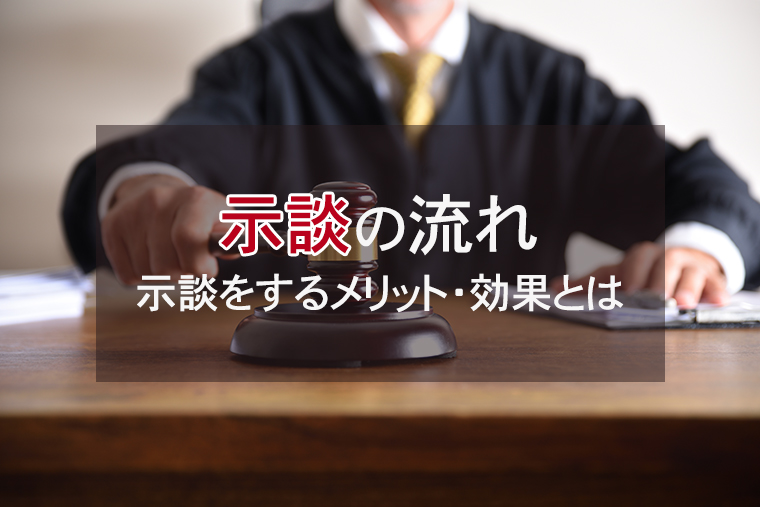
[参考記事]
刑事事件の示談の流れ|示談をするメリット・効果とは?
【示談ができないときは贖罪寄付】
盗撮では被害者を特定できないケースもあります。また、被害者が示談を受け入れてくれないケースもあります。このような場合、示談に代わるものとして、贖罪寄付をするという方法もあります。贖罪寄付とは、被害者のいない犯罪の被疑者や、被害者に示談を拒否された被疑者が、罪を反省して償う気持ちを示すために行う寄付です。
日本弁護士連合会や各地の弁護士会が贖罪寄付を受け付けており、寄付された金銭は公益的な目的で使われ、寄付を受けたという証明書を発行してくれます。この証明書を被疑者が反省している証拠のひとつとして検察官に提出して不起訴処分を求めるのです。示談の成功ほどの強力な効果はありませんが、実務においては有利な事情として考慮されています。
5.盗撮で逮捕されたら弁護士に相談を
初犯・在宅事件であっても、盗撮行為で起訴され有罪判決を受けることがあります。
事件の捜査が始まったばかりならば、起訴処分を回避するために出来ることは沢山あります。
しかし、時間の経過により被害者との示談等は難しくなっていきます。
刑事事件は時間との勝負です。そのため、いち早く弁護士に相談し、早期に対応するべきです。
泉総合法律事務所の代表弁護士・泉義孝は、刑事事件を得意としており、解決実績も豊富です。
盗撮事件を起こしてしまった場合、ぜひ弁護士泉にご相談ください。無料相談も実施しております。
6.盗撮の初犯に関する実際の質問
-
Q.同一女性に連続で盗撮をしました。初犯ですが、罪は重いですか?
会社内のトイレで盗撮をしているカメラが見つかってしまい、問い詰められた結果、私が犯人だと申告しました。
同僚の女性1人をターゲットに、30回ほど盗撮を行ってしまいました。初犯ではありますが、相当罪は重いでしょうか?
A.示談ができなければ起訴の可能性が高いです。
トイレ内の盗撮ですと、撮影罪に問われることと思います。
同一女性の盗撮を目的に約30回行っていたとのことですが、トイレ内にカメラを設置していたとなれば、他にも被害女性が多数いることが考えられます。
従って、初犯でも厳しい処罰となると思います。その同一女性や、他の被害女性全員と示談できれば、初犯であれば不起訴となる可能性もあります。
一方、示談できない場合は、略式起訴による高額の罰金の可能性が高いですが、起訴(公判請求)の可能性も否定できません。弁護士に早急に弁護依頼すべき事案です。