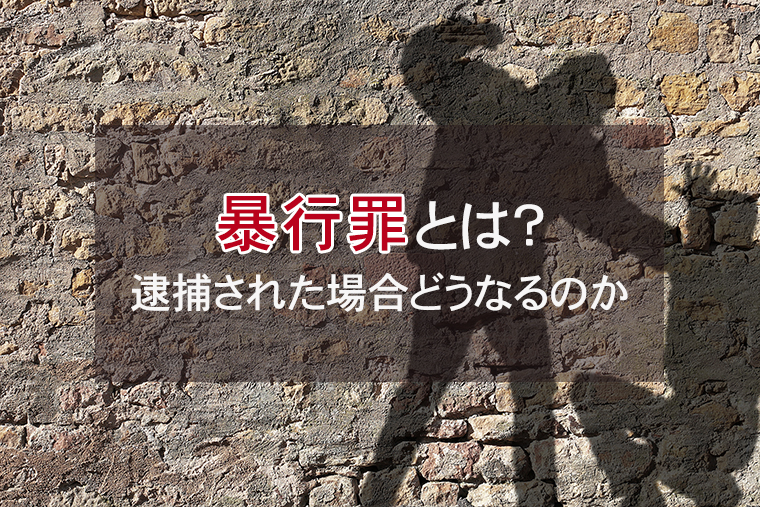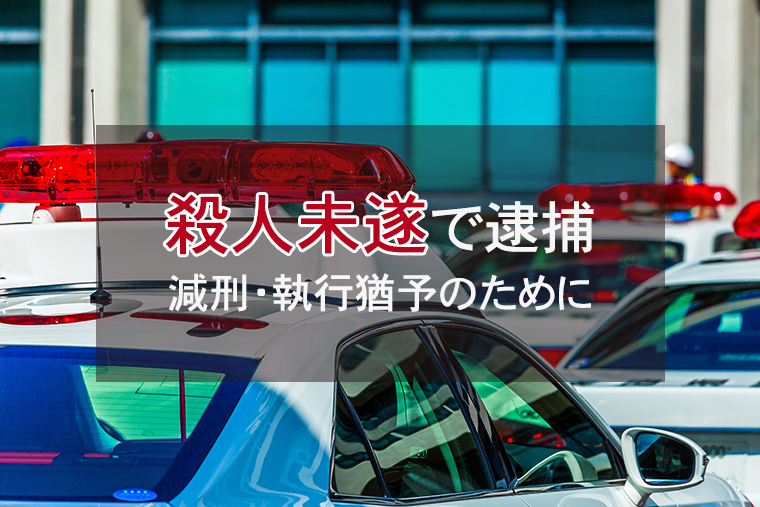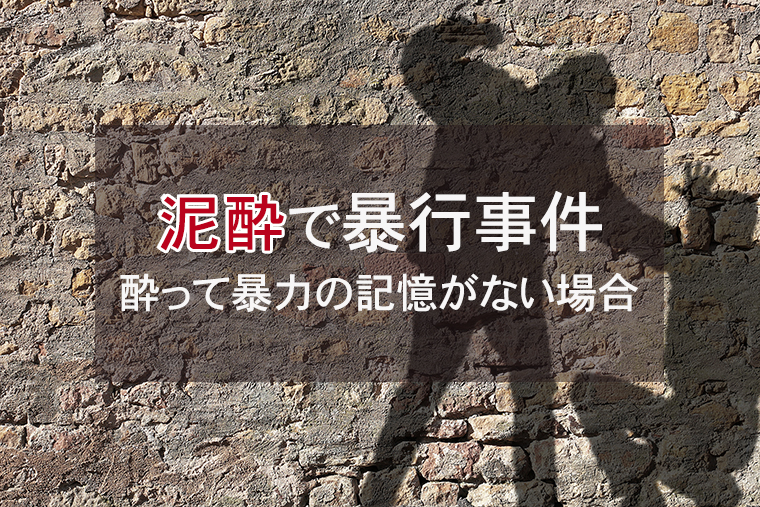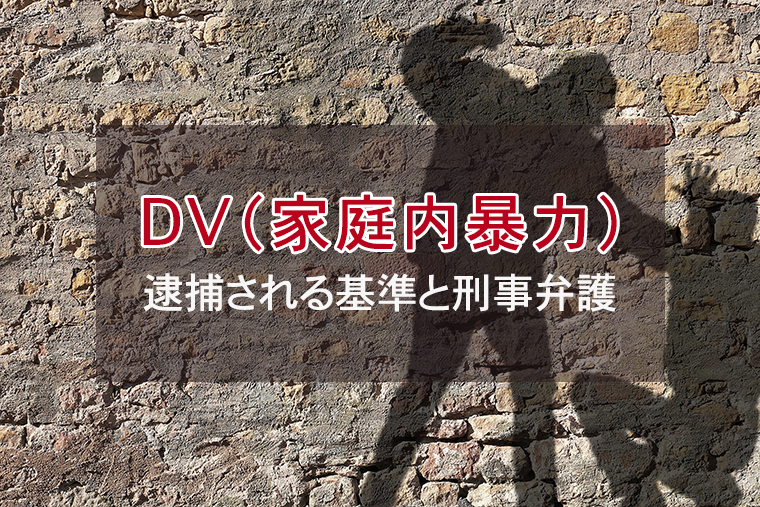過剰防衛とは?正当防衛との違いと要件
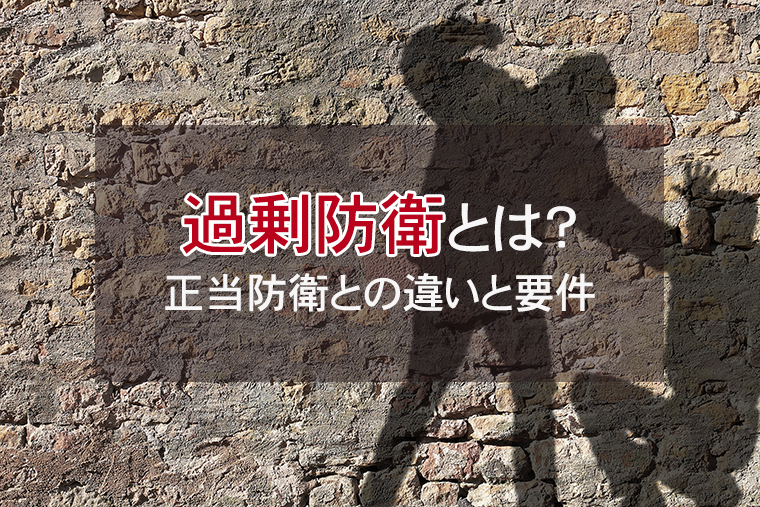
刑法上、自己又は他人の権利を守るためにやむを得ずにした行為について「正当防衛」が認められる可能性があることは、ご存知の方が多いと思います。
ここでは、その「正当防衛」と混同されがちな「過剰防衛(防衛の程度を超えた行為)」について、その要件や判例を解説します。
ちなみに、正当防衛については、下記のコラムをご覧ください。
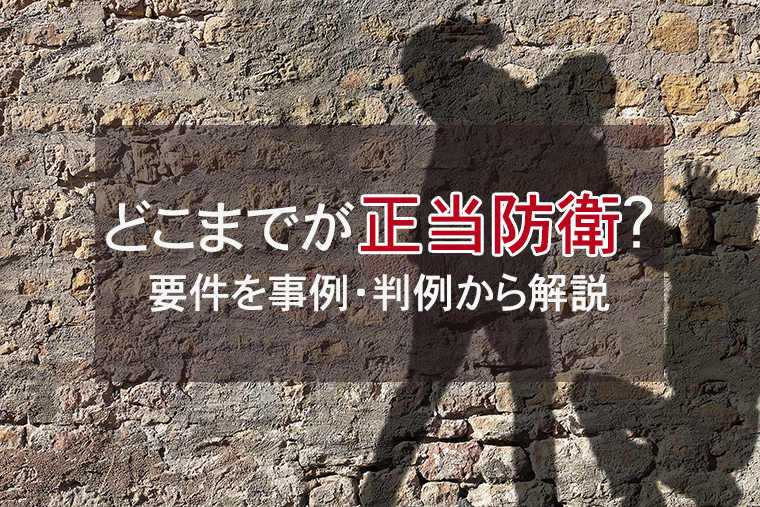
[参考記事]
どこまでが正当防衛か?要件を事例・判例から解説
1.過剰防衛とは
過剰防衛とは、防衛の程度を超えた行為をいいます。
刑法36条2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
「防衛の程度を超えた」(36条2項)とは、急迫不正の侵害に対して防衛の意思で反撃行為をしたが、その行為が「やむを得ずにした」とは認められない場合、すなわち、防衛の相当性の要件を欠くことをいいます。
過剰防衛は正当防衛の要件を満たさないので違法性は阻却されず、犯罪が成立しますが、情状によって、刑の減軽又は免除を受けることができます。
必ず減軽・免除されるというのではなく、裁判官の裁量によってこのような扱いを受けることも可能と、いうことです。
【緊急避難という防衛もある】
なお、「緊急避難」は処罰されません(37条1項)。
正当防衛や過剰防衛は、違法な侵害に対して反撃する「正対不正」の関係にある行為であるのに対し、緊急避難は、第三者の正当な利益を犠牲にするものであって、「正対正」の関係にある点において本質的な差異があります。
「カルネアデスの板」の話(古代ギリシャの哲人カルネアデスが挙げた、船が難破して海中に投げ出された者が1人を支える浮力しかない板から他人を突き落として助かることが許されるかという例)は、このような緊急避難の特徴を端的に示すものです。
2.質的な過剰と量的な過剰
過剰防衛には、素手による攻撃に対して刃物で反撃して死亡させるような「質的な過剰」があります。
判例には、下駄で打ちかかってきた相手を匕首で刺し殺した行為を過剰防衛としたものがあります(大判昭8・6・21大刑集12・834)。
一方、反撃によって相手の侵害が終了したにもかかわらず、なお反撃を続ける「量的な過剰」もあります。
量的な過剰については、途中で急迫不正の侵害は存在しなくなっているので、これを過剰防衛として刑の減免を適用できるかどうかが問題となります。
判例では、最判昭34.2.5(刑集13・1・1)が、被告人が防衛行為に出た後、既に侵害態勢が崩れて横倒しになった被害者に対して、更なる追撃行為に出た結果、被害者を死亡させた事案に関し、「被告人の本件一連の行為」が全体として過剰防衛に該当すると判断しています。
ポイントは、最初の反撃行為と、不正の侵害が終了した後の反撃行為を、全体として一体の行為と評価できるか否かです。
一体の行為と評価できれば、「全体として防衛行為ではあるが過剰なもの」として過剰防衛を適用し、刑の減免が可能となります。
逆に一体の行為と評価できなければ、不正の侵害が終了した後の反撃行為は、「そもそも防衛行為ですらないもの」なので、過剰防衛は適用できず、刑の減免は認められません。
判例では、2つの行為が、時間的・場所的に密接し、ひとつの意思に貫かれている(意思の連続性がある)場合でなければ、一体の行為とは評価できないとしたものがあります(最判平20.6.25・刑集62・6・1859)。
3.まとめ
以上が、「過剰防衛」についての解説です。
刑事事件には思わぬところで巻き込まれてしまうものです。
正当防衛のつもりで行動しても、それが過剰防衛と見なされ逮捕されてしまうことがあるかもしれません。過剰防衛が成立するか否か等は、厳密な法的判定が必要であり、法律の専門家でなくては、その見極め、見通しがつきません。
過剰防衛行為をしてしまった方は、お早めに刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。