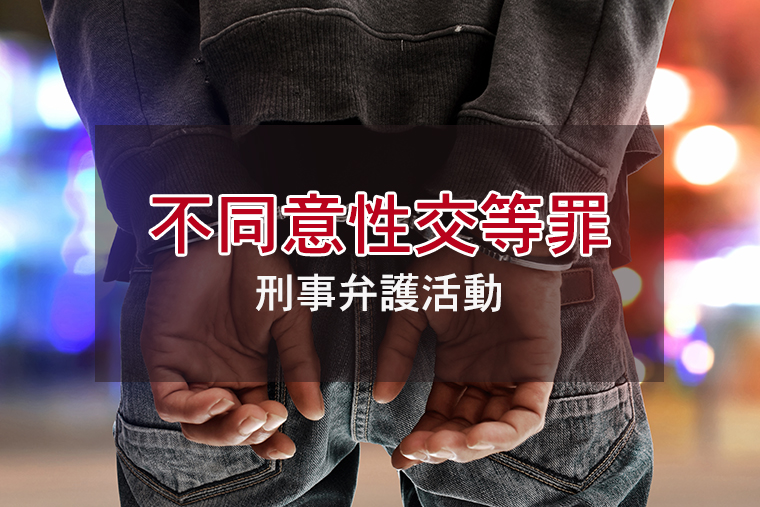合意の上の性行為で訴えられた!不同意性交等罪で逮捕される可能性

2023年の刑法改正により、従来の強制性交等罪は「不同意性交等罪」へと変わり、性的同意の概念が大きく見直されました。
同意があったと思っていても、相手が「同意していなかった」と主張すれば、刑事事件に発展する可能性があります。
本記事では、「お互い合意のもとで性行為をしたはずなのに、被害届を出されてしまった」「合意の上で性行為をしたと思っていたのに、強姦(レイプ)で訴えると言われてしまった」という方に向けて、不同意性交等罪の成立要件と、どのようなケースで逮捕されるリスクがあるのか、そして万が一訴えられた場合の対処法について解説します。
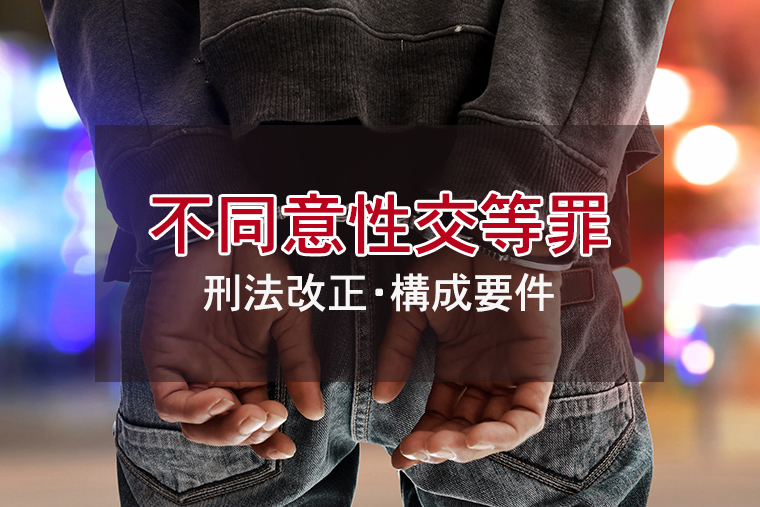
[参考記事]
不同意性交等罪とは?|刑法改正による変更点と構成要件
1.不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の成立要件
2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」は「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」へと名称が変更されました。
この改正の最大のポイントは、「暴行・脅迫」という要件が撤廃され、相手の「同意しない意思」を形成・表明・全うすることが困難な状態での性行為が処罰対象となったことです。
「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」について、両罪に共通する重要な要件が、以下の8つの類型です。
- 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けた
- 心身や身体の障害を生じさせること又はそれがある
- アルコールもしくは薬物を摂取させること又はそれらの影響がある
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にある
- 不意打ちなど、同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること、又はその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがある
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮している
これらの状態にある相手に対して行為を行った場合、たとえ明確な拒絶がなくても「不同意」として犯罪が成立する可能性があります。
(1) 不同意性交等罪
不同意性交等罪は、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で、「性交、肛門性交、口腔性交、膣または肛門に身体の一部または物を挿入する行為であってわいせつなもの」を行った場合に成立します。16歳未満の者に対して行った場合は、仮に相手方の合意があったとしても不同意性交等罪が成立します。
法定刑は5年以上の拘禁刑と非常に重く、未遂も処罰対象となります。
(2) 不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で、わいせつな行為を行った場合に成立します。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。
「わいせつな行為」とは、性交等には至らないものの、相手の性的自由を侵害する行為全般を指します。具体的には、身体の性的部位(乳房や陰部)への接触、キスの強要、衣服を脱がせる行為、自分以外の者と性交させる行為などが該当します。不同意性交等罪と同様に、16歳未満の者は合意があっても処罰対象となり、未遂も処罰されます。
2.性行為への同意の有無はどう判断するか
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪において最も重要かつ難しいのが、「同意があったかどうか」の判断です。
改正刑法では「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」という基準が設けられましたが、実際の事件では当事者間の認識にズレが生じることが少なくありません。
(1) そもそも「同意」とは何か?
性行為における「同意」とは、単に「拒絶しなかったこと」や「黙っていたこと」を意味するのではありません。
法的には、相手が「自由な意思に基づいて性行為を受け入れる意思表示をした」ことが同意の本質です。
つまり、以下のような状況では同意があったとは認められません。
- 「嫌だ」と言わなかった
- 抵抗をしなかった
- 恐怖や圧力により仕方なく応じた
- 酩酊状態や睡眠中など、判断能力が低下していた
- 避妊すると言いながらしなかった、わいせつな行為ではないと言い聞かせたなど、重要な事実について誤解させた
反対に、以下のような事情がある場合、同意があったと認められる可能性が高まります。
- 行為前に言葉や文章などによる明示的な同意の意思表示があった
- 行為後も良好な関係が継続していた
- 性行為について肯定的な内容のメッセージのやり取りがあった
(2) 刑事裁判における同意・合意の判断
実際の刑事裁判では、以下のような要素を総合的に考慮して同意の有無が判断されます。
- 当時の被害者の様子(酩酊の程度、意識状態、身体的反応)
- 同意を確認する行動の有無
- 行為前後のメッセージやSNSのやり取り
- 目撃証言や防犯カメラの映像
- 医学的証拠(傷害の有無、血中アルコール濃度など)
- 被害者の供述内容の一貫性と具体性
- 被害申告に至った経緯
- 被害者が虚偽申告をする動機があるかどうか など
ただし、これらがあっても、相手が後から「実は同意していなかった」と主張した場合、捜査機関による取調べや裁判を受ける可能性はあります。
特に、以下のような状況では「相手も同意していたはず」という思い込みが発生しやすく、結果的に刑事事件へと発展するリスクがあります。
- 飲酒後の性行為:相手がどの程度酩酊していたかが争点になります。「一緒に飲んでいた」だけでは同意の証明にはなりません。
- 恋愛関係・既婚関係:交際中や夫婦間であっても、相手が拒否する権利は当然あり、同意のない性行為は犯罪となります。
仮に過去に同意があったとしても、その時々で同意は必要です。
同意の有無が不明確な場合は、性行為を控えるという慎重な判断も求められます。
3.不同意性交等罪などで被害届を出された場合の対処法
万が一、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪で被害届を出された場合、適切な初動が事件の行方を大きく左右します。
逮捕・起訴を回避し、社会生活への影響を最小限に抑えるためには、法的に正しい対処が不可欠です。
まず、被害届が出されたことを知った時点で、直ちに刑事事件に精通した弁護士に相談することが最優先です。警察からの呼び出しや任意の事情聴取があった場合でも、弁護士の助言なしに対応することは避けるべきです。
不用意な発言や対応が、後の捜査や裁判で不利な証拠として使われる可能性があります。特に取り調べでは、捜査官の誘導や圧力により事実と異なる供述をしてしまうリスクがあります。
弁護士を通じて対応することで、法的に適切な主張を行い、不当な取り調べから身を守ることができます。
(1) 相手方の同意があったことを主張する
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪では、実際に相手の同意があった場合、それを客観的な証拠とともに主張することが重要です。
同意を裏付ける証拠の例としては、以下の通りです。
- メッセージやSNSのやり取り:行為の前後に相手が性行為に同意していたことを示すメッセージや、親密な関係を示すやり取り
- 行為後の行動:性行為の後も良好な関係が続いていたことを示す証拠(デートの記録、連絡の頻度など)
- 相手の状態:相手が酩酊していなかった、意識が明瞭だったことを示す証拠(店の防犯カメラ映像、一緒にいた友人の証言など)
これらの証拠を適切に収集・整理し、捜査機関や裁判所に提出することで、同意があったことを主張します。
ただし、証拠の収集にあたって相手への直接接触は厳禁です。証拠隠滅や口裏合わせを疑われ逮捕のリスクが高まるだけでなく、被害者が恐怖心を抱けば脅迫罪などの別の犯罪に問われる可能性もあります。
(2) 犯罪の故意がなかったことを主張する
仮に相手が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にあったとしても、行為者がそのことを認識していなかった場合には、犯罪の故意が認められず、不同意性交等罪は成立しません。
刑法では、犯罪が成立するためには「故意」、すなわち犯罪事実を認識していることが必要です。
不同意性交等罪においては、相手方が段落1で述べた8つの類型のいずれかの状態にあることを被疑者が認識していたことが故意の内容となります。
故意がなかったと主張できる場合としては、以下のようなものが考えられます。
- 普通に会話ができていた、歩行も正常だったなど、相手が酩酊しているようには到底見えなかった
- 相手から「いいよ」という発言があったり、自ら行為に応じる態度を取ったりと、積極的な意思表示があった
このような事情がある場合、「相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることを認識していなかった」と主張することで、故意の不存在を立証していきます。
ただし、このような故意の主張は慎重に行う必要があります。客観的な状況から「不同意だと認識していたはずだ」と判断されるケースも多いため、説得力のある主張をするためには弁護士による綿密な事実関係の整理が不可欠です。
(3) 被害者との示談の重要性
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は非親告罪であるため、被害者との示談が成立しても、それだけで必ず不起訴となるわけではありません。
しかし、示談の成立は、起訴・不起訴の判断や量刑に極めて大きな影響を与えます。
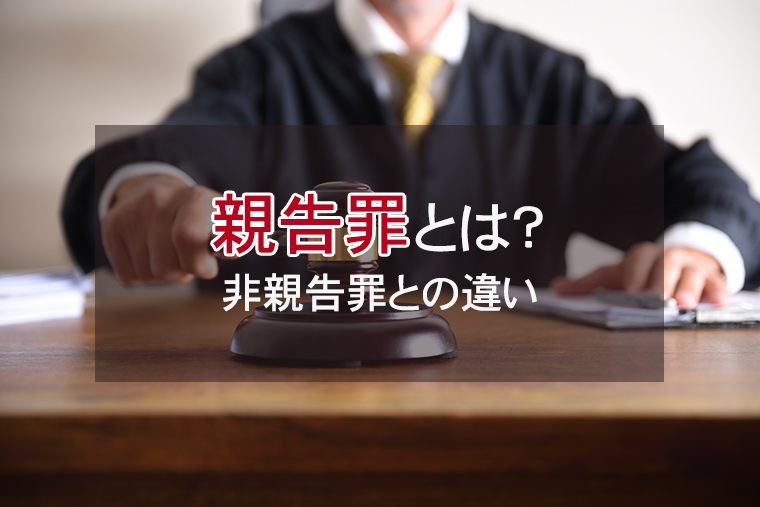
[参考記事]
親告罪とは?非親告罪との違いをわかりやすく解説
被害者との示談がもたらすメリットとしては、まず、不起訴処分の可能性が高まることが第一です。
検察官は起訴・不起訴を判断する際、被害者の処罰感情や事件の悪質性を考慮します。示談が成立し、被害者が「許す」という意思を示した場合、検察官は「起訴する必要性が低い」と判断しやすくなります。特に初犯で、軽く触れるのみのわいせつ行為にとどまるなど被害が比較的軽微なケースでは、示談成立により不起訴となる可能性が大幅に高まります。
仮に起訴されてしまった場合でも、示談成立は重要な情状事由となります。裁判では「被害者との間で示談が成立し、被害弁償がなされている」ことが有利に考慮され、執行猶予や減軽判決につながる可能性が高まります。
さらに、早期の示談成立が叶えば、逮捕・勾留を回避できる可能性も高まります。
早期に示談交渉を開始し、被害者との和解が見込める状況を示すことで、「逃亡や証拠隠滅のおそれが低い」と判断され、逮捕や勾留を回避できる場合があります。
示談書に「民事上の請求権を放棄する」旨の条項を盛り込むことで、後日の民事訴訟を防ぐこともできます。
なお、示談交渉は必ず弁護士を通じて行う必要があります。被疑者本人や家族が直接相手に連絡することは、脅迫や口止めと受け取られるリスクがあること、被害者の恐怖心を増大させる可能性があることなどから絶対に避けるべきです。
弁護士が間に入ることで、冷静かつ適切な条件で示談交渉を進めることができます。示談金の額、謝罪の方法、示談書の内容など、法的に適切な形で合意を形成していきますのでご安心ください。
示談金は事案の内容(被害の程度、常習性、被疑者側の資力など)によって大きく変動します。被害者側が高額な示談金を求める場合もあり、交渉には専門的な知識と経験が必要です。
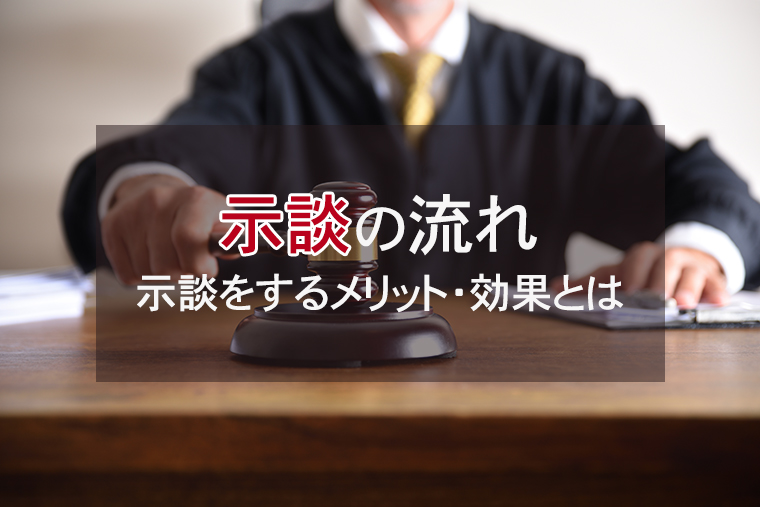
[参考記事]
刑事事件の示談の流れ|示談をするメリット・効果とは?
被害者が示談を拒否する場合や、そもそも連絡が取れない場合もあります。そのような場合でも、「贖罪寄付」という方法があります。
これは、被害者に代わって公益団体などに寄付を行うことで、反省の意思を示すものです。示談成立ほどの効果はありませんが、情状面で一定の考慮を受けられる可能性があります。
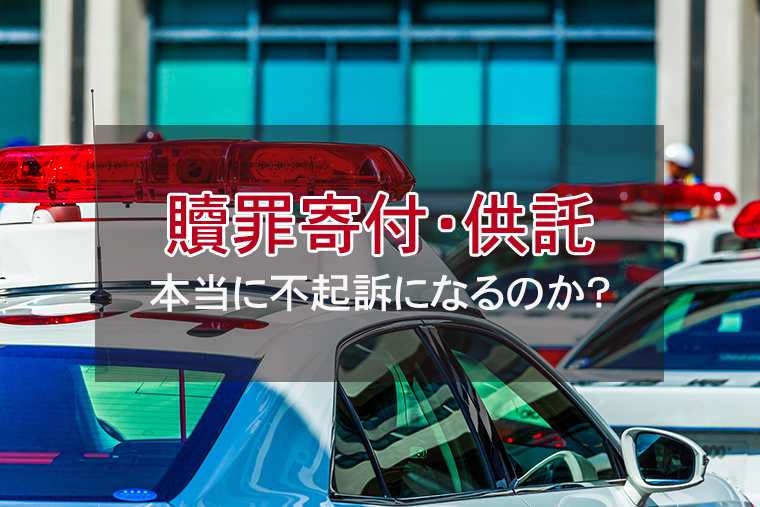
[参考記事]
贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?
4.まとめ
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は、2023年の刑法改正により、従来よりも広い範囲で性犯罪が処罰されるようになりました。「合意があった」と思っていても、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあれば犯罪が成立する可能性があります。
特に、不同意性交等罪は非常に重い犯罪であり、有罪となれば実刑判決の可能性も高い犯罪です。だからこそ、早期の段階から弁護士に依頼し、適切な弁護活動と示談交渉を進めることが、事件解決への最善の道となります。
万が一被害届を出された場合は、直ちに弁護士に相談し、同意があったことや故意がなかったことを適切に主張していきましょう。弁護士は、示談交渉などを通じて不起訴や量刑軽減を全力で目指していきます。
お困りの方は、泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。