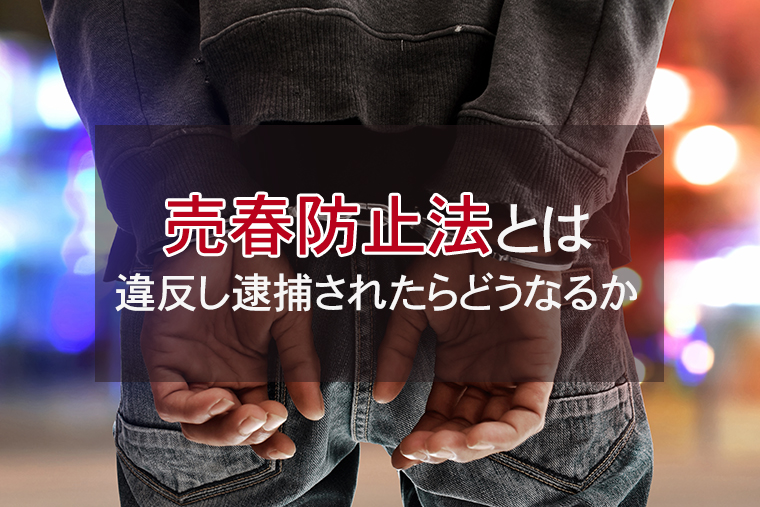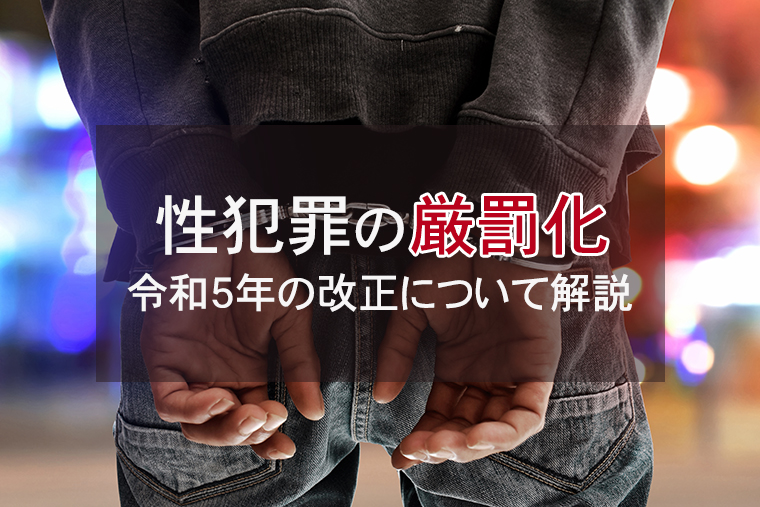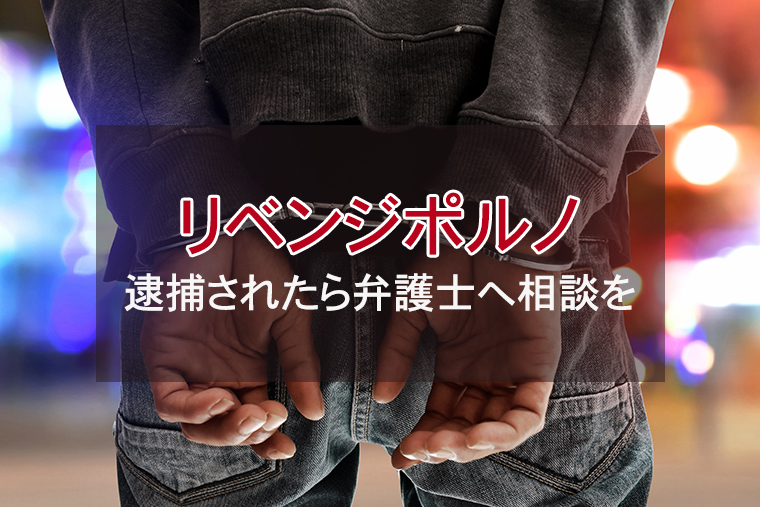性犯罪のDNA鑑定(検査)で犯人は特定できる?
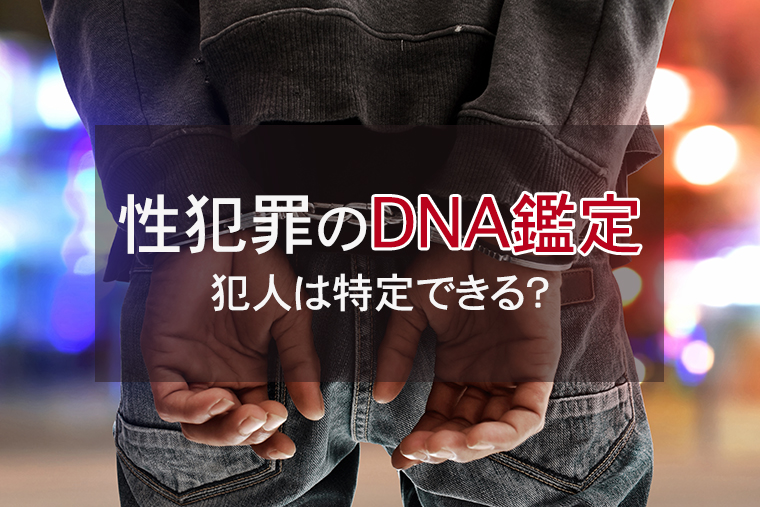
今日、DNA鑑定が犯罪捜査の手段として用いられるケースが数多く存在します。
警察庁の発表によれば、令和元年から令和5年におけるDNA鑑定実施件数は、毎年26万件を超えています。
※警察庁「令和6年警察白書」85頁、図表2-74「DNA型鑑定実施件数の推移(令和元年~令和5年)」による
DNA鑑定は、性犯罪の犯人を特定するためにも活用されます。
痴漢行為、不同意わいせつ行為(刑法176条)、不同意性交等行為(刑法177条)といった性犯罪が行われると、被害者の衣服・身体表面・身体内部や犯行現場に、犯人の精液・唾液・毛髪・皮膚片などが付着したり残されたりすることが多く、これを資料として犯人のDNAが明らかにされるのです。
では、このような性犯罪のDNA鑑定はどのように行われるのでしょう?
また、その鑑定結果には、どの程度の正確さ・精度があるのでしょうか?
1.DNA鑑定とは?
(1) DNAについて
DNAとは、「デオキシリボ核酸」の略称です。
人の細胞の中にある核(細胞核)には、父親と母親から半分ずつ受け継いだ、23対(合計46本)の染色体があります。染色体は、DNAとその他のタンパク質でできています。
DNAは「生命の設計図」と呼ばれ、私たちの身体を形づくるタンパク質を合成する設計図の役割があり、その設計図の情報(遺伝情報)を親から子へ伝える役割も担います。
DNAは4種類の化学物質からなる高分子で、この化学物質の配列は「二重らせん」構造となっています。
この化学物質の並び方(配列)には、個人差のある部分があります。並び方(配列)自体の違いや、特定の並び方(配列)が反復する回数などの違いです。
この違いを「DNA多型」と呼びます。「多型」とは、多様性という意味です。
(2) DNA鑑定の内容
DNA鑑定(DNA型鑑定)は、このDNA多型に着目して、個人を識別する方法です。
なお、「DNA鑑定」と「DNA型鑑定」は、同じ意味と理解して差し支えありません。
現在、日本の犯罪捜査で主に用いられている鑑定方法を「STR判定」と呼び、これは「鎖長多型」のひとつです。
「STR」とは、「Short(短い)Tandem(縦並び)Repeat(繰り返し)」の略であり、2ないし5種類の化学物質(塩基)の配列の繰り返しという比較的短い反復単位に着目して、その出現回数から、DNA型の同一性を鑑定する方法です。
2.性犯罪におけるDNA鑑定
(1) DNA鑑定の対象となる資料
性犯罪の捜査におけるDNA鑑定は、通常、捜査機関が、被害者や被疑者の身体や衣類、犯行現場などに残された生体資料を採取するところからスタートします。
DNA鑑定の対象となる主な生体資料は、血液、精液、膣液、唾液、毛根鞘の付いた毛髪、皮膚、筋、骨、歯、爪、臓器等の組織片です(※警視庁刑事局長「DNA型鑑定の運用に関する指針について(通達)」警察庁丙鑑発第14号・丙刑企発第34号)。
たとえば、被害者の衣服に精液が付着していたケースで、すでに嫌疑のある被疑者が判明しているならば、その被疑者のDNA多型と、採取された精液のDNA多型が一致するか否かが鑑定されます。
(2) DNA型のデータベースについて
未だ被疑者が不明の場合でも、DNA型のデータベースに登録されたDNA型情報との一致が調べられます。
たとえば、過去に同種の前科でDNA型を鑑定され、登録された者が犯人であれば、その者の犯行とわかります。
現在では、国家公安委員会の規則(※DNA型記録取扱規則)に基づき、犯罪現場に遺留された資料のDNA型を記録する「遺留DNA型記録」と、被疑者の身体から採取された資料のDNA型を記録する「被疑者DNA型記録」を登録するDNA型記録検索システムが運用されています。
3.DNA鑑定の流れ
現在、日本の犯罪捜査で主に用いられている「STR判定」の作業手順は、①DNAの抽出、②PCR増幅、③PCR産物の分離、④STR型の分析という4つのステップを踏みます。
(1) DNAの抽出
鑑定の対象となる資料からDNAを抽出します。
これには化学物質(フェノール・クロロフォルム)を溶剤として用いる抽出方法や、特殊な繊維フィルターを用いてDNAを分離する「DNA精製キット」を利用する方法があります。
(2) PCR法によるDNAの増幅
多くの場合、遺留品などから採取できる素材はわずかであり、抽出できるDNAも微量で、分析するに十分な量ではありません。
そこで、PCR法(ポリメラーゼ連鎖反応法)という技術を使って、DNAを増幅します。ひらたく言えば、分析に必要なDNAのコピーを大量に作成するのです。
現在では、微量のDNA抽出液から、全自動でDNAを増幅できる卓上装置が利用されています。
(3) PCR法での産物を分離
PCR法で増やされたDNAの高分子を分離し、分析します。これには電気泳動という技術が用いられます。
高分子は、特定の液体中において電気的な力の作用を受けると、その分子量に応じた距離だけ移動するという特性を持ちます。これを利用してDNAの分子を分析に適した形に分離します。
(4) STR型の分析
電気泳動で分離されたDNAを、STR型検出器(レーザー検出を用いた自動分析装置)を使って分析します。そのデータは、「エレクトロフェログラム」というチャート形式で出力され、これを読解することによりDNA型を判断します。
鑑定にかかる時間は、捜査機関の鑑定部門の忙しさにもよりますが、一般的には殺人などの緊急を要する重大事件では優先的に処理され、数日から1週間程度で鑑定の結果が出ます。
それ以外の場合は、数ヶ月単位を要する場合もあります。
4.DNA鑑定はどこまで信頼できる?
(1) DNA鑑定の信頼性
たとえば「STR判定」では、採取されたDNAについて、その15カ所について化学物質(塩基)の繰り返しを分析します。すべてが一致した場合には、同じ型の他人が存在する確率は「10の20乗」分の1だとされています(*1)。「10の20乗」分の1とは、「1兆の1億倍」分の1です。
また、STR判定において、日本人にもっとも出現頻度の高い配列反復の組み合わせでも、15カ所全てが偶然に一致する他人が存在する確率は、約4兆7千億人に1人でしかないという説明もされています(*2、*3)。
*1:押田茂實・岡部保男・泉澤章編著「Q&A見てわかるDNA型鑑定(第2版)」(現代人文社・91頁)
*2:梅津和夫「DNA鑑定・犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで」講談社・81頁
*3:警察庁「平成20年警察白書」(「特集:変革を続ける刑事警察」、第3節「変革を続ける刑事警察」、「2 科学技術の活用」)
(2) 安易にDNA型鑑定の結果を信頼できない理由
以上の数字からは、DNA型鑑定による個人の識別能力は絶対的であり、100%信頼できると思われそうです。
しかし、安易にDNA型鑑定の結果を盲信することはできません。その理由は次のとおりです。
- DNA型鑑定は、その鑑定において狙った特定の部位DNA型を検査するものに過ぎず、すべてのDNA型を検査するわけではないので、他の鑑定方法で検査をすれば不一致となる可能性を常に100%排除できるわけではありません。
- 資料の採取時・保管時・鑑定実施時のそれぞれの段階で、別人の唾液・血液・細胞片などが混入し、資料が汚染され、正しい結果が出ない危険性もあります。
- 鑑定に用いられた検査キットや検査機器が適正・正常でない場合や、鑑定人の鑑定技量・経験が不足している場合なども、鑑定結果の正確性が疑われます。
- 万一にもあってはならないことですが、鑑定結果が意図的に改ざんされる危険もあります。
【実際に捜査機関のDNA鑑定の信用性が否定された裁判例】(福岡高裁平成7年6月30日判決・みどり荘事件・判例時報1543号181頁)
強姦致死・殺人罪の事案です。被告人が任意提出した毛髪のDNA型と、犯行現場に残された毛髪のDNA型が一致したとして、一審は、無期懲役の有罪判決としました。しかし、控訴審の弁護団は、鑑定に使われたのは、被告人が任意提出した毛髪とは異なる、別人の毛髪(被害者または被害者の姉の毛髪)である可能性があることや、鑑定手法の妥当性に問題があることなどを主張し、鑑定人尋問において、当該鑑定が破綻していることを明らかにし、無罪判決を得ました。
5.実際にDNA鑑定で犯人が特定され、逮捕・有罪となった事例
最近、DNA鑑定によって性犯罪の犯人が判明し、有罪判決を受けた事案がありますので、ご紹介します。
2015年9月、佐賀市で一人暮らしだった女子学生が、見知らぬ男に背後から押し倒され、顔を殴られ、胸をもまれる被害に遭いました。被害者が叫び声をあげたところ、男は逃走しました。現場には、男のスポーツタオルとスリッパが残されました。
被害を警察に届けましたが、犯人は不明のままでした。
しかし、事件から9年を経た2024年、佐賀県警がスポーツタオルとスリッパを再鑑定したところ、男のDNA型が検出でき、県内の男性A(36歳)が逮捕され、強姦傷害罪等で起訴されました。そして、2025年6月、佐賀地裁により懲役4年の実刑判決が下されました。
※RKB毎日放送・2025年6月19日記事「『死んでしまう、あの時感じた恐怖、全く忘れられない』若い男性の姿に動悸 おびえる毎日・・・性被害にあった女性(当時20)その後の人生」
6.DNA鑑定は拒否できない?
捜査機関が被疑者のDNA鑑定を実施する場合には、①被疑者から口腔内細胞の任意提出を受けて資料とする場合と、②裁判所の令状(鑑定処分許可状)を得て、被疑者の血液を採血する場合があります。
被疑者が採血に抵抗する場合は、鑑定処分許可状だけでなく、裁判所の身体検査令状を得る必要があります(※前記の警視庁刑事局長「DNA型鑑定の運用に関する指針について(通達)」警察庁丙鑑発第14号・丙刑企発第34号)。
口腔内細胞の任意提出を求められた場合は、任意処分なので拒否できます。
しかし、裁判所の令状(鑑定処分許可状、身体検査令状)がある場合は、強制処分なので拒否できません。抵抗しても、強制的に押さえつけられて採血されてしまうと考えましょう。
7.刑事事件弁護は弁護士にお任せを
性犯罪の捜査においてDNA鑑定が行われ、被疑者のDNA型と資料のDNA型が一致するとの鑑定結果となっても、常に100%信頼できるものではありません。
身に覚えがないのに性犯罪の嫌疑をかけられ、DNA鑑定で犯人だとされてしまった場合、被疑者本人だけで潔白を明らかにすることは非常に困難です。できるだけ早い段階で、刑事事件に強い弁護士を依頼する必要があります。
弁護人となった弁護士は、その鑑定の正確性を様々な角度から吟味し、その信用性を検討します。たとえば、次のような諸点から冤罪を主張することができるかもしれません。
- 科学的に確立した鑑定方法・鑑定技術によるものか
- 鑑定人の知識・技能は未熟ではなかったか
- 鑑定人の手順、試薬量、抽出・増幅などの時間設定に誤りはないか
- 資料が微量過ぎて反応が不鮮明ではなかったか
- 意図的・作為的な汚染はなかったか
- 検査装置の故障・誤動作はなく、検査キットの試薬に異常はなかったか
- 結果の判定・鑑定書の記載にミスはないか
もっとも、弁護士がDNA鑑定の内容をしっかりと吟味・検討するには、その前提として当該事件の内容・事実関係を十分に把握している必要があります。
したがって、捜査段階のできるだけ早期に弁護士を選任しておくことが肝要です。
刑事事件の被疑者となりお困りの方、刑事弁護の依頼を考えている方は、どうぞお早めに弁護士にご相談ください。