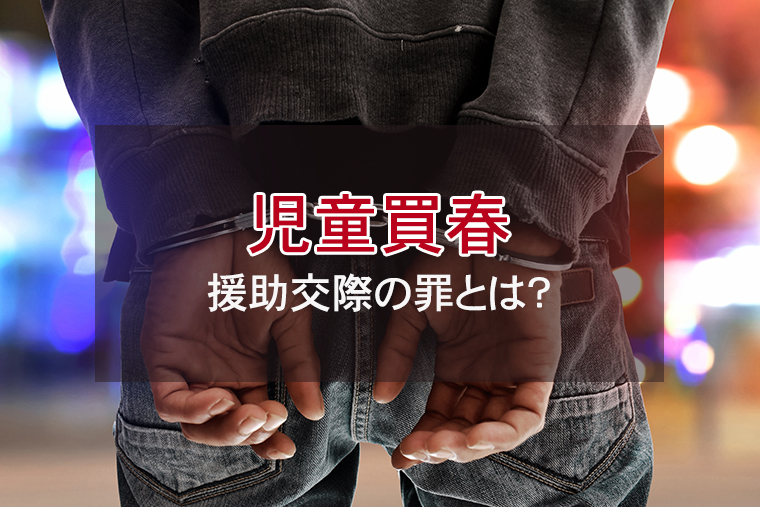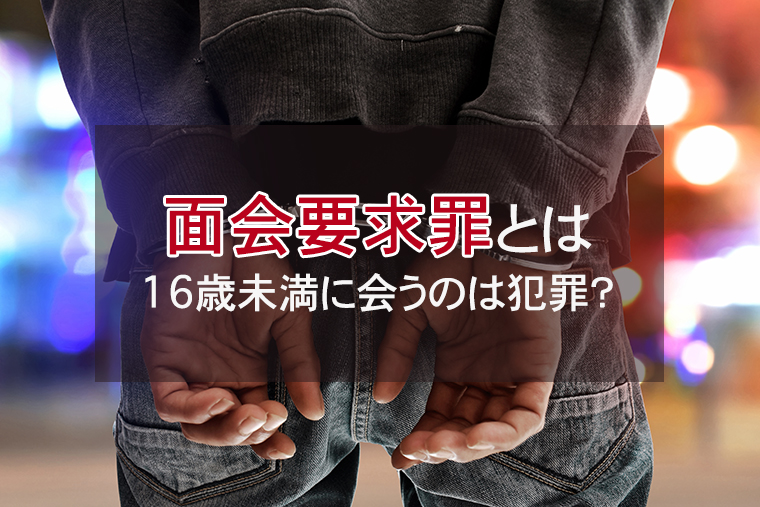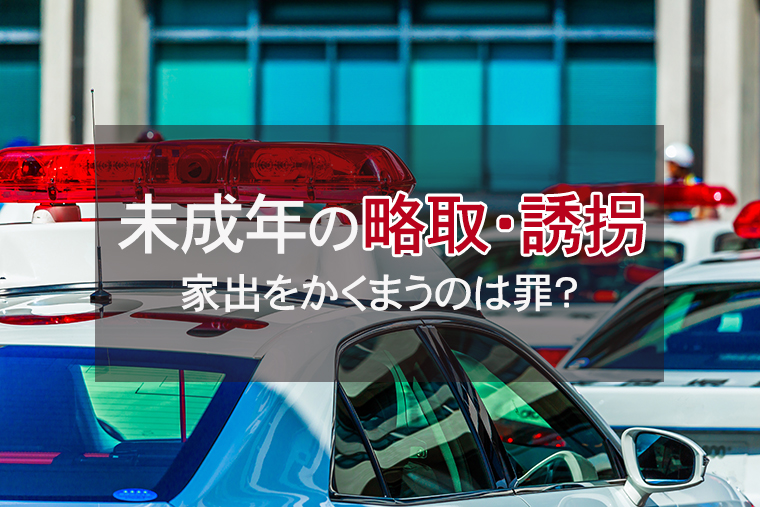児童福祉法違反を解説|児童との性行為で逮捕されてしまったら

18歳未満の児童に対する淫行(性行為)等は、「児童福祉法」「青少年保護育成条例」「児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)」などによって厳しく罰せられます。
もし児童に対する淫行をしてしまったならば、速やかに弁護士に相談をして、重い刑事処分を免れるための弁護活動を受けるべきです。
この記事では、児童をめぐる淫行の規制のうち「児童福祉法違反」に該当する行為の内容と、違反行為をした場合の刑事罰、正しい対応方法などについて解説します。
1.児童福祉法とは?
児童福祉法で定義される「児童」の対象年齢は、男女問わず「満18歳に満たない者」(=18歳未満の者)です。
児童福祉法1条では、すべての「児童」には、以下の福祉を等しく保障される権利がある旨が規定されています。
- 適切に養育されること
- 生活を保障されること
- 愛され、保護されること
- 心身の健やかな成長、発達、自立が図られること
児童は、大人への成長過程にあることから、精神的に未成熟な段階といえます。
そのため、周りの大人が児童を不当に利用したり、判断能力の未熟さに乗じて不快な行為を強いたりすることを規制する必要があるのです。
児童福祉法では、こうした脅威から児童を保護し、健全な成長をサポートすることを目的として、児童の支援に関する各種の制度や、児童に対する禁止行為などに関するルールを定めています。
2.児童福祉法における淫行の罪
(1) 児童福祉法違反に当たる行為
児童福祉法の中でも重要なのが、児童福祉法34条に定められた児童に対する一般的な禁止行為に関する規定です。
これに違反すると、児童福祉法違反として処罰の対象となります。
具体的に、児童に対するどのような行為が禁止されているのかというと、以下の通りです。
- 身体に障害または形態上の異常がある児童を公衆の見せ物にする行為
- 児童にこじきをさせ、または児童を利用してこじきをする行為
- 公衆の娯楽を目的として、15歳に満たない児童に曲芸などをさせる行為
- 満15歳に満たない児童に戸々について、または道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
- 児童に午後10時から午前3時までの間、家・店舗・路上などで物品の販売、配布、展示もしくは拾集または役務の提供を業務としてさせる行為
- 家・店舗・路上などで物品の販売、配布、展示もしくは拾集または役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、キャバクラ、ホストクラブ、ソープランド、店舗型ファッションヘルス、テレフォンクラブなどを営む場所に立ち入らせる行為
- 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
- 児童に淫行をさせる行為
- 児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、そのことを知っているにもかかわらず、児童を引き渡す行為および当該引渡し行為のなされるおそれがあることを知っているにもかかわらず、他人に児童を引き渡す行為
- 成人および児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあっせんする行為
- 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的で、児童を自己の支配下に置く行為
(2) 「児童に淫行をさせる行為」について
上記の児童福祉法違反に当たる行為としてもっとも代表的なものが、「児童に淫行をさせる行為」です。
本来人間には性的自由があり、誰と性的な関係を持つかを自分で自由に決定することができます。
しかし、18歳未満の児童の場合、性的な行為に関するリスクへの理解や判断能力が十分でないことが多いです。そのことに付け込む不当な企みを抱いた大人によって、児童が性的に搾取されてしまうケースも少なくありません。
そこで、児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為を、刑事罰をもって禁止しています。
では、同規定にいう「児童に淫行をさせる行為」は、どのような行為を指すのでしょうか?
まず、「淫行」とは、性行為やそれに類するわいせつ行為(性交類似行為)をいいます(判例:最高裁昭和47年11月28日決定参照)。
上記の定義からすると、性交(性器同士の挿入行為)・肛門性交・口頭性交が「淫行」に該当することは言うまでもありません。
これらに加えて、性的な目的を持って児童の身体に触れる行為や、自慰行為を強制する行為など、直接的な性交に至らない行為についても「淫行」に該当すると考えられます。
そして、児童に淫行を「させる行為」とは、児童に対して事実上の支配力を及ぼして、他者との淫行を強いる行為を意味します。
典型的には、暴行や強迫を用いて児童に他者との淫行を強制した場合が挙げられます。
さらに、直接的な暴行や強迫が行われなかったとしても、児童に対して指導的・上位の立場(学校や塾の教師、先輩など)を利用して、淫行を事実上強制したと評価される場合についても、児童福祉法違反に該当します。
(3) その他の児童に対する淫行の罪との違い
未成年と性行為を行うと、児童福祉法違反以外にも以下のような罰則を受ける可能性があります。
| 青少年保護育成条例違反 | 青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行なった |
|---|---|
| 児童買春の罪 | 金銭・商品などの対価を渡して18歳未満の児童を性的行為をした |
| 売春防止法違反 | 児童の売春をあっせんした、あるいは児童を支配し売春をさせた |
| 不同意性交等罪 | 暴行・脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交(=性交等)をした (相手が16歳未満の場合には、相手方の同意があっても処罰対象) |
| 不同意わいせつ罪 | 暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした (相手が16歳未満の場合には、相手方の同意があっても処罰対象) |
このように、満18歳未満の児童に淫行をする、あるいは児童買春をする行為は、複数の法律・条例によって禁じられています。
仮に児童福祉法違反に当たらないようなケースでも、上記のいずれかの罪が該当する可能性があります。
【児童福祉法と青少年保護育成条例の違い】
児童福祉法は、国が制定した「法律」です。したがって、児童福祉法は日本全国に対して適用されます。
これに対して青少年保護育成条例は、各都道府県などの自治体が独自に制定している「条例」です。したがって、青少年保護育成条例は、その自治体の中で起こった行為に対してのみ適用されるという違いがあります。
青少年保護育成条例では、それぞれの自治体における青少年(児童)保護の方針を反映して、児童福祉法による禁止行為の範囲を拡大しているケースが多くなっています。特に、「青少年とみだらな性交または性交類似行為をする行為」については、児童福祉法の規定とは異なり、青少年が任意に応じた場合であっても、相手方が条例違反・処罰の対象となることに注意が必要です。
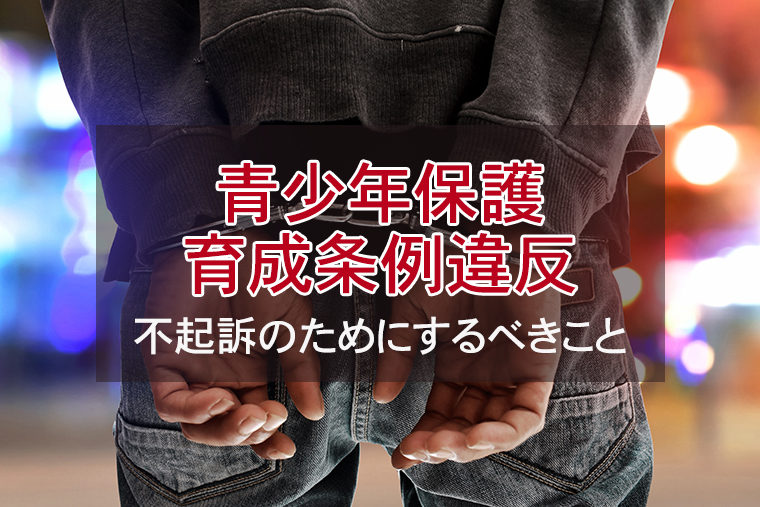
[参考記事]
青少年保護育成条例違反で逮捕された!不起訴のためにするべきこと
3.児童福祉法違反を犯すとどうなる?
児童福祉法違反を犯した場合、加害者に対しては、刑事罰や民事上の損害賠償などのペナルティが課されます。
(1) 児童福祉法違反の罰則を受ける
前述の児童福祉法違反に該当する各行為に設定されている法定刑は、以下のとおりです。
- 児童に淫行をさせる行為(児童淫行罪)
10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科(児童福祉法60条1項) - 上記以外同法34条1項に定める禁止行為
3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科(同条2項)
具体的に科される刑事罰の内容は、行為の悪質性・反省や被害回復(示談)の有無・前科の有無(初犯かどうか)などの情状を考慮して決定されます。
なお、通常の児童福祉法違反の時効は3年ですが、児童淫行罪の時効は7年です。
これらのことからも、児童淫行罪がいかに許し難い行為とされているかが分かります。
(2) 被害児童に対する損害賠償義務を負う
児童に対する淫行、その他の児童福祉法違反に当たる行為は、民法上の不法行為に該当する可能性もあります(民法709条)。
この場合、被害児童や家族が被った精神的損害(慰謝料)などを賠償しなければなりません。当然ながら、これは罰金や拘禁刑とは別のものです。
賠償すべき金額はケースバイケースで決定されますが、数百万円規模の高額に及ぶケースもあるので注意が必要です。
4. 児童福祉法における示談の重要性
淫行などの児童福祉法違反に当たる行為をしてしまった場合、逮捕・勾留の後に起訴される可能性が高いといえます。
刑事事件の被疑者を起訴するかどうかは、犯罪事実の内容や、被疑者に関する情状など、あらゆる事情を総合的に考慮したうえで、検察官の判断により決定されます。
児童福祉法違反は、様態によっては重い処分を科せられる可能性があります。特に実刑判決を回避するためには、被害児童の家族(親)と示談をすることが大切です。
検察官が起訴・不起訴の判断をする際、その時点で被害児童の家族(親)との示談・和解が成立していれば、被害者の精神的損害がある程度回復されたものとして、被疑者にとって有利な情状として働きます。
もちろん、示談をしたからといって必ず不起訴になるわけではなく、犯情などが重く考慮されて起訴に至るケースはあります。
特に児童買春では、示談が成立していても実刑となるケースは少なくありません。
しかし、少しでも不起訴の可能性を高めるためには、弁護士を通じて被害家族との間で早期に示談・和解を成立させることが大切です。
また、起訴・不起訴を判断する段階だけではなく、刑事裁判における判決内容を決定する際にも、示談・和解が成立しているかどうかは重要な考慮要素となります。
たとえば、示談が成立することによって、
- 本来拘禁刑相当であるところ、罰金刑に減軽される
- 拘禁年数が短くなる
- 本来実刑判決相当であるところ、執行猶予が付く
など、被告人に対して寛大な判決が下される可能性が高まります。
もし児童福祉法違反で起訴されてしまった場合でも、その後弁護士を通じて、被害児童の家族(親)と根気強く示談交渉を行えば、重い刑事処分判決を回避することに繋がります。
ただし、被害児童の親が抱いている怒りの感情が強く、示談交渉が難航するケースも多々存在します。
そのため、加害者本人が直接示談交渉を行うと、かえって被害者側の態度を強硬化させることにもなりかねません。
この点、弁護士は第三者的な立場から、被害者側に感情を抑えていただけるように配慮しつつ、示談交渉の早期妥結に向けて尽力いたします。
ご自身の児童福祉法違反に当たる行為に思い当たる場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
5.まとめ|児童福祉法違反は弁護士へ
このように、児童福祉法では、18歳未満の児童の健全な成長を支える観点から、淫行をはじめとして児童に対するさまざまな不適切行為が刑事罰をもって禁止されています。
もし児童福祉法違反を犯し、捜査機関による捜査が行われている場合には、すぐに刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
被害児童家族との示談交渉や、その他の依頼者にとって有利な情状をアピールする活動によって、依頼者を一日も早く刑事手続きから解放できるように尽力いたします。