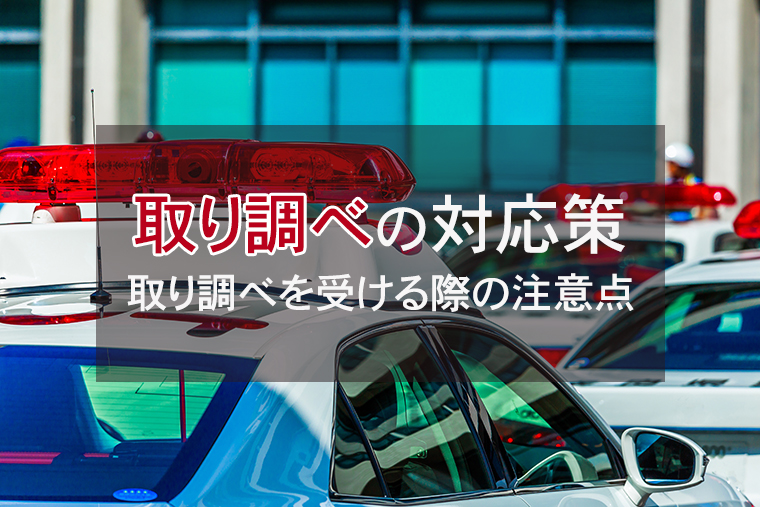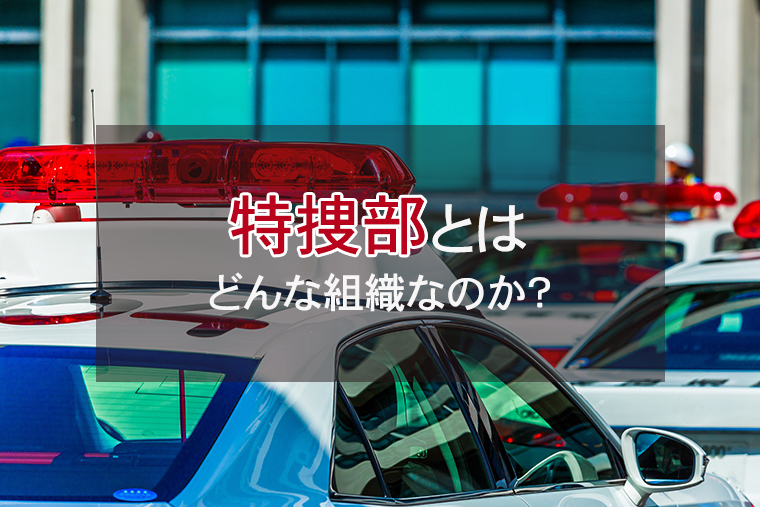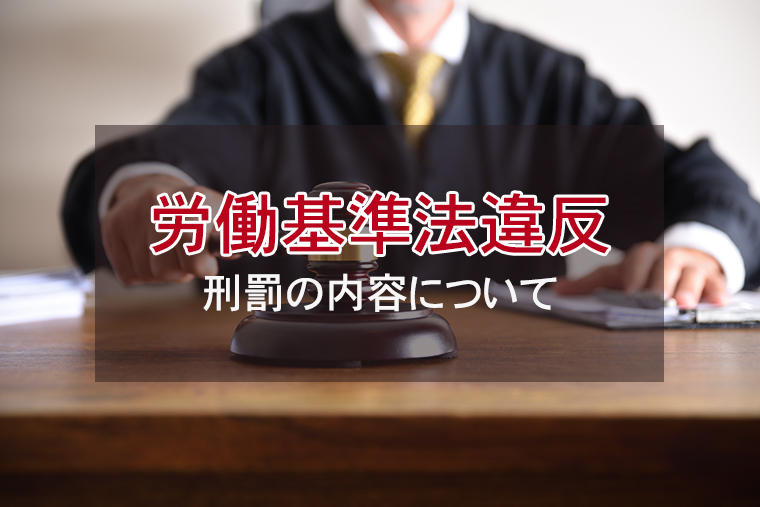検察庁について|どのような組織なのか?
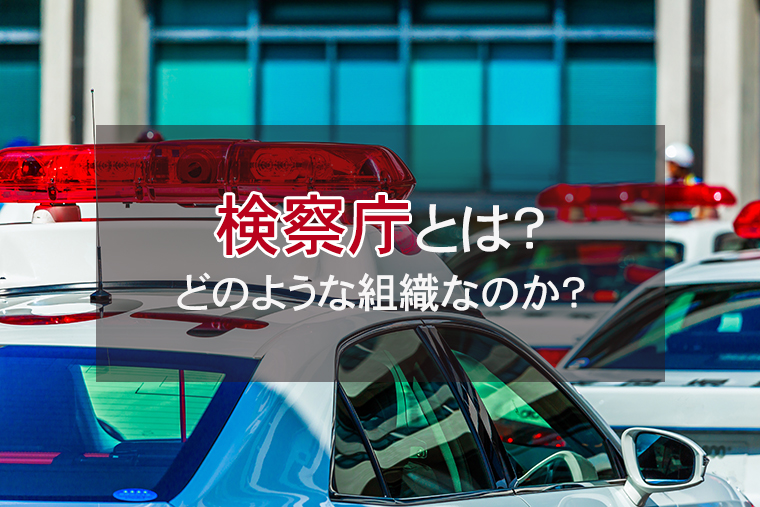
犯罪の嫌疑をかけられ、被疑者として警察署での取り調べを受けたものの、幸い逮捕はされず家に帰ることができたとします。
しかし、ほっとしていても、しばらく経ってから「検察庁」から出頭を要請する連絡を受ける場合があります。
刑事事件の捜査の多くは、警察署での取り調べで終わるわけではありません。
最終的な事件処理は検察庁の検察官が行うので、そのために呼び出されるのです。
この記事では、普段は馴染みのない「検察庁」の組織と、その役割を解説します。検察庁への出頭を要請された場合の対応方法については別記事で詳しくご説明しますので、こちらも是非ご覧ください。
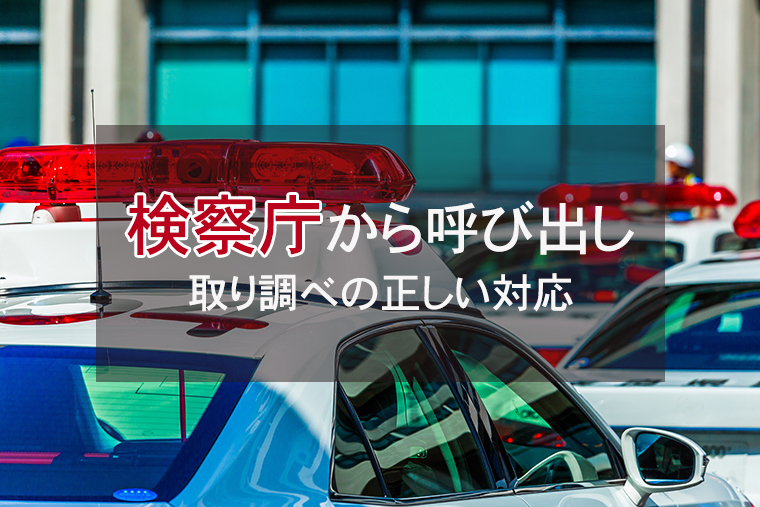
[参考記事]
検察庁からの呼び出し!取り調べを受ける場合の正しい対応
1.検察庁とはどのようなところ?
検察庁は、法務省に所属する行政機関です。
検察官の仕事のメインとなるのは、犯罪の捜査を行い、刑事事件の公訴を行って裁判所に法の適用を請求し、裁判所が下した裁判(判決)の執行を監督することです。
検察は、主に刑事裁判の遂行を担う役割があるため、「最高裁判所」「高等裁判所」「地方裁判所」「簡易裁判所」という裁判所の組織に対応して、検察庁も「最高検察庁」「高等検察庁」「地方検察庁」「区検察庁」という4種類が置かれています。
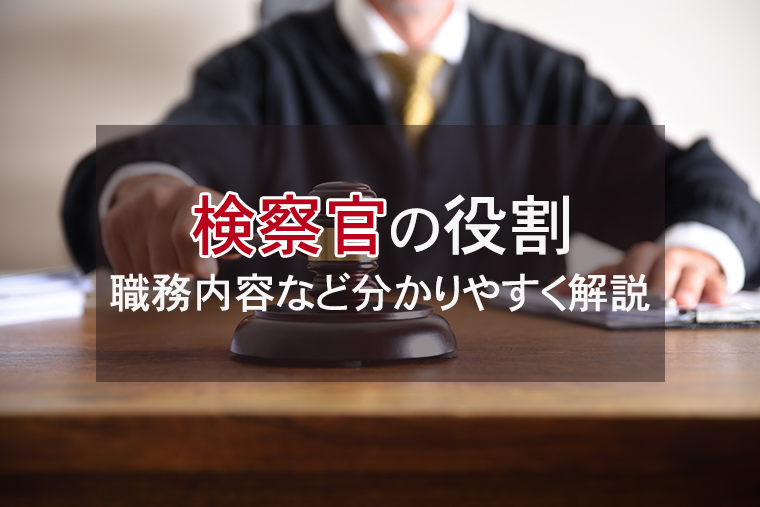
[参考記事]
検察官(検事)の役割・職務内容を分かりやすく解説
2. 区検察庁とは?
(1) 区検察庁の概要
区検察庁、通称「区検」は、全国438か所にあります。
区検察庁には、検事・副検事が置かれ、罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている刑など、比較的軽微な犯罪の捜査・公判・裁判執行の指揮監督などの仕事を行います。
検事または副検事は、その庁の職員を指揮監督します。複数の検事が属する区検察庁、検事と副検事の属する区検察庁の場合は、その庁の職員を指揮監督する「上席検察官」が置かれます。
(2) 首都圏の区検察庁
【東京都】
①東京区検察庁、②八丈島区検察庁、③伊豆大島区検察庁、④新島区検察庁、⑤立川区検察庁、⑥八王子区検察庁、⑦武蔵野区検察庁、⑧青梅区検察庁、⑨町田区検察庁【神奈川県】
①横浜区検察庁、②神奈川区検察庁、③保土ケ谷区検察庁、④鎌倉区検察庁、⑤藤沢区検察庁、⑥相模原区検察庁、⑦川崎区検察庁、⑧横須賀区検察庁、⑨小田原区検察庁、⑩平塚区検察庁、⑪厚木区検察庁【埼玉県】
①さいたま区検察庁、②越谷区検察庁、③熊谷区検察庁、④川越区検察庁、⑤秩父区検察庁、⑥川口区検察庁、⑦大宮区検察庁、⑧久喜区検察庁、⑨飯能区検察庁、⑩所沢区検察庁、⑪本庄区検察庁【千葉県】
①千葉区検察庁、②佐倉区検察庁、③千葉一宮区検察庁、④松戸区検察庁、⑤木更津区検察庁、⑥館山区検察庁、⑦八日市場区検察庁、⑧佐原区検察庁、⑨市川区検察庁、⑩銚子区検察庁、⑪東金区検察庁
3.地方検察庁とは?
(1) 地方検察庁の概要
地方検察庁、通称「地検」は、地方裁判所および家庭裁判所に対応する検察庁で、全国50か所(各都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路)にあります。
さらに、地方裁判所および家庭裁判所の各支部に対応して、203支部が設けられています。
地方検察庁の検事は、内乱罪などの国家的重大犯罪や、罰金以下の刑にあたる軽い犯罪を除いた、ほとんどの刑事事件の捜査・公判・裁判執行の職務を担います。
各地方検察庁の長が、「検事正」です。その地方検察庁と管内の区検察庁の職員を指揮監督する役割です。検事正を補佐するのが、「次席検事」です。
(2) 首都圏の地方検察庁
- 東京地方検察庁(立川支部)
- 横浜地方検察庁(川崎支部・相模原支部・横須賀支部・小田原支部)
- さいたま地方検察庁(越谷支部・川越支部・熊谷支部・秩父支部)
- 千葉地方検察庁(佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部)
(3) 地方検察庁内部の組織
各地方検察庁の内部には、担当部署が置かれています。
たとえば、規模の大きい東京地方検察庁には、捜査・公判にかかわる部署として、①刑事部、②交通部、③公安部、④特別捜査部、⑤公判部があります。大阪地方検察庁、名古屋地方検察庁も同様です。
参考:東京地方検察庁機構|大阪地検の概要について|名古屋地方検察庁の機構
4.高等検察庁とは?
(1) 高等検察庁の概要
高等検察庁、通称「高検」は、高等裁判所に対応する検察庁です。全国8カ所にあり、また、高等裁判所の支部に対応した支部が6か所あります。
高等検察庁は主に控訴された刑事事件の捜査・公判・裁判執行などを担います。
各高等検察庁の長が、「検事長」です。その高等検察庁と、その管内の地方検察庁・区検察庁の職員を指揮監督する役割です。検事長を補佐するのが「次席検事」です。
(2) 全国の高等検察庁
- 札幌高等検察庁
- 仙台高等検察庁(秋田支部)
- 東京高等検察庁
- 名古屋高等検察庁(金沢支部)
- 大阪高等検察庁
- 広島高等検察庁(岡山支部・松江支部)
- 高松高等検察庁
- 福岡高等検察庁(宮崎支部・那覇支部)
5.最高検察庁とは?
最高検察庁は、最高裁判所に対応する検察庁で、東京1か所のみです。
最高裁判所は、各高等裁判所の扱った裁判で、主に上告された事件を担当しますから、最高検察庁は、これに対する捜査・公判・裁判執行の指揮監督などの仕事を担います。
最高検察庁の長が、「検事総長」であり、全国の検察庁の職員を指揮監督します(検察庁法7条1項)。最高検察庁で検事総長を補佐するのが、「次長検事」です。検事総長が事故などの際に職務を代行する役割もあります。
6.検察庁に呼び出しをされた場合はどうする?
刑事事件を起こし、警察での取り調べ(事情聴取)を終えて帰され「在宅事件」となっている場合、突然検察庁から呼び出されることがあります。
検察に呼び出される理由としては、捜査上の取り調べのため、あるいは取り調べの最終判断のためというケースが多いでしょう。
「厳しく追求されるのでは」「刑罰が待っているのでは」などと不安に思うのは当然のことですが、検察庁からの呼び出しを拒否・無視したりすると、例え在宅捜査になっていても、被疑者に「逃亡のおそれ」又は「罪証隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕されることもあり得ます。
逮捕されたケースでは、最大で3日間にわたり身体拘束され、警察での取り調べを受けます。その後も勾留された場合、最大で20日間身体拘束が続きます。
そして、最終的には起訴され、刑事裁判となってしまうおそれすらあります。
以下のコラムでは、検察庁から被疑者に呼び出しがきた場合に拒否した場合はどうなるのか、呼び出しがあった場合の正しい対応方法(弁護士へ相談するメリット)等を解説しています。
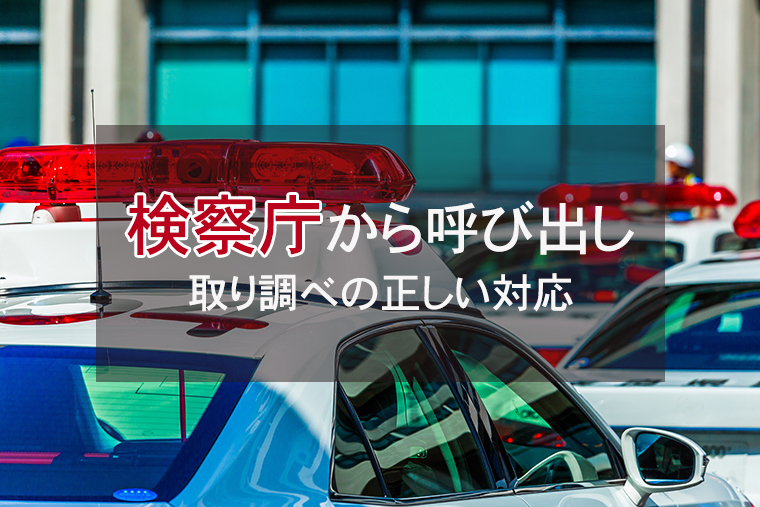
[参考記事]
検察庁からの呼び出し!取り調べを受ける場合の正しい対応
7.まとめ
検察官は、刑事事件の被疑者を起訴するか否かを決める重大な権限を持っており、その権限を行使するために、被疑者を検察庁へ呼び出して取り調べを行います。
したがって、その呼び出しを無視することは、自ら不利な状況を作り出すことになりかねません。
呼び出しを受けたならば、直ちに弁護士に相談をし、対応策のアドバイスを受けることがお勧めです。