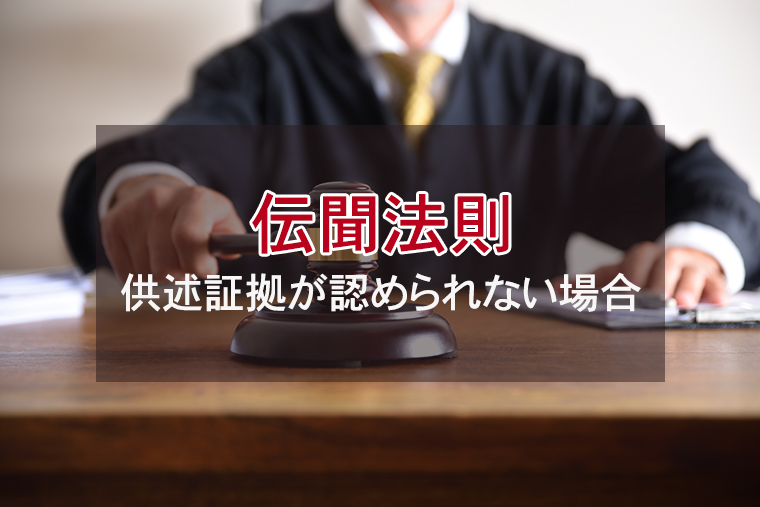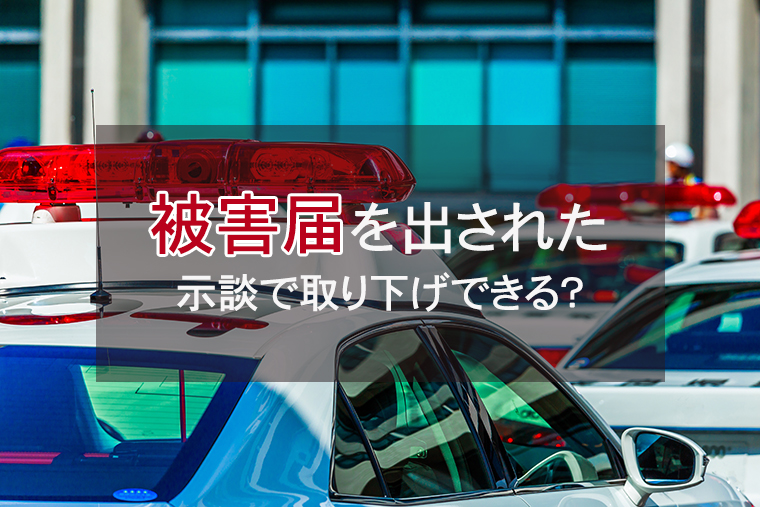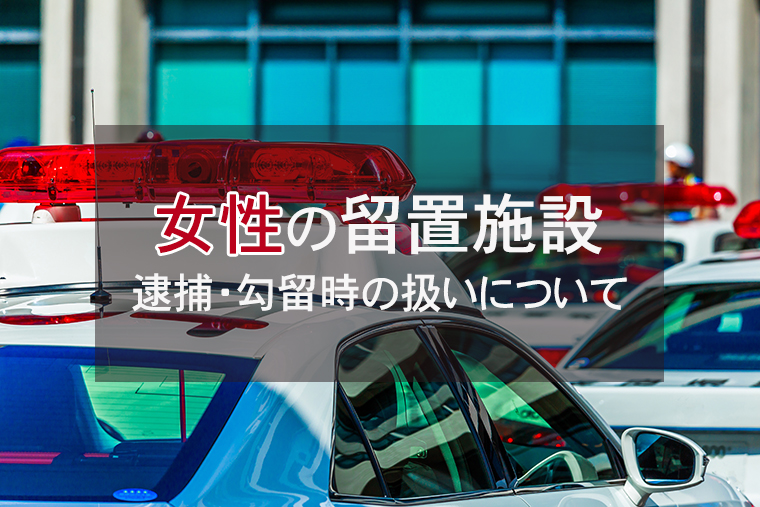公判請求とは?裁判の流れ、略式請求との違いを解説
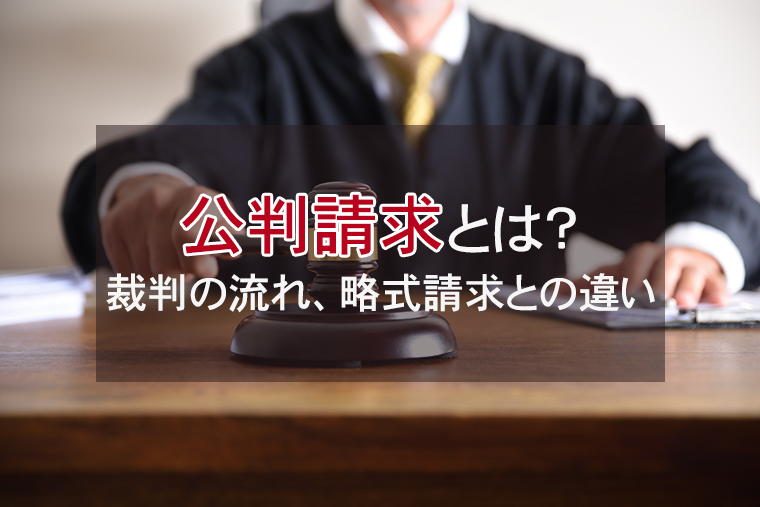
検察官は、刑事事件で必要な捜査を遂げた後、公訴を提起して「公判請求」をする場合があります。これにより、いわゆる「刑事裁判」が開かれることになります。
軽微な刑事事件であり、かつ初犯ならば、公判請求までされることは稀と言えます。
しかし、重大事件や再犯の場合、被害者との示談が成立しなかった場合には、公判請求となる可能性も0ではありません。
今回は、刑事事件の被疑者となってしまった方やその家族に向けて、「公判請求」について解説していきます。
1.公判請求とは?
(1) 公判請求は「起訴処分」の一つ
検察官は、捜査の上で被疑者に犯罪の嫌疑があり、かつ訴訟条件を満たしている場合であっても、必ず起訴するわけではありません。
諸事情(被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況、初犯であるかどうかなど)を総合考慮の上、起訴するか否かを決定します。
起訴されるか否かは、被疑者にとって重大な分岐点となります。起訴されて有罪判決が出れば、懲役刑・罰金刑等に処され、前科もついてしまうからです。
起訴となった場合、検察官は「①略式請求」か「②公判請求」を選択することになります(他に「③即決裁判請求」もありますが、実務上ほとんど利用されません)。
このように、「公判請求」というのは、検察官が行う起訴処分の中の一つです。
略式請求になるか公判請求になるかも、被疑者にとっては重大な分岐点といえます。
というのも、公判請求は略式命令請求に比べて被告人の負担が大きくなるからです。
(2) 略式請求と公判請求の違い
①略式請求
略式請求(略式起訴・略式裁判)とは、起訴されても公判は開かれず、簡素な起訴手続きで被告人の罪責を罰金または科料にとどまって判断するものです。
略式請求が可能なのは、「簡易裁判所の管轄に属し、100万円以下の罰金又は科料を科し得る事件」であり、かつ、「略式手続によることについて被疑者に異議がないこと」が前提になります。
つまり、略式命令は採用されるのは、比較的軽微な事件ということになります。
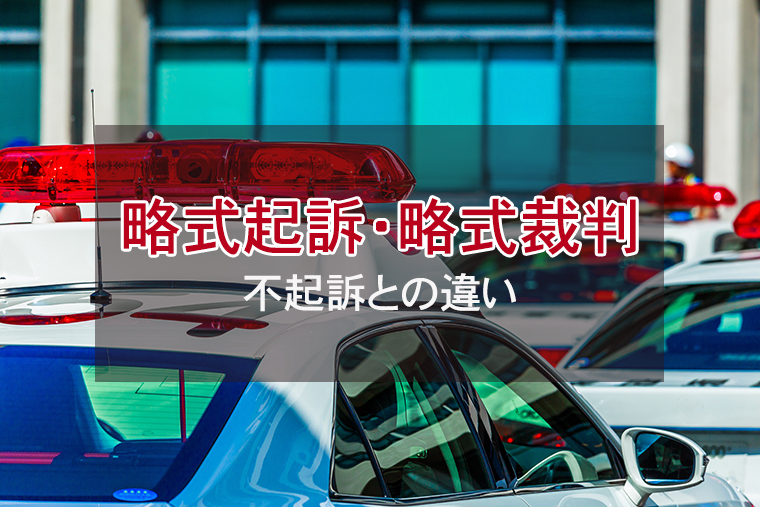
[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
②公判請求
これに対して、公判請求では、裁判所の公開の法廷(公判)での証拠調べ等を経た後、有罪判決となれば罰金刑にとどまらず拘禁刑が科されるおそれが生じます(もっとも、情状により執行猶予が見込まれることもあります)。
証拠調べ手続きでは、念入りな準備が必要となります。また、正式な裁判ということで、仮に情状からいって執行猶予判決が十分見込まれる場合であっても、その厳格な雰囲気から被告人にかかるプレッシャーは軽いものではありません。
よって、被疑者としては、何とかして公判請求を回避して、略式命令請求や不起訴を獲得することが重要となります。
2.公判(刑事裁判)の流れ
刑事裁判の公判では、以下の手続きの流れを経て結審します。
(1) 冒頭手続
冒頭手続は、公判の開始時に行われる手続きです。
起訴状朗読
検察官が、被告人に対する訴因(罪名と事実)を読み上げます。
起訴状朗読によって、審理の対象・犯罪事実(公訴事実)が明確になります。
黙秘権の告知
裁判長が、被告人に黙秘権を告知します。
被告人は、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」(刑訴法311条1項)とされており、自己に不利益な供述か否かにかかわらず、一切の供述を拒否することが認められています。
人定質問
被告人の氏名、生年月日、住所等の確認をします。
これにより、起訴状に記載された被告人が本人であることを確認し、人違いを防ぐ目的です。
罪状認否
検察官は、起訴事実について間違いがないかを被告人に質問します。被告人は、「間違いありません」「争います」等の認否を行えます。
(2) 冒頭陳述
検察官と弁護人が、それぞれの主張の概要を述べます。
裁判官や裁判員が事件の全体像を把握するために行われる手続きと言えます。
検察官は、起訴事実をどう立証するかの計画を説明します。
弁護人は、争点や弁護方針を明らかにします。この陳述は任意ですが、特に否認事件の場合、公訴事実のどの点について争うのか、という点について陳述します。
(3) 証拠調べ手続
証拠書類・証拠物
証拠調べ手続は公判の中核をなす段階で、事件の真相を明らかにするために様々な証拠を取り調べます。
主な手続きは、証拠書類・証拠物の取調べです。
供述調書、鑑定書、現場写真、凶器等の確認をしますが、ここで証拠の信用性や証明力について双方が争うことも多いです。
証拠調べ手続きは、まず事前に提出された証拠の採否を決定し、通常は検察官立証→弁護人立証の順で進行します。
弁護人は、検察官の証拠に対して、「同意する」「不同意」「異議がある」「必要なし」といった意見を述べます。つまり、犯罪の立証責任は検察官側にあるということです。
次に、弁護人が証拠請求します。証拠請求の内容については、以下のようなものがあります(自白事件の場合)。
- 被害者から取り付けた示談書
- 本人の謝罪文
- 身元引受人になった家族などの上申書、情状証言
証人尋問
証人の出廷・人定確認後に宣誓を行い、主尋問、反対尋問、再主尋問の順で実施されます。
主尋問
証人を申請した側が最初に行う尋問です。つまり、検察側証人であれば検察官が、弁護側証人であれば弁護人が実施します。
証人から自分側に有利な事実を引き出すことが目的となります。主尋問では、「はい」「いいえ」で答えられるような質問ではなく、証人に自由に語らせる必要があります。例えば「被告人を見かけましたか」ではなく「その時何を見ましたか」という形で尋問します。
反対尋問
主尋問に続いて、証人を申請しなかった側が行う尋問です。主尋問で述べられた証言の信用性を弾劾し、自分に有利な事実を引き出すことが目的です。
反対尋問では、具体的で限定的な質問により証人を追及できます。証人の記憶違いや矛盾点を指摘し、「あなたは○○と述べましたが、実際は××だったのではありませんか」といった形で証言の信用性を争います。また、証人の人格や能力に関する事項についても一定の範囲で質問が可能です。
再主尋問
反対尋問で出てきた事項について、証人を申請した側が補充的に行う尋問です。反対尋問で攻撃された証言の信用性を回復させることが主な目的となります。
再主尋問の範囲は反対尋問で取り上げられた事項に限定されており、新たな事実について尋問することはできません。反対尋問で指摘された矛盾について合理的な説明を求めたり、誤解を解く機会を証人に与えたりします。
この後、必要に応じて再反対尋問、さらに裁判官による補充尋問が行われることもあります。
こうして、証人の証言の信用性が多角的に検討され、事実認定の精度が高められる仕組みとなっています。
(4) 被告人質問
すべての立証が終了すると、裁判長が証拠調べの完了を確認して終了を宣言し、次の被告人質問段階へ移行します。
まずは弁護人から、被告人に有利な事情を引き出します。否認事件であれば、無罪立証にかかわる内容について質問します。
一方、自白事件であれば、被告人に対して被害者に対する謝罪、犯行の動機や背景事情、反省状況などを中心に質問していきます。
弁護人からの被告質問が終わると、検察官は検察官の主張を補強する質問を行います。
そして、最後に、争点の解明に必要な事項について、裁判官が被告人に対して質問します。
被告人質問において、被告人の人格や反省の程度なども明らかにされます。
(5) 検察官の論告求刑
被告人質問が終わると、検察官は証拠に基づいて「どの程度の刑を求めるか」を明らかにします(求刑)。
求刑とともに、検察官は犯行の悪質性、被告人の身上、前科前歴、被害状況、反省状況などから、量刑の妥当性などを詳細に論じます。
論告とは、証拠を総合して被告人の有罪性を論証することです。
(6) 弁護人の最終弁論
弁護人が事件や被告人について意見を述べます。弁護人による最後の弁護活動とも言える段階です。
犯罪事実について否認をするのなら、無罪を求める陳述を行います。
自白事件ならば、有罪を前提として、被告人の反省状況、被害回復、社会復帰の可能性等を主張し、刑の軽減を求める弁護を行います。
(7) 被告人の意見陳述
被告人自身が最後に意見を述べる機会です。
よく見られるのは、以下のような陳述です。
- 反省の弁、被害者・遺族への謝罪
- 今後の生活に対する決意表明
- 刑の軽減を求める嘆願
これらについては短時間で簡潔に述べることが基本ですので、事前に弁護人と打ち合わせをするというケースも多いでしょう。
被告人が意見を述べれば、それをもって刑事裁判の審理が終了となります(=結審)。
(8) 判決言い渡し
裁判官(裁判員裁判では裁判員と裁判官の合議)による最終判断として、判決とその理由が述べられます。
言い渡される判決の内容は以下のとおりです。
- 主文:有罪・無罪、刑の種類と重さの宣告
- 理由:認定した事実、適用法条、量刑の理由
- 執行猶予の有無や控訴権についての説明
- 被害者等への配慮事項がある場合はその説明
控訴しないのであれば、これで刑事裁判が終了となります。
なお、公判期日の回数は、事件の内容や争い方によって異なりますが、公訴事実(起訴された犯罪事実)に争いのない事件であれば1回の期日で結審することもあります。
ちなみに、一定の刑事事件について、通常の刑事裁判の手続を簡略化して迅速に事件を終結させるための手続として、「即決裁判手続」が導入されています。
即決裁判手続の対象となる事件は、事案明白かつ軽微であること、証拠調べの速やかな終了の見込があることなどの事情を考慮して相当と認められるものに限定されています。
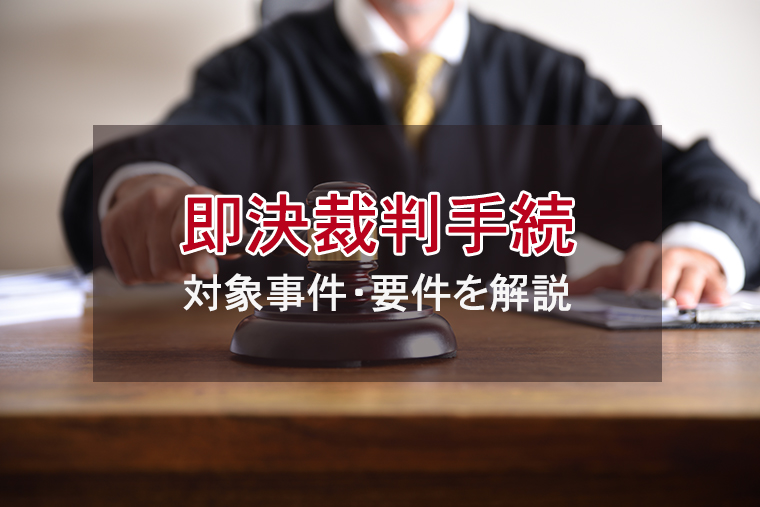
[参考記事]
即決裁判手続とは?対象事件・要件を解説
3.公判請求を避けるための弁護活動
刑事事件弁護で重要なのは、「不起訴処分を目指すこと」「起訴は避けられない事案であっても、公判請求を避けること」です。
起訴されなければ、刑罰が科されることも前科がつくこともありません。
また、公判請求を避けることができれば、被疑者は起訴となっても裁判を受けることなく罰金の納付のみですぐに釈放されます。
不起訴のためには、被害者との示談を成立させる、あるいは贖罪寄付などを行うのが最も効果的です。
示談ができなかったり、事件内容が悪質であったりするなど、起訴される公算が高い場合には、作成した意見書を検察官に提出するなど略式命令請求(罰金)にとどめるように検察官を説得することになります。
それでも公判請求となってしまった場合は、できる限り軽い刑罰や、執行猶予の獲得を目指して準備することになります。
万が一公判請求となってしまった際には、被告人質問の準備や、情状証人の準備などのために、ご依頼者様やそのご家族にもご協力いただくことになります。
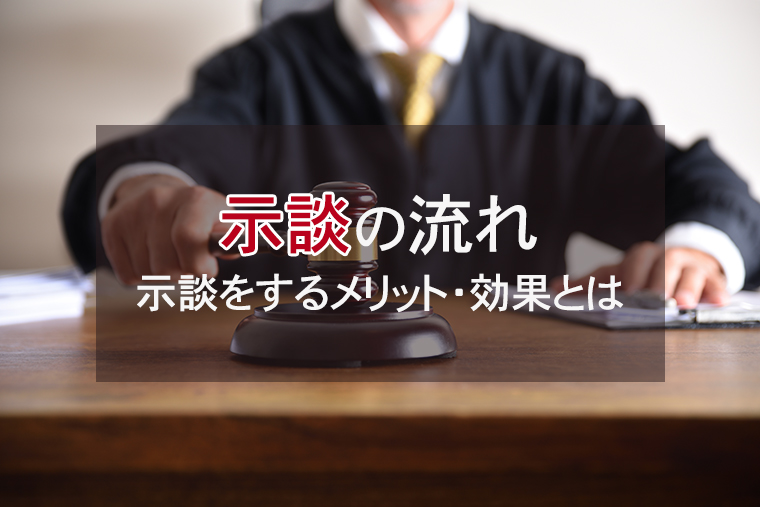
[参考記事]
刑事事件の示談の流れ|示談をするメリット・効果とは?
4.刑事事件は泉総合法律事務所へ
「公判請求を回避するために何をすべきか」「公判において軽い刑を求めるには何をしたらいいか」は個別の事件によって異なります。刑事事件でお悩みの方は、一度刑事弁護経験豊富で公判の弁護にも強い泉総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件はスピード勝負です。初回相談は無料となっておりますので、お悩みの方は是非お早めにご相談ください。