当て逃げの罪|罰金・前科を防ぐ対策方法

「交通事故を起こしてしまい、その場から立ち去ってしまった」という事例は少なくありません。
「事故の瞬間は軽微だと思った」「相手に怪我はないようだった」「後で連絡しようと思っていた」など、様々な理由があったとしても、現場を離れてしまった事実は変わりません。
パニック状態・恐怖心から咄嗟に取ってしまったものでも、このような行動は「当て逃げ」となり、刑事事件として逮捕・起訴される可能性があります。
当て逃げをしてしまった場合、加害者は刑事責任と民事責任の両方に問われます。道路交通法違反による罰則と被害者への損害賠償だけでなく、点数の加点という行政責任も負うことになります。当て逃げは想像以上に深刻な結果を招く可能性があるのです。
しかし、実際に逃げてしまった後でも、適切な対応を取ることで最善の解決策を見つけることは可能です。
「今から自首すべきか」「弁護士に相談した方がいいのか」「どのような処罰を受けるのか」といった不安や疑問を抱えながら一人で悩み続けるのではなく、一度弁護士へご相談ください。
本コラムでは、当て逃げをしてしまった加害者が取るべき行動、弁護士に依頼するメリット、そして今後の見通しについて解説します。
1.当て逃げの罪
当て逃げは、車を運転していて、他の車両・道路上の構造物・施設などの物を損傷したにも関わらず、そのまま走り去ってしまう行為です。
仮にすぐに戻ってくるつもりだったとしても、一度事故現場から走り去ってしまえばそれは当て逃げとなります。
(1) 危険防止措置義務違反と報告義務違反
当て逃げは道路交通法違反となるのは冒頭の通りです。
具体的には、まず「危険防止措置義務違反」(道路交通法72条1項前段)です。
危険防止措置義務の内容は、事故によって起きる道路上の危険を防止するため必要な措置を講じることです。たとえば、事故車両が道路上に停止して他の車両の通行に支障をきたしている場合、車両を安全な場所に移動させる、ハザードランプや発炎筒で後続車に危険を知らせる、といった行為がこれに該当します。
また、道路に散乱した積荷やガラス片などを除去する、漏れた燃料やオイルによる二次被害を防ぐための措置を取ることなども含まれます。
現場の状況によっては、事故車両や散乱物が他の車両や歩行者にとって重大な危険要因となる可能性があります。これを放置して立ち去る行為は、交通の安全を軽視した悪質な行為として評価されるのです。
他にも、当て逃げは第72条第1項後段に定められた「報告義務違反」にもなります。
運転者は、警察官に事故の発生日時、場所、死傷者数、損壊した物及びその損壊の程度、事故に関係する車両の積載物などを「直ちに」報告する義務があります。この報告を怠って現場を離れる行為が当て逃げの中核となる違反行為なのです。
道路交通法72条1項
【前段:救護義務・危険防止措置義務】
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。【後段:報告義務】
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
実際の処罰では、事故の状況や危険の程度によって量刑が左右されます。
特に、高速道路での事故や交通量の多い幹線道路での事故では、危険防止措置を怠ったことによる社会的影響が大きいとして、より重い処分が科される傾向があります。
また、危険防止措置を怠ったことで二次的な事故が発生した場合、当初の事故加害者がその責任も負うことになる場合があります。
当て逃げの対象となる「物」の定義
当て逃げ事件においての「物」の定義は、一般的な理解よりもかなり広範囲に及んでいます。
まず、道路上に存在する他の車両です。自動車、バイク、自転車はもちろんのこと、停車中であっても走行中であっても接触すれば当て逃げの対象となります。
また、ガードレール、信号機、道路標識、街灯、電柱、橋梁など、道路に設置されている各種の構造物や公共物への衝突も、ぶつかったならば報告義務が発生します。
さらに、道路沿いにある建物や工作物も対象となり得ます。店舗の壁面、住宅の塀、自動販売機、看板なども「物」として認定される可能性があります。
特に注意すべきは、私有地内の構造物であっても、道路に面している場合や道路交通に関連する場所にある場合は当て逃げの対象となることです。
野生動物との衝突は一般的に当て逃げの対象外とされることが多いですが、飼い犬や飼い猫などのペット、牛や馬などの家畜については「物」として扱われる場合があります。
なお、損傷の程度や価値の大小は関係ありません。軽微な接触、擦り傷程度の損傷であっても、相手方の「物」に損害を与えた事実があれば報告義務が発生します。
また、自分の車両に損傷がない場合でも、相手方に損害を与えていれば当て逃げに該当する可能性があるため、事故の認識があった場合はしっかりと報告をすることが求められます。

[参考記事]
交通違反でも刑事事件に!道路交通法違反の種類と罰則
(2) 刑罰(懲役・罰金)
では、実際に当て逃げをすると、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?
危険防止措置義務違反の罰則
1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑報告義務違反の罰則
3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金刑
両罪が成立する場合、より重い危険防止措置義務違反「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑」で罰せられます。
なお、これとは別に、当て逃げを起こした場合は運転免許の点数(違反点数)も加点され、30日間の免許停止処分となります。
2.当て逃げの加害者になってしまったら
とは言うものの、一度逃げてしまった場合にはどのように対応するのが良いのでしょうか?
(1) 警察に届け出る
時間が経過していても、当て逃げを警察に届け出ることには重要なメリットがあります。
最大のメリットは、「自首」として刑事処分の軽減がのぞめます。
刑法では、自首した場合に刑の減軽が認められており、裁判官や検察官は自首の事実を量刑において有利に考慮します。事故後すぐに届け出なかった事情があったとしても、自ら進んで事実を申告する姿勢は、強い反省の意思を示すものとして評価されるのです。
当て逃げは、現場に残った車両の痕跡や防犯カメラ、ドライブレコーダーなどの記録から、後日警察から呼び出しを受ける可能性が高いです。
後日逮捕や任意同行に恐れて日々を過ごすならば、自ら警察に届け出ることには大きなメリットがあると言えます。
さらに、早期に届け出ることで証拠の保全や事実関係の整理が適切に行われるという利点もあります。
時間が経過するほど、事故現場の状況や車両の損傷状況などの証拠が失われ、事実関係が曖昧になってしまいます。しかし、自ら届け出て捜査に協力することで、事故の態様・過失の程度を正確に把握できますので、不当に大きな責任を負うことを避ける(適正な責任の範囲を明確にする)ことができるのです。
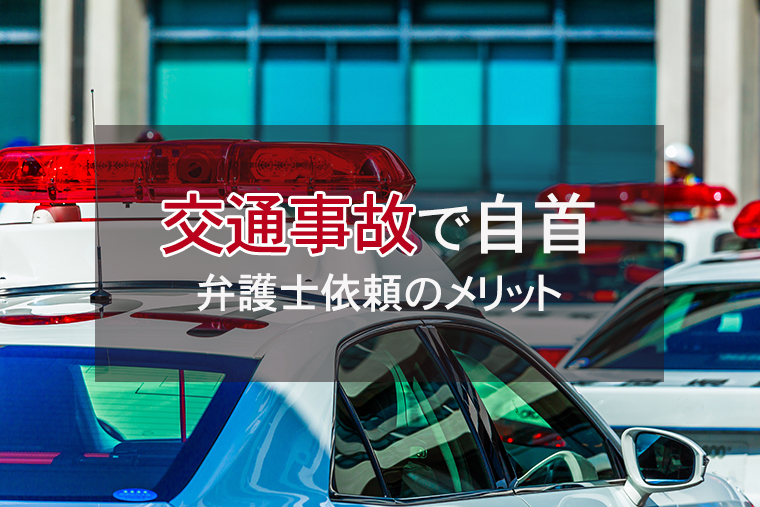
[参考記事]
ひき逃げ・当て逃げをしてしまい自首をしたい場合の弁護士依頼
なお、交通事故後、早期に物損事故を警察に届け出ると、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえる可能性があります。
交通事故証明書がない場合、保険会社が保険金の支払いを拒むことがあります。
そうすると、車の修理代や被害者への治療費が自費となってしまい、多大な損害を被ることになるでしょう。
(2) 被害者と示談交渉を行う
自ら警察に出頭すれば、被害者との示談交渉も進めやすくなります。
被害者の多くは、加害者が逃げたことに対する憤りや不信感を抱いています。しかし、加害者が自ら事故を届け出ることでその感情は和らぐケースも多く、その後の建設的な話し合いの土台を作ることができます。
示談が成立すれば、民事上の損害賠償問題が解決するだけでなく、刑事処分においても良い情状として考慮され、起訴を免れる可能性が高くなります。
なお、危険防止措置義務や報告義務を定めた道路交通法は、社会全体における交通の安全・円滑という法益を守るものですので、「被害者」という概念はないとされます。
それでも、当て逃げで壊された車の所有者など、物損の被害者に対して民事上の示談が成立すれば、これを良い情状として取り扱ってもらえます。
3.当て逃げの解決事例
(1) 飲酒運転の当て逃げで執行猶予を獲得
Aさんは、深夜に飲酒をした状態で自動車を運転してしまいました。
交差点を進行していたところで、前の車が一旦停止したのに気が付かず、その車に後ろから衝突してしまいました。
衝突後、Aさんは少し車を走らせて近くのコンビニで被害者と話をしましたが、そこでの話し合いがまとまらず警察に通報がされました。Aさんは飲酒運転の罪と報告義務違反で起訴されてしまいました。
弁護士に相談をしたAさんとしては、「当初から事故を警察に報告する気はあったのに、先に被害者によって通報されてしまっただけで報告義務違反が成立するのはおかしい」という考えでした。
そこで、酒気帯び運転の罪については情状面で有利な主張をし、報告義務違反については争うことにしました。
報告義務違反については、Aさんと被害者の話が食い違っていたため、両者の言い分をよく検討したうえで、現場の確認や証拠の吟味をしました。
最終的には、被害者の証人尋問を行い、法廷で事実を明らかにしました。
酒気帯び運転の罪については、処分が少しでも軽くなるよう、反省の態度が顕著であることをしっかりアピールしました。また、Aさんを監督してくださる方を選んだうえで、法廷で証言してもらいました。
結果として、報告義務違反・酒気帯び運転の罪とあわせてAさんは有罪判決となりましたが、反省の態度が酌まれ執行猶予となりました。
(2) ひき逃げ事件の扱いを当て逃げに変えて不起訴処分
Bさんは、夜間に自動車でバイクに追突してしまいました。怖くなってしまったBさんは、警察へ連絡せずに現場から逃走してしまいました。
その後、Bさんは警察に検挙される前に弁護士に相談にいらっしゃいました。
Bさんは、運転免許がなければできない仕事をしており、Bさんおよびそのご家族としては免停だけは避けたいと考えていました。
Bさんの依頼が迅速だったこともあり、被害者の方は人身事故の届け・診断書の提出をしていない段階でした。
そこで、弁護士から早急に示談交渉をした結果、無事示談をすることができ、怪我に関する診断書の提出を免れました。そのため、人身事故ではなく物損事故として処理されることになったため、ひき逃げではなく当て逃げ事案として処理されることになりました。
示談も成立していたことも重なって、結果として、不起訴となりました。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
4.当て逃げをしたらお早めに弁護士へ相談を
以上から分かるよう、物損事故を起こした場合でも警察にすぐ報告する必要があります。交通事故の当事者となった場合には、必ず警察に連絡しましょう。
それと同時に、泉総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士までお早めにご相談ください。
なお、泉総合法律事務所では、当て逃げ事件のうち飲酒運転や無免許運転が原因だという案件にも対応しております。

[参考記事]
危険運転過失致死傷罪の刑事弁護全般







本件では、被害者の方は、元々示談に応じる姿勢であり、Bさんに刑事手続的な罰を与えたいとはそこまでは考えてはいないようでした。
しかしながら、被害者の方は100万円単位の高額な示談金を請求してきました。
被害者と粘り強く交渉を続けた結果、最終的にはこちらの許容限度内の金額で被害届の提出をしないという内容の示談をすることができました。早期のうちに依頼されたことが結果的に功を奏した事案と言えます。
[参考記事]
ひき逃げの罪|必ず逮捕・起訴されるのか?