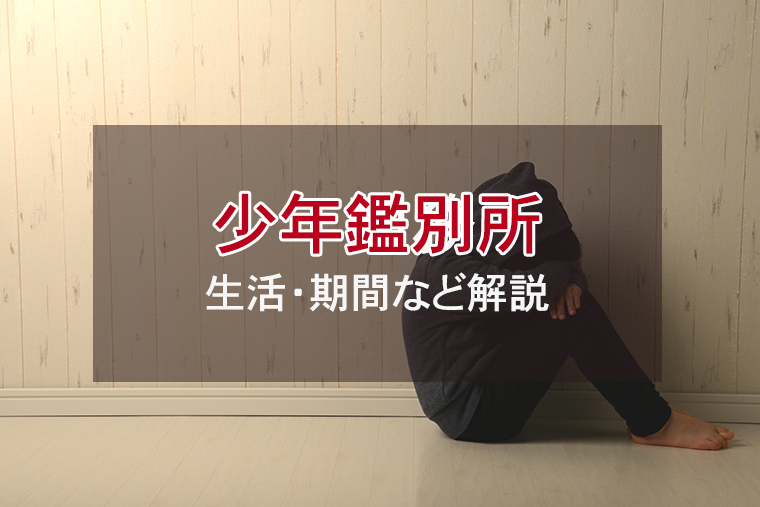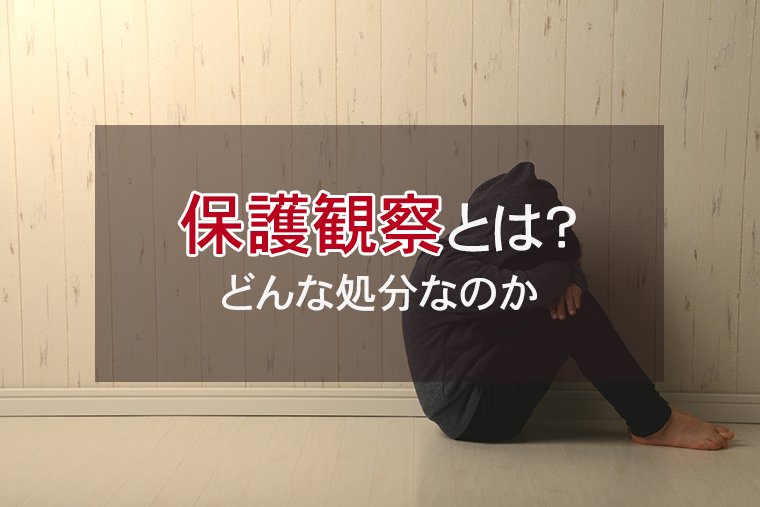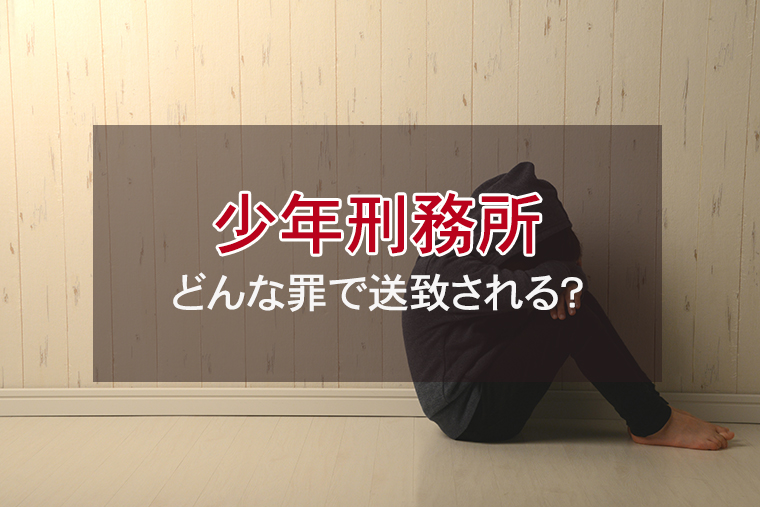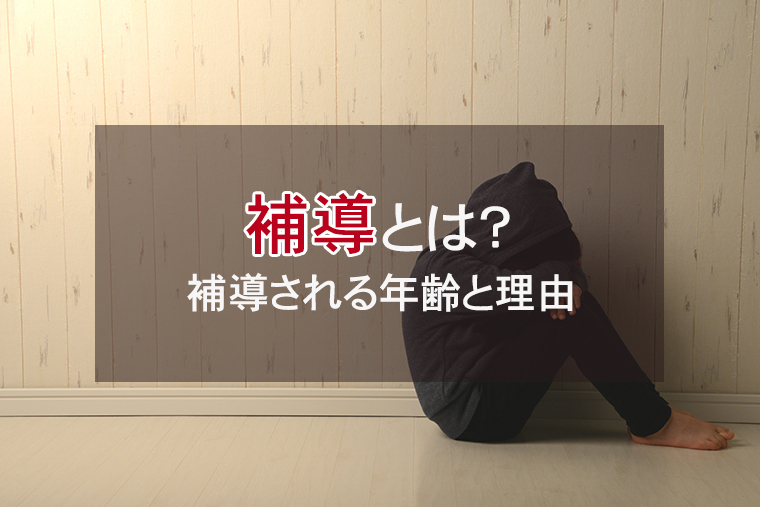20歳未満の成人の少年法|18歳・19歳が罪を犯したらどうなる?
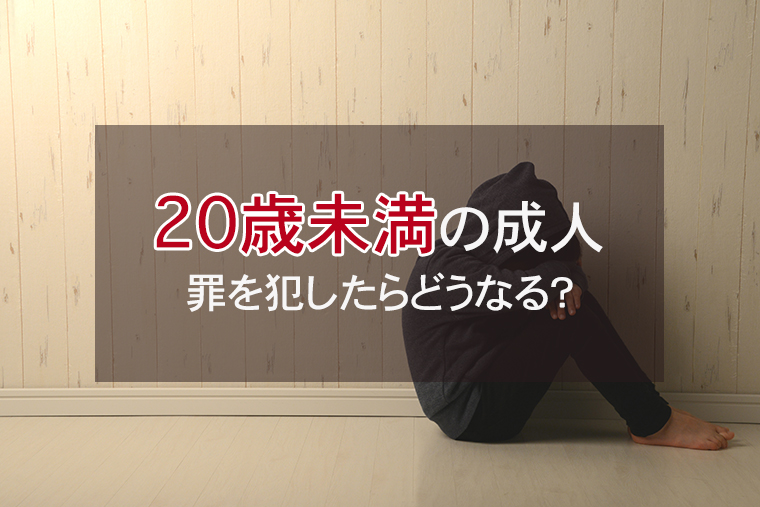
Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/izumilawnet/izumi-law.net/public_html/wp-content/themes/izumi-law/izumi-common-inc/izumi-common-extra-functions.php on line 49
少年法は、原則として20歳未満の者を対象とします。
民法改正により成人年齢が18歳となりましたが、少年法の適用対象が20歳未満という制度は維持されています。
一方、令和2年に少年法が改正され、少年のうち18歳以上の者は「特定少年」とされました。
これにより、18歳以上・20歳未満、つまり18歳と19歳の者が罪を犯した場合には、少年法の適用範囲であるとはいえ、以前より厳しい処分が科される可能性が高くなりました。
この記事では、20歳未満の成人(18歳と19歳の成人)に適用される少年法について解説していきます。
1.少年法における「少年」の種類
少年法適用の対象となる少年について、以下の4種類に分けられます。
- 触法少年:刑罰法令に触れる行為を行った14歳未満の少年
- 犯罪少年:刑罰法令に触れる行為を行った14歳以上の少年
- ぐ犯少年:その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある17歳以下の少年
- 特定少年:刑罰法令に触れる行為を行った18歳と19歳の少年
14歳未満の者が刑罰法規に触れる行為(触法行為)を行っても、刑事責任年齢に達していないので、「犯罪」は成立せず、刑事手続の対象外です。刑法は満14歳以上の者を対象としており、14歳未満の者の行為を不可罰としています。
一方、他方、14歳以上の者が刑罰法規に触れる行為を行えば「犯罪」が成立します。犯罪を犯した14歳以上20歳未満の者は「犯罪少年」と呼びます。
成人の刑事事件では、刑事裁判にかけるか否かは検察官が決めます。
これに対し、犯罪少年の事件は(捜査の必要性の強度に応じてルートは変わるものの)全て家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が少年審判にかけるかどうか、および処分内容をどうするかを決めます(=全件送致)。
少年審判では刑罰を目的とせず、少年に反省を促し、その健全な育成をはかる各種の「保護処分」等を決定します。
しかし、重大犯罪など一定のケースでは、成人と同様に刑事罰を与えるか否かを決める刑事裁判手続にかけられる場合があります。刑事裁判で有罪判決を受ければ成人と同様に刑罰が科されますし、前科もつきます。
この犯罪少年のうち、特に18歳と19歳の少年を「特定少年」と呼びます。
特定少年も少年法の適用対象ですが、後述の通り、特定少年は逆送決定となり、成人事件同様に刑事裁判所に起訴されてしまう可能性が高くなります。
2.18歳・19歳の少年の少年事件手続き
(1) 逆送となる可能性が高い
送致を受けた家庭裁判所では、犯罪の有無、事件の悪質性、少年の要保護性などを調査して、少年を少年審判にかけるか否かを判断します。
しかし、一定の場合には、成人と同様の刑事裁判手続にかけるために、事件を家裁から検察官に送致する場合があります。これを「逆送」と呼びます。
逆送されて起訴された場合の刑事裁判では、原則として20歳以上の成人事件と同様に取り扱われることになります。
逆送は、次の場合に行われます。
- 死刑・拘禁刑に当たる罪の少年事件で、調査の結果、罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき
- 犯行時に16歳以上の少年が、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件
- 18歳、19歳のときに犯した死刑、無期又は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件
重要なのは、2021年5月の少年法の改正により、18歳以上の少年については3が追加となったことです。例えば、不同意性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪などが新たに原則逆送対象となります。
特定少年ならば、どのような犯罪でも家裁が刑事処分を相当と認めるときは逆送となると考えておきましょう。
また、少年法56条では、拘禁刑の言渡しを受けた少年の受刑者は、「特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する」こととしています。
しかし、これは特定少年を除きます。つまり、特定少年の受刑者は他の成人と同じ場所に収監されるということです。
(2) 保護処分の内容の違い
特定少年の保護処分の内容も、17歳以下の少年の保護処分と異なります。
特定少年の保護処分は以下のうちのどれかで、家庭裁判所が決定します。
- 少年院送(3年以下)
- 2年間の保護観察(遵守事項に違反した場合には少年院に収容できる)
- 6ヶ月の保護観察
保護観察の期間は、通常は20歳に達するまでで、20歳となるまでの期間が2年に満たない場合は2年間です。
特定少年だからといって20歳に達すれば保護観察が解除されるというわけではありません。
また、18歳未満の少年ならば、「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」という処分もあり得るところ、特定少年はこれがありません。
児童自立支援施設は、不良行為やそのおそれなどのある18歳未満の少年を入所させる施設で、児童養護施設は保護者がいない、あるいは虐待を受けているなどの18歳未満の少年を入所させる施設です。少年院とは異なり開放的な施設ですので、そのような環境での生活指導が相当と判断された18歳未満の少年が送致されることになります。
3.20歳未満で前科がつくリスク
少年審判で少年院送致などの処分を受けても、これらは刑罰ではないため前科にはなりません。
しかし、少年であっても、刑事裁判で有罪となり刑が言い渡された履歴は前科として記録が残ります。
前科は、罰金刑を含む一切の刑が対象となり、執行猶予となった場合も対象です。よって、少年刑務所での服役も前科となります。
重大なのは、18歳・19歳の前科は不利益が大きくなるということです。
前科がつくことの不利益としては、以下のものが考えられます。
- 履歴書の賞罰欄へ記載しなければならない
- 公務員などへの就職や、国家資格の取得が制限される
- 海外へ渡航する際、渡航先の判断で入国できないことがある
- 再び罪を犯した場合に重く処罰されることがある
ただし、18歳未満の少年が罪を犯した場合、上記1と2の不利益については特例があり、刑の執行を受け終わるか執行猶予となった場合は前科として扱われません。
特定少年はこの特例の対象外ですので、例外なく上記の不利益を全て受けることになってしまいます。
さらに、少年の事件は実名報道が禁止されていますが、特定少年が起訴された場合は実名報道の禁止が解除されます。
よって、18歳・19歳の少年の事件が実名報道され、前科とともに将来の就職などに大きな影響を与えるリスクがあるのです。
4.少年事件は弁護士に相談を
少年法改正により、18・19歳の者は「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。特定少年が重大な犯罪を犯した場合、従来の少年とは扱いが大きく変わります。
特定少年は、検察官へ送致されて刑事裁判にかけられる可能性が高くなります。
逆送されて起訴されれば、成人と同様の刑罰が適用され、前科がつきます。また、特定少年が逆送されて公訴提起(起訴)された場合、実名報道が解禁されてしまいます。
実名報道されると、インターネット上に当該情報が半永久的に残ってしまい、新しい交友関係や学歴・職歴を築く際にも悪影響が生じかねません。
特定少年が刑事事件を起こしてしまったならば、少年事件に対応する弁護士に依頼いただくことをおすすめします。
弁護士から家庭裁判所に働きかけることで逆送を回避できる可能性があるほか、仮に逆送され起訴されてしまったケースでも、弁護士は実名報道をしないよう働きかけたり、刑罰を軽くするための活動に尽力します。