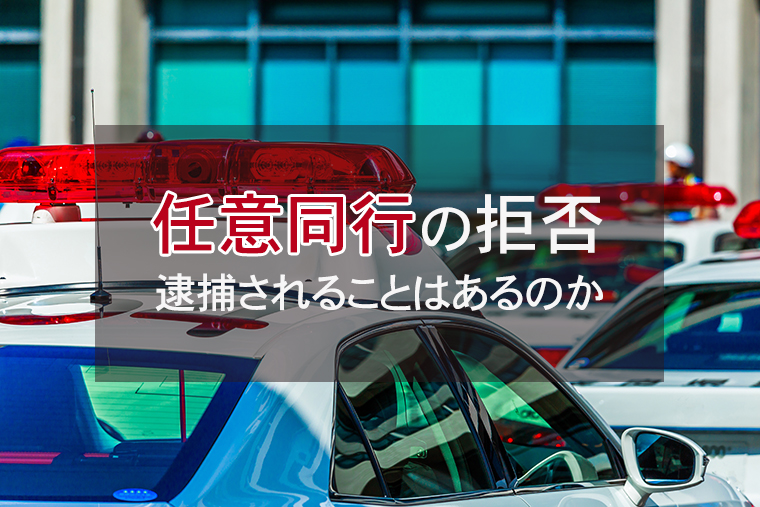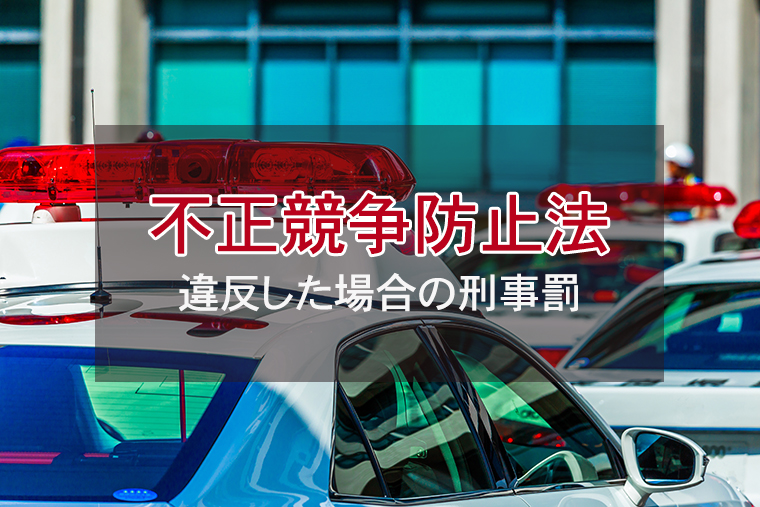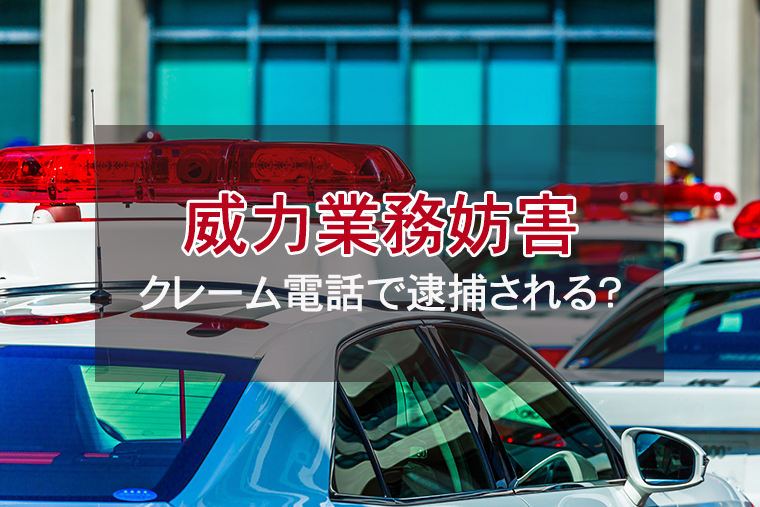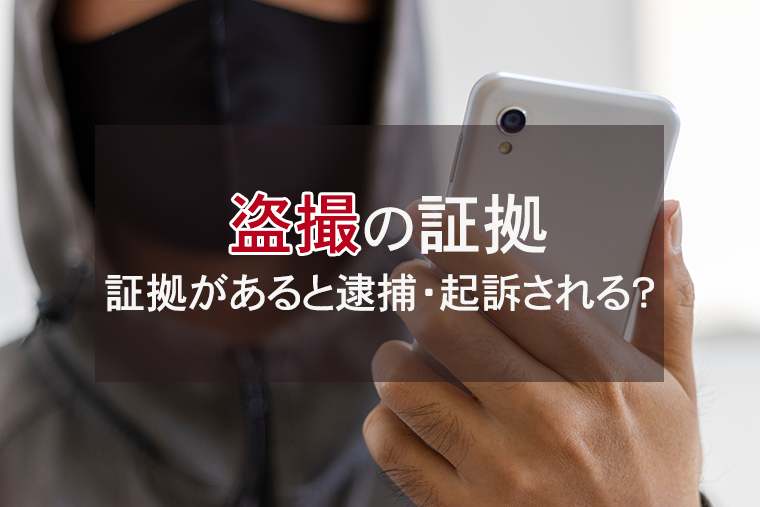公務執行妨害罪で逮捕されたらどうなる?
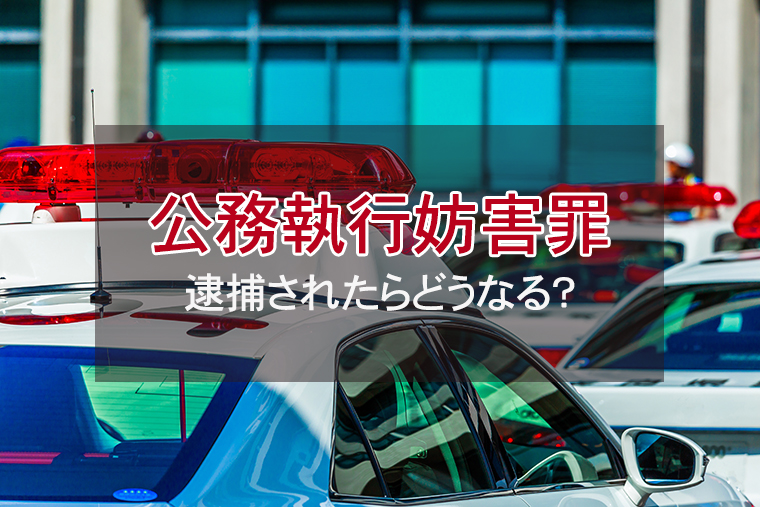
警察官の職務質問に抵抗したり、消防士の救助活動を妨げたりする行為は、「公務執行妨害罪」に該当する可能性があります。
公務執行妨害罪で逮捕された後は警察署で取り調べを受けることになりますが、その後の流れや刑罰の重さについて正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。
本記事では、公務執行妨害罪で逮捕された場合の具体的な流れ、勾留期間、起訴の可能性、そして有罪になった際の刑罰について詳しく解説します。
また、逮捕後にどのような対応を取るべきか、弁護士に相談するタイミングなど、実際に役立つ情報もお伝えします。万が一の事態に備えて、被疑者やその家族の方はぜひご覧ください。
1.公務執行妨害罪とは?
公務執行妨害罪は、刑法第95条第1項に規定されている犯罪です。
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
典型的な事例としては、以下のようなものが考えられます。
- 職務質問中の警察官を突き飛ばす
- 違法駐車の取り締まり中の警察官に暴言を吐き、威嚇する
- 火災現場で消防士の消火活動を妨害する
- 裁判所の執行官が差し押さえを行う際に抵抗する
- 税務調査を拒否し、職員に暴力を振るう
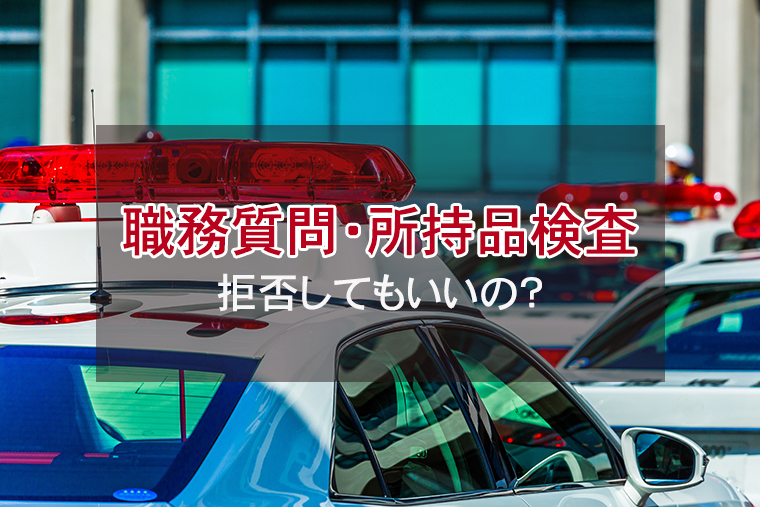
[参考記事]
職務質問・所持品検査って拒否してもいいの?
公務執行妨害罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 公務員であること
対象となるのは国や地方公共団体の公務員です。具体的には、警察官、消防士、市役所職員、税務職員、裁判所職員、検察官、刑務官などが該当します。
ここでいう「公務員」は、刑法第7条で定義される広い概念です。国家公務員法や地方公務員法上の公務員だけでなく、法令により公務に従事する者も含まれます。
たとえば、みなし公務員とされる特定郵便局長や、一部の公共交通機関の職員なども該当する場合があります。
また、公務員の補助者(警察官に協力する民間人など)は、原則として本罪の対象にはなりませんが、状況によっては別の罪が成立する可能性があります。
(2) 職務を執行中であること
公務員が「適法な職務」を執行している最中でなければなりません。この要件には2つの重要なポイントがあります。
- 適法性: 職務が法令に基づいた適法なものである必要があります。違法な職務執行に対する抵抗は、公務執行妨害罪には該当しません。たとえば、令状なしの違法な逮捕、職務質問の範囲を超えた強制的な所持品検査、権限のない立ち入り調査などに抵抗した場合は、本罪は成立しないとされています。
- 職務執行中の認定: 公務員が職務を開始してから終了するまでの間である必要があります。勤務時間中であっても、休憩中や私的な用事で行動している場合は「職務執行中」とは認められません。ただし、緊急時の対応など、勤務時間外でも職務として認められるケースもあります。
判例では、職務の適法性について、手続きに軽微な違法があっても実質的に職務の範囲内であれば適法と判断される場合もあり、個別の事案ごとに慎重な判断が必要です。
(3) 暴行または脅迫があること
公務員の職務執行に対して、暴行(物理的な力の行使)または脅迫(害悪を告知して恐怖心を与える行為)を加える必要があります。
暴行の範囲
暴行は、直接公務員の身体に触れる必要はありません。判例では、以下のような行為も暴行と認定されています。
- 警察官を突き飛ばす、殴る、蹴るなどの直接的な暴力
- 公務員に向かって物を投げつける
- 公務員の進路を塞いで押し合う
- 公務員が使用する器具を奪い取る、破壊する
- 大声で騒ぎ立てて業務を妨害する
暴行の程度については、軽微なものでも成立し得ます。たとえば、警察官の腕を掴んで振り払う行為でも、職務執行を妨害する意図があれば暴行と認められる可能性があります。
脅迫の内容
脅迫は、公務員またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産などに対して害悪を告知し、恐怖心を与える行為を指します。具体的には以下のような例があります。
- 「殺すぞ」「家族に危害を加えるぞ」などの発言
- 刃物などの凶器を示して威嚇する
- 「お前の不正を暴露するぞ」などの名誉毀損的な告知
脅迫は、相手に恐怖心を与える程度のものである必要があり、単なる暴言や不快な発言だけでは脅迫とは認められない場合もあります。
(4) 故意があること
公務執行妨害罪の成立には、公務員が職務を執行していることを認識し、その職務を妨害する意思(故意)が必要です。
まず、相手が公務員であり、現に職務を執行中であることを認識している必要があります。ただし、公務員であることを確実に知っている必要はなく、「公務員かもしれない」という未必の認識でも足りるとされています。
制服を着た警察官や、身分証を提示した公務員に対する行為であれば、認識があったと判断されやすくなります。
また、職務の執行を妨害する意思が必要です。ただし、職務を完全に阻止する意図までは必要なく、職務執行を困難にする認識があれば足ります。
仮に公務員であることや職務執行中であることを知らずに妨害してしまった場合は、公務執行妨害罪は成立しません。たとえば、私服警察官が身分を明かさずに職務質問を行い、それを不審者と勘違いして抵抗した場合などは、故意がないため本罪には該当しない可能性があります。
ただし、状況から容易に公務員であることが分かる場合や、身分を告げられたにもかかわらず抵抗した場合は、故意があったと認定されやすくなります。
2.公務執行妨害罪で逮捕されたらどうなる?
(1) 逮捕から検察官送致
公務執行妨害罪で逮捕されると、まず警察署に連行され、身柄を拘束されます。
逮捕には「現行犯逮捕」と「通常逮捕」の2種類がありますが、特に警察官に対する暴行が多い公務執行妨害罪では、現行犯逮捕される割合が高い傾向にあります。
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を検察官に送致するか、釈放するかを決定しなければなりません。この間に取り調べが行われ、事件の詳細について供述を求められます。
逮捕期間中は家族との面会は制限されてしまいますので、この段階から正しい対処方法を知るには弁護士を呼ぶしかありません。
(2) 勾留の判断
警察から検察官に送致されると、送致を受けた検察官が引き続き被疑者を取り調べます。
検察官は送致から24時間以内(逮捕から通算72時間以内)に、「勾留請求」をするか「釈放」をするかの判断を下します。
勾留請求は、 さらに捜査が必要と判断した場合に裁判所に対して被疑者の勾留を請求するというものです。
公務執行妨害罪を含める刑事事件全般では、重大事件ではなくても、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断されると勾留請求される可能性が高くなります。
一方、勾留の必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されます。ただし、釈放されても捜査は継続され、後日在宅のまま起訴される可能性もあります。
裁判所が勾留を決定した場合、原則として10日間、更に捜査が必要とされれば最大で20日間の身体拘束が継続されます。つまり、逮捕から起訴・不起訴の決定までには最大23日間身柄を拘束される可能性があります。
この期間、仕事や学校に行くことはできず、社会生活に大きな影響が生じます。
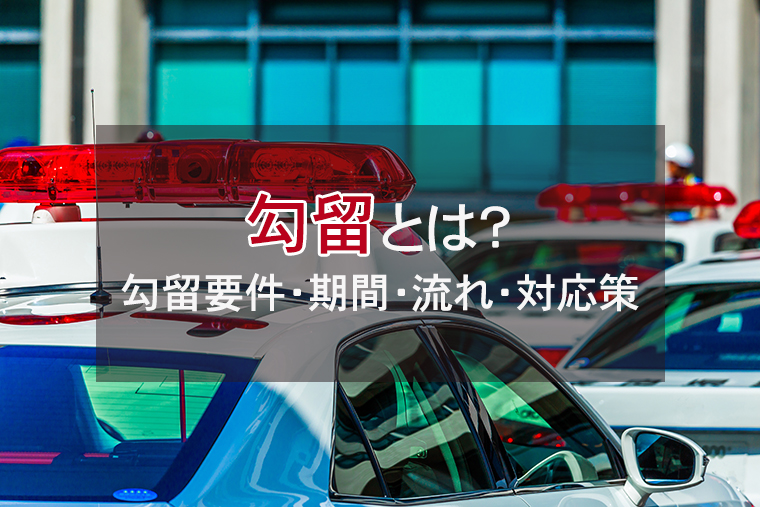
[参考記事]
勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説
(3) 起訴・不起訴の判断
そして、勾留期間満了までに、検察官は起訴・不起訴の処分を決定します。
証拠が十分にあり、刑事裁判にかけるべきと判断した場合に起訴されます。
公務執行妨害罪では、暴行の程度、前科の有無、反省の態度などが総合的に考慮されます。初犯で暴行の程度が軽微な場合でも、公務員に対する犯罪であるため起訴される可能性は比較的高いといえます。
しかし、比較的軽微な事案である場合のほか、深く反省している姿勢が見られる場合や被害者との示談が成立している場合では、正式な裁判を開かずに書面審理のみで罰金刑を科す略式手続きが取られることがあります。
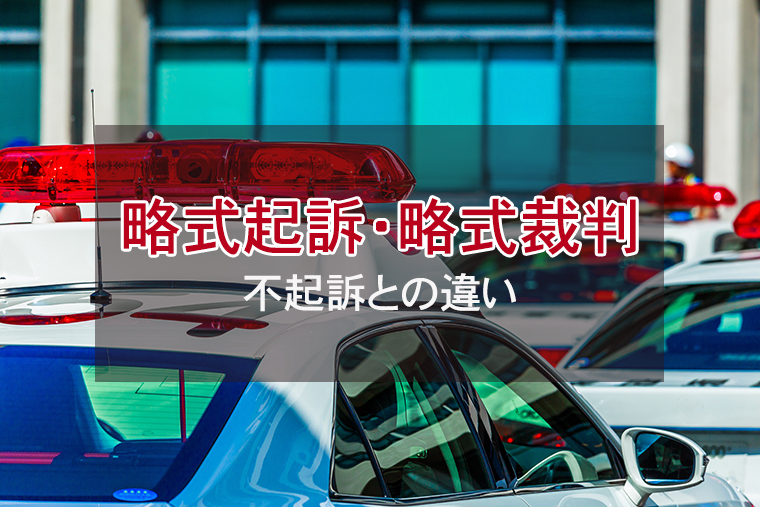
[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
起訴後は保釈請求が可能になります。裁判所が認めれば保釈金を納付することで釈放されますが、事件の内容によっては保釈が認められにくいケースもあります。
一方、証拠不十分である場合のほか、罪を犯したことが事実であってもその反省や被害回復の具合などにより起訴をしないと判断してもらえた(=起訴猶予となった)場合には、不起訴となります。
示談が成立している、初犯である、暴行の程度が極めて軽微などの事情があれば、不起訴処分となる可能性もあります。
(4) 起訴後の刑事裁判
起訴後の裁判では、検察官が起訴内容を立証し、弁護人が被告人の主張を展開します。
事案の内容にもよりますが、比較的軽微な事件では1〜3回程度の公判で結審することが多いです。
有罪判決の場合、法定刑の範囲内(3年以下の拘禁形または50万円以下の罰金)で刑が言い渡されます。初犯で情状が良好な場合は執行猶予付き判決や罰金刑となることもありますが、暴行の程度が重い場合や前科がある場合は実刑判決となる可能性が高まります。
早期の釈放や不起訴処分を目指すためには、弁護士のサポートが不可欠です。
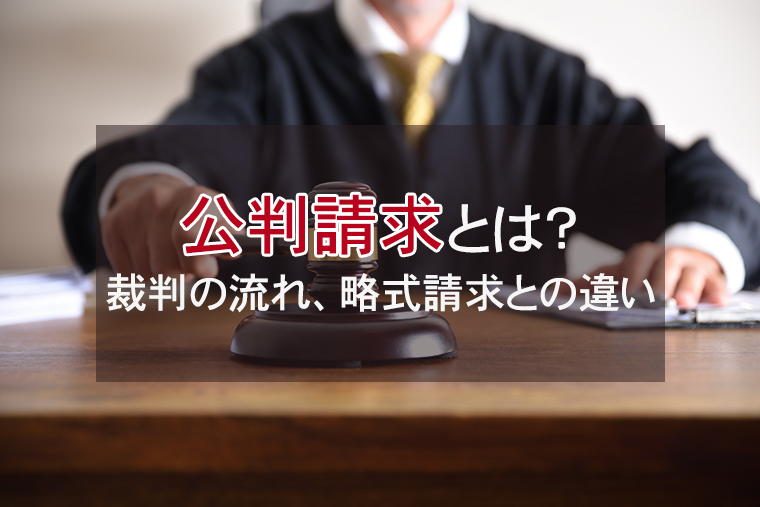
[参考記事]
公判請求とは?裁判の流れ、略式請求との違いを解説
3.公務執行妨害罪で逮捕された場合は弁護士に相談すべき
公務執行妨害罪で逮捕された場合、できるだけ早く弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士のサポートがあるかないかで、その後の処分や社会生活への影響が大きく変わる可能性があります。
(1) 早期釈放の可能性を高める
まず、逮捕直後から弁護士が活動を開始することで、早期釈放の可能性が高まります。
弁護士は、検察官が勾留請求する前に意見書を提出したり、裁判所に勾留の必要性がないことを主張したりできます。勾留が認められなければ逮捕から72時間以内に釈放され、その後は通勤・通学などこれまで通りの生活を送ることができます。
勾留が決定された後でも、弁護士は勾留の取消を目指して勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行うことができます。
早期釈放により、逮捕による社会生活への影響を抑えることができます。
どうしても長期間の欠勤・欠席が必要になる場合、弁護士は家族に会社・学校に対する適切な説明方法をアドバイスしながら、解雇や退学などの不利益を避けるための対応を検討します。
(2) 不起訴処分を目指せる
弁護士は、不起訴処分を獲得するための様々な活動を行います。
最も代表的な弁護活動は、被害者である公務員やその所属機関と示談交渉です。被害者との示談が成立すれば、刑事事件では不起訴処分獲得・減軽となる可能性が大きく高まります。
公務執行妨害罪では、被害を受けた公務員個人だけでなく所属する組織(警察署、消防署など)との関係も考慮する必要があり、専門的な交渉が求められますので、弁護士のサポートは必要不可欠です。
更に、検察官に対して、犯行の動機や背景、被疑者の反省の態度、社会的な影響などを詳細に説明した意見書を提出します。初犯である、暴行の程度が軽微である、深く反省しているなどの事情を適切に伝えることで、不起訴処分や略式起訴(罰金刑)、執行猶予判決となる可能性が高まります。不起訴処分となれば前科はつきません。
事案によっては、弁護士は捜査機関が収集した証拠を精査し、職務の適法性や暴行の程度について法的な問題点を指摘することで、公務執行妨害罪の成立自体を争うことも可能です。
(3) 取り調べへの適切な対応ができる
逮捕直後の取り調べは、その後の処分を大きく左右します。
弁護士は接見を通じて、取り調べでどのように供述すべきか、何を注意すべきかを具体的にアドバイスします。状況によっては黙秘権を行使すべき場合もありますが、弁護士は法的な観点から、どのタイミングで黙秘権を行使すべきか助言できます。不用意な供述が不利な証拠となることを防ぎ、事実に基づいた適切な供述ができるようサポートできるのです。
更に、長時間の取り調べや誘導的な質問、虚偽の自白の強要など、違法・不当な取り調べが行われた場合には、弁護士がその問題点を指摘し適切に対処しますので安心です。
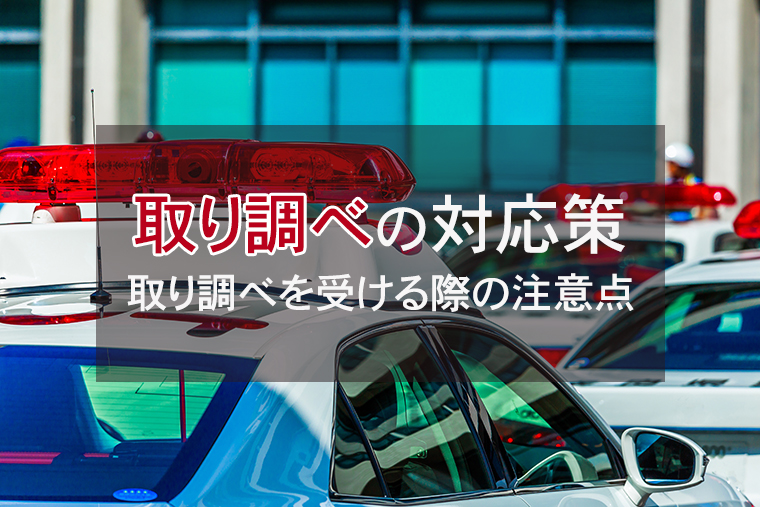
[参考記事]
警察による取り調べの対応策を弁護士がアドバイス
(4) 裁判での有利な弁護活動
起訴された場合でも、弁護士のサポートにより刑を軽減できる可能性があります。
被告人の反省の態度、更生の意欲、家族の監督状況などを裁判所に詳しく説明し、執行猶予付き判決や罰金刑などの軽い刑を目指します。
あるいは、職務の適法性や暴行・脅迫の有無について争う余地がある場合、証拠に基づいて無罪を主張します。
なお、起訴後は保釈請求が可能になります。弁護士が適切な保釈請求を行うことで、裁判を待つ間、社会生活を送りながら裁判の準備することができます。
4.まとめ
このように、公務執行妨害罪で逮捕された場合、弁護士のサポートは不可欠です。早期釈放、不起訴処分、刑の軽減など、弁護士の活動によって得られるメリットは非常に大きく、その後の人生に大きな影響を与えます。
そこで、弁護士にはできるだけ早く相談することが重要です。
逮捕直後から弁護士が活動することで、勾留阻止や早期釈放の可能性が高まります。また、取り調べが始まる前に法的アドバイスを受けることで、不利な供述を避けることができます。
家族が逮捕された場合も、すぐに弁護士に連絡し、接見を依頼することをお勧めします。
お困りの方は、泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。