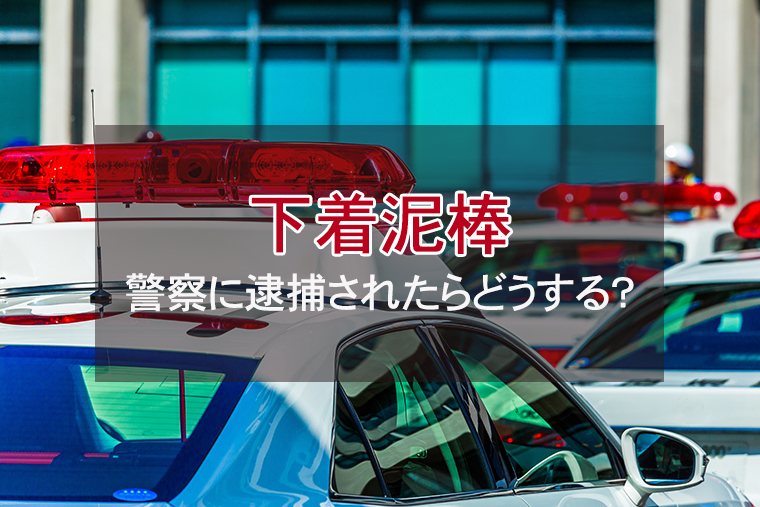ひったくりで逮捕された!窃盗・強盗で逮捕された後の流れ

「ひったくり」は窃盗罪に該当し、場合によっては強盗罪として扱われることもあります。
逮捕後は、警察署での取り調べ、検察への送致、勾留・起訴の判断など、複雑な刑事手続きが進んでいきます。
この記事では、ひったくりによる窃盗罪・強盗罪で逮捕された後にどのような流れで手続きが進むのか、そして逮捕された場合に取るべき対応について解説します。
1.ひったくりの罪について
「ひったくり」は被害者から財物を奪い取る行為ですが、その手口や状況によって「窃盗罪」か「強盗罪」のいずれかが成立します。
両者では法定刑が大きく異なるため、どちらの罪に問われるかは非常に重要と言えます。
(1) 窃盗罪
ひったくりの多くは窃盗罪(刑法第235条)として処理されます。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者」に成立する犯罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
ひったくりが窃盗罪となるのは、被害者が気づかない隙に、あるいは抵抗できないほどの瞬間的な力でバッグなどを奪い取った場合です。
例えば、歩行中の被害者の背後からバイクで近づき、一瞬でバッグをひったくって逃走するような典型的なケースがこれに該当します。
被害者が転倒したり怪我をしたとしても、それが結果的なものであれば窃盗罪と暴行罪(あるいは傷害罪)にとどまることが一般的です。

[参考記事]
窃盗罪の初犯で逮捕・起訴される?どんな処分になるのか
(2) 強盗罪
一方、暴行や脅迫を用いて財物を奪った場合は、強盗罪(刑法第236条)が成立します。強盗罪の法定刑は5年以上の拘禁刑で、窃盗罪よりもはるかに重い刑罰が科されます。
ひったくりの中でも、被害者の身体を押したり引っ張ったり、抵抗を抑圧するような力を加えた場合は強盗罪となる可能性があります。
具体的には、抵抗する被害者のカバンを腕ごと強く引っ張る、被害者を突き飛ばして転倒させる、バッグを奪うために被害者の身体を押さえつけるなど、相手の反抗を抑圧する程度の暴行があれば強盗罪に該当します。
さらに、ひったくりの際に被害者が怪我をし、その怪我が重傷であれば強盗致傷罪(刑法第240条)となり、無期または6年以上の拘禁刑という極めて重い刑罰が科される可能性があります。
【ひったくりが強盗罪とされた最高裁裁判例】最高裁昭和45年12月22日決定
被疑者は、通行人の女性の背後から自動車を運転して近づき、車の窓から女性のハンドバッグの手提げ紐をつかんで引っ張りました。しかし、女性が手を離さなかったため、被疑者は手提げ紐をつかんだまま自動車を進行させ、結果として女性を引きずられ転倒して傷害を負いました。本件では強盗致傷罪の成立が認められました。
(3) 窃盗・強盗の違い(境界線)
両罪の境界は「暴行・脅迫の程度」にあります。
判例では、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があれば強盗罪、そうでなければ窃盗罪とされています。実務上は、被害者が抵抗する間もなく一瞬で奪い去った場合は窃盗罪、被害者との間で引っ張り合いや押し合いがあった場合は強盗罪と判断される傾向があります。
どちらの罪に問われるかによってその後の処分や量刑が大きく変わってくるため、事件の状況を正確に把握し、適切に主張していくことが重要です。
2.ひったくりで逮捕されたらどうなる?
ひったくり=窃盗・強盗は犯罪行為ですので、警察に検挙されれば刑事手続きが進んでいきます。
(1) 逮捕・警察の取り調べ
ひったくりで逮捕されると、まず警察署に連行されて取り調べを受けます。
逮捕には「現行犯逮捕」と「通常逮捕」があり、ひったくりの場合は犯行直後に現場で取り押さえられる現行犯逮捕のケースが多く見られます。
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を検察官に送致するか、釈放するかを決定しなければなりません。この48時間の間、留置場で身柄を拘束され、警察官による取り調べが行われます。
取り調べでは、犯行の動機、手口、被害品の処分方法、共犯者の有無などについて詳しく聴取されます。
逮捕直後は外部との連絡が制限されることが一般的ですが、被疑者は逮捕直後から弁護士を依頼する権利があり、家族などへの連絡も弁護士を通じて行うことができます。
家族は、警察からの連絡で被疑者が逮捕されたということを知ることになりますが、「なぜ逮捕されたのか」「どのような処分の見込みなのか」という点については教えてもらえないのが通常です。
(2) 検察官送致(送検)
警察が事件を検察官に送致することを「送検」といいます。刑事事件へ原則として全件が送検されますので、ひったくりの被疑者は検察に書類ごと身柄を送致されると考えましょう。
送致されると、検察官による取り調べが行われます。検察官は送致を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留請求するかを判断します。
この24時間と警察の持ち時間48時間を合わせて、逮捕から最大72時間が「逮捕段階」となります。逮捕期間中は家族との面会もできません。
この72時間以内に勾留請求されなければ、いったん釈放されて在宅事件として捜査が続くことになります。
(3) 勾留
検察官が勾留請求し、裁判官がこれを認めると、さらに10日間の身柄拘束が続きます。
勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められます。ひったくりが強盗致傷罪などの重大犯罪となった場合も勾留の危険性は高くなります。
勾留中も検察による取り調べが続き、勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
勾留中は、弁護士との接見(面会)が自由にでき、家族との接見も原則として可能です。ただし、証拠隠滅のおそれがあるとして接見禁止決定が出されている場合は、弁護士以外との面会が制限されます。
被疑者は、勾留期間中に弁護士を代理人として被害者への被害弁償や示談交渉を進め、不起訴を目指すことになります。
なお、起訴・不起訴の判断に至るまでの捜査が完了しないなどやむを得ない事由がある場合、検察官の請求によりさらに最大10日間の勾留延長が認められることがあります。つまり、逮捕から最長23日間、身柄を拘束される可能性があるのです。
(4) 起訴・不起訴の判断
不起訴処分となれば、刑事裁判は開かれず、その時点で身柄が釈放されます。
不起訴の理由には「嫌疑なし」(被疑者が犯人であるという証明が十分にできないできない)、「嫌疑不十分」(証拠が不十分)、「起訴猶予」(犯罪は認められるが、情状を考慮して訴追しない)などがあります。
初犯で被害額が少額、被害者との示談が成立している、反省の態度が明確といった事情があれば、起訴猶予による不起訴処分となる可能性が高まります。
一方、常習性がある、被害額が高額、複数の余罪がある、被害者との示談が不成立といった場合は、起訴される可能性が高くなります。

[参考記事]
起訴猶予とは?不起訴・無罪との違い
起訴されると刑事裁判が開かれ、有罪・無罪および刑罰が判断されます。
しかし、窃盗罪など比較的軽微な事件の場合、本人が罪を認めていれば「略式起訴」という簡易な手続きで罰金刑が科されることもあります。略式起訴では正式な裁判は開かれず、書面審理のみで罰金の金額が決定されます。
※強盗罪には罰金刑がないため、強盗罪にあたるひったくりで略式起訴となることはありません。
ただし、罰金刑でも前科がつくことに変わりはありません。
2024年の統計によれば、ひったくりを含む単純な窃盗罪で起訴された総数2万9,667人のうち、正式起訴が2万3,960人(80.7%)、略式起訴が5,707人(19.3%)であり、約2割が略式起訴です(※2024年検察統計調査「表番号24-00-08・罪名別、被疑事件の既済及び未済の人員」)。
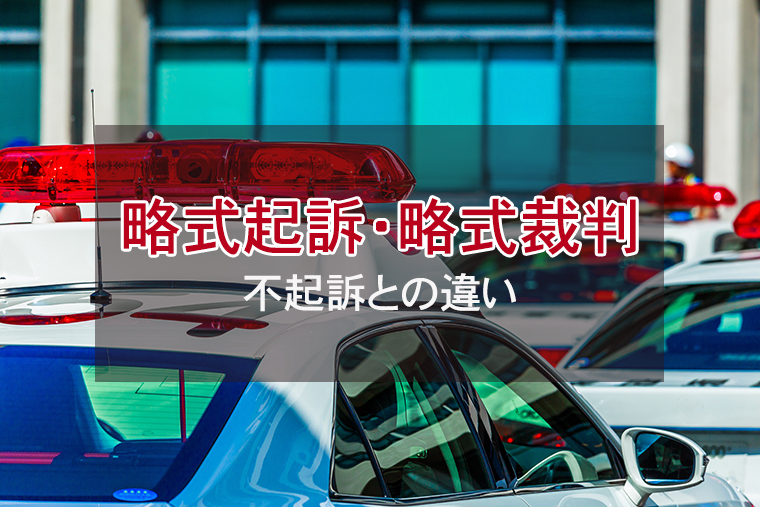
[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
3.ひったくりで逮捕された場合の対処法
ひったくりで逮捕された場合、起訴・不起訴の判断までに適切な対応を取ることで、不起訴処分の獲得や刑の軽減につながる可能性があります。
(1) 早期に弁護士を選任する
逮捕後、最も重要なのは早期に弁護士を選任することです。被疑者は逮捕直後から弁護士を依頼する権利があり、弁護士は逮捕後すぐに接見(面会)することができます。
弁護士は、取り調べに対するアドバイス、被害者との示談交渉、身柄解放に向けた活動、家族との連絡・伝言など、様々な場面でサポートをしてくれます。
特に、身柄事件では逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長23日間しかなく、この限られた時間の中で効果的な弁護活動を行うには、早期の依頼が不可欠です。
(2) 取り調べへの適切な対応
逮捕後は警察や検察による取り調べが繰り返し行われます。そして、その取り調べへの対応はその後の処分に大きく影響します。
取り調べでは、事実を正直に話すことが重要です。虚偽の供述をしたり黙秘を続けたりすることは、「反省をしていない」と捉えられてしまい不利に働くことがあります。特に証拠が明確な事件では、素直に事実を認めて反省の態度を示すことが、情状面でプラスに評価されます。
ただし、記憶が曖昧なことについて取調官の誘導に乗って事実と異なることを認めてはいけません。証拠の状況によっては、時には黙秘をすることが有利に働くこともあります。
また、余罪を追及されて身に覚えのないことを認めさせられそうになった場合は、毅然と否認する必要があります。
供述調書には必ず目を通し、自分が話した内容と異なる部分があれば署名・押印を拒否することができます。
このような対応方法について、一般の方がその場で考えながら適切に対処をすることは難しいものです。弁護士と相談しながら、慎重に対応することがお勧めです。
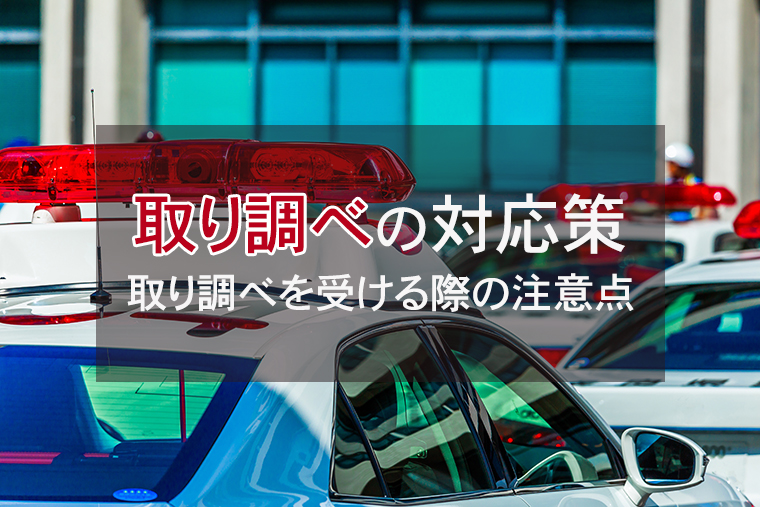
[参考記事]
警察による取り調べの対応策を弁護士がアドバイス
(3) 示談交渉の重要性
ひったくり事件で逮捕された後の対応として最も重要なのが、被害者との示談交渉です。
示談とは、被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで、民事上の損害賠償問題を解決する合意のことです。
民事の責任を果たす示談であっても、その示談が成立すれば刑事事件において検察官や裁判官の判断に良い影響を与えます。
特にひったくり事件では、被害者の処罰感情が強いケースが多く、示談の成否が起訴・不起訴の判断を左右することが少なくありません。初犯で被害額が比較的少額、かつ被害者との示談が成立していれば、起訴猶予による不起訴処分となる可能性が高まります。
起訴された場合でも、示談成立は情状面で有利に働き、執行猶予や刑の軽減につながります。
なお、示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきです。
まず、加害者本人や家族が直接被害者に連絡を取ろうとすると、被害者に更なる恐怖や不安を与えてしまい、かえって処罰感情を強めてしまう危険性があります。ひったくりの被害者は身体的・精神的に大きく傷ついており、加害者側からの接触を望まないことがほとんどです。
そもそも、逮捕・勾留されている場合、本人は外部との連絡が制限されているため、自ら示談交渉を進めることは物理的に不可能です。
弁護士であれば、第三者的な立場から冷静に交渉を進めることができ、被害者も安心して話し合いに応じやすくなります。弁護士は警察や検察を通じて被害者の連絡先を知り、適切な方法で示談交渉を進めてくれます。
示談金は、被害品の時価、被害者の治療費や精神的苦痛などを考慮して決定されます。
ひったくり事件の場合、被害品の価値に加えて、被害者が受けた恐怖や精神的ダメージに対する慰謝料が上乗せされるのが一般的です。
示談金額について合意できれば、示談書を作成します。示談書には、示談金の額、支払方法、被害者が加害者を許す旨、今後民事上の請求をしない旨などが記載されます。場合によっては、被害者が刑事処罰を望まない旨の「宥恕条項」を入れることもあり、これがあると不起訴や刑の軽減により有利に働きます。
示談が成立したら、速やかに示談書を検察官や裁判所に提出します。起訴前に示談が成立すれば不起訴の可能性が高まり、起訴後であっても量刑判断において有利な事情として考慮されます。
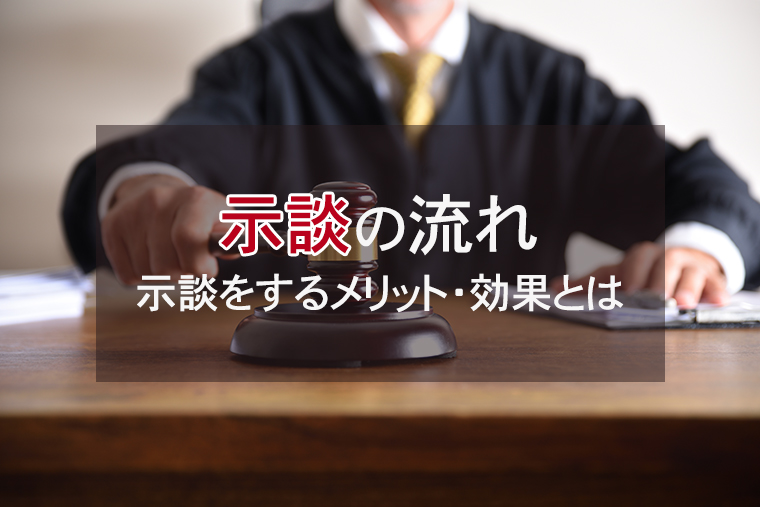
[参考記事]
刑事事件の示談の流れ|示談をするメリット・効果とは?
(4) 示談が難しい場合の賠償方法
もちろん、被害者が示談を拒否するケースもあります。特に被害者が大きな恐怖を感じていたり、怪我を負っていたりする場合は、感情的に示談に応じられないこともあります。
示談が成立しない場合でも、被害弁償の意思を示すことが重要です。被害品の価値相当額を供託する(法務局に預ける)、贖罪寄付を行うなどの方法で、反省と償いの意思を示すことができます。これらの対応も、情状面でプラスに評価される要素となります。
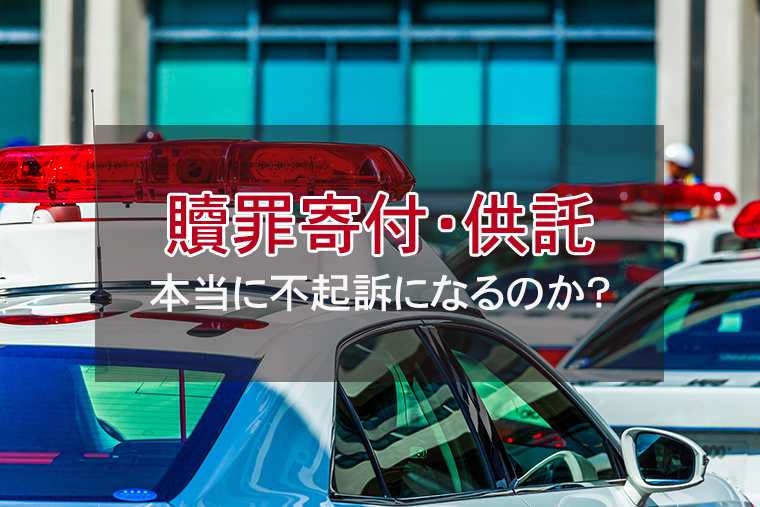
[参考記事]
贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?
4.まとめ
ひったくりで逮捕された場合、窃盗罪か強盗罪かによって刑罰の重さが大きく異なります。
逮捕・勾留後は最長23日間という限られた時間の中で起訴・不起訴が判断されるため、早期の対応が極めて重要です。
最も効果的な対処法は、弁護士を通じた被害者との示談交渉です。示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予の可能性が高まります。
また、取り調べには誠実に対応し、家族の監督体制を整え、反省と再犯防止の意思を明確に示すことも大切です。
また、逮捕・勾留によって仕事や学業に影響が出る場合は、早期の身柄解放を目指すことも重要です。
弁護士は意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告、勾留請求の取り消しなどの手続きを通じて、身柄の早期解放を図ることができます。
一度の過ちで人生を棒に振ることのないよう、ひったくりで逮捕されてしまったら逮捕直後から弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。