覚せい剤で逮捕された場合の刑罰と弁護活動について

覚せい剤(覚醒剤)の薬物事件は、初犯でも実刑判決の可能性がある重大な犯罪です。
しかし、適切な弁護活動により、執行猶予や減軽処分を獲得できる場合もあります。
本コラムでは、覚せい剤取締法違反の法定刑、量刑の傾向、そして弁護士が行う具体的な弁護戦略について解説します。
早期の弁護士依頼が、その後の人生を大きく左右します。
1.覚せい剤取締法違反の法定刑
覚せい剤取締法違反(覚醒剤取締法違反)となる主な行為と、その罰則は以下のようになっています。

このように、覚せい剤は法定刑として罰金刑がない重大犯罪です。逮捕・起訴されてしまった場合、執行猶予がつかない限りは実刑となると理解しておきましょう。
その他の薬物犯罪と処罰法については、以下のコラムもご覧ください。

[参考記事]
薬物事件を取り締まる法律の種類と刑罰
2.覚せい剤で逮捕された場合の流れ
刑事犯罪で逮捕後は、検察官が「勾留の必要なし」と判断すれば釈放され、在宅にて捜査が行われることがあります。
しかし、覚せい剤など薬物に関する事件は、逮捕・勾留されることが通常です。
在宅での捜査が認められるのは、被疑者に逃走や証拠隠滅の危険がないケースのみです。
しかし、覚せい剤に限らず、薬物事犯は「①証拠薬物の隠滅が容易であること」「②入手先という共犯者が存在すること」から、証拠隠滅や共犯者との口裏合わせの危険性が高いと認識されているため、釈放が認められることは少ないです。
勾留後は、引き続き検察官による捜査が行われます。
まずは10日間勾留され、さらに勾留の期限を超えてなおやむを得ない事由があると認められて勾留延長されれば、追加で最長10日(合計で最大20日間)勾留され、日常生活から完全に隔離されてしまいます。薬物事件では、尿検査に時間を要することもあり、勾留が長引くケースが多々あります。
勾留期間が満期を迎えるまでに、検察官は起訴・不起訴を決定します。
3.覚せい剤事件の弁護活動
(1) 早期の釈放を目指す
覚せい剤事件の場合、そのほとんどは逮捕・勾留されます。勾留をしなければ、証拠隠滅や仲間との口裏合わせを図る可能性が高いとみなされているだけでなく、再び覚せい剤を利用するリスクが極めて高いと考えられるためです。
被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放を目指して、以下の弁護活動を全力で行います。
- 勾留請求をしないよう検察官に対して要求する
被疑者の家族の身元引受書や上申書、意見書を検察官に提出して釈放を働きかけます。 - 勾留決定しないよう裁判官に要求する
勾留のもたらすデメリットなどを記載した意見書を裁判官に提出して釈放を働きかけます。 - 勾留決定を取り消してもらうよう裁判官に対して要求する
いわゆる、“準抗告”が認められれば勾留決定取消し釈放となります。 - 起訴後の保釈請求をする
弁護士が身元引受人を用意し、かつしっかりとした保釈請求をすれば、保釈が認められることもあります。
(2) 贖罪寄付などによる減軽
覚せい剤犯罪は、いわゆる「被害者のいない」犯罪です。
そのため、痴漢、盗撮、暴行などの被害者がいる事件とは異なり、示談を取り付ける刑事弁護活動はありません。
その代わりに、公的団体へ贖罪寄付を行います。
もっとも、示談と異なり、贖罪寄付をすることで執行猶予になるという大きな効果は期待できないことに注意が必要です。
贖罪寄付をどのくらいの金額でどこの団体にするかは、弁護人が検察官と連絡を取りながら検討していきます。
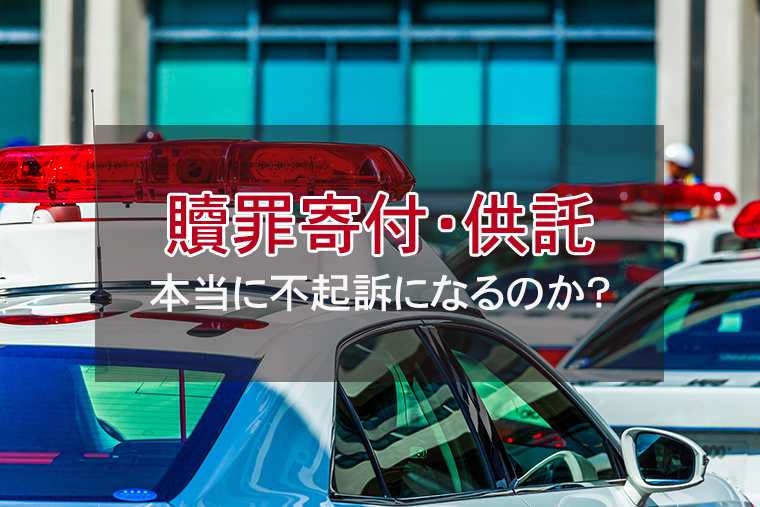
[参考記事]
贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?
(3) 再犯の防止策を整備・主張
薬物犯罪の事実を認めるのであれば、「何故、薬物に手を出してしまったのか?」「自分の考え方、生活態度、交友関係などのどこに問題があったのか?」を真剣に考え、「二度と薬物に接しないためには、どのように改善することが必要か?」に自分なりの答えを見つけましょう。
弁護士として具体的におすすめする再犯の防止策は、薬物依存症の治療に重点を置いている病院・クリニック(心療内科など)での治療や、更生支援施設(回復支援施設)での更生、雇用先や家族による監督の実施です。他にも、「別の新しい趣味を見つける」「健全な交友関係をもって薬物に触れる機会をなくす」など、自らを管理する努力も必要となります。
弁護士は、病院・クリニックの紹介、監督を約束してもらうための雇用先や家族との交渉(誓約書・報告書の作成)といったサポートを行います。

[参考記事]
薬物事件で逮捕された!不起訴・実刑回避のためにするべきこと
4.覚せい剤所持事件の解決事例
最後に、執行猶予中に覚せい剤を所持・使用した事例で、刑事弁護により懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けた事例をご紹介します。
※ご依頼は、執行猶予になるように弁護を行ってほしいというものでした。
40代男性のAさんは、覚せい剤を使用したことが発覚して逮捕され、起訴されてしまいました。
逮捕前の段階で、Aさんご自身が泉総合法律事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。
Aさんには、過去にも覚せい剤を使用した前科があり、その際に執行猶予になっていました。
今回は二度目の裁判であることから、Aさんに覚せい剤と決別してもらうべく、薬物依存治療を専門的に行っている病院を紹介し、通院をしてもらいました。
また、弁護士がAさんの勤務先の代表者の方と交渉して、引き続きAさんを雇用しながら監督することを約束してもらいました。
裁判では、病院での治療の結果が記載された診断書、雇用主が雇用を続けるという意思を示していることを記載した報告書を提出したほか、Aさんの内縁の奥さんに情状証人として出廷してもらい、今後のAさんの監督を約束してもらいました。
また、Aさんご自身も裁判官の前で具体的な反省の言葉を述べるなどしました。
検察官からは懲役1年6か月が求刑されましたが、治療をしていることや、雇用主・奥さんの監督が期待できることなどが考慮され、懲役1年6か月・4年間の執行猶予(保護観察付)の判決が宣告され、実刑を避けることができました。
今回の事件のように、同種の前科があり、一度執行猶予になっている場合は、二度目の執行猶予を獲得することは一般的に困難なことが多いです。
しかし、再犯のおそれが低いことを証明できれば再度の執行猶予を獲得できる場合もあります。
今回は、Aさんに早い段階で専門の医療機関での治療を受けていただいたことや、周囲にAさんを監督することができる人がいたことから、それらの事実を裁判で立証することによって、再度の執行猶予を獲得することができました。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
5.薬物事件も泉総合法律事務所へご相談ください
薬物事件は、適切な対応をしなければ初犯でも起訴・実刑となる可能性がある犯罪です。
逆に言えば、弁護士による早期の弁護活動で、執行猶予の獲得や刑期の軽減が期待できる場合があります。
裁判では、社会復帰に向けた治療プログラムへの参加、専門クリニックへの通院、再犯を防止できる環境調整などを主張することが重要です。
一人で悩まず、薬物事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
6.覚せい剤取締法違反に関する実際の質問
-
Q.執行猶予期間中に再度覚せい剤で逮捕されたら刑務所行きですか?
現在、半年前の覚せい剤自己使用事件で懲役1年半・執行猶予3年の判決を受け、執行猶予期間中です。しかし、また覚せい剤で逮捕されてしまいました。刑務所行きは確実ですか?A.実刑判決の回避は難しいと思われます。
執行猶予期間中に罪を犯した場合、ふたたび執行猶予判決を受けるためには、
①1年以下の拘禁刑の言い渡しを受け
②情状に特に酌量すべきものがあるときに限る
と定められています(刑法25条2項本文)。今回のケースでは、半年という短期間でふたたび覚せい剤を使用しており、反省していないと評価されてしまいます。
さらに、覚せい剤の自己使用自体が10年以下の拘禁刑と重大犯罪であるため、今回の裁判で実刑判決を回避することは難しいです。1年以下の拘禁刑の言い渡しを受けることさえも非常に厳しいと思われます。
Q.彼氏が覚せい剤で逮捕されましたが、実刑になりますか?
同棲してる彼氏が昨日の早朝に逮捕されました。
逮捕された理由としては、すでに逮捕されている仕事仲間の方とお金を出し合って覚せい剤を購入したためです。この場合、どのような判決が下される可能性が高いですか?
A.否認事件になるので、弁護士にご相談ください。
初犯であり、所持量から見て営利目的ではなければ(つまり、自己使用目的ならば)、通常、1年6ヶ月の拘禁刑・執行猶予3年あたりではないかと思われます。
ただし、「お金を貸しただけ」ということなら否認事件になりますので、本人が弁護士とよく相談することをお勧めします。






