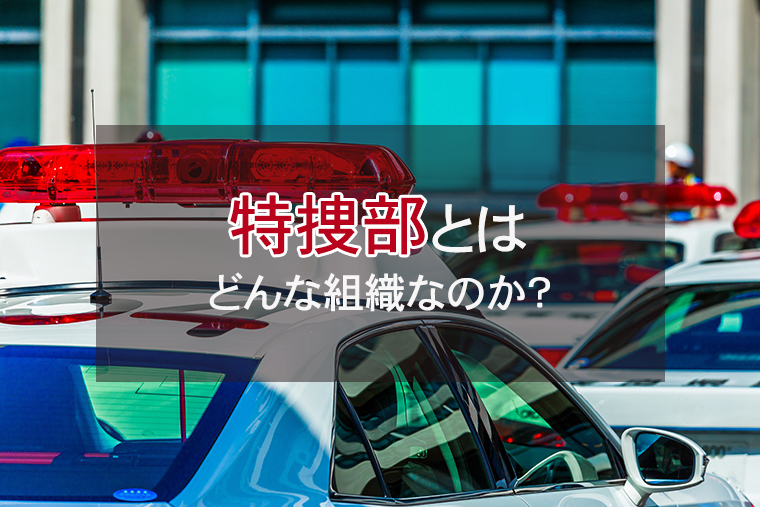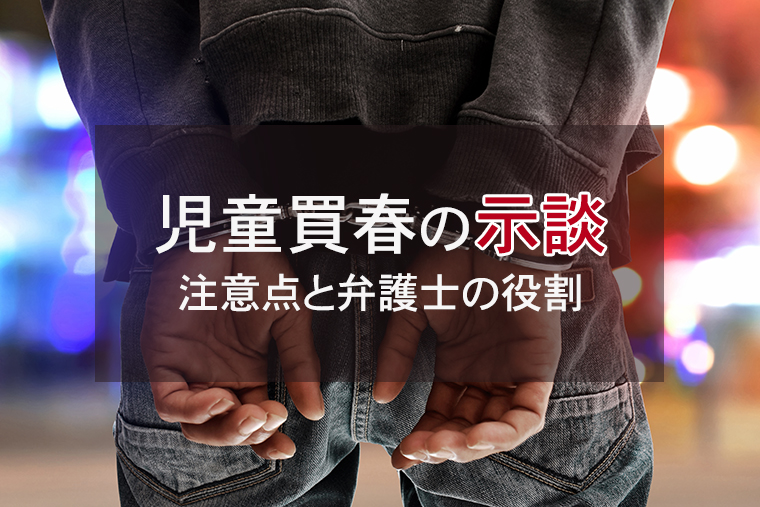検察庁からの呼び出し!取り調べを受ける場合の正しい対応
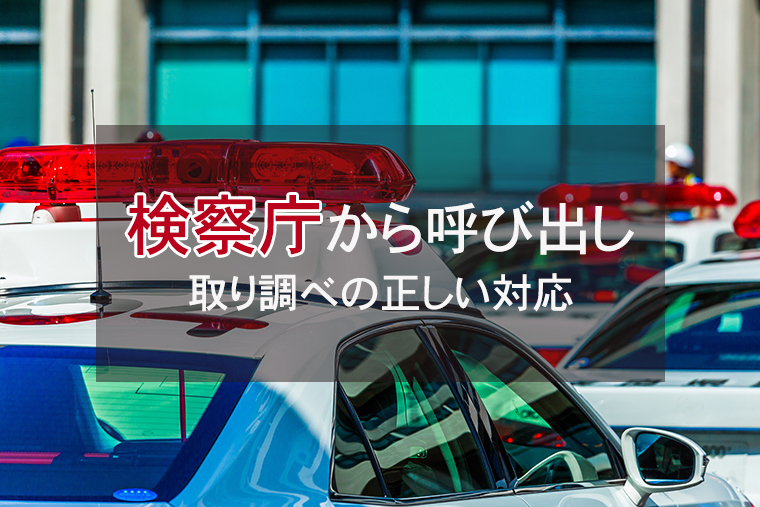
刑事事件を起こし、警察での取り調べ(事情聴取)を終えて帰され「在宅事件」となっている場合、突然検察庁から呼び出されることがあります。
検察に呼び出される理由としては、捜査上の取り調べのため、あるいは取り調べの最終判断のためというケースが多いです。
検察庁での取り調べは、刑事事件の捜査過程において重要な手続きの一つなので、誠実に対応する必要があります。
「何を話せばいいのだろう」「突然逮捕されたらどうしよう」「厳しく追求されるかもしれない」などと不安に思うのは当然ですが、適切な知識と準備があれば、突然の呼び出しにも冷静に対応することができます。
本記事では、検察庁からの呼び出しを受ける理由から、取り調べを受ける際に気をつけるべきこと、弁護士依頼の重要性まで、知っておくべき基本的な知識を解説します。
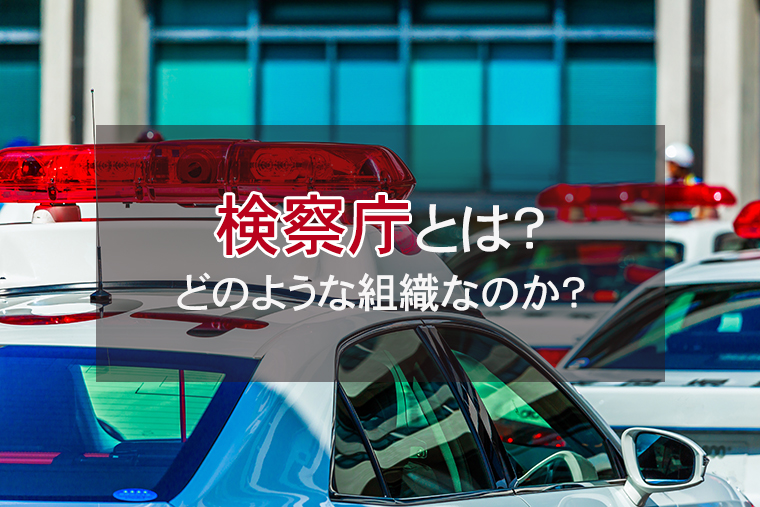
[参考記事]
検察庁について|どのような組織なのか?
1.検察官に呼び出される理由
刑事事件を起こしてこれが警察に発覚した場合(刑事事件の被疑者となった場合)、警察署で取り調べを受け、その内容を調書にとられます。
その後、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、住居・勤務先もはっきりしているならば、警察は身体拘束は不要としてそのまま家に帰してくれるのが通常です。
その後、該当の事件は「在宅事件」として捜査が進みます。
在宅事件を含む刑事事件において、取り調べは警察だけで終わるものではなく、ほとんど必ず検察庁に呼び出され、再度の取り調べを受けます。
多くの方は「何故、警察と検察で同じことを繰り返さなくてはならないのか?」と疑問に思うかもしれません。
検察官は、警察官による取り調べの後、これを補充する形で被疑者の取り調べを行います。
(1) 警察による捜査の適正をチェックする
検察官は、被疑者を起訴するか否かを決める権限を持っています(刑訴法247条)。
被疑者を起訴するのか、裁判にかけのるかというのは、被疑者の人生を左右する重大な問題です。その権限を行使する検察官としては、警察からの報告や、警察で作成された調書を鵜呑みにすることなく、自ら被疑者を取り調べ、警察の捜査内容の適正をチェックする必要があります。
検察官は法律の専門家として、公判維持、すなわち起訴して有罪判決を得ることができるか否かという視点で、警察の捜査や法適用に問題や見落としがないか精査し、必要があれば、補充捜査を指示したり、自ら補充捜査を実施したりする役割を担っているのです。
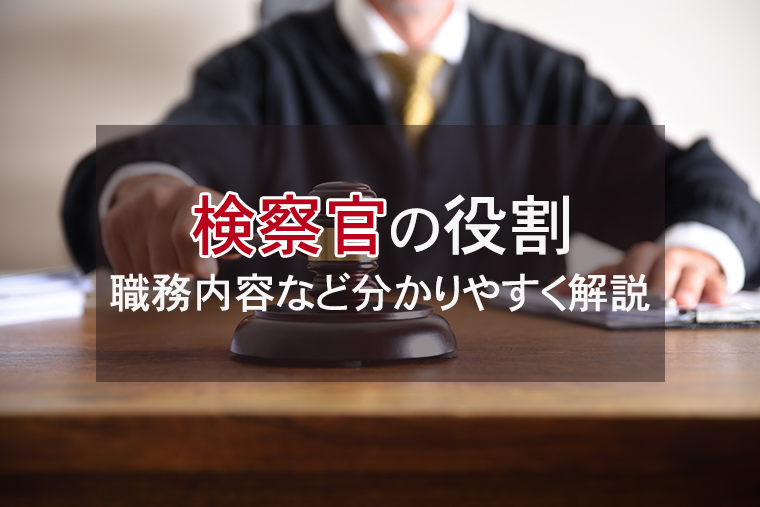
[参考記事]
検察官(検事)の役割・職務内容を分かりやすく解説
(2) 起訴・不起訴処分の判断に用いる
起訴・不起訴は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」(刑訴法248条)という諸般の事情を総合考慮して判断します。
このような総合的な判断をするためには、やはり検察官が被疑者を直接に取り調べ、対話し、その人となりを知ることが不可欠です。
(3) 略式手続・即決裁判の手続きのための取り調べ
略式手続とは、軽微な事件につき、正式な公判ではなく、簡易裁判所の書面審理だけで、100万円以下の罰金または科料を科す手続です(刑訴法461条1項)。
この手続では、検察官が被疑者に制度を説明し、その同意を得た上で、簡易裁判所に対し略式起訴(略式命令請求)を行う必要があります。
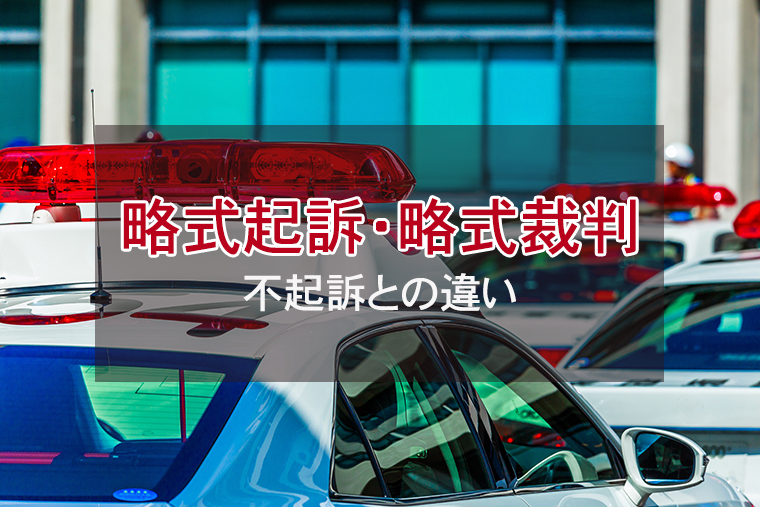
[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
一方の即決裁判とは、明白かつ軽微な事件につき、公判を早期に開き、証拠調べ手続を簡略化したうえ、その日のうちに、罰金刑または執行猶予付き拘禁刑を言い渡す裁判手続です(同350条の161項)。この手続でも、検察官が被疑者の同意を得た上で、裁判所に対して、起訴と同時に即決裁判手続の申立てを行う必要があります。
これらの簡略化された手続は、通常、被疑者にとっても出廷の負担などがない有利な制度です。
しかし、被疑者に制度の説明を行い、同意を得るためにも、検察官が被疑者を直接に取り調べる機会が必要です。
2.呼び出しを拒否した場合はどうなるか
逮捕・勾留で身柄を拘束されていない(=在宅事件である)限り、検察庁から出頭を要請されても、これを拒むことは自由です。
しかし、正当な理由もなく拒否すれば、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕・勾留される危険性があります。
また、出頭要請に応じないと、真摯な反省がみられないと評価されて、起訴・不起訴の判断にあたって、不利な事情となるリスクもあります。したがって、検察庁への出頭要請を拒否するべきではありません。
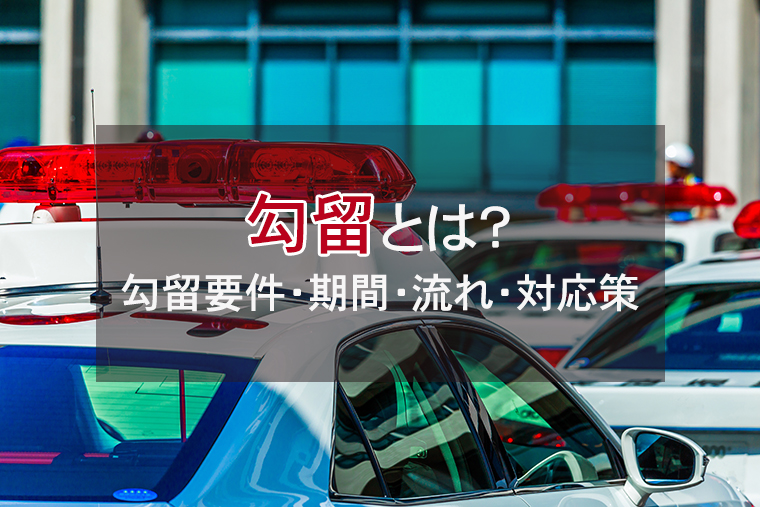
[参考記事]
勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説
3.呼び出しへの対応を弁護士に相談するメリット
検察庁から呼び出しを受けた場合は、まず弁護士に相談することがベストです。
弁護士は、刑事事件の弁護人として、犯罪の嫌疑を受けた被疑者の権利・利益を守ることを職務とする法律の専門家です。
刑事事件の被疑者の弁護を弁護士に相談することは、主に、次のような点でメリットがあります。
- 捜査の流れや、裁判手続など、刑事手続全般について、詳しい説明を受けることができます。
- 黙秘権の行使や、供述調書への署名拒否など、被疑者の利益を守るための権利・手段について教えてもらうことができます。
- その事案において、検察官から受けるであろう質問など、取り調べの内容を予想し、どのように対応するべきかにつき、助言を受けることができます。
- 出頭前に相談をしておくことで、万一、逮捕された場合に、既に事情を十分に把握した弁護士によって、早期に効果的な弁護活動を展開することができます。
- 適切な刑事弁護活動の結果、身柄拘束期間の短縮や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
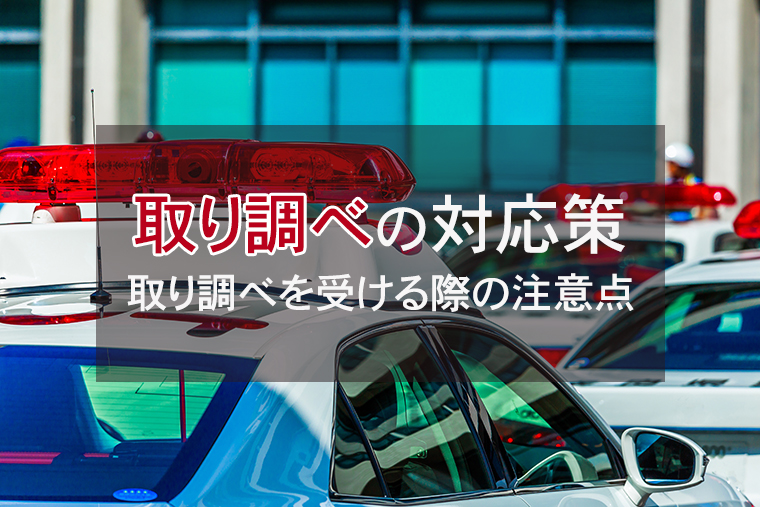
[参考記事]
警察による取り調べの対応策を弁護士がアドバイス
4.まとめ
検察庁からの呼び出しは、刑事事件において重大な局面となります。
黙秘権の行使、供述調書の確認といった冷静な対応が重要ですが、法的知識のない一般の方が検察官を相手に一人で対応するのは極めて困難です。
取り調べでの対応次第で、その後の処分や裁判の行方が大きく左右されます。だからこそ、刑事事件に精通した弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士は適切なアドバイスを行い、被疑者の方の権利を守ります。
呼び出しを受けた際は、一人で抱え込まず早期に弁護士へご相談ください。